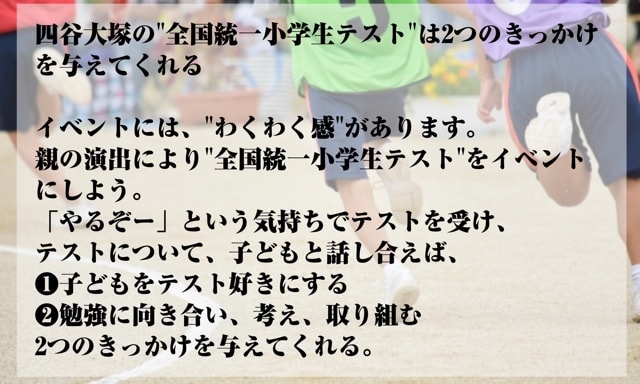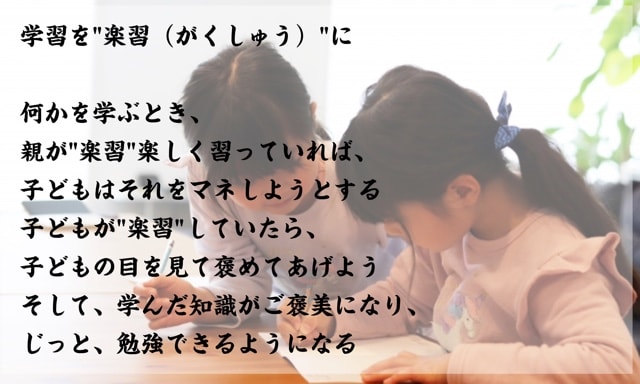
こんにちは、四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、楽習について書きます。
❤︎親が子どもに望むことは、学習習慣
誰かに命令されてやる。
これは習慣ではありません。
子ども自身が
"机に向かう習慣"を持つか、
持たないかは、
子どもの人生に大きな影響を与えます。
つまり、
体を静止した状態に保ち、
考えることができる習慣です。
❤︎机に向かう子どもたちは不自然
"自ら机に向かう"子どもたちは、
なぜ向かうのでしょうか。
それは、
学習の習慣を身につけることが大事だ
と思っているからではありませんし、
まして、
自然に身につくものでもありません。
❤︎多動な子ども
子どもは本来、
四六時中動き回る生き物だからです。
"多動"が普通なのです。
机に向かって座っているのは
本来"不自然"です。
❤︎外からの力が必要
不自然な"机に向かってすわる"ということをさせるには、
"外からの4つのこと"が必要になります。
❶ 親の勉強に対する面白いというイメージ
❷親が"楽習"しているのを見ること
❸親から褒められること
❹知識が得られというご褒美
ただし、
一度きちんと習慣化さえしてしまえば、
それが自然になり、
やらないと気持ち悪い状況になります。
❤︎親の勉強に対するイメージ
親自身が、
勉強を
"我慢するもの"
と考えていませんか。
これでは、
勉強は"苦行"でしかありません。
それもと、"楽しいもの""面白いもの"
と思っていますか。
この親の勉強に対するイメージが、
子どもの勉強に対するイメージを大きく左右します。
❤︎"勉強"は真似ることから
"勉強"は、真似ることから始まります。
小さな子どもたちは、
勝手にマネして、学ぶのです。
そして、
マネる最も身近なお手本の存在が、
お母さんとお父さんです。
❤︎親自身が"楽習(がくしゅう)"する
わが子が自ら机に向かう習慣づくりのために、
親子が行うべきことは、
自ら机やリビングテーブルに向かう習慣、
何事も、
楽しく習う"楽習"の姿勢を見せることです。
❤︎子どもを褒めてはいけない?
勉強は子どもの為なので、
褒める必要はない。
褒めると、
褒めてもらいたいから机に向かうようになる
といわれることがありますが、
そもそも勉強は、
みんなの為にするものです。
みんなの事を思って、
「こうなったら、みんな幸せになるかもしない」と願い、勉強します。
だから、
親から褒められて得られる幸せ感が、
勉強をいい方向に向かわせます。
❤︎子どもが自ら勉強を始めたら、しっかり褒めてあげよう
私は、
しっかり褒めてあげたいと思います。
子どもの目をしっかり見て、
最高の笑顔で褒めてあげましょう。
子どもの勉強する姿勢を
心から悦びましょう。
❤︎学びから得られた知識が2つ目のご褒美
そして、
できたこと、
知識を得たことが、
なによりも大きなご褒美になります。
しっかりと聞いてあげましょう。
❤︎まとめ。学習を"楽習"しよう
何かを学ぶとき
親が"楽習"楽しく習っていれば、
子どもはそれをマネしようとします。
子どもが"楽習"していたら、
子どもの目を見てしっかりと褒めてあげましょう。
そして、学んだ知識が好奇心を刺激するご褒美になり、
机に向かって、じっと勉強できるようになっていきます。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、楽習について書きます。
❤︎親が子どもに望むことは、学習習慣
誰かに命令されてやる。
これは習慣ではありません。
子ども自身が
"机に向かう習慣"を持つか、
持たないかは、
子どもの人生に大きな影響を与えます。
つまり、
体を静止した状態に保ち、
考えることができる習慣です。
❤︎机に向かう子どもたちは不自然
"自ら机に向かう"子どもたちは、
なぜ向かうのでしょうか。
それは、
学習の習慣を身につけることが大事だ
と思っているからではありませんし、
まして、
自然に身につくものでもありません。
❤︎多動な子ども
子どもは本来、
四六時中動き回る生き物だからです。
"多動"が普通なのです。
机に向かって座っているのは
本来"不自然"です。
❤︎外からの力が必要
不自然な"机に向かってすわる"ということをさせるには、
"外からの4つのこと"が必要になります。
❶ 親の勉強に対する面白いというイメージ
❷親が"楽習"しているのを見ること
❸親から褒められること
❹知識が得られというご褒美
ただし、
一度きちんと習慣化さえしてしまえば、
それが自然になり、
やらないと気持ち悪い状況になります。
❤︎親の勉強に対するイメージ
親自身が、
勉強を
"我慢するもの"
と考えていませんか。
これでは、
勉強は"苦行"でしかありません。
それもと、"楽しいもの""面白いもの"
と思っていますか。
この親の勉強に対するイメージが、
子どもの勉強に対するイメージを大きく左右します。
❤︎"勉強"は真似ることから
"勉強"は、真似ることから始まります。
小さな子どもたちは、
勝手にマネして、学ぶのです。
そして、
マネる最も身近なお手本の存在が、
お母さんとお父さんです。
❤︎親自身が"楽習(がくしゅう)"する
わが子が自ら机に向かう習慣づくりのために、
親子が行うべきことは、
自ら机やリビングテーブルに向かう習慣、
何事も、
楽しく習う"楽習"の姿勢を見せることです。
❤︎子どもを褒めてはいけない?
勉強は子どもの為なので、
褒める必要はない。
褒めると、
褒めてもらいたいから机に向かうようになる
といわれることがありますが、
そもそも勉強は、
みんなの為にするものです。
みんなの事を思って、
「こうなったら、みんな幸せになるかもしない」と願い、勉強します。
だから、
親から褒められて得られる幸せ感が、
勉強をいい方向に向かわせます。
❤︎子どもが自ら勉強を始めたら、しっかり褒めてあげよう
私は、
しっかり褒めてあげたいと思います。
子どもの目をしっかり見て、
最高の笑顔で褒めてあげましょう。
子どもの勉強する姿勢を
心から悦びましょう。
❤︎学びから得られた知識が2つ目のご褒美
そして、
できたこと、
知識を得たことが、
なによりも大きなご褒美になります。
しっかりと聞いてあげましょう。
❤︎まとめ。学習を"楽習"しよう
何かを学ぶとき
親が"楽習"楽しく習っていれば、
子どもはそれをマネしようとします。
子どもが"楽習"していたら、
子どもの目を見てしっかりと褒めてあげましょう。
そして、学んだ知識が好奇心を刺激するご褒美になり、
机に向かって、じっと勉強できるようになっていきます。