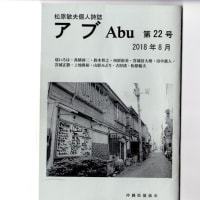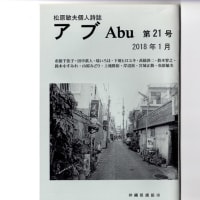ノートⅣ 後期詩編―詩集「瞳詩編」、「渚詩編」、「碧詩編」
清田政信はこの三冊の詩集を三部作とよんだ。発行年は「瞳詩編」「渚詩編」が1982年、「碧詩編」が1984年2月である。1984年9月に出された最後の著作である『造形の彼方』の巻頭に詩「沈黙」が掲載されている。ぼくらが正当に読める詩作品はこの「沈黙」(初出1984・4)が最後と思われる。
沈黙
岬はすすみ
岬はとまどい
言葉は当てる対象を失った
媾曳が切れたとき
血は刃をのんで柔らいでいる
線は夜を閉じて
密度を
何う並べおわった
絵を見たんだ
言葉と色彩は相入れぬから
私は刺すような
溢れを記述していったんだ
これは独在だろうか
ならば対象は消えているから
堅く抜けていった あの
精神の穂先が正確に
虚無の噴いている面につき当たった
宿酔!
遠くで確執がきれいに散ったんだ
贅をふるいおとす
自問を
しなやかに
ひとつの禁をむすぶ手の放心
砂が匂っている
陽がねむっている
息づまるような淋しさ
すでにみえるイメージは去ったから
けずられていく自我を
空を通っていく
火と呼べ
「絵をみたんだ」というのは、前月3月に「知性の神話」というエッセイで山元恵一の絵画についての美術批評を書いているので、山元の絵と思われる。清田の詩は言葉が現在や現実を土台に出てくる。
三部作が、ある女性との関係を歌った詩であることは明らかである。愛の共感域を求めて言葉なきところを言葉で構築しようとする詩想が三部作を貫いている。最後の詩集『碧詩編』でその女性と切れていることが謳われているから、この「沈黙」も時期からして、その「切れ」を謳っていると解する。
「言葉は当てる対象を失った/媾曳が切れたとき/血は刃をのんで柔らいでいる」というのは現実を語っている。対幻想としての女性、関係としての女性、詩を生み出すニンフとしての女性……が不在となった。関係がきれたとき、ほんとうの関係がみえる。「宿酔」!といった。「散った」といった。「息づまるような淋しさ」とは正直な抒情だろう。
「沈黙」も、関係の創り出す魂のうごきで書いている。関係の作り出す情念が現実を背景に自動速記的に語られている。「岬」は自我の代名詞としてみる。性的なイメージも含んでいる。この愛は生活社会に背いたエロスだから、その愛の線は夜を閉じる。絵に比喩された対象である愛は消え、「精神の穂先が正確に虚無の噴いている面につき当たった」と詩人は転換する。そして「宿酔!」と醒めた現実に戻ってくる。「遠くで確執がきれいに散ったんだ」。この愛の彷徨が「ひとつの禁をむすぶ手の放心」であることにも気づいてしまう。
この詩は恋愛の終わりをうたった恋歌であるとみなすことができる。
三部作は係累や生活や関係や状況をとりこんだ、現実の女性との関係を書いている。ふたりの世界をひとりの世界から照射する角度で書かれている。
なぜ三部作が生まれたのか。このころ、清田は同人誌『詩・批評』を離れ、個人誌の性格をもった『詩・現実』で孤絶しながら書いていたように思う。このころになるともう詩的交友のつきあいが、あまりなかったようだ。よく「ひとり街にでる」という表現の言葉があるが、街は独りを癒す場所として与えられている。彼にまつわる生活的・家族的な醜聞を聞くのもこのころである。実生活的には妻との関係の破綻、家庭の崩壊、ある女性との交際、同棲していた時期になる。私小説作家的な生活を想像させる。
三部作のはじめの『瞳詩編』に「きみ」という語彙が多く顕れるようになっている。これまでの詩にでてくる「きみ」は詩を発する不特定の「きみ」であった場合が多いが、この「きみ」は具体的な像をもった「きみ」である。このころ出会い、詩人の魂をめざめさせた女性である。「なぎさ」とか「みどり」とかいう名詞がときどきでてくるが、それは名付けられぬ対象を喚起するものであったかしれない。それが「きみ」になった。
たとえばきみを問いつめて
わたしは眼をふせたまま
沈黙をさけ 沈黙に
みつめられる一瞬がある かくて
嵐をはらんだまま 遂げざりし冬は
二人の中を通り 終息するのだ
それもいい きみのやわらい熱に
みちびかれて 肉の深みに
突きさす 茎のわななき
それもいい 衣を脱ぎ ひきしまる
裸身にのこる 最後の
羞恥もすてたきみに 今
私は何を捧げればいい
(透明な苦しみ・『瞳詩編』)
エロスのはじまりと性愛の充溢した世界と官能的言辞の生成。『瞳詩編』、『渚詩編』には珍しく「あとがき」がない。それは必要がなかったからだろう。現在進行形で関係と詩が進んでいたからと思われる。関係の現実を背景に愛の詩編が豊穣にうまれた。「嵐」の予兆と愛の緊張をうたった詩編から読み取れるものは、言葉がいつも〈きみ〉にむかっていることだ。こういう関係の詩的世界に読者は読む位置をもつだけだ。と同時にこうもいうことができる。恋愛は個人的なものでありながら、他者に通ずる普遍的なモチーフである。素材的にポップな詩である。だが、それを、たやすくみせないのは清田が彼自身の詩的情念で深くつかまえた関係をうたうところにある。
北川透は『瞳詩編』にはさまれた栞で書いている。
……散文詩「瞳へむかう言葉」のなかに、〈この島を死の島と言った人がいる。昼の労働におわれ、いま地酒を汲んでいる彼らは、きっと安らぎへ向かって肉声をしずめているのだ。血のこびりついた刺身を食べる。百年一日のように同じ恋唄をうたっている。三味線は耳膜をなぐりつけながら鳴り続ける。一つの狂い、一つの虚脱へ落ちていくのだ。〉という部分がある。もっとこういう場面を内向化し、デフォルメさせたことばが欲しい。その意味では、彼のことばは、いまでもあまりに黒田喜夫的、清水昶的な戦後詩でありすぎる。そして、黒田や清水の風土や感性を抜かざるをえないだけ抽象的で、無性格になる。
ここを越えてほしい。わたしたちの戦後詩を踏みにじって欲しい。
(恋唄あるいは南方について―『瞳詩編』覚書』
この文章が書かれたのは1982年3月である。北川透が感じ取っているのは、詩の自閉の予兆、ひとりの彼方である。だから、外部の、というか、清田は「過去や故郷は追憶によってではなく、現在の情況にたちむかう思想の透徹によって発見されていくものだということ。現在をよく生きている者にだけ故郷は時制を破砕して肉迫するのだ」(清水昶論Ⅱ)といった論理の繊細さをいっていたわけだし、北川が、そこを場面化してデフォルメすることを求望していることは理解できる。が一方では、この三部作は、はたして「黒田喜夫的、清水昶的な戦後詩」であったか、ぼくには今でも疑問である。
きみの背は不安に柔らげられて反り
痛みに鳴っている
もう帰ることはできない
まだ一度もきたことのない
胸つき峠の明晰な切り岸
そこからみおろす世界の高さ
(相聞・『渚詩編』)
帰るところはないか
帰るところはないようだ
帰りえぬゆえに
戸を蹴り さけがたく
歩きはじめる 前のめりの
眩暈の中へ帰って行くのさ
(諧謔・『渚詩編』)
「帰る」という動詞は故郷や家やらがあてになるが、ここまで来たら「帰る」言葉の方向が別の意味をもつ。帰る場所のないところへ帰ることだ。失われたもの。そこが帰る場所だ。そこは詩人しか感じ取れないところだ。
最後の詩集、『碧詩編』は、「沈黙」とおなじ線状でうたったものが多く対象(女)を喪失した寂寥がモチーフとなっている。
夢をねむらせるように
声を低く
霧にしわぶきながら私は背をふんで
一人の住まいへ帰っていくのだ
(日常・『碧詩編』)
三部作をどう評価するか。言葉だけでは解釈できない世界がある。詩人は、このころ40歳代。恋唄を多作し、性愛もエロスも抒情も詩に捧げている。『碧詩編』にポール・エリュアールを意識したという文章がある。とすれば女性はガラのように詩的啓示を与える存在だったか。その成果が三部作であり、『愛すなわち詩』のような、ということになろうか。
中期にあった〈村〉、〈風土〉、〈民衆〉へ対峙するまなざしから詩をすくい上げる詩的発想が、三部作ではみえない。彼にとって、この三部作の世界は、近代や街や都市の内実を、ひとりの女性のなかに発見して、なにかをつかみとろうと苦悶した結果ではないか。したがって、村の原感情と近代に引き裂かれた、言葉が落ち着くことのない変容の関係を歌っているようにみえる。二人の関係自体に自足する甘い恋歌ではないのだ。
ひとつの異質と関わってまた一つの詩集になった。三部作はこれで完結する。……(略)……女は去り作品だけが残った。女は関係を完結して生活を処する方法を知らなかった。馴れることで生活から生まれる新しいイメージを支えるという深い思慮をもちあわせていなかった。(『碧詩編』あとがき)
未来はないから
私は身軽になって
街を走るにまかせているんだ
(言葉・『碧詩編』)
1984年(?)以後、清田政信は、病境の深い闇の彼方にいったまま、書いていない。この詩人ほど詩に自らの生と存在をかけた詩人はいないのではないか。ぼくは今、清田政信という詩人の生活と栄光と悲惨を想っている。 (完)
(この文章は、沖縄で出されている『脈』81号「特集沖縄の詩人 清田政信」(2014年8月)に書いた「清田政信についてのランダム・ノート」を「改題」して連載しています。)
なお、今年(2017年)の3月末、沖縄で「清田政信研究会」という組織が立ち上がって、活動を開始したことをお伝えしておきます。