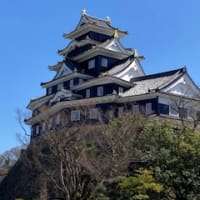先日の産経新聞の「正論」に、筑波大学大学院教授の古田博司氏が、かう書いてゐた。
現代から見ると、近代という時代には実にヘンな「理念」を人々が信じていた。「歴史の必然」といい、あらすじを決める何者かが歴史のなかに潜んでいると、20世紀日本の代表的知識人、福田恆存までが信じていた。彼は「近代化という仕事は歴史の必然に従っておこっている」(『福田恆存対談・座談集』第二巻)と、語っていた。ところが近代化は東アジア諸国では必然にはならなかった。
さうかなといふ疑問を抱いたが、福田恆存の文章を引用しながら、はつきりそれは「誤読」であると言へるところまではいかなかつた。が、やはり違ふと思ふ。近代化といふのが歴史の必然でなければ、中世までが必然なのか。あるいは歴史に必然はないといふ考へなのか。普遍と特殊といふ二分法で、普遍がなくて特殊だけがあるといふお考へなのか。それならば、大学などといふ西洋の近代教育制度に寄りかかつた場に職を得てゐる現状をどうお考へになるのだらうか、さう毒づきたくもなる。成否はともかく攘夷、開国、民主化、立憲政治と続いた日本近代の成立史を偶然といふふうに認識することは可能なのだらうか。次々に疑問が浮かんできた。
「東アジア諸国」に近代化が未だ訪れてゐないのは、それが途上であるからではないか。そして近代化を成し遂げたやうに見える国でさへ、その未熟な姿は、近代化を自生的に成し遂げる前に「必然的に」覆ひかぶさつてきてしまつたといふ事情によるものであるやうに思ふ。
福田恆存は、戦後すぐの書物『近代の宿命』の「あとがき」(昭和22年6月20日)にかうある。
かならずしも意識的に努めたわけではなかつたが、終戰後ぼくの關心の赴くところ、おのづとひとつの主題を形づくつた。それは、ヨーロッパの近代を背景に日本の近代の特殊性を設定したいといふことにほかならなかつた。こゝに収録した十一の文章はそのときどきに雜誌に發表したものではあるが、書名のごとき『近代の宿命』といふ主題のもとに統一と聯關とをもつてゐる。本文のうちでも幾度か觸れてきたことであるが、もしぼくたちの近代に宿命的な悲劇性と複雑性とがあるとすれば、それは近代の確立の未熟といふことそのことのうちにではなく、未熟でありながらそのまゝにヨーロッパ近代の主題を共有してしまつたことのうちに求められよう。みづから剥ぎとることのできる假面ならばたかが知れてゐる。また假面の下に黄色の皮膚をみとめまいとするなら、それはそれで話は簡單である。が、ぼくたちの苦しさは、ヨーロッパの近代を、もちろんぼくたち自身の生肌の表情とはいへず、それかといつてむげに假面だともいひきれぬところにある。この假面はかぶりとほせもせず、もとより脱ぎすてることもできない。人格者の兄をもつた雙生兒のアイロニーであらうか。
近代は宿命である。しかし、「未熟でありながらそのまゝにヨーロッパ近代の主題を共有してしまつた」ところに、その宿命があるから、その進捗に差が生まれるのである。古田氏の論考と福田のそれと、どちらがより正確に東アジアの状況を見てゐるか、結論は明らかであらう。昭和22年、1947年、今から70年前にすでに福田恆存には見えてゐたのである。
 |
保守とは何か (文春学藝ライブラリー) |
| 浜崎 洋介 | |
| 文藝春秋 |