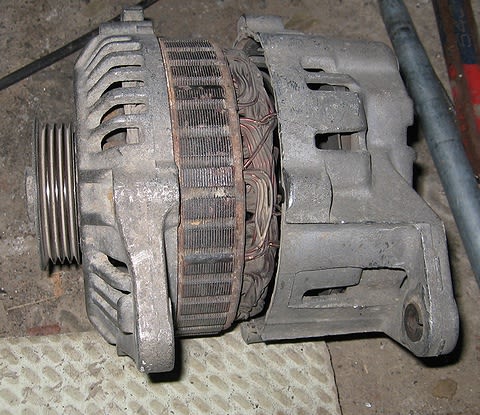今日、昼間から夕方に掛けて、青空が広がる天気だったので、夜に星空が
期待できるかも。
現状での、コンパクトデジカメによるコリメート撮影での天体撮影において
ピント合わせと、光軸合わせの2つの課題が残っている。光軸合わせは以前
LEDライトを使って行ったが、どうも左右、上下の中心は合わせられるが
前後の最良点が少し判りづらく、現状まだ完全に合っていない気がしていた。
そんな訳で夜に備え、帰宅後↓の材料で光軸合わせの治具を作ってみた。

ご存じの方もおられると思うが、スターパーティオーナーの考案した
光軸合わせ治具を真似させて頂く事とした。
先ずは、鏡筒の先端にサイズの合うゴミ箱を丁度良い長さにカット

続いて外枠になる少し大きめのゴミ箱もサイズに合わせて、カット。

外枠のゴミ箱に電球と電池ボックス、スイッチを取り付ける

最後に、両面テープで始めにカットした内枠用のゴミ箱を張り付けて完成


暗くなって、雲が増えてきたが、昨日の様に雲の切れ間から星空が覗く
事を期待して、外に13cmをセットアップする。ちなみに、光軸合わせ治具
を使って光軸を合わせをしている所はこんな感じ↓

なかなか、開口面にフラットな光が当たっている感じで、カメラの
液晶モニターにいい感じで、外枠のオレンジ色が写る。よしよしうまく
行った感じだな。後は、星空を待ってその成果を試すだけ!
しかし、待てどくらせど初めの極軸合わせの為の、北極星が顔を出さない。
だいたい北に向けた赤道儀の後ろで、椅子に座って、北の空を眺めながら、
2時間ほど待ったが相変わらず北極星が見えてこない。夜空は、部分的に
ベガが見えたり、アルタイルが見えたりしているが雲が多く、長い時間
雲の切れている状態は余り続かない感じだ。

↑極軸望遠鏡用の暗視照明をセットして北極星が見えるのを待つ
そうこうしている内に、雲間から何やら水滴が落ちて来る様な、、、、
雨?一気には降り出さないが、時折、風の中に水滴が混じってる感じ。
空は相変わらず、切れ間も有る曇り空状態で北極星は見えない。
さすがに、今夜は諦めて、撤収することにした。せっかくの新兵器が
試せなくて残念だ。
ちなみに、1時間後にはかなりの雨が降り出していた。
撤収して正解だったか、、、
2011.8.24(8/28)
期待できるかも。
現状での、コンパクトデジカメによるコリメート撮影での天体撮影において
ピント合わせと、光軸合わせの2つの課題が残っている。光軸合わせは以前
LEDライトを使って行ったが、どうも左右、上下の中心は合わせられるが
前後の最良点が少し判りづらく、現状まだ完全に合っていない気がしていた。
そんな訳で夜に備え、帰宅後↓の材料で光軸合わせの治具を作ってみた。

ご存じの方もおられると思うが、スターパーティオーナーの考案した
光軸合わせ治具を真似させて頂く事とした。
先ずは、鏡筒の先端にサイズの合うゴミ箱を丁度良い長さにカット

続いて外枠になる少し大きめのゴミ箱もサイズに合わせて、カット。

外枠のゴミ箱に電球と電池ボックス、スイッチを取り付ける

最後に、両面テープで始めにカットした内枠用のゴミ箱を張り付けて完成


暗くなって、雲が増えてきたが、昨日の様に雲の切れ間から星空が覗く
事を期待して、外に13cmをセットアップする。ちなみに、光軸合わせ治具
を使って光軸を合わせをしている所はこんな感じ↓

なかなか、開口面にフラットな光が当たっている感じで、カメラの
液晶モニターにいい感じで、外枠のオレンジ色が写る。よしよしうまく
行った感じだな。後は、星空を待ってその成果を試すだけ!
しかし、待てどくらせど初めの極軸合わせの為の、北極星が顔を出さない。
だいたい北に向けた赤道儀の後ろで、椅子に座って、北の空を眺めながら、
2時間ほど待ったが相変わらず北極星が見えてこない。夜空は、部分的に
ベガが見えたり、アルタイルが見えたりしているが雲が多く、長い時間
雲の切れている状態は余り続かない感じだ。

↑極軸望遠鏡用の暗視照明をセットして北極星が見えるのを待つ
そうこうしている内に、雲間から何やら水滴が落ちて来る様な、、、、
雨?一気には降り出さないが、時折、風の中に水滴が混じってる感じ。
空は相変わらず、切れ間も有る曇り空状態で北極星は見えない。
さすがに、今夜は諦めて、撤収することにした。せっかくの新兵器が
試せなくて残念だ。
ちなみに、1時間後にはかなりの雨が降り出していた。
撤収して正解だったか、、、
2011.8.24(8/28)