「ええとさあ」
と一緒に行った姉が言いました。
「こう言うのは昔、なんて言ったっけ。あっ、そうそう、アングラ・・。」
「はあ、なるほど。」
なんて言うか、初体験的な難解さがそこにはありました。
台詞、多し。
その台詞は美しく、追いかけていくのも大変です。追いかけていった台詞は、舞台的比喩なのかと思ったら、しっかり物語の骨格を成していたりで下谷万年町の迷路のような町並みにも匹敵するほど、脳内をかき混ぜられます。
台詞にもあった、ぐちゃぐちゃの脳みそ。
ああ、それは見ている私たちの、その時の状態を言っているのではないかしら。
だけど台詞が多くて難解なのは「架空畳」と言う劇団で経験済み、負けじと喰らいついて行きました。すると、物語は実は意外なほど単純である事が見えてくるのです。
「身毒丸」では冒頭3分で滂沱の涙。その後ずっと泣いていて疲れ果ててしまいましたが、このお芝居ではじっと見つめたり笑ったりするので忙しくて涙は無縁。目も乾いて、のどもイガイガ。客席で濡れているのは前列3列ぐらいのお客さんたちで、きっとその人たちは、お芝居の流れをじっと見つめ、「来るぞ来るぞ」と身構えて、瓢箪池からバシャッと来たら「来たあ~!!」とビニールを引っ張ると言う、アトラクション的楽しさもあったわけで、何とはなしに羨ましかったです。
でも、ワタクシ、ラスト3秒でううっと涙が溢れてしまいました。
その涙は、私が歳を取って来て今と言うところにたどり着いているから、沸き起こってきた感情なのではないかと思いました。
ああ、歳を取るってやっぱり良い事が多いなあとこういう時、私は思いますよ。若かったら、きっとそのシーンでも私は泣けないと思います。でもおばちゃんを泣かすそのシーンを作っているのは、若き三人なのよね。
ちょっとそう思うと、微妙な気持ちにもなってきますが。
と、それは棚の上に置いておいて、以下はネタバレしています。
 <季節の花300>サフラン。劇中に出てきた花は、実はこんな花だったのですね。
<季節の花300>サフラン。劇中に出てきた花は、実はこんな花だったのですね。
クロッカスは花サフランとも呼ばれ、お仲間。そう思うと、茎が結構短くて、御尻から花を咲かせると、もっと御尻直結な花だったんじゃないかなと、細かい所でダメだしなどをしてみたりして・・・。
まあ、御尻の花の件から入ると、イメージがカタカタと妖怪のように音を立てそうなので、そこは口笛吹いて次にいくことにします。
でもやっぱりこの花をイメージして見た方が舞台の綺麗さが分かるかも知れませんね。
蜷川さんの舞台は、いつも美術さんが綺麗です。
人は何で窓とその向こう側の灯を見ると、胸がキューンとなるのでしょうか。
大人の文ちゃんが佇む町。窓とその向こうの工場で働く人の影は遠い世界。それよりも遠いのはかつて住んでいた下谷万年町。
この下谷万年町と言うのは実在した町で、東京で有名な大貧民窟だったそうです。場所的には上野駅の近く。
劇中で物語の底辺をなしている総監が上野の山で女装の暴漢に襲われたと言うのは本当にあった事件らしく、「下谷万年町物語」は、作者の唐十郎の自叙伝的物語だと言われています。
先日もウチの夫などとテレビを見ていて、良い時代になったよねなどと語り合っていました。こんな不景気な時代なのになにが良い時代と感じたのかと言えば、自分が本来の自分で堂々と生きていける時代なのかと思ったからでした。
すべての人がそうと言うわけではありませんが、これはオカマさんたちを指して思ったことです。ちょっと前までは、彼らのお仕事と言ったら「お水の花道」ぐらいしか道は開かれていなかったと思います。それゆえ、多くの人は自分の本来の姿を隠して世の中にまぎれて暮らしていたのかもしれません。隠さずに生きていこうと思ったら、それは万年町のオカマさんのように生きていたのかもしれません。
中には貧しさゆえに、職業としてその道を選んだ人もいたのかもしれません。
卑猥と猥雑。混沌の中の生命力。
彼らはエネルギッシュでありながら、誰一人美しくないのです。
尋常ではない人たちの間に紛れ込んだ、少年とノーマルな男、そしてただひとりの女だけが、まるで花のように美しいのでした。
現実の中の過ぎていった時代は、夢のように美しくそして切ない・・・・
まるで猥雑と混沌の現実はオカマたちの集団のようで、その中で煌く過去の思い出は若き三人のような気もしてしまうのでした。
AAAの西島隆弘。繊細な少年を最後まで演じ切って思っていたとおり素晴らしかったです。
既に失ってしまった6本目の指。その無い指で一体なにを掴むのか。
水の底にある既に無い劇団の上演されなかった芝居のベルがなり、そして幕が開く。
その時思わず心の中で、
「告白されなかった思い。渡されなかった手紙。書かれなかった小説。」と6本目の指で掴みそうなものが頭の中を駆け巡りました。
藤原竜也の洋ちゃんが語るその台詞は美しかったです。
でも水の底からキティを救い出すと、
「一体何を掴んだというのだ。」と言う彼の台詞に文ちゃんが
「少なくとも独り言を言わなくて良い相手を」と応えます。いきなり来る比喩と現実の台詞の混沌。
美しいと言えば、宮沢りえの美しかった事。池の底から出てきた彼女は音楽も衣装も照明の効果も確かにあったけれど、神々しくて登場してきただけでジーンとしました。
― 変わる、きっと何かが。―
水の底でしか聞こえなかった開幕ベルを、現実に鳴らす事ができる予感が走ります。
人生にはそんな出会いが必ずあるはず。そしてその出会いは強烈でいつまでも自分の中の何かを支配していくものなのかも知れません。文ちゃんのように。それは最後に感じた事なのですが、ゆえにあの神々しさだったのかも知れません。文ちゃんにとっても洋ちゃんにとっても、人生が変わる瞬間だったから。
ヒロポンと言う薬は、かつて聞いたことはあっても漠然としていたので調べてみました。
「疲労がポンと取れるからヒロポン」と言われているんだなどと言う俗説があったようなのですが、これは薬屋さんで売られていた薬のれっきとした名前だったのですね。神経を麻痺させて眠気と疲れを感じなくさせる薬だったのです。最初は軍が深夜出撃の兵士などに使用していたものが戦後には強壮剤として街中に広まってしまったようなのです。
疲れても、まだもうちょっと頑張らなくちゃならない人たち、芸人さんや日雇い労働者の間に広まってしまいました。何しろ薬屋で買えるのですから「ヒロポン、良いでぇ。疲れなんかスッキリ取れるでぇ。」なんて噂を聞いたら、うっかりその罠に嵌る人は多数いたのに違いありません。だけどこの薬は麻薬です。副作用は強い依存性と常習性。そしてその後遺症は何年も後から出てきて、幻覚や妄想に悩まされるとも聞きました。
私たちが知っている有名な芸人さんの中にも、その自叙伝などでヒロポン中毒で苦しんだ事を告白している方もいらっしゃいます。
その薬を打つ為の注射器を持つことによって、6本目の指を持つことになってしまったキティ。
6本目の指は、やっぱり幻をつかむ為のものなのか。
火事の中の鏡の中のブロマイドを掴もうとした話やサフラン座、つまりサフラン病院に舞い戻ってくるキティの話は暗く辛いものがありました。その病院で彼女が摘むサフランの花は一筋の希望だったのかも知れません。
なかなかだったキティと文ちゃんとの二人羽織のダンスや、それにいろいろな意味を込めて思わずクスリと笑った洋ちゃんを加えた三人の歌とダンス、書きたい事はたくさんあります。
だけど他の事は諦めてもやっぱり書いておきたいのは、一気に嵐のように進んだラストへの流れについてだと思います。
キティの強烈な個性とパワーは、時には愛する男を押しつぶしてしまう事があるのかもしれません。
「助けてあげただろ?」
キティは洋一のピンチを救ったと言うのに、洋一はそれでも「自分を返せ」と罵るばかりです。
そして彼は退場。
その後に出てきた時には、既に死んでいて見ている者の心にもポッカリと穴を空けさせてしまうのです。
藤原竜也目当て。
そう言う観客が山のようにいる劇場で、思いもよらず彼の沈黙が訪れるのです。
もう一度立って、動いて、何かしゃべって。
キティの願いは見ている者達の願いのようです。
彼女が取るカウントのなんと悲しい事か。
もちろん彼は蘇りません。
そして台詞なく、文ちゃんが池の中に沈もうと何度も試みるシーンが続きます。
水の底には上演されなかった芝居の開演ベルが鳴る。
時はそこでは逆回転するかのように。
そしてラスト。宮沢りえ、会心の一撃。そんなシーンでした。もしもこのシーンでキティが輝いていなかったら幕を下ろすことができないと思います。
「さあ一緒に行こう、文ちゃん。」
だけれど洋ちゃんはキティの背中で死んだままです。
まるでそれは決して戻る事のできない過去と言う時間のように。
既に消えてしまった下谷万年町のように。
キティはその蘇らない過去を背負った、文ちゃんにとっては、少年の日の女神だったのかも知れません・・・・・・・・・・・・
と、結んだら、感想としても綺麗に纏まると思います。
でも実は本音は違います。
ラストは文ちゃんの過去への憧憬であり妄想なのですから
キティ「行こう、文ちゃん」
洋一「さあ行こう、文ちゃん。」と蘇った洋ちゃんが輪唱のように言い手を差し出しても良かったと思うのです。
それでも蘇らなかった洋一。
それは文ちゃんが洋一の死を目撃していて、キティの死を信じていなかったからと言うだけではなく、それこそが彼の無意識の願望であったからなのではないかと思いました。洋ちゃんと呼んで慕っていた、青年洋一。文ちゃんは洋一の事を本当に好きだったと思います。だけどそこにキティと言う女性が存在するようになった時、少年期の最後を過ごしていた文ちゃんの中には何かが心を突き動かしていたと思いました。ゆえに、洋一は蘇らずキティと言う女神に、背負われて登場すると言う存在であって欲しかったのだと思いました。
そして洋一の死には、死ぬなんて事は思っていなかったにせよ、文ちゃんの何らかの裏切りがあったのではないかと思ってしまったのは、やはり考えすぎと言えるかもしれません。












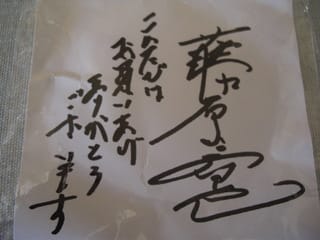



 夫殿曰く。「何でこれが『相棒』なんだ。」私「紅茶&紅茶だからじゃない?」
夫殿曰く。「何でこれが『相棒』なんだ。」私「紅茶&紅茶だからじゃない?」 美味しかったのですが、甘かったです。我が家では4つに切っておやつにちょうど良かったです。
美味しかったのですが、甘かったです。我が家では4つに切っておやつにちょうど良かったです。
 ダイエット
ダイエット 」←、このアイコン返上しようかな。が、しかしなぜか未だにふくよかなワタクシ。なんで?
」←、このアイコン返上しようかな。が、しかしなぜか未だにふくよかなワタクシ。なんで? 家計管理・・・・なのだそうです・・・。
家計管理・・・・なのだそうです・・・。 家中のゴミステと整理整頓
家中のゴミステと整理整頓 お仕事
お仕事 綺麗でいよう&美しいものに拘る。
綺麗でいよう&美しいものに拘る。


 映画
映画 お芝居
お芝居 読書。
読書。 絵画鑑賞、もしくは博物館系のお出掛けは5箇所。まあまあでした。
絵画鑑賞、もしくは博物館系のお出掛けは5箇所。まあまあでした。 「最初に出てきたやつが犯人。」と言いました。
「最初に出てきたやつが犯人。」と言いました。 」
」 ←これは夫。「今の吉田栄作だったよな。」
←これは夫。「今の吉田栄作だったよな。」




