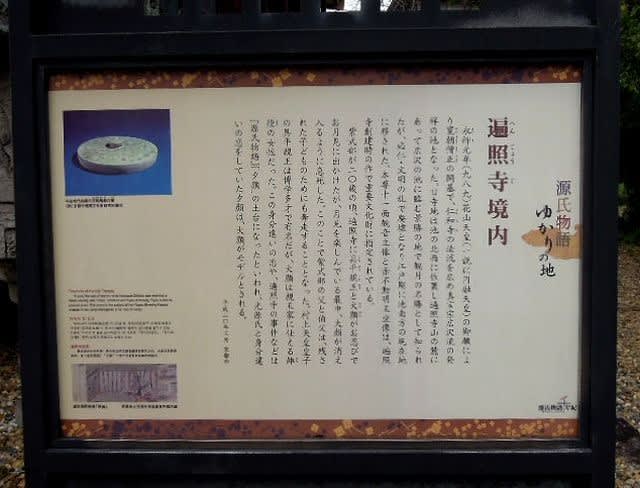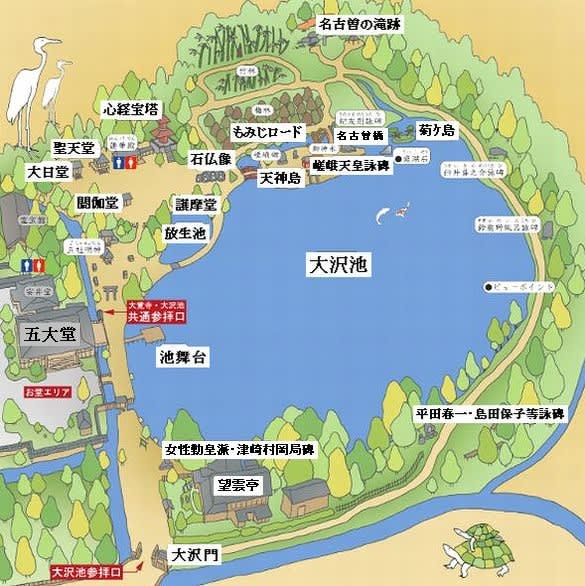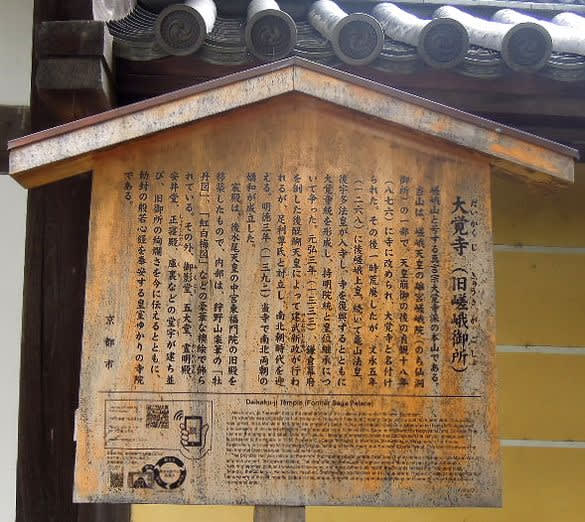② 源光庵「丸い窓のある山門から書院」のつづきです。

書院から見える本殿へ向かいます。

本殿に入る廊下の敷居に
「萬徳殿」の扁額が掲げられています。

そして、本殿の入口から見えたのは
「伏⾒桃⼭城遺構の⾎天井」

本殿に入って右に見えたのは
「悟りの窓」と「迷いの窓」です。
悟りの窓

何事にもとらわれないおおらかな気持ちを
「禅と円通」の心で表しています。
迷いの窓

生きることや病、死ぬことなど日々のさまざまな苦しみの
「人間の生涯」を表しています。
どちらも仏の教えで、枯山水の庭園が見える窓でした。

あれは・・・?
茨木市「総持寺」・伊勢寺・金戎光明寺で見たことがある

少し耳が長いのですが「亀趺(キフ)」だと思います。

血天井 手形跡と

天井いっぱいに見えるのは

本堂の⾎天井は、伏⾒桃⼭城の遺構です。
慶⻑5年7⽉(1600年)徳川家康の忠⾂、⿃居彦右衛⾨元忠⼀党1800⼈が⽯⽥三成の軍 勢と交戦し討死、残る380余⼈が⾃刃したときの恨跡です。

⿃居元忠は「三河武⼠の鑑」と称される武将で
血の付いた床板を供養の為にこちらに移したものです。

ここにも足型跡が・・・
2024年9月度ハイキングで
模擬天守「伏見桃山城」へ行ったことが思い出されます。
京都には、養源院、正伝寺など
いくつかの寺に血天井が移築されていますが
私が血天井を初めて見たのは
2014年11月の「京都 ・大原 宝泉院」でした。

源光庵を後にして「光悦寺(こうえつじ)」にむかいます。

書院から見える本殿へ向かいます。

本殿に入る廊下の敷居に
「萬徳殿」の扁額が掲げられています。

そして、本殿の入口から見えたのは
「伏⾒桃⼭城遺構の⾎天井」

本殿に入って右に見えたのは
「悟りの窓」と「迷いの窓」です。
悟りの窓

何事にもとらわれないおおらかな気持ちを
「禅と円通」の心で表しています。
迷いの窓

生きることや病、死ぬことなど日々のさまざまな苦しみの
「人間の生涯」を表しています。
どちらも仏の教えで、枯山水の庭園が見える窓でした。

あれは・・・?
茨木市「総持寺」・伊勢寺・金戎光明寺で見たことがある

少し耳が長いのですが「亀趺(キフ)」だと思います。

血天井 手形跡と

天井いっぱいに見えるのは

本堂の⾎天井は、伏⾒桃⼭城の遺構です。
慶⻑5年7⽉(1600年)徳川家康の忠⾂、⿃居彦右衛⾨元忠⼀党1800⼈が⽯⽥三成の軍 勢と交戦し討死、残る380余⼈が⾃刃したときの恨跡です。

⿃居元忠は「三河武⼠の鑑」と称される武将で
血の付いた床板を供養の為にこちらに移したものです。

ここにも足型跡が・・・
2024年9月度ハイキングで
模擬天守「伏見桃山城」へ行ったことが思い出されます。
京都には、養源院、正伝寺など
いくつかの寺に血天井が移築されていますが
私が血天井を初めて見たのは
2014年11月の「京都 ・大原 宝泉院」でした。

源光庵を後にして「光悦寺(こうえつじ)」にむかいます。