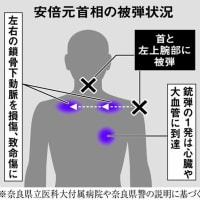●ハイデッガー~存在の探求の中で、「新しい朝」を待望
前の項目に19世紀後半から第1次世界大戦、第2次世界大戦までを一気に書いたが、この危機と不安の時代に、西方キリスト教の神学と哲学の直面する課題に真摯に取り組んだ思想家たちがいる。ハイデッガー、ヤスパース、バルト、ブルトマン、ティリッヒらである。
最初にドイツの哲学者、ハイデッガーとヤスパースから述べたい。
マルティン・ハイデッガーは、1889年に生まれ、1976年に亡くなったドイツの哲学者である。カトリック教会の職員の子として生まれ、大学では、はじめ神学を、次いで哲学を修めた。フッサールのもとでアリストテレス哲学の現象学的解釈に携わり、さらに初期ギリシャ哲学の存在に関する思索を研究し、それによってデカルト以来の近代西洋思想の限界を突破することに取り組んだ。
1914年7月に始まった第1次世界大戦は、近代西洋文明の危機を継げる出来事だった。その危機の時代にハイデッガーは、キルケゴールの実存の哲学に共鳴し、プロテスタントの新約聖書学者ブルトマンと対話を重ねた。またニーチェのニヒリズムの思想を深刻に受け止めつつ、独自の哲学を構築した。
1927年に発表した主著『存在と時間(Sein und Zeit)』は、ドイツを始めとして西欧諸国に大きな衝撃を与えた。Seinには「存在」という訳語が定着しているが、無との対比からいうと「有(う)」の方がふさわしい。本稿では、定訳に従う。
ハイデッガーは、『存在と時間』で、西洋における形而上学の主題である「存在とは何か」という問いを根源的に問い直した。「存在(有ること)」は、ギリシャ哲学で「ト・エオン(to eon)」といい、パルメニデスは万物の始源(アルケー)と考え、アリストテレス以来、存在(on)について考究する学問は存在論(ontology)と呼ばれる。ギリシャ哲学を摂取したキリスト教神学において、存在は唯一神の属性だった。ハイデッガーは、神学的に「神とは何か」と問うのではなく、哲学的に「存在とは何か」と問うた。
本書は、第1部の一部が発表されたのみで、その続きの部分及び第2部は発表されずに終わった。発表された部分の大要は、次のとおりである。
ハイデッガーは、人間を現存在(Dasein)と呼ぶ。現存在は自己の存在を問題とする唯一の存在者であるとして、これを現象学的・解釈学的に分析し、存在者がそこから生じてくる存在に至ろうとする。これが彼の基礎的存在論である。
現存在は他者や事象と関わりながら、現に世界の中に存在し、自分の存在をいかに形成すべきかを気遣いながら存在している存在者である。こうした現存在の存在様式を世界内存在という。また、気遣うべき自己の存在を「実存」という。
現存在は世界の中に投げ出されて、死に向かっている存在である。また、無に直面しておののく不安な存在である。人間は、死にさらされた各自の固有な実存を見つめつつ、自分固有の実存であろうと覚悟して世界内存在する時に、実存の「本来性」が実る。これに反して、不安を回避し、あいまいな日常性に安住して自己の実存に目覚めずにいる状態を、実存の「非本来性」という。
これらの二種の実存は、究極的に、現存在の「時間性」に基づいて出現する。本来性を可能とする時間性は、死へと「先駆」し、自分の既在を「取り返し」ながら、他者や事象との関わりにおいて成り立つ自分の世界内存在の状況を見つめ、そこに立ち入っていこうとするあり方をいう。これに対し、非本来性を出現させる時間性とは、現在の周囲の状態の中に自分を見失って引きずり込まれているあり方をいう。そして、自分の死を先取りすることによって、いっそう強く覚醒された本来性への覚悟と決意が、実存の根底を形作ると指摘している。
第1部の後半では、あらゆる存在の意味了解の地平として時間の現象を取り出すことが予定されていた。また第2部は、存在論史の破壊と名付けられ、伝統的な存在論の基本概念の構造を解体し、かつてその構造の根底に流れていた存在体験の思索的反復を追求しようと構想されていた。
多くのキリスト教徒は、『存在と時間』を読んで死を思う時、死後、天国へ行くか地獄へ行くか、最後の審判で永遠の生命を得るか、永遠の死に至るかを考えるだろう。また、非本来性とは罪によって神から離れている状態であり、神に心を向けて本来性を取り戻すことが信仰だと考えるだろう。だが、ハイデッガーは、もはやそうした伝統的なキリスト教思想を信じていない。『存在と時間』以後、ハイデッガーはキリスト教思想に戻ることなく、独自の思索に沈潜していく。
1930年代のドイツは、ナチスの支配下に置かれた。ハイデッガーは、『存在と時間』の課題を抱えつつ、大きな思想的な転回を行った。その変化は、1935年ごろから顕著になった。転回後の思想を後期思想と呼ぶ。後期のハイデッガーは、言葉を「存在の家」であるとして、ヘルダーリンやリルケなどの詩を手がかりにして、存在の解明に取り組んだ。また、ニーチェの思想を徹底的に読み解き、独自の解釈を深めていった。
後期思想では大要、次のような思想が説かれた。万物の根源である「存在」は、さまざまな「存在者」の姿をとって、おのれを顕わにしながら、自らは「存在者」の陰に隠れてしまう。「存在」は、おのれを隠すという仕方によってしか、おのれを顕わにしない。そのため、人間は、自分の周囲に現れるさまざまな「存在者」の修羅場に眼を奪われて、根源の「存在」を見失い、「存在忘却」に陥ってしまう。この根源の「存在」を見失った迷誤の歴史が、「存在の歴史」である。この歴史のなかに人間は置かれており、現代は、その迷誤の極致にある。根源の「存在」を見失ったまま、人間は、存在者の中心の座を占め、その知と意志において、人間中心主義になり、人間が存在者全体を支配し、収奪しようとしている。この迷誤の「存在の歴史」は、プラトンに始まり、近代以降とりわけデカルトを介して展開し、その結果が、現代の「技術」の時代である。この時代においては、存在者全体が利用し尽くされ、収奪されていき、人間の住まうべき「故郷」が失われる故郷喪失が、世界の運命となる。ハイデッガーは、この存在の故郷を喪失した現代という「夜の時代」を超えて、「新しい朝と始まりの時代」を待望している。
こうしたハイデッガーの後期思想は、詩的・象徴的な言葉で語られている。しかし、「存在」を「神」に置き換えれば、その示唆するものが明らかになってくる。存在とは、西洋哲学史において、神を哲学的な概念で表したものであるから、こうした置換が可能である。そのように置換して読み解くならば、西洋では、キリスト教化された後だけでなく、それ以前の初期ギリシャの時代から、真の神が見失われたまま、歴史が進んできた。その行き着いた先が、現代の科学技術による自然の支配・収奪の文明であり、とりわけ核兵器の脅威にさらされた人類の危機である。ハイデッガー自身は、その真の神を見出し得ていない。だが、彼は、現代という故郷喪失の「夜の時代」に絶望せず、「新しい朝と始まりの時代」の到来を待ち望んだ。夜は光のない闇の世界であり、朝は光の輝く世界である。存在の故郷とは、失われた光の世界であり、朝とは、故郷への帰還の朝である。私は、ハイデッガーの詩的・象徴的な表現を、このように解釈することが可能だと思っている。
ハイデッガーは、キリスト教に新しい朝となる時代の到来を期待していない。聖書の記述を信じるキリスト教徒であれば、イエス=キリスト自身の再臨を待望し、最後の審判の時に臨むところだろう.だが、ハイデッガーは、そうした聖書に基づく信仰をもっていない。また、それに代わる独自の存在論的思考に基づく信仰に達してもいない。この点、次に書くヤスパースがキリスト教を越えた超越者への「哲学的信仰」を表明し、危機にある人類に「信仰と愛」を説いたのとは、異なっている。
次回に続く。
前の項目に19世紀後半から第1次世界大戦、第2次世界大戦までを一気に書いたが、この危機と不安の時代に、西方キリスト教の神学と哲学の直面する課題に真摯に取り組んだ思想家たちがいる。ハイデッガー、ヤスパース、バルト、ブルトマン、ティリッヒらである。
最初にドイツの哲学者、ハイデッガーとヤスパースから述べたい。
マルティン・ハイデッガーは、1889年に生まれ、1976年に亡くなったドイツの哲学者である。カトリック教会の職員の子として生まれ、大学では、はじめ神学を、次いで哲学を修めた。フッサールのもとでアリストテレス哲学の現象学的解釈に携わり、さらに初期ギリシャ哲学の存在に関する思索を研究し、それによってデカルト以来の近代西洋思想の限界を突破することに取り組んだ。
1914年7月に始まった第1次世界大戦は、近代西洋文明の危機を継げる出来事だった。その危機の時代にハイデッガーは、キルケゴールの実存の哲学に共鳴し、プロテスタントの新約聖書学者ブルトマンと対話を重ねた。またニーチェのニヒリズムの思想を深刻に受け止めつつ、独自の哲学を構築した。
1927年に発表した主著『存在と時間(Sein und Zeit)』は、ドイツを始めとして西欧諸国に大きな衝撃を与えた。Seinには「存在」という訳語が定着しているが、無との対比からいうと「有(う)」の方がふさわしい。本稿では、定訳に従う。
ハイデッガーは、『存在と時間』で、西洋における形而上学の主題である「存在とは何か」という問いを根源的に問い直した。「存在(有ること)」は、ギリシャ哲学で「ト・エオン(to eon)」といい、パルメニデスは万物の始源(アルケー)と考え、アリストテレス以来、存在(on)について考究する学問は存在論(ontology)と呼ばれる。ギリシャ哲学を摂取したキリスト教神学において、存在は唯一神の属性だった。ハイデッガーは、神学的に「神とは何か」と問うのではなく、哲学的に「存在とは何か」と問うた。
本書は、第1部の一部が発表されたのみで、その続きの部分及び第2部は発表されずに終わった。発表された部分の大要は、次のとおりである。
ハイデッガーは、人間を現存在(Dasein)と呼ぶ。現存在は自己の存在を問題とする唯一の存在者であるとして、これを現象学的・解釈学的に分析し、存在者がそこから生じてくる存在に至ろうとする。これが彼の基礎的存在論である。
現存在は他者や事象と関わりながら、現に世界の中に存在し、自分の存在をいかに形成すべきかを気遣いながら存在している存在者である。こうした現存在の存在様式を世界内存在という。また、気遣うべき自己の存在を「実存」という。
現存在は世界の中に投げ出されて、死に向かっている存在である。また、無に直面しておののく不安な存在である。人間は、死にさらされた各自の固有な実存を見つめつつ、自分固有の実存であろうと覚悟して世界内存在する時に、実存の「本来性」が実る。これに反して、不安を回避し、あいまいな日常性に安住して自己の実存に目覚めずにいる状態を、実存の「非本来性」という。
これらの二種の実存は、究極的に、現存在の「時間性」に基づいて出現する。本来性を可能とする時間性は、死へと「先駆」し、自分の既在を「取り返し」ながら、他者や事象との関わりにおいて成り立つ自分の世界内存在の状況を見つめ、そこに立ち入っていこうとするあり方をいう。これに対し、非本来性を出現させる時間性とは、現在の周囲の状態の中に自分を見失って引きずり込まれているあり方をいう。そして、自分の死を先取りすることによって、いっそう強く覚醒された本来性への覚悟と決意が、実存の根底を形作ると指摘している。
第1部の後半では、あらゆる存在の意味了解の地平として時間の現象を取り出すことが予定されていた。また第2部は、存在論史の破壊と名付けられ、伝統的な存在論の基本概念の構造を解体し、かつてその構造の根底に流れていた存在体験の思索的反復を追求しようと構想されていた。
多くのキリスト教徒は、『存在と時間』を読んで死を思う時、死後、天国へ行くか地獄へ行くか、最後の審判で永遠の生命を得るか、永遠の死に至るかを考えるだろう。また、非本来性とは罪によって神から離れている状態であり、神に心を向けて本来性を取り戻すことが信仰だと考えるだろう。だが、ハイデッガーは、もはやそうした伝統的なキリスト教思想を信じていない。『存在と時間』以後、ハイデッガーはキリスト教思想に戻ることなく、独自の思索に沈潜していく。
1930年代のドイツは、ナチスの支配下に置かれた。ハイデッガーは、『存在と時間』の課題を抱えつつ、大きな思想的な転回を行った。その変化は、1935年ごろから顕著になった。転回後の思想を後期思想と呼ぶ。後期のハイデッガーは、言葉を「存在の家」であるとして、ヘルダーリンやリルケなどの詩を手がかりにして、存在の解明に取り組んだ。また、ニーチェの思想を徹底的に読み解き、独自の解釈を深めていった。
後期思想では大要、次のような思想が説かれた。万物の根源である「存在」は、さまざまな「存在者」の姿をとって、おのれを顕わにしながら、自らは「存在者」の陰に隠れてしまう。「存在」は、おのれを隠すという仕方によってしか、おのれを顕わにしない。そのため、人間は、自分の周囲に現れるさまざまな「存在者」の修羅場に眼を奪われて、根源の「存在」を見失い、「存在忘却」に陥ってしまう。この根源の「存在」を見失った迷誤の歴史が、「存在の歴史」である。この歴史のなかに人間は置かれており、現代は、その迷誤の極致にある。根源の「存在」を見失ったまま、人間は、存在者の中心の座を占め、その知と意志において、人間中心主義になり、人間が存在者全体を支配し、収奪しようとしている。この迷誤の「存在の歴史」は、プラトンに始まり、近代以降とりわけデカルトを介して展開し、その結果が、現代の「技術」の時代である。この時代においては、存在者全体が利用し尽くされ、収奪されていき、人間の住まうべき「故郷」が失われる故郷喪失が、世界の運命となる。ハイデッガーは、この存在の故郷を喪失した現代という「夜の時代」を超えて、「新しい朝と始まりの時代」を待望している。
こうしたハイデッガーの後期思想は、詩的・象徴的な言葉で語られている。しかし、「存在」を「神」に置き換えれば、その示唆するものが明らかになってくる。存在とは、西洋哲学史において、神を哲学的な概念で表したものであるから、こうした置換が可能である。そのように置換して読み解くならば、西洋では、キリスト教化された後だけでなく、それ以前の初期ギリシャの時代から、真の神が見失われたまま、歴史が進んできた。その行き着いた先が、現代の科学技術による自然の支配・収奪の文明であり、とりわけ核兵器の脅威にさらされた人類の危機である。ハイデッガー自身は、その真の神を見出し得ていない。だが、彼は、現代という故郷喪失の「夜の時代」に絶望せず、「新しい朝と始まりの時代」の到来を待ち望んだ。夜は光のない闇の世界であり、朝は光の輝く世界である。存在の故郷とは、失われた光の世界であり、朝とは、故郷への帰還の朝である。私は、ハイデッガーの詩的・象徴的な表現を、このように解釈することが可能だと思っている。
ハイデッガーは、キリスト教に新しい朝となる時代の到来を期待していない。聖書の記述を信じるキリスト教徒であれば、イエス=キリスト自身の再臨を待望し、最後の審判の時に臨むところだろう.だが、ハイデッガーは、そうした聖書に基づく信仰をもっていない。また、それに代わる独自の存在論的思考に基づく信仰に達してもいない。この点、次に書くヤスパースがキリスト教を越えた超越者への「哲学的信仰」を表明し、危機にある人類に「信仰と愛」を説いたのとは、異なっている。
次回に続く。