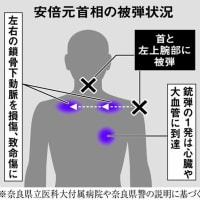●救いと人間の自由意志(続き)
予定説は、パウロに始まりキリスト教の主流をなす考え方となっている。パウロの説は、アウグスティヌスによって整備され、ローマ・カトリック教会で確立された。宗教改革を起こしたルターもこれを継承し、さらにカルヴァンが論理的に徹底した。
予定説は、有神教において、神が人格的であり、かつ人間世界に介入するという超越神の観念のもとでのみ成り立つ救済の原理である。神を立てない無神的宗教では、予定説は成り立たない。これに替わる救済の原理の代表的なものが、因果説である。物事は、原因―条件―結果の関係において起こるという考え方である。
因果説によると、人間は善行・功徳を行うと、それが良い原因になって良い結果をもたらし、救済を得られる。善行を積めばそれだけ救われ、悪行を積めばそれだけ救われなくなるという因果応報の論理に基づく。予定説と因果説は、救済の原理として、全く異なる説である。仏教や道教は因果説である。キリスト教にも、こうした考え方はあるが、少数派である。基本的に、予定説は救いにおける人間の自由意志を認めず、因果説は自由意志を認める。ただし、それらを折衷した中間的な考え方もある。
予定説に立ち、自由意志による救いを否定するパウロの思想は、古カトリック教会に受け継がれた。だが、5世紀の始め、重要な論争が起った。ペラギウスは、神は人間を善なるものとして創造したのであり、原罪は人間の本質を汚すものではない、人間は神からの恩寵を必要とはせず、自分の自由意志で功徳を積むことによって救霊に至ることができると説いた。これに対し、教父アウレリウス・アウグスティヌスは、人間に選択の自由はあるが、選択の自由の中にも神意の采配が宿っており、人間単独の選択では救いの道は開けず、神の恩寵と結びついた選択によってのみ道が開けると説いた。単純に言えば、ペラギウスは人間には自由意志があると主張し、アウグスティヌスは自由意志を否定したことになる。この論争を、ペラギウス論争という。416年のカルタゴ会議、431年のエフェソス公会議でペラギウス主義は異端として排斥された。
ローマ・カトリック教会は、アウグスティヌスの自由意志否定説をもとに救霊予定説を教義として確立した。しかし、異端とされた自由意志を認める考え方が絶えることはなかった。
東方正教会は、西方教会に比べ、より積極的に自由意志を肯定する。オリヴィエ・クレマンは、著書『東方正教会』でその要点を次のように書いている。東方正教会では「神は、自らの生命に預からせるために人間を造られた。神の形を持つ者として、神は人間を造られた。言い換えれば、人格的な存在、自由な存在として人間を造られたのである」と考える。しかし「人間が生の根源である生ける神から離れたこと」によって、「死が現世をおおうようになった。以後、死は神によって創造されたよきものをすべて腐敗させ、宇宙は、人間によって悪魔の目くるめくばかりの破壊の中に投げ込まれてしまった。このように悪とは神から離れていることをいうが、これは人格的存在が自由意志をもって選び取った状態である。つまり、悪とは人間が神の愛を拒み、神の手になる愛をナルシシズム的な愛へと転落させてしまうことである」とクレマンは書いている。「人間は、もはや神へと高まることはできない。そのため、神は自ら人間のもとに降りてこられ、人間になられた」。マリアが神の受肉を受け入れ、イエスが誕生した。「人間は罪に陥り、堕落してしまった。そのため人間が神と一体化し、神化するには、どうしてもキリストによる罪の贖いと苦悩に満ちた救いが必要であった」、「人間を蘇生させるために、神は敢えて死と地獄の苦しみを受けに降りてこられた。この血の十字架を通して、神ははじめて、神と人間とを分け隔てた壁を打ち砕くことができたのである」というのが、クレマンによる東方正教会の教義の核心である。
東方正教会では、西方教会より、積極的に自由意思を肯定するので、人間の努力によって神に近づこうとする修道が発達した。3世紀に聖アントニウスがエジプトで修道生活を行ったのが、修道院のはじめとされる。修道院は、東方で発達した後、西方でも盛んになった。
カトリック教会では、中世になると、修道院が勢力を増していき、修行を含む善行の積み重ねによって救済に至るという考え方が、段々優勢になっていった。ローマ・カトリック教会は、その後、実質的には人間の自由意志を認め、善行や功徳を積むことを奨励している。
中世スコラ学の代表的な学者であるトマス・アクィナスは、救済を得るには人間の努力や善行が必要であるとした。神の恩恵を得て回心する過程において、信仰だけではなく、人間の努力や行為が意味を持つ。また、努力に応じてより高い水準に至るという考え方である。これは、人間の自由意志を認める立場である。自由意志を認めるならば、人間の努力が救いに結び付くという因果説になる。それでいてトマスは予定説を否定していないから、予定説と因果説の折衷であり、一部に因果説を含む予定説になる。
トマスによれば、自由意志を持つ人間は、ただ放っておいても倫理的な行動するわけではない。そこで、不断の指導と援助を与えるものが必要となる。その指導と援助を行うのが、教会である、とトマスは説く。このトマスの教学理論によって、カトリック教会は、救いをもたらす秘蹟の権威の強化、教会や修道院の規範の厳格化を進めた。その結果、絶対的な権威と権力を持つに至った。だが、それによってまた腐敗・堕落の道を下って行くことにもなった。その下降の行き着く先が、免罪符の発行である。免罪符を購入すれば、天国に行けるという教えは、16世紀のヨーロッパでマルティン・ルターから厳しい批判を受け、西方キリスト教における宗教改革を引き起こすことになった。
ルターは、修道院で厳しい修行を行った。だが、どれほど厳しい修行を行っても、修行では救いは得られないと認識した。そして、救いはただ神の恩寵によるという考え方に至った。人文主義者でカトリックの神学者のデジデリウス・エラスムスが『自由意志論』を著して自由意志を肯定する主張をすると、ルターは『奴隷意志論』を公表して、人間は奴隷と同じで人間の意志の自由など一切ないと説いた。ルターは、人間に意志の自由があるという説は、ペラギウスの説と同じであり、到底、容認できないと反駁した。
ルターは神の絶対性を強調することにより、人間の自由意志を否定した。救済は、人間の善行・功徳によって得られるのではなく、全く神の意思によるとした。ルターはパウロ以来の予定説を継承し、救済における因果説を否定した。これは、ローマ・カトリック教会が古代においてはパウロ=アウグスティヌスの救霊予定説を教義としていながら、中世においてはトマス・アクィナスが因果説と予定説を折衷した教義に変化していたことへの反論ともなっている。
ルターの予定説を極限まで進めたのが、ジャン・カルヴァンである。カルヴァンは、ルターの考え方は不十分だとし、予定説を論理的に徹底した。予定説は、神は予めすべての人間を、ある者は救いに、ある者は滅びに予定したとするが、カルヴァン以前の予定説は、アダムとエバは自由意志によって原罪を犯したのであり、予定は堕罪後の人間に関するものとする。これを堕罪後予定説という。これに対し、カルヴァンは、アダムとエバが原罪を犯したことも神が予定していたことだとする。これを堕罪前予定説という。二重に予定されていたと考えるので、二重予定説ともいう。
カルヴァンが予定説を徹底して堕罪前予定説を説いたのは、堕罪後予定説では神はアダムとエバが罪を犯すことを前もって知らなかったことになり、神の全知が否定されるからである。堕罪前予定説には、全知全能の神ゆえ、堕罪も予定していたとして論理的な一貫性がある。しかし、この説は、神の絶対性を強調するあまり、人間の自由意志を完全に否定することになる。
カルヴァンによると、神は死後永遠の生命を与える人間をすでに選び、他の人間は永遠の死滅に予定した。誰が選ばれているかは、神のみぞ知る。自分が選ばれた人間かどうかは、誰にもわからない。そのうえ、この世における人間の努力は、神の救いを得るためには一切関係ない。つまり人間が神の決定を変えることは、絶対に不可能とカルヴァンは考えた。それは天地創造の時に、予め決まっているのである。カルヴァンによれば、「人間のとるべき態度は、ただこの鉄の必然性たる神の意志に服従するだけ」である。この説に従う場合、イエス・キリストの選びを信じる以外に安心は得られない。
カルヴァンの予定説では、人間は「救われる者」と「救われない者」とに、このうえなく不平等に創造されていることになる。敬虔崇高な善人が救済されず、悪逆非道の悪人が救済されることもあり得る。それほどまでに神を超越的で絶対的な存在とし、また人間を無力なものと考えるのが、カルヴァンの予定説である。
次回に続く。
予定説は、パウロに始まりキリスト教の主流をなす考え方となっている。パウロの説は、アウグスティヌスによって整備され、ローマ・カトリック教会で確立された。宗教改革を起こしたルターもこれを継承し、さらにカルヴァンが論理的に徹底した。
予定説は、有神教において、神が人格的であり、かつ人間世界に介入するという超越神の観念のもとでのみ成り立つ救済の原理である。神を立てない無神的宗教では、予定説は成り立たない。これに替わる救済の原理の代表的なものが、因果説である。物事は、原因―条件―結果の関係において起こるという考え方である。
因果説によると、人間は善行・功徳を行うと、それが良い原因になって良い結果をもたらし、救済を得られる。善行を積めばそれだけ救われ、悪行を積めばそれだけ救われなくなるという因果応報の論理に基づく。予定説と因果説は、救済の原理として、全く異なる説である。仏教や道教は因果説である。キリスト教にも、こうした考え方はあるが、少数派である。基本的に、予定説は救いにおける人間の自由意志を認めず、因果説は自由意志を認める。ただし、それらを折衷した中間的な考え方もある。
予定説に立ち、自由意志による救いを否定するパウロの思想は、古カトリック教会に受け継がれた。だが、5世紀の始め、重要な論争が起った。ペラギウスは、神は人間を善なるものとして創造したのであり、原罪は人間の本質を汚すものではない、人間は神からの恩寵を必要とはせず、自分の自由意志で功徳を積むことによって救霊に至ることができると説いた。これに対し、教父アウレリウス・アウグスティヌスは、人間に選択の自由はあるが、選択の自由の中にも神意の采配が宿っており、人間単独の選択では救いの道は開けず、神の恩寵と結びついた選択によってのみ道が開けると説いた。単純に言えば、ペラギウスは人間には自由意志があると主張し、アウグスティヌスは自由意志を否定したことになる。この論争を、ペラギウス論争という。416年のカルタゴ会議、431年のエフェソス公会議でペラギウス主義は異端として排斥された。
ローマ・カトリック教会は、アウグスティヌスの自由意志否定説をもとに救霊予定説を教義として確立した。しかし、異端とされた自由意志を認める考え方が絶えることはなかった。
東方正教会は、西方教会に比べ、より積極的に自由意志を肯定する。オリヴィエ・クレマンは、著書『東方正教会』でその要点を次のように書いている。東方正教会では「神は、自らの生命に預からせるために人間を造られた。神の形を持つ者として、神は人間を造られた。言い換えれば、人格的な存在、自由な存在として人間を造られたのである」と考える。しかし「人間が生の根源である生ける神から離れたこと」によって、「死が現世をおおうようになった。以後、死は神によって創造されたよきものをすべて腐敗させ、宇宙は、人間によって悪魔の目くるめくばかりの破壊の中に投げ込まれてしまった。このように悪とは神から離れていることをいうが、これは人格的存在が自由意志をもって選び取った状態である。つまり、悪とは人間が神の愛を拒み、神の手になる愛をナルシシズム的な愛へと転落させてしまうことである」とクレマンは書いている。「人間は、もはや神へと高まることはできない。そのため、神は自ら人間のもとに降りてこられ、人間になられた」。マリアが神の受肉を受け入れ、イエスが誕生した。「人間は罪に陥り、堕落してしまった。そのため人間が神と一体化し、神化するには、どうしてもキリストによる罪の贖いと苦悩に満ちた救いが必要であった」、「人間を蘇生させるために、神は敢えて死と地獄の苦しみを受けに降りてこられた。この血の十字架を通して、神ははじめて、神と人間とを分け隔てた壁を打ち砕くことができたのである」というのが、クレマンによる東方正教会の教義の核心である。
東方正教会では、西方教会より、積極的に自由意思を肯定するので、人間の努力によって神に近づこうとする修道が発達した。3世紀に聖アントニウスがエジプトで修道生活を行ったのが、修道院のはじめとされる。修道院は、東方で発達した後、西方でも盛んになった。
カトリック教会では、中世になると、修道院が勢力を増していき、修行を含む善行の積み重ねによって救済に至るという考え方が、段々優勢になっていった。ローマ・カトリック教会は、その後、実質的には人間の自由意志を認め、善行や功徳を積むことを奨励している。
中世スコラ学の代表的な学者であるトマス・アクィナスは、救済を得るには人間の努力や善行が必要であるとした。神の恩恵を得て回心する過程において、信仰だけではなく、人間の努力や行為が意味を持つ。また、努力に応じてより高い水準に至るという考え方である。これは、人間の自由意志を認める立場である。自由意志を認めるならば、人間の努力が救いに結び付くという因果説になる。それでいてトマスは予定説を否定していないから、予定説と因果説の折衷であり、一部に因果説を含む予定説になる。
トマスによれば、自由意志を持つ人間は、ただ放っておいても倫理的な行動するわけではない。そこで、不断の指導と援助を与えるものが必要となる。その指導と援助を行うのが、教会である、とトマスは説く。このトマスの教学理論によって、カトリック教会は、救いをもたらす秘蹟の権威の強化、教会や修道院の規範の厳格化を進めた。その結果、絶対的な権威と権力を持つに至った。だが、それによってまた腐敗・堕落の道を下って行くことにもなった。その下降の行き着く先が、免罪符の発行である。免罪符を購入すれば、天国に行けるという教えは、16世紀のヨーロッパでマルティン・ルターから厳しい批判を受け、西方キリスト教における宗教改革を引き起こすことになった。
ルターは、修道院で厳しい修行を行った。だが、どれほど厳しい修行を行っても、修行では救いは得られないと認識した。そして、救いはただ神の恩寵によるという考え方に至った。人文主義者でカトリックの神学者のデジデリウス・エラスムスが『自由意志論』を著して自由意志を肯定する主張をすると、ルターは『奴隷意志論』を公表して、人間は奴隷と同じで人間の意志の自由など一切ないと説いた。ルターは、人間に意志の自由があるという説は、ペラギウスの説と同じであり、到底、容認できないと反駁した。
ルターは神の絶対性を強調することにより、人間の自由意志を否定した。救済は、人間の善行・功徳によって得られるのではなく、全く神の意思によるとした。ルターはパウロ以来の予定説を継承し、救済における因果説を否定した。これは、ローマ・カトリック教会が古代においてはパウロ=アウグスティヌスの救霊予定説を教義としていながら、中世においてはトマス・アクィナスが因果説と予定説を折衷した教義に変化していたことへの反論ともなっている。
ルターの予定説を極限まで進めたのが、ジャン・カルヴァンである。カルヴァンは、ルターの考え方は不十分だとし、予定説を論理的に徹底した。予定説は、神は予めすべての人間を、ある者は救いに、ある者は滅びに予定したとするが、カルヴァン以前の予定説は、アダムとエバは自由意志によって原罪を犯したのであり、予定は堕罪後の人間に関するものとする。これを堕罪後予定説という。これに対し、カルヴァンは、アダムとエバが原罪を犯したことも神が予定していたことだとする。これを堕罪前予定説という。二重に予定されていたと考えるので、二重予定説ともいう。
カルヴァンが予定説を徹底して堕罪前予定説を説いたのは、堕罪後予定説では神はアダムとエバが罪を犯すことを前もって知らなかったことになり、神の全知が否定されるからである。堕罪前予定説には、全知全能の神ゆえ、堕罪も予定していたとして論理的な一貫性がある。しかし、この説は、神の絶対性を強調するあまり、人間の自由意志を完全に否定することになる。
カルヴァンによると、神は死後永遠の生命を与える人間をすでに選び、他の人間は永遠の死滅に予定した。誰が選ばれているかは、神のみぞ知る。自分が選ばれた人間かどうかは、誰にもわからない。そのうえ、この世における人間の努力は、神の救いを得るためには一切関係ない。つまり人間が神の決定を変えることは、絶対に不可能とカルヴァンは考えた。それは天地創造の時に、予め決まっているのである。カルヴァンによれば、「人間のとるべき態度は、ただこの鉄の必然性たる神の意志に服従するだけ」である。この説に従う場合、イエス・キリストの選びを信じる以外に安心は得られない。
カルヴァンの予定説では、人間は「救われる者」と「救われない者」とに、このうえなく不平等に創造されていることになる。敬虔崇高な善人が救済されず、悪逆非道の悪人が救済されることもあり得る。それほどまでに神を超越的で絶対的な存在とし、また人間を無力なものと考えるのが、カルヴァンの予定説である。
次回に続く。