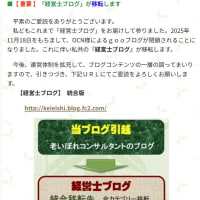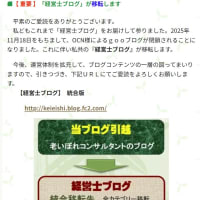■【心 de 経営】『書話力』を高める3-7111 テーマの選び方・話し方は目的に応じて変わる

*
私には、「正しい日本語」とはなにか、というようなことを書いていくだけのバックグラウンドがあるわけではありません。一方で、人前でお話をする機会が多々あります。少しでも「美しい日本語ですね」と言われるような言い方をしたいと平素からこころがけています。
経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。
経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

■【あたりまえ経営のすすめ】3 すべてのコンサルタント・士業、ビジネスパーソンがめざす一歩上の発想とスキル
時代に即したスキルを磨きながら、業務に活かし、自分の更なる成長に繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。その方法は、多岐にわたると思います。
「あたりまえ経営のきょうか書」シリーズの第三章として、経営コンサルタントという仕事を通して、感じてきたことを、ビジネスパーソンに共通する面を中心にお話しています。
しかし、このコーナーは、もともとはコンサルタント・士業などの経営の専門家向けに執筆したものですので、その論調になっています。ビジネスパーソンの皆様には、それを踏まえてお読みくださるようお願いします。

■7110 〃話のタネ〃 テーマ・話材の選び方
ロジカル・ライティングを基本に「書話力」についてお話しています。
その書話力の基本を体得できましたら、次は、実際に取り組んでみましょう。それには「何について書くのか」という原点に戻った思考が不可欠です。

ロジカル・ライティングを基本に「書話力」についてお話しています。
その書話力の基本を体得できましたら、次は、実際に取り組んでみましょう。それには「何について書くのか」という原点に戻った思考が不可欠です。

■7111 テーマの選び方・話し方は目的に応じて変わる
ビジネス界では、『時間要素』ということを常に意識していなければなりません。多忙で、毎日、時間と競争している人が多いからです。
相手が結論を急ぐ人の場合には、既述の通り、まず結論を端的に話し、持ち時間に応じて説明の濃度を変えて話すということは基本でしょう。
相手の理解度に応じても、話す内容やレベルを考える必要があります。一般的な幼稚園の子供に対して話す場合と、専門性に長けた人に話す場合には大きく異なります。このように、相手に応じて、話し方やその内容、ストーリ順序、強調点などは異なってきます。
*
聞き手側が表現豊かであったり、感覚の鋭い人であったりするときに、私が利用するのは、「相手がイメージ化・映像化しやすい表現法」というやり方です。
それは、聞き手の五感に繋がるように表現することです。例えば、「やや大きめの緑色のナットで締め付けてあるので、ナットが緩むことはほとんどありません」というように、私達がしばしば表現するような説明で終わらせないことです。
「やや大きめの緑色のナット」ではなく、「経が12mmの六角で、厚みは3mmと薄く、若葉にくすみをかけたような、本体と同系色で目立たないようなメッキをしたナット」というように視覚や精度の解るデータを付加して話します。
後半部分も、「トルクレンチで所定の○○の締め圧で、ダブルナット締めをし、逆絞めトルクは△△にして絞めてありますので、ナットに緩みが出る確率は1%もありません」というようにします。説明は少々長くなりますが、故障回避や精度を出すために、細心の配慮をしていますと言うことを言外に伝えた表現法で成功している某精密機器メーカーもあります。
このナットの表面はピカピカで、指を近づけるとそれが映るほどです。しかし、なぜピカピカにしているのか、その会社の技術者は、その場では、あえて説明をしません。お客様が、「なぜ、そのようにピカピカにメッキをかけるのですか」と質問が出てから始めて、自分の作戦に引っかかってきたなと内心思いながら、その目的・効能を話していました。
このメーカーの技術者ように、五感やデータで話をするというのは相手に信頼感を持っていただけます。五感でも、例えば、形状や大きさ、材質、色をはじめ、データにも結びつけながら話すことにより、相手の受ける印象や理解度は大きく異なってきます。相手が、そのような詳細なデータを望んでいない場合には、「ナットを二重にして締め付け方向を逆にして、締め付けが緩まないようにしているのですよ」などと軽く流せば良いのです。
ビジネス界では、『時間要素』ということを常に意識していなければなりません。多忙で、毎日、時間と競争している人が多いからです。
相手が結論を急ぐ人の場合には、既述の通り、まず結論を端的に話し、持ち時間に応じて説明の濃度を変えて話すということは基本でしょう。
相手の理解度に応じても、話す内容やレベルを考える必要があります。一般的な幼稚園の子供に対して話す場合と、専門性に長けた人に話す場合には大きく異なります。このように、相手に応じて、話し方やその内容、ストーリ順序、強調点などは異なってきます。
*
聞き手側が表現豊かであったり、感覚の鋭い人であったりするときに、私が利用するのは、「相手がイメージ化・映像化しやすい表現法」というやり方です。
それは、聞き手の五感に繋がるように表現することです。例えば、「やや大きめの緑色のナットで締め付けてあるので、ナットが緩むことはほとんどありません」というように、私達がしばしば表現するような説明で終わらせないことです。
「やや大きめの緑色のナット」ではなく、「経が12mmの六角で、厚みは3mmと薄く、若葉にくすみをかけたような、本体と同系色で目立たないようなメッキをしたナット」というように視覚や精度の解るデータを付加して話します。
後半部分も、「トルクレンチで所定の○○の締め圧で、ダブルナット締めをし、逆絞めトルクは△△にして絞めてありますので、ナットに緩みが出る確率は1%もありません」というようにします。説明は少々長くなりますが、故障回避や精度を出すために、細心の配慮をしていますと言うことを言外に伝えた表現法で成功している某精密機器メーカーもあります。
このナットの表面はピカピカで、指を近づけるとそれが映るほどです。しかし、なぜピカピカにしているのか、その会社の技術者は、その場では、あえて説明をしません。お客様が、「なぜ、そのようにピカピカにメッキをかけるのですか」と質問が出てから始めて、自分の作戦に引っかかってきたなと内心思いながら、その目的・効能を話していました。
このメーカーの技術者ように、五感やデータで話をするというのは相手に信頼感を持っていただけます。五感でも、例えば、形状や大きさ、材質、色をはじめ、データにも結びつけながら話すことにより、相手の受ける印象や理解度は大きく異なってきます。相手が、そのような詳細なデータを望んでいない場合には、「ナットを二重にして締め付け方向を逆にして、締め付けが緩まないようにしているのですよ」などと軽く流せば良いのです。


■ バックナンバー
© copyrighit N. Imai All rights reserved