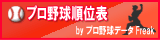東京新聞「ふくしま作業員日誌」には泣ける…
【政治・経済】
お盆も休めず、熱中症も続出

福島第1原発で働く作業員たちに社会部の記者がじかに取材し、必死に収束作業に当たっている彼らの肉声をつづった不定期連載。11年8月に始まり、すでに60回を超えている。たとえば、こんな感じだ。
〈子どもに被ばくの影響が出るかもしれないと言っても、結婚してくれる人はいるだろうか。被ばくのことを話すと、みんな逃げる〉(29歳男性作業員=6月29日付)
生々しい本音が語られていて、伝わるものがあるのだが、中でも、15日の44歳男性作業員の話は響いた。
〈今年もお盆は休めない。東京電力からは「急いで作業をしてくれ」と言われている。(中略)でも熱中症は続出しているし、工程表通りに進まないからと、現場を急がせるのはどうなのか〉
〈「休んでいる場合じゃない。とにかく世間にやっているのを見せろ」と言われてきた〉
〈俺も(津波で)親戚を失った。(中略)お盆には亡くなった人が戻ってくるかもしれない。お盆ぐらい仕事を休み、故郷で墓参りをしたい〉
ふだん作業に当たっている約3000人の作業員たちも人の子。自然な感情だろうが、ひとつ、気になった。〈熱中症は続出〉のくだりだ。猛暑で過酷な作業を強いられたら、バタバタ倒れても不思議はない。東電広報担当者が言う。
「18日までお盆期間で、今は約1100人が作業に当たっています。一昨年に23人、昨年は7人が熱中症で医療行為を受けた反省を踏まえ、今年は午後2時から5時まで作業を休止するなど、熱中症対策も取っています。今年は7月24日までに2人。続出? それは作業員さんの感覚でしょう。8月のデータ? 7月24日までのものが最新です」
44歳男性作業員の話とは、かなり違う。
ゲンダイネットより