




東京の門松は松と竹だけですっきりしていました。
そういえば、新春の六本木ヒルズのイベントでにみんなで歌った「1月1日」の歌詞にも、
年のはじめの ためしとて
終わりなき世の めでたさを
松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ たのしけれ
とあるし、元々、松と竹だったのでしょう。
ビルなどに飾られた立派なものばかりではなく、家や船に若松の枝が飾られているのがいい感じでした。


門松(かどまつ)は、お正月に家の門の前などに立てられる一対になった松や竹の正月飾りのことですが、古くは、木のこずえに神が宿ると考えられていたことから、門松は年神を家に迎え入れるための依り代という意味合いがあったそうです。
新年に松を家に持ち帰る習慣は平安時代にはじまり、室町時代に現在のように玄関の飾りとする様式が決まったといわれています。
名古屋熱田神宮の「熱田祭典年中行事図絵」が、門松のはじまりのようすとして、NHKテレビのあさイチで紹介されていました。


注連飾りと餅花はすこし華やかでした。

広島の門松は、竹は3本か5本、松の下に、梅、南天、紅白の葉牡丹などを植え込んだものが多いようです。


















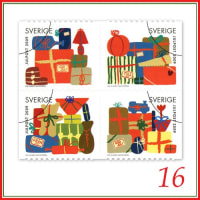

ユミさんとこで紹介されてた熊手とか、お飾りとか繭玉とか、昔からの日本らしいお祝い事を彩る素敵なものっていいですよね。
少し、気持ちが引き締まる嬉しさというか。
1月1日。。。恥ずかしながら、初めてタイトルと正確な歌詞を知りました。なるほど。。。
私はシンプルな東京の門松になれていますが
広島の門松は華やかなんですね~
銀座はこの前までクリスマスデコレーションが華やかだったので お色直しが大変なのかもしれませんね
(*^_^*)
歌にあるように竹と松なんですね。
粋です。
地域によって違うので面白いですね。
昔は必ず家の門や車にもついてたけど…
今はお店などにしか飾られていませんね。
こうして色々見るとお正月気分が蘇ってきます♪
やっぱメイさんのお着物いいわぁー☆
最後のフォトの門松が見慣れてます、島根もこんな感じです
雪が降ったら南天の実を目にした雪ウサギを何個も作った思い出があります~
門松から取ってしまって親に怒られたことも(笑)
和さんのお家の方ではどんな門松なのでしょう。
関西圏で生まれ育っているので、東京のシンプルなのが新鮮でした。
ユミさんのところでは熊手が紹介されていましたね。
1月1日の作詞者は出雲大社宮司の千家尊福(せんげたかとみ)さんです。
>すのさん
お正月を東京で過ごしたのがはじめてでしたので、シンプルな門松が新鮮でした。
各地でいろいろなバリエーションがあるのでしょうね。
外国ではクリスマスツリーは年明けまで飾られていますが、日本はあわただしいですよね。
>Donnさん
粋でいなせな江戸の文化が引き継がれているんですね。
熱田神宮の昔の絵の様式もいいですね、もし、再現されたら見に行きたいです。
>まーく2さん
つい最近までお飾りを車にもつけて走っていましたが、ほとんど見なくなりました。
注連飾りは地方によってずいぶん違いがありますが、門松はほとんど同じだと思っていました。
うふふ、メイの着物は縮緬の生地に助けられていますね、古い本絹です。
>アゲハ母さん
関西から西の方は大体紅白の葉牡丹を植え込みますね、島根県もそうなのですね。
雪うさぎの目に南天の実を使うとかわいいですね。
お正月にはゆで卵で雪うさぎを作っていましたが、そのときは人参を小さく切って目にして、南天の葉を耳にしていました。
仕事終わった後にマラソンで夜の熱田神宮へお参りして帰ったのを思い出しました。
僕の主観ですが東京の門松はなんとなく職人さんの香りがしますね。広島の門松はお花屋さんが作ったのかなと思うくらいアレンジというか華やかです。
船に付けてある「松」にまで気づくなんてやはりjunさんはアンテナの張り方が違いますね☆
熱田神宮のお近くにも住んでらしたのですね。
夜の熱田神宮はさぞ神秘的だったことでしょう。
おーしおさんのおっしゃるとおり、たしかに東京の門松は職人さんの香りがしますね。
船の松、心意気ですよね、六本木ヒルズでは、囲いに使う工事用のコーンにも小さな注連縄がかけてありました。
小さな注連飾りはつい最近まで、この辺りでも車や自転車につけて走っていましたね。