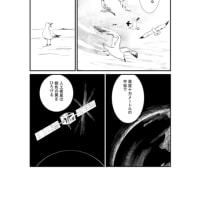「この家は古いですが普請はしっかりしているんですよ。あと二十年はこのままで大丈夫でしょう」
漁師は申し訳なさそうにごま塩の頭を振った。
「そうですか。もし、このさきリフォームをお考えの時は、どんな小さな改修でも結構です。ぜひ当社をよろしくお願いします」
パンフレットや仮申し込みの書面を鞄に戻して、麻子は立ち上がった。
彼女は工務店の営業職だ。とび込みで入った一軒だった。
「お父さん、磯のほうへ遊びに行ってもいい?」
奥の引き戸のかげから小さな女の子が顔をのぞかせた。
下校してきたばかりらしく、背中から下ろしたランドセルを提げている。
「潮だまりの深い場所へは近づかないようにな」
網を繕う手を動かしはじめた漁師に、麻子はもう一度頭を下げて、扇風機が大きな音を立てている土間から外へ出た。
赤松の林の山が迫った道は半分が影になっていた。日の当たる家には洗濯物が干されている。軽自動車のなかで日報をつけ終わった麻子は、磯へ行ってみる気になった。さっきちらっと見ただけの女の子を、ちゃんと見てみたい気がしたのである。どうしてかはわからない。
灯台の立っている岬の下が岩場の磯だった。笹色の海をながめていると波音にさそわれているような気がした。
子供たちが遊んでいて、中に女の子も二人混じっていたが、あの髪の長い子は見当たらなかった。
カニを追っていたらしい年長の男の子が、岩の割れ目に手を突っ込んだまま首をかしげてこちらへ怪訝そうな目を向けてきたので、麻子は散歩のふりをして波打ち際を歩いた。
十分ほど待ってみたが、あの子は現れなかった。麻子はがっかりしたが、その落胆は自分でも意外なほどだった。
カニを捕まえた男の子がみんなに自慢している。ほかの子は感心したり水を掛け合ったりしていた。
子供の頃の麻子はしあわせではなかった。楽しい記憶もあまりない。小学二年のときに突然警察が家に来て父親を連れていった。傷害罪での逮捕だったが、のちに被害者が亡くなったので殺人罪になった。母に連れられて家を出、別の町で暮らすことになったが、それきり父とは会っていない。
車へ向かう足元で浜昼顔が風にふるえていた。
麻子は下請け会社の作業員を連れて、クレーム処理に来ていた。
個人宅の工事で、中年夫婦は外壁の色あいが見本と少しちがっているなどと文句をつけ、外構の基礎にセメントの粉がこぼれているのを見つけると勝ち誇ったように工事がずさんだと言い立てた。しまいには全額の工事代金は払えないと一方的に宣言した。
こうした顧客の身勝手に、麻子は慣れっこになっていた。
「工事を中止して足場を全部外してちょうだい」
「個人宅のもめごとでそこまでするなんて、上が許可を出さないんじゃないですか」
作業員がおどろいて目をみはった。
「あなたは下請け会社の人間でしょ、これはわたしの会社が請けた工事なのよ」
あわてた作業員はポケットから携帯電話を取り出した。「そうなんだ、元請けさんの意向だから、明日にでも撤去に取り掛かってくれ」
顧客ははじめは人当たりの良いおだやかな夫婦に見えたものだったが、工事が進むにつれて人が変わった。こうした人間が世間にはおどろくほど多い。麻子は人を信用するということができなくなっていた。
恋人の矢代に呼び出されたのは、ホテルの二階のフランス料理店だった。官庁勤めの会計士だ。話は、沖縄の役所に再就職することになった。結婚して一緒についてきてくれ幸せにするから。というものだった。
テーブルに置かれたキャンドルで、神経質そうな細い顔にかけた眼鏡が光っていた。
「わたしは行かないわ」
「どうしてだい?」
戸惑った顔の恋人の質問にこたえず、麻子は料理に口をつけた。
矢代がほかの女の子とも付き合っていたことを、麻子は知っていた。ひとりは営業所の契約社員だ。髪を染めた華やかな子だ。通勤には親が買ってくれたというアクセラの赤いセダンを使っている。自分とはまったくタイプのちがう子だった。
小さいころから生きることだけで精一杯だった。殺人犯の家族が母子二人で身寄りのない世間に暮らしてきたのだ。
矢代は麻子を説得しようとさかんに声をかけていたが、麻子の耳には入らなかった。おいしいものを自分だけが食べてはもうしわけないわ、母さんにはデパートの地下で何か買って帰ろう。そんなことを考えていた。
タクシー乗り場にいると、ホテルの駐車場から出てきた矢代が、軽くクラクションを鳴らして道路へ出て行った。
ホテルの前にはオフィスやいろいろな店の入ったビルが立ち並んでいて、夜にも関わらず街路樹のアカシアの葉が緑に輝いていた。ブティックや居酒屋、一つ一つの看板の字が鮮やかだった。矢代とはもう会うことはないだろう。結婚の申し出を断り、別れを告げた。とくにさびしいという気持ちはなかった。
ほかの社員に聞こえるようにという思惑にちがいなかった。西山営業所長はことさら声を大きくしていた。
「独断で工事をやめさせたのは規則違反だ。わかるね。今度からは会議に諮ってから決めるように」
部屋のなかがしんとなったのを見計らって、こんどは楽しそうに喉を鳴らした。
「たてまえは以上の通りだ。みんなも規則を守るよう心掛けて仕事をしてくれ。ところで瀬川麻子君、あの夫婦はささいなことで本社のほうにまでしつこく電話をかけてきていて応対の者が参っていたのだ。お得意様気取りの勘違い夫婦にはきみのとった処置はよく効いただろうよ。よくやったとは言わないがね」
西山所長は社員の蔭口によれば暴君である。着任して三年だがその間に売り上げを二倍に伸ばした。自分の方針に一切妥協することなく社員を統率したのである。麻子は所管の役所との折衝の仕方や許可の取り方、下請けの扱い方まで一から叩き込まれた。おかげで本社の研修では最優秀の表彰を受けることになった。西山は麻子にとって、ただ一人、信用できる人間だった。
「それから、きみを課長補佐にするよう推薦しておいた。飯田橋の次長が下に置きたいと言ってきてるんだがそれでもいいだろう。とにかく昇進だ。おめでとう。ほかの土地へ移りたくなかったらこのまま俺の下にいてかまわない。以上だ」
暴君にはかなわない。西山のあごが角張って筋肉の盛り上がっているのは、いつも唇を引き結んでいるせいかしらとおもった。
まもなく辞令が出て、麻子には所長室に近い場所にデスクが与えられた。肩書が上がっても、麻子は外回りの営業に進んで出た。
車でも徒歩でも走るのが好きだった。新しい景色へ切り込んで行くとき、快いスリルを感じた。つねに刺激を求めながら、しかし一方で、ときどき、自分が遠い過去に忘れてしまったものを探しているような気がするのがふしぎだった。
漁師町を再訪して、あの女の子の家をたずねてみた。土間は開いていたが家人の気配はなかった。今日は遠くまで漁にでかけたらしい。
郵便局の赤いポストのところまで引き返してくると、風に乗って子供たちの歓声が聞こえた。灯台近くの磯までは日除けを掛けた八百屋の脇の道を下りればずぐだった。
砂浜の波打ち際に、岩場で遊んでいるほかの子供たちとはなれて、あの子がいた。
紺色の水着を着て立っている。夕日に当たって、顔をオレンジ色にかがやかせ、背中まである髪がゆれていた。
近づいて行くと無邪気なようすで麻子に正面を向けた。
「こんにちは、お名前なんて言うのかな」
自然にそうきいていた。
「吉岡えり」
「そう、えりちゃんていうの。いいお名前ね」
女の子は照れた顔でうなずいてみせると、友達の大勢いる岩場へ駆けて行った。
一度だけ母に連れられて、父親が収監されている刑務所に出かけたことがあった。待つように言われ、雨の降るバス停で一人、高い塀に囲まれた大きな建物へ肩を落として入って行った母が戻るのを、いつまでも待っていた気がする。
あの子はえりだったが、父が逮捕される前の楽しかった頃の自分にちがいないと麻子は思っていた。
漁師は申し訳なさそうにごま塩の頭を振った。
「そうですか。もし、このさきリフォームをお考えの時は、どんな小さな改修でも結構です。ぜひ当社をよろしくお願いします」
パンフレットや仮申し込みの書面を鞄に戻して、麻子は立ち上がった。
彼女は工務店の営業職だ。とび込みで入った一軒だった。
「お父さん、磯のほうへ遊びに行ってもいい?」
奥の引き戸のかげから小さな女の子が顔をのぞかせた。
下校してきたばかりらしく、背中から下ろしたランドセルを提げている。
「潮だまりの深い場所へは近づかないようにな」
網を繕う手を動かしはじめた漁師に、麻子はもう一度頭を下げて、扇風機が大きな音を立てている土間から外へ出た。
赤松の林の山が迫った道は半分が影になっていた。日の当たる家には洗濯物が干されている。軽自動車のなかで日報をつけ終わった麻子は、磯へ行ってみる気になった。さっきちらっと見ただけの女の子を、ちゃんと見てみたい気がしたのである。どうしてかはわからない。
灯台の立っている岬の下が岩場の磯だった。笹色の海をながめていると波音にさそわれているような気がした。
子供たちが遊んでいて、中に女の子も二人混じっていたが、あの髪の長い子は見当たらなかった。
カニを追っていたらしい年長の男の子が、岩の割れ目に手を突っ込んだまま首をかしげてこちらへ怪訝そうな目を向けてきたので、麻子は散歩のふりをして波打ち際を歩いた。
十分ほど待ってみたが、あの子は現れなかった。麻子はがっかりしたが、その落胆は自分でも意外なほどだった。
カニを捕まえた男の子がみんなに自慢している。ほかの子は感心したり水を掛け合ったりしていた。
子供の頃の麻子はしあわせではなかった。楽しい記憶もあまりない。小学二年のときに突然警察が家に来て父親を連れていった。傷害罪での逮捕だったが、のちに被害者が亡くなったので殺人罪になった。母に連れられて家を出、別の町で暮らすことになったが、それきり父とは会っていない。
車へ向かう足元で浜昼顔が風にふるえていた。
麻子は下請け会社の作業員を連れて、クレーム処理に来ていた。
個人宅の工事で、中年夫婦は外壁の色あいが見本と少しちがっているなどと文句をつけ、外構の基礎にセメントの粉がこぼれているのを見つけると勝ち誇ったように工事がずさんだと言い立てた。しまいには全額の工事代金は払えないと一方的に宣言した。
こうした顧客の身勝手に、麻子は慣れっこになっていた。
「工事を中止して足場を全部外してちょうだい」
「個人宅のもめごとでそこまでするなんて、上が許可を出さないんじゃないですか」
作業員がおどろいて目をみはった。
「あなたは下請け会社の人間でしょ、これはわたしの会社が請けた工事なのよ」
あわてた作業員はポケットから携帯電話を取り出した。「そうなんだ、元請けさんの意向だから、明日にでも撤去に取り掛かってくれ」
顧客ははじめは人当たりの良いおだやかな夫婦に見えたものだったが、工事が進むにつれて人が変わった。こうした人間が世間にはおどろくほど多い。麻子は人を信用するということができなくなっていた。
恋人の矢代に呼び出されたのは、ホテルの二階のフランス料理店だった。官庁勤めの会計士だ。話は、沖縄の役所に再就職することになった。結婚して一緒についてきてくれ幸せにするから。というものだった。
テーブルに置かれたキャンドルで、神経質そうな細い顔にかけた眼鏡が光っていた。
「わたしは行かないわ」
「どうしてだい?」
戸惑った顔の恋人の質問にこたえず、麻子は料理に口をつけた。
矢代がほかの女の子とも付き合っていたことを、麻子は知っていた。ひとりは営業所の契約社員だ。髪を染めた華やかな子だ。通勤には親が買ってくれたというアクセラの赤いセダンを使っている。自分とはまったくタイプのちがう子だった。
小さいころから生きることだけで精一杯だった。殺人犯の家族が母子二人で身寄りのない世間に暮らしてきたのだ。
矢代は麻子を説得しようとさかんに声をかけていたが、麻子の耳には入らなかった。おいしいものを自分だけが食べてはもうしわけないわ、母さんにはデパートの地下で何か買って帰ろう。そんなことを考えていた。
タクシー乗り場にいると、ホテルの駐車場から出てきた矢代が、軽くクラクションを鳴らして道路へ出て行った。
ホテルの前にはオフィスやいろいろな店の入ったビルが立ち並んでいて、夜にも関わらず街路樹のアカシアの葉が緑に輝いていた。ブティックや居酒屋、一つ一つの看板の字が鮮やかだった。矢代とはもう会うことはないだろう。結婚の申し出を断り、別れを告げた。とくにさびしいという気持ちはなかった。
ほかの社員に聞こえるようにという思惑にちがいなかった。西山営業所長はことさら声を大きくしていた。
「独断で工事をやめさせたのは規則違反だ。わかるね。今度からは会議に諮ってから決めるように」
部屋のなかがしんとなったのを見計らって、こんどは楽しそうに喉を鳴らした。
「たてまえは以上の通りだ。みんなも規則を守るよう心掛けて仕事をしてくれ。ところで瀬川麻子君、あの夫婦はささいなことで本社のほうにまでしつこく電話をかけてきていて応対の者が参っていたのだ。お得意様気取りの勘違い夫婦にはきみのとった処置はよく効いただろうよ。よくやったとは言わないがね」
西山所長は社員の蔭口によれば暴君である。着任して三年だがその間に売り上げを二倍に伸ばした。自分の方針に一切妥協することなく社員を統率したのである。麻子は所管の役所との折衝の仕方や許可の取り方、下請けの扱い方まで一から叩き込まれた。おかげで本社の研修では最優秀の表彰を受けることになった。西山は麻子にとって、ただ一人、信用できる人間だった。
「それから、きみを課長補佐にするよう推薦しておいた。飯田橋の次長が下に置きたいと言ってきてるんだがそれでもいいだろう。とにかく昇進だ。おめでとう。ほかの土地へ移りたくなかったらこのまま俺の下にいてかまわない。以上だ」
暴君にはかなわない。西山のあごが角張って筋肉の盛り上がっているのは、いつも唇を引き結んでいるせいかしらとおもった。
まもなく辞令が出て、麻子には所長室に近い場所にデスクが与えられた。肩書が上がっても、麻子は外回りの営業に進んで出た。
車でも徒歩でも走るのが好きだった。新しい景色へ切り込んで行くとき、快いスリルを感じた。つねに刺激を求めながら、しかし一方で、ときどき、自分が遠い過去に忘れてしまったものを探しているような気がするのがふしぎだった。
漁師町を再訪して、あの女の子の家をたずねてみた。土間は開いていたが家人の気配はなかった。今日は遠くまで漁にでかけたらしい。
郵便局の赤いポストのところまで引き返してくると、風に乗って子供たちの歓声が聞こえた。灯台近くの磯までは日除けを掛けた八百屋の脇の道を下りればずぐだった。
砂浜の波打ち際に、岩場で遊んでいるほかの子供たちとはなれて、あの子がいた。
紺色の水着を着て立っている。夕日に当たって、顔をオレンジ色にかがやかせ、背中まである髪がゆれていた。
近づいて行くと無邪気なようすで麻子に正面を向けた。
「こんにちは、お名前なんて言うのかな」
自然にそうきいていた。
「吉岡えり」
「そう、えりちゃんていうの。いいお名前ね」
女の子は照れた顔でうなずいてみせると、友達の大勢いる岩場へ駆けて行った。
一度だけ母に連れられて、父親が収監されている刑務所に出かけたことがあった。待つように言われ、雨の降るバス停で一人、高い塀に囲まれた大きな建物へ肩を落として入って行った母が戻るのを、いつまでも待っていた気がする。
あの子はえりだったが、父が逮捕される前の楽しかった頃の自分にちがいないと麻子は思っていた。