帰宅途中にある図書館の、オススメコーナーにあったのが「ふせんノート術」(晋遊舎)。監修・坂下仁。
ノートの活用も、授業で教えたいことのひとつです。
わたしはできるだけポイントを絞って継続的に書かせたいのですが、前の題材とつなげたり、一時間ごとにページ分けてしまったりする生徒もいる。
わたし自身のノートの作り方も練っているつもりではあるのですが、実際に板書すると変更することもあります。
付箋紙なら張り替えたり外したりするのが容易なのでは?
実際、去年からは毎時間行う漢字テストの問題を付箋に書いて、授業する予定のページに貼っています。
先日黒板をイメージしたノートを買ったから、そこで使ってみてもいいかもしれません。
付箋配置にも、いろいろあるのです。
上下左右に並べるグリッド法、敷き詰めるようにするタイル法、ツリー法、タイムライン法、書いたことを隠したり(マスク法)分けて書いたり(ブレイク法)、多様な技があるようです。
それはともかく、この本をめくっているとき、守衛さんが現れて司書さんとお話をしていたため帰るに帰れず……。
なんでも、北海道から自転車で長野まで行くつもりの女の子(27)が公園にテントを張りたいといっているとのこと。
家に泊めるわけにもいかないし、駐在さんに連れて行ったそうです。
まだまだ冒険者はいるもんなんだなー、と思いました。
ノートの活用も、授業で教えたいことのひとつです。
わたしはできるだけポイントを絞って継続的に書かせたいのですが、前の題材とつなげたり、一時間ごとにページ分けてしまったりする生徒もいる。
わたし自身のノートの作り方も練っているつもりではあるのですが、実際に板書すると変更することもあります。
付箋紙なら張り替えたり外したりするのが容易なのでは?
実際、去年からは毎時間行う漢字テストの問題を付箋に書いて、授業する予定のページに貼っています。
先日黒板をイメージしたノートを買ったから、そこで使ってみてもいいかもしれません。
付箋配置にも、いろいろあるのです。
上下左右に並べるグリッド法、敷き詰めるようにするタイル法、ツリー法、タイムライン法、書いたことを隠したり(マスク法)分けて書いたり(ブレイク法)、多様な技があるようです。
それはともかく、この本をめくっているとき、守衛さんが現れて司書さんとお話をしていたため帰るに帰れず……。
なんでも、北海道から自転車で長野まで行くつもりの女の子(27)が公園にテントを張りたいといっているとのこと。
家に泊めるわけにもいかないし、駐在さんに連れて行ったそうです。
まだまだ冒険者はいるもんなんだなー、と思いました。










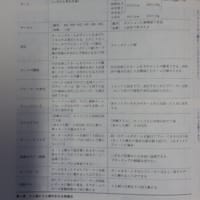

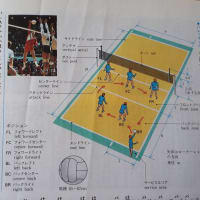

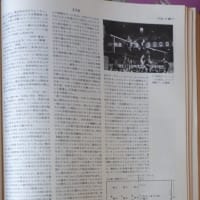

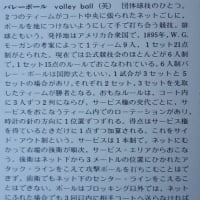

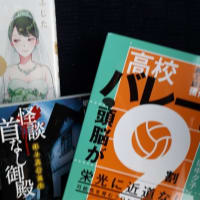
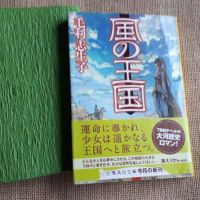
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます