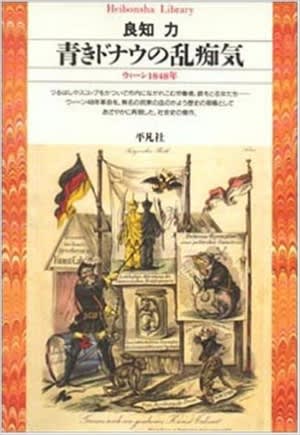『諸國畸人傳』は、江戸時代の畸人10名の列伝である。
冒頭におかれるのは小林如泥。如泥は濁らずに、ジョテイと清んで発音する。西の左甚五郎とも呼ばれる名工である。1753年(宝暦3年)生、1813年(文化10年)没。不味公松平治郷治下の松江城下に居住し、月照寺不昧公廊門の葡萄の透かし彫りほか、数々の逸話と作品とを残した。
本書には、その逸話や作品の幾つかが紹介され、あわせて著者の所感が披露される。紹介を要約すれば、石川淳の仕事は並の郷土史家の作業と異ならなくなる。本書を並の郷土史と区別するのは、語り口である。
たとえば、松江の町に古書店が絶無に近い、と指摘して続ける。
「ここで松江藩の學問について語るにはおよばないが、不味流はどうも後世に古本はのこさなかつたやうである。その代わりに、巷の茶と庭との仕掛けの中から、如泥をとり出してみせるといふ手妻をのこした」
松平治郷の文化政策は、文献を残さず、喫茶の習慣と工芸品を残した。
つまるところ、そういうことだが、「巷の茶と庭との仕掛けの中から、如泥をとり出してみせる」と書くと、一介の工匠が後光を帯びてくる。読者を翻弄する言葉の魔術である。
だが、感嘆するのはまだはやい。
宍道湖は、むかしも今も宍道湖である。落日は、むかしも今も落日である。如泥が住み暮らした大工町、いまの灘町にちかい島根県立美術館付近で湖畔に臨めば、如泥がみた光景とほぼ同じ光景を21世紀の私たちもまのあたりにすることができる。美しい・・・・。なんぴともが同じ印象を抱くだろう。だが、ひとたび石川淳が筆をとると、美しい、ではすまない。
「湖畔の、このあたりに立つて、宍道湖に於て見るべきものはただ一つしか無い。荘麗なる落日のけしきである。そして、これのみが決して見のがすことのできない宍道湖の自然である。雲はあかあかと燃え、日輪は大きく隅もなくかがやき、太いするどい光の束をはなつて、やがて薄墨をながしかける空のかなたに、烈火を吹きあげ、炎のままに水に沈んで行く。おどろくべき太陽のエネルギーである。それが水に沈むまでの時間を、ひとは立ちながらに堪へなくてはならない」
神業とでもいうしかない言葉の喚起力である。烈火を吹きあげるのは、ひとり日輪のみではない。石川淳があやつる言葉も烈火を吹きあげる。しかも、遊び心はたっぷりと。遊刃余地あり、とはかくのごときか。ひとたびこの文章に酔えば、もはや本書を忘れて宍道湖の落日を見ることはできない。
夕闇とともに工匠は家へ帰り、小林如泥の章は閉じる。
さいわい、私たちの前には、まだ9人の畸人が待ち受けている。
□石川淳『諸國畸人傳』(石川淳選集第15巻所収、岩波書店、1981。中公文庫、2005)
↓クリック、プリーズ。↓



冒頭におかれるのは小林如泥。如泥は濁らずに、ジョテイと清んで発音する。西の左甚五郎とも呼ばれる名工である。1753年(宝暦3年)生、1813年(文化10年)没。不味公松平治郷治下の松江城下に居住し、月照寺不昧公廊門の葡萄の透かし彫りほか、数々の逸話と作品とを残した。
本書には、その逸話や作品の幾つかが紹介され、あわせて著者の所感が披露される。紹介を要約すれば、石川淳の仕事は並の郷土史家の作業と異ならなくなる。本書を並の郷土史と区別するのは、語り口である。
たとえば、松江の町に古書店が絶無に近い、と指摘して続ける。
「ここで松江藩の學問について語るにはおよばないが、不味流はどうも後世に古本はのこさなかつたやうである。その代わりに、巷の茶と庭との仕掛けの中から、如泥をとり出してみせるといふ手妻をのこした」
松平治郷の文化政策は、文献を残さず、喫茶の習慣と工芸品を残した。
つまるところ、そういうことだが、「巷の茶と庭との仕掛けの中から、如泥をとり出してみせる」と書くと、一介の工匠が後光を帯びてくる。読者を翻弄する言葉の魔術である。
だが、感嘆するのはまだはやい。
宍道湖は、むかしも今も宍道湖である。落日は、むかしも今も落日である。如泥が住み暮らした大工町、いまの灘町にちかい島根県立美術館付近で湖畔に臨めば、如泥がみた光景とほぼ同じ光景を21世紀の私たちもまのあたりにすることができる。美しい・・・・。なんぴともが同じ印象を抱くだろう。だが、ひとたび石川淳が筆をとると、美しい、ではすまない。
「湖畔の、このあたりに立つて、宍道湖に於て見るべきものはただ一つしか無い。荘麗なる落日のけしきである。そして、これのみが決して見のがすことのできない宍道湖の自然である。雲はあかあかと燃え、日輪は大きく隅もなくかがやき、太いするどい光の束をはなつて、やがて薄墨をながしかける空のかなたに、烈火を吹きあげ、炎のままに水に沈んで行く。おどろくべき太陽のエネルギーである。それが水に沈むまでの時間を、ひとは立ちながらに堪へなくてはならない」
神業とでもいうしかない言葉の喚起力である。烈火を吹きあげるのは、ひとり日輪のみではない。石川淳があやつる言葉も烈火を吹きあげる。しかも、遊び心はたっぷりと。遊刃余地あり、とはかくのごときか。ひとたびこの文章に酔えば、もはや本書を忘れて宍道湖の落日を見ることはできない。
夕闇とともに工匠は家へ帰り、小林如泥の章は閉じる。
さいわい、私たちの前には、まだ9人の畸人が待ち受けている。
□石川淳『諸國畸人傳』(石川淳選集第15巻所収、岩波書店、1981。中公文庫、2005)
↓クリック、プリーズ。↓