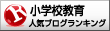2011年4月29日、映画『八日目の蝉』(ようかめのせみ)が公開された。原作は、直木賞作家・角田光代によって、2005年11月21日から2006年7月24日まで読売新聞夕刊に連載された小説で、第2回中央公論文芸賞を受賞した作品である。『八日目の蝉』の単行本は、2007年中央公論新社より出版され、また2010年にはNHKがテレビドラマとして放映し、そして2011年1月に中公文庫より文庫本が出版された。
私は、ゴールデンウイークに読む本の一冊として、中公文庫の『八日目の蝉』を購入し、映画公開日の頃にその本を読んだ。今回のブログでは、細かいあらすじはさておいて、書評と言うより、私がこの小説を読み進めているときに感じたことを中心に綴りたいと思う。
この小説『八日目の蝉』は、主人公・野々宮希和子が犯罪を犯すところからスタートする。希和子は、かつて愛人であった秋山丈博の家に無断で入り込み、眠っていた赤ちゃん恵理菜を誘拐してしまう。野々宮希和子の犯罪動機の不条理は、アルベール・カミュの『異邦人』を、私に連想させる。殺人の動機を問われ、「太陽が眩しかったから」と答えたムルソーの、人間の持つ不条理と同様に、希和子は犯罪現場で、「乳児の匂いと暖かさ」から逃れるすべを無くして、衝動的に犯罪を犯してしまったように思う。
人間社会にあって、最も忌むべき犯罪の一つである、幼児誘拐に手を染めてしまった主人公の側に立って、この小説を読み進めている自分にふと気付く。希和子は、恵理菜を薫と名づけ、我が子として養育し、各所を転々と移動しながら逃亡生活を送る。逃げきることは不可能と感じながらも、この母子が逃げおおせて、限られた条件下でもいいから幸福を感じて、生き抜いてほしいと願いながら読んでしまう。
この小説の1章は、野々宮希和子の目を通して、苦渋の中にも一時の幸福を感じる逃避行が描かれている。「逃げおおせれば、どこだって。私の首に腕をまわし薫は笑う。なんて重いんだろう。なんて大きくなったんだろう。私に笑いかけた、許すように笑いかけたあのちいさなあたたかい子が。どうか、どうか、どうか、どうかお願い、神さま、私を逃がして。」1章の最後に描かれた野々宮希和子の心情が心を打ち、その願いが1章の全体を要約していると言ってよい部分である。
そして、それに続くように、「そのときの事を私は覚えている。」という語り口で、この親子が引き離された時の情景を、短く恵理菜の追憶として記している。ある意味で幸福に過ごしてきた親子に、悪夢とも言えるが、ついに訪れた離別の一瞬を、恵理菜の遠い過去の出来事として語らせる。もう戻ることのない二人の生活が、時間のフィルターを経ることにより、無常感を漂わせて私の胸に迫ってくる。
それに続く2章は、それから17年後、成長し大学生になった恵理菜を主人公にして描かれている。かつて母子が、逃避行中に住んでいたエンジェルホームにいた千草と言う女性を介在役として、恵理菜が思い出すことを避けてきた幼児期の過去と、成人した恵理菜の現在が語られる。

この小説の主題は、「母と子の絆と愛」であると私は思う。
近年、自分が産んだ子どもを虐待し、ついには死に至らしめてしまう親もいる。子どもを産んだことが、母親になる条件ではない。母親として子どもを愛し育てる本能と、健やかに子を養育する義務を認識して、初めて母親と言える。
生物学的に見て、人間の赤ちゃんは他の動物と異なり、すべて未熟児として生まれてくる。すべての行為を、親またはそれに準じた者に依存することにより、生きていける存在の赤ちゃん。壊れそうな危なっかしい生き物であるにも拘らず、周囲の人間を引き付け、時にはマジシャンのように人を虜にする赤ちゃん。希和子もまた、このいたいけな赤ちゃんの虜になってしまった。
乳児そして幼児と成長する過程で、その子の一生を左右する養育環境。綱渡りのような逃亡生活の中で、子どもは育つのだろうか。いつかこの親子が捕まって、今の生活に終止符が打たれたとき、この子どもはどのように生きていくのだろう、生きていけばよいのだろう。この命題が、この小説を読み進める間中、私の心の中で重苦しい旋律となって流れ続ける。
この小説の主題である母親と子どもの関係からすれば、男親と子どもは極めて限定された関係のように感じてしまう。この小説に登場する男は、そうした条件に合うように設定された、情けなく肉のみを求めるむなしい存在として描かれている。男と女、夫と妻、父親と母親、そうした雌雄の差で語る危なっかしい関係の対極に、『母と子』の関係が隠然と確固たる存在としてクローズアップされてくる。
また、この小説を読み進めるうちに、もう一つの命題に私は思いを馳せてしまう。『乳児・幼児期の母親は、その子の原風景を形成する役割を果たす』ということ。乳児の目が利くようになった時、その前にいて自分を世話する者を、自分の親と認識するのかもしれない。
生まれた直後のガンの雛が、動いて声を出すものを親と認識する現象…雛の頭の中に一瞬の映像が定着される『刷り込み』の現象は、人間にも当てはまるのかも知れない。それがガンの雛のように一瞬でないにしろ、乳児期に傍にいた者を、親と認識するのは当然と思われる。したがって、生物学的な単なる生みの母より、乳幼児期の育ての親のほうが、子どもにとって重要である場合が多いと言えるだろう。

4歳の時に家族の元に戻った恵理菜は、誘拐された特別な子どもとして、周囲から奇異な目で見られることが、明らかに誘拐犯である野々宮希和子が原因であるとして、憎しみの感情を抱く。しかし憎むべきは、その育ての母と思いながらも、その母のぬくもりを追慕し、逃亡生活の中で経験した幼き頃の思い出に、いつしか引かれていく。
その心情の変化は、「八日目の蝉」の比喩によって示されている。
知っての通り、蝉はおよそ7年間、真っ暗な地中で過ごし、太陽の燦々と輝く地上に出て、7日ほどで死んでしまう。8日目の蝉とは、多くの仲間が死に絶えた8日目に、まだ死なずに生き長らえている蝉のことを指している。
哀れとも言える蝉のこうした生を、恵理菜はやがて肯定的に捉えていく。
ペシミスティック・ネガティブな捉え方から、オプティミスティック・ポジティブに生きようとする姿勢の変化は、希和子と同じような運命の糸に操られ、恵理菜がバイト先で知り合った妻帯者・岸田の子どもを身ごもると言う出来事の、彼女の対処の仕方で示される。
希和子の場合は、恵理菜の父・秋山丈博との間にできた子を中絶し、その堕胎手術が原因で子宮内癒着になり、もう子どもを産めない体になってしまう。希和子は、生まれることが叶わなかったその子どもを彼岸から連れ戻し、薫と名付けて育てたのかも知れないと、私には思われる。
しかしそれに対して恵理菜は、社会的規範や因習を越えて、またこれからの実生活上の困難をも承知で、子どもを産み育てることを決意する。希和子が果たし得なかった願望を、成就させようとするかのような恵理菜の意志は、生に対する前向きな姿勢と、この小説の主題「母と子の絆と愛」に帰結する。
ただ人間の持つ不可解さは、恵理菜が身ごもった子を堕胎するつもりで病院へ行ったはずが、医師の何気ない会話を聞いて、子を産むことを決めたことにも表れている。
「けれど、緑の季節に生まれると聞いたとき、その気持ちが一瞬にして吹っ飛んだ。今ここにいるだれかは私ではないんだ、と思った。この子は目を開けて、生い茂った新緑を真っ先に見なくちゃいけない。」
人は思い悩み一大決心で決めたと思ったことが、実は一瞬の不可思議な事象によって、あたかも見えざる運命の糸に手繰り寄せられるように、人生の舵を切っているのかもしれないと感じてしまう。
最後の重要テーマは、育ての母であり成長する過程で自分を苦しめた原因を作った誘拐犯の希和子と、成長した恵理菜との和解はあるのかということ。
この誘拐犯であり、一時母でもあった希和子が、最も自分を愛し慈しんでくれた存在であることを、恵理菜は忌み嫌いそして否定すべきこととしてきたが、幼児期を思い起こすにしたがって、追慕する心情が芽生える。
2章の最後に、再び希和子の目を通して、短く最後の物語が語られる。幼い頃に母・希和子と暮らした小豆島へ、恵理菜と千草は向かうために、フェリー乗り場へ来ていた。希和子も、薫と暮らした小豆島に渡ろうとするが、最後の決断ができずに岡山に留まり、仕事帰りにフェリーの発着所に来ることを日課としていた。
二人が住んだ小豆島、逃避行ではあるが幸福も感じた生活、その思い出に吸い寄せられるように、二人は接近する。その希和子と恵理菜が、偶然にもフェリーの待合室で出会うのだが、お互いを認識できずにすれ違ってしまう。読んでいる側は、ここで感動的な出会いがあり、二人の間に暗黙でも良いから、和解が成立することを期待するのだが、余韻を残すように、二人の人生はすれ違ってしまう。
希和子は、女性二人連れの恵理菜と千草を眺めながら、心の中で思う。
『あの島で子どもを産めるなんて、なんと幸福なことだろうか。子どもはきっと、凪いだ海を、浮かぶような島々を、風にはためくオリーブの葉を、高く澄んだ空を、目を開いてすぐに見るだろう・・・』
そして、フェリーへと向かう恵理菜と千草に向かって、いつも二十歳前後の女の子を見かけるとするように、希和子は心の中で呼びかける。
「薫。待って、薫。日陰から日向へと足を踏み出した妊婦の女の子が、何かに呼ばれたようにこちらをふりかえる。何かをさがすように目を泳がせ、そして前を向き歩いていく。光が彼女を包み込む。薫。彼女の姿を目で追いながら、希和子は心の内で、そっとつぶやく。おろかな私が与えてしまった苦しみからどうか抜け出していますように。どうかあなたの日々がいつも光に満ちあふれていますように。薫。」
この眼差しは、子どもに対する母のもの以外の何物でもないと私は思う。犯罪を犯して勝手なことを!という見方もあるが、そこを経たからこそより純粋な見方もできるという事もあろう。それなるがゆえに、希和子の心に対して、私は神々しささえ感じざるを得ない。
八日目の蝉・希和子は生き長らえながら、
犯した罪の贖罪に、清らかな心で薫の安寧を祈り続ける。
「八日目の蝉」の生を、肯定的にとらえながら・・・・・・。