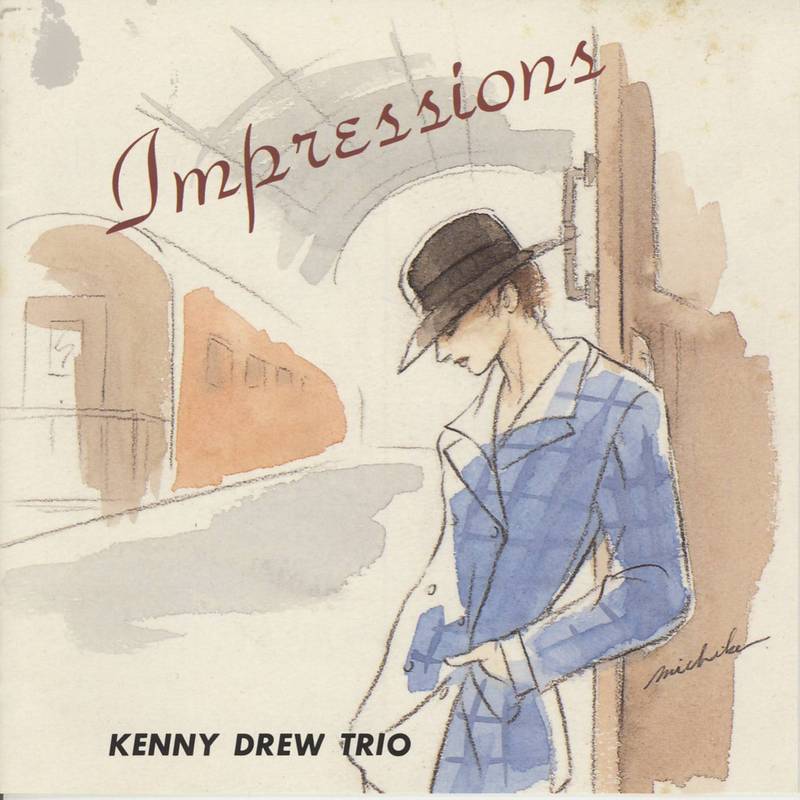●今日の一枚 98●
Rickie Lee Jones
 毎日、4時か5時におきて仕事をする。もう10数年来の習慣だ。子供が小さい頃、自分の時間をつくるため、早い時間に寝かしつけ、朝早く起きることをはじめたのだ。今では夜遅いこともあるので、寝不足のこともあるが……。
毎日、4時か5時におきて仕事をする。もう10数年来の習慣だ。子供が小さい頃、自分の時間をつくるため、早い時間に寝かしつけ、朝早く起きることをはじめたのだ。今では夜遅いこともあるので、寝不足のこともあるが……。
朝の自分の時間は至福の時間だ。家族が寝静まり、私は書斎で仕事をし、あるいは読書する。ボリュームを絞って聴く音楽も悪くない。音が小さいことによって、音楽の芯みたいなものが、感じられることもある。
この10日程、ほとんど毎日のように朝の時間に聴くアルバムがある。リッキー・リー・ジョーンズの『浪漫』だ(1979年作品)。ちょと前に、時々みるブログ「朱音」さんが取り上げたのをみて、そういえばあったなと、ほんとうにしばらくぶりに思いだした。ずっと、カセットテープで聴いていたので(テープが伸びるほどだ)、思い切ってCDを購入した。
なかなかいい。シンプルなサウンドの中からリッキー・リーの歌声が控えめで静かに浮かび上がってくる。早朝にボリュームを絞って聴くにはうってつけだ。
リッキー・リー・ジョーンズの登場は、衝撃的ではなかったが、新鮮だった。それまでのシンガー・ソングライターが内省的でフォークやカントリーをベースにしていたのに対して、彼女のサウンドはジャズのテイストに溢れ、個性的でより自由に歌っているように感じたものだ。しかも、決してでしゃばらないバックのサウンドと、時に明るく、時にしっとりと、か細い声で歌うリッキー・リーのボーカルは、たいへん新鮮でさわやかさだった。そのお洒落なサウンドは、心の奥の柔らかな部分に届く何かをもっている。リッキー・リーの歌声は、我々に言葉ではなく、音楽のメッセージを確かに伝えてくれるのだ。
70年代から80年代初頭には、こういう個性的で才能あふれるセンシティブな女の子たちが確かに存在したように思う。遠い昔を思い起こしながら、今朝もリッキー・リーを聴いた。