Ⅳ
ドーラベルンの地下5千メートルには、歴代の剣王クラスしかその存在を知らぬ秘密の闘技場がある。
ドーラベルンの中でも最高レベルの耐久力を誇るその地下空間は、100メートル以上の広さがあり、かなりの明るさで満たされている。その明かりは人工的であるが。
その青銅色をした闘技場の真ん中辺りに、バルマードの到着を待つヤマモトの姿がある。
ヤマモトが柔軟代わりに木刀を振り回していると、少し遅れて、完全武装のバルマードがやって来た。
「ちょ、バルマード!? オメガはともかく、なんで対テーラ用のバトルアーマーなんて着けてくるかな」
「いやー、師匠相手に本気を出させるには、このくらいは着ておかないとですね。私、全力でいきますけど、師匠は作務衣と木刀でいいんですか」
ヤマモトは一瞬、無口になり、あれこれ頭の中でシュミレーションする。そして、赤茶けた髪を掻きながら、右手に木刀を構える。
「まあ、やってみよう」
「それでこそ我が師。では、ハンデを有効活用させてもらいますかな!!」
そう言うと、いきなりバルマードはオメガ・レプリカの剣気を最高レベルまで高めた!
恐るべき剣気!!!
いきなり戦士レベルを100まで上昇させたバルマードからは、周囲の何もかもを破壊してしまうほどの凄まじいオーラが噴出している!!
その破壊力は半径50キロの地形を一気に消し飛ばすほどの勢いだが、闘技場の外壁は微塵の揺れも無く、それを耐えている。
ヤマモトもそのバルマードの本気に圧倒されてか、木刀を握る手に汗がにじむ。
「いくらなんでも、完全武装のマスタークラス相手にこれはきついぞ、バルマードよ」
木刀をちょんちょんと指差すヤマモトに対し、バルマードはギラついた獣のような目でヤマモトに言う。
「師匠もさっさと伝家の宝刀を抜けばよろしい、転送用のラインはアクティブにしてありますからなっ」
刹那! バルマードはヤマモトの頭上に白く煌めくオメガ・レプリカを振り下ろす!!
ズーーーンッ、という重い音と共にヤマモトは木刀でそれを受け流すが、その一撃で木刀はヒビだらけになる。
「ほら、師匠。次は砕け散って、怪我をなさいますぞ。師匠を本気にさせるには、私などでは本気以上の実力が必要でしょう!!」
バルマードは瞬時に間合いを取って、更に剣気を高める。それと共に、形相も獣のように激しさを増し、盛り上がる筋肉には無数の血管が浮かぶ。
バルマードは狂戦士(バーサーカー)化し、限界を超える力を引き出している。
これは、同時に理性を失う行為でもあり、バルマードはすでに痛覚を失うという危険な状態にまで己を高めている。戦士レベルは100+で、測定域にはない。
「やばいな、ワシも本気にならんと長生き出来んの」
「フハハハハッ!!! さあ、師匠、お互い、全力で叩き潰し合いましょう!!」
ヤマモトは木刀を投げ捨てると、ヤマモトの加護を失った木っ端は、微塵も残さず砕け散った。
と、同時に両手を広げたヤマモトのそれぞれの手に、違う形をした二つの光が収束する!!
右手にはバルマードの持つオメガ・レプリカと同系のシルエットが、左手には異様に長い太刀のシルエットが現れ、それらは実体化する。
「師匠ヤマモト、いや、『剣皇トレイメアス』よ。オメガと第六天魔王を、私ごときに抜いてくれた事を、一戦士として感謝する!」
「やれやれ、こいつを使うのは魔神や六極神相手だけで十分なのに」
刀身を現した状態でヤマモトの元に転送された二つの伝説の剣。
ヤマモトはオメガを手前に持ち、第六天魔王を後ろに構える。すると、ヤマモトの剣気はみるみると高まり、バルマードに匹敵するオーラを周囲に放ち始める。
一つ違うところは、バルマードに比べ、ヤマモトの剣気はとても安定しており、美しい清水のような波紋で伝わってくる。
バルマードは、ヤマモトに斬りかかりながらこう叫ぶ。
「さすがに戦闘経験の差が出ますな!! なんと美しきライトフォースの響き」
「強さにはあまり関係ないよ。勝負は勝たないと意味ないから、そういった綺麗さとか不要かなぁ」
二人が一言交わす間に、バルマードは一千回にも及ぶ剣撃を繰り出していた。
ヤマモトは涼しい顔をして、二本の剣でそれを受け流す。
バルマードはその速攻を繰り出す為に、剣撃を加えるラインの質量を0に変換して、空気抵抗などをなくしている。ヤマモトはそのラインの変化を瞬時に読み取り、剣が振り下ろされる前に、受け流しの姿勢に入っている。
ただ、これは『伝説の剣皇』であるヤマモトであるからこそ成しえる技で、並みの戦士なら、バルマードのこの攻撃速度に対応出来ず、ひたすらシールドで耐えるしかない。
その場合、あっという間にシールドは砕かれてしまうだろうが。
「さすが、我が師!! 我が神速剣を見事にかわされますなっ!」
「いや、結構、しんどいよ。・・・もう一万撃くらいくれてるでしょ。一回、流し損ねると致命傷だからね~」
ヤマモトはそう言いながらもバルマードに一撃を加えたが、バルマードのバトルアーマーは平然とそれを耐える。ヤマモトとしても、バルマードの神速の剣をかわしながら、鋭い一撃を放つのは至難である。
「ところでさ、バルマード。ウィルちゃんって、たしか10歳くらいまで中性だったよね?なんで男の子にしたのよ?」
「ハッハッハッ!! 簡単ですよ、師匠。女の子にしたら、嫁に出さなきゃならないでしょ? その点、王子ならその心配はありませんからなッ」
「今なら、女の子に戻せるでしょ。ちょうどワシ、あんな子を嫁に欲しかったりするのよ。・・・だめ?」
「師匠のパパ上になるなど、御免こうむりたいですなッ! 私が嫁にしたいくらいなのに」
二人はそうやって馬鹿げたやり取りをしているが、剣の方では人類最強を決めるような決戦をしている。
ウィルハルトの話に少し触れるが、ウィルハルトは極めて稀有とも呼べる中立の性を持って生まれてきた戦士である。
中性の戦士は、戦天使同様に貴重な存在で、生まれた時から戦士レベル限界値が最高の100と決まっている。戦士レベルは当人の容姿にも反映され、故にウィルハルト(女性時の名は、ウィルローゼ)は、戦天使セリカ(現・魔王ディナス)とも肩を並べる程の美形である。
戦士レベルが100に達するまでは、性の変更は可能な上、一定(16~18歳)の年齢に達すると老化すらしなくなる。
はるか昔、一人だけその中性の人物が存在したが、その人物を巡って、大陸を三分する帝国(アスレウス帝国・ホーヴレウス帝国・ミストレウス帝国)間で大戦が勃発した。
そして、その勝者であるミストレウス帝国・皇帝サードラルの妻として、その人物は迎え入れられた。
名を、『覇王妃・オーユ』という。セリカの姉である。
バルマードは、今一度、ヤマモトとの間合いを取り直し、その剣を鞘に収めた。
「これでは、埒が明きませんな、師匠」
ヤマモトはバルマードの次の手に気付いて、苦笑いをする。
「バルマード、それはないよ。これは、稽古だよ、け・い・こ」
「我が剣など、異界の神々すらをも畏怖せしめ、『剣神グランハルト』と恐れられた、トレイメアス剣皇陛下には、そよ吹く風でありましょうに」
ヤマモトの本名は、『グランハルト=トレイメアス=ミストレウス』である。
覇王サードラルの実弟として、その覇王の剣(つるぎ)であった時は『グランハルト』の名を用いていたが、覇王サードラル無き今では、字(あざな)である『トレイメアス』名の方を主に用いている。
覇王を継ぐ意思がまるで無い彼は、「グランハルト」や「ミストレウス」といった覇王家に連なる名を封印している。
古代の文書などに記述のほとんどない「トレイメアス」の名を名乗っているのも、古の大帝国・ミストレウス帝国の威光から、己を遠ざける意味合いもあった。
「グランハルト=ミストレウス」の名を名乗れば、それはミストレウス帝国の皇帝継承権第一位の名の人物を意味する。
もし自身が覇王として、大陸に君臨してしまえば、世界の進化は止まる。
絶対強者を前に大陸は安定し、群雄は鳴りを潜め、以後、強力な戦士の誕生は望めないだろうと彼は考えたのだ。
覇王サードラル時代の帝国には、十分に強力な戦士たちが多数存在し、異界の敵とも決戦し得る戦力があった。
が、覇王サードラルを失ったその過去の大戦により、エグラートの戦力は十分の一以下にまで衰退していた。
故にそんな状態の大陸を、覇王グランハルトの名で統一する事を彼は望まなかった。
世界の進化を止めてしまえば、次に来るであろう異界の神々との決戦の時に、人類の敗北は必至であろうと、激戦の中を生き抜いた彼はそう感じずにはいられなかったのだ。
そして、彼が約束された覇王の座を彼が捨てて、五千年もの時が流れた。
もし彼がその時、覇王となっていたならば、この稀代の剣王・バルマードも誕生することもなかったであろう。
現在ではさらに『ヤマモト』と名を変え、半隠居生活を送っている彼だが、彼自身の過去の実績があまりにも絶大過ぎて、その僅かな記述しか残されていないトレイメアスの名でさえ伝説化しており、その語頭や語尾には常に『剣皇』の名が付き纏っていた。
口伝いに勇名が知れ渡ったと推測される。
目の色を変えたバルマードに、ちょっとジジくさい口調でヤマモトは言う。
「バルマード、そりゃ、年老いたワシでは耐えられんて」
「フフッ、ご冗談を。実年齢はともかく、肉体年齢ハタチのピッチピチの師匠に、腰がどうのこうのとか、持病のシャクがなどとは言わせませんぞ。その無限の若々しさが羨ましいですな、顔はオッサンですがネ」
そう言って、バルマードは居合いの構えを取る。
バルマードのその構えから、それがただ事でない錬気の姿勢であることがヤマモトには分かる。
「おだてても駄目だからね。いくらワシでも、マスタークラスのお前さんの奥義なんて喰らったら、ただじゃすまないよ。それにワシ、攻撃型の戦士だからね、防御下手だからね!!」
バルマードは柄に右手の平をそえ、莫大な量のライトフォースを、鞘に納まるオメガ・レプリカへと圧縮していく。
「模擬戦とはいえ、ここまでの剣気を錬成したのは初めてですよ。鞘を握る手がちぎれそうな勢いです」
「だったら、やめとけって。お前さんがめちゃくちゃな強さなのは師匠であるワシが良くわかっとるからの。お前さんの勝ちでいいから、今からでもやめてくんない?」
一度、オメガ・レプリカを鞘に戻したのは、超絶な剣気の圧縮の為であり、刀身をさらした状態でここまでの力の集束は、バルマードにさえ難しい。
鞘の中のオメガ・レプリカには、マイクロブラックホールを形成するほどの高密度のエネルギーが蓄積され始めている。
鞘は周囲の光を限定的に喰らい、黒い、漆黒とも言える色をして、ギギッ、ギギッと鳴き始める。
「や、やばいな・・・。オメガを使いこなす事の出来るバルマードなら、ダーククリスタルの暗黒エネルギーすら剣気に変えておるな。この闘技場の狭さでは、かわすのは難しいぞ」
ヤマモトは攻撃型の戦士である。
彼は、戦士レベルを大きく凌駕する圧倒的攻撃力を有しているが、と同時に防御は紙のように薄く、脆い。それを神速の動きで回避することによって補っているのだが、この限られた空間ではその機動も生かせず、かといって防御するにも、超が付くほどの攻撃型のヤマモトが、その力を防御に回しても、大きくレベルダウンしたシールドしか形成することができず、同じ攻撃型のバルマードの、しかも奥義クラスとなればそれを耐えられるハズもない。
「バトルアーマーに遮蔽された分の力を、ワシに悟られずライトフォースの錬成に使いおったか。錬気があまりにも早すぎるからのう。それでいて、あの高速の剣撃を見せるとは、底が知れぬの。・・・バルマードよ、お前さん、ワシをはめたな」
「人聞きの悪い。ハンデをもらったって言ってたでしょうに。喰らうの嫌なら、今の、隙だらけの私を狙えばよいだけでしょう」
「で、出来るかッ!!! お前さんを倒せても、暴発に巻き込まれて、ワシは消し飛んでしまうわい! シールドで耐え得る範囲までも逃げれんし」
バルマードがその血管の浮き出た右手で、柄を強く握る!
抜刀のタイミングを誤れば、バルマードもバトルアーマーだけを残して、この世から消し飛ぶ。
清々しいほどにいい顔をするバルマードだが、内心はその緊張感で、柄を握る手にも汗がにじむ。
「いやぁ、この一瞬を味わえる相手など、私は師匠をおいて他を知りませぬ。戦士たるもの、一度は自分の限界というやつを試したくなるものじゃないですか、ねえ?」
「ねえ。って、知るかーーーッ!! こんなことなら、ティヴァーテくんだりまで、わざわざ来るんじゃなかった。とほっ・・・」
次の瞬間、バルマードは高らかに叫び声を上げ、ついにオメガ・レプリカを抜刀する!!!
「剣皇剣・烈空波、第五の太刀『常闇』ッ!!」
一閃、ヤマモトに向かってバルマードから光の筋が流れると、周囲は漆黒の闇に没した。
音はない。
そして、光もない
暫しの沈黙の後、その姿を現したのは、全力を出し切って膝を折り、青銅色をした石畳の床にオメガ・レプリカを突き立てた、バルマードであった。
バルマードは全身から大量の汗を流し、身に付けたそのバトルアーマーも随分重たそうにしている。
「・・・いやぁ、さすが師匠。無駄に永くは生きていませんな」
バルマードがそう呟くと、消え行く闇の隙間から、ケホッ、ケホッと咳をしながら、ボロボロになった作務衣姿のヤマモトが、二本の剣をクロスさせた状態で姿を現す。
「焦ったーッ!!! つか、常闇はねえだろ。ワシの技のまるパクリじゃんか!! 寿命が300年くらい縮んだぞッ!」
「まあ、結果オーライと言うことで」
「気軽に言うなッ!!」
ヤマモトは、バルマードの奥義を受ける瞬間に、オメガと第六天魔王をクロスさせ、内側に向かって奥義を放っていた。
バルマードよりも練気が十分でない分を二本の剣のダーククリスタルによって補い、奥義最弱の一の太刀『宵闇』を大量発生させ、マイクロブラックホールの矢となったバルマードの奥義を薄皮一枚の所で受け止め、それを数百億分の一単位で分解、開放を繰り返すことで、多少のダメージを受けながらも、それを中和する事に成功する。
この間、ヤマモトはコンマ1秒を体感300年に置き換え、延々と一の太刀を錬成しては、手数を稼ぐ為にギリギリの最短距離で、バルマードの五の太刀『常闇』へと打ち込んでいた。
このような荒業をやってのける人類の戦士など、後にも先にもヤマモト一人くらいであろう。
ヤマモトは目に大きなクマを作って、まるで徹夜明けで多数の原稿を仕上げた人気作家のような、まどろんだ瞳をバルマードの方に恨めしく向けていた。
対照的に、全てを出し切って、スッキリさわやかな笑顔を取り戻したバルマードは、徐にヤマモトの方へと近付き、彼の耳元でこう囁いた。
「そろそろウィルハルトが、得意のスウィーツを仕上げている頃です。今日一日、ウィルハルトを貸してあげますから、一緒に上へと参りましょう」
「ま、まぢかーーー!? ウィルちゃん貸してくれるの? いいの? 本当にいいの?」
現金な感じで、スタミナを一気に回復させたヤマモトは、まるで子供のようにグラサンの奥の瞳を輝かせて、バルマードに何度も確認する。
「いいですよ、師匠にはお世話になりっぱなしだし」
「やったー! 今日はウィルちゃんにご本を読んで聞かせて、天蓋付きのベットで添い寝なんかしちゃうぞ! うひょひょ、うひょうひょ!!」
バルマードは、師匠のやや危なげな発言に、少しだけその笑顔を歪ませたが、まあこのオッサンが、ウチの天使に手を出す勇気がないのは知っていたので、なんとなく、うんうんと自分を納得させた。
そう、彼にその甲斐性があれば、その彼の妻は、きっとこの名で呼ばれていただろう。
『剣皇妃・オーユ』と。
ドーラベルンの地下5千メートルには、歴代の剣王クラスしかその存在を知らぬ秘密の闘技場がある。
ドーラベルンの中でも最高レベルの耐久力を誇るその地下空間は、100メートル以上の広さがあり、かなりの明るさで満たされている。その明かりは人工的であるが。
その青銅色をした闘技場の真ん中辺りに、バルマードの到着を待つヤマモトの姿がある。
ヤマモトが柔軟代わりに木刀を振り回していると、少し遅れて、完全武装のバルマードがやって来た。
「ちょ、バルマード!? オメガはともかく、なんで対テーラ用のバトルアーマーなんて着けてくるかな」
「いやー、師匠相手に本気を出させるには、このくらいは着ておかないとですね。私、全力でいきますけど、師匠は作務衣と木刀でいいんですか」
ヤマモトは一瞬、無口になり、あれこれ頭の中でシュミレーションする。そして、赤茶けた髪を掻きながら、右手に木刀を構える。
「まあ、やってみよう」
「それでこそ我が師。では、ハンデを有効活用させてもらいますかな!!」
そう言うと、いきなりバルマードはオメガ・レプリカの剣気を最高レベルまで高めた!
恐るべき剣気!!!
いきなり戦士レベルを100まで上昇させたバルマードからは、周囲の何もかもを破壊してしまうほどの凄まじいオーラが噴出している!!
その破壊力は半径50キロの地形を一気に消し飛ばすほどの勢いだが、闘技場の外壁は微塵の揺れも無く、それを耐えている。
ヤマモトもそのバルマードの本気に圧倒されてか、木刀を握る手に汗がにじむ。
「いくらなんでも、完全武装のマスタークラス相手にこれはきついぞ、バルマードよ」
木刀をちょんちょんと指差すヤマモトに対し、バルマードはギラついた獣のような目でヤマモトに言う。
「師匠もさっさと伝家の宝刀を抜けばよろしい、転送用のラインはアクティブにしてありますからなっ」
刹那! バルマードはヤマモトの頭上に白く煌めくオメガ・レプリカを振り下ろす!!
ズーーーンッ、という重い音と共にヤマモトは木刀でそれを受け流すが、その一撃で木刀はヒビだらけになる。
「ほら、師匠。次は砕け散って、怪我をなさいますぞ。師匠を本気にさせるには、私などでは本気以上の実力が必要でしょう!!」
バルマードは瞬時に間合いを取って、更に剣気を高める。それと共に、形相も獣のように激しさを増し、盛り上がる筋肉には無数の血管が浮かぶ。
バルマードは狂戦士(バーサーカー)化し、限界を超える力を引き出している。
これは、同時に理性を失う行為でもあり、バルマードはすでに痛覚を失うという危険な状態にまで己を高めている。戦士レベルは100+で、測定域にはない。
「やばいな、ワシも本気にならんと長生き出来んの」
「フハハハハッ!!! さあ、師匠、お互い、全力で叩き潰し合いましょう!!」
ヤマモトは木刀を投げ捨てると、ヤマモトの加護を失った木っ端は、微塵も残さず砕け散った。
と、同時に両手を広げたヤマモトのそれぞれの手に、違う形をした二つの光が収束する!!
右手にはバルマードの持つオメガ・レプリカと同系のシルエットが、左手には異様に長い太刀のシルエットが現れ、それらは実体化する。
「師匠ヤマモト、いや、『剣皇トレイメアス』よ。オメガと第六天魔王を、私ごときに抜いてくれた事を、一戦士として感謝する!」
「やれやれ、こいつを使うのは魔神や六極神相手だけで十分なのに」
刀身を現した状態でヤマモトの元に転送された二つの伝説の剣。
ヤマモトはオメガを手前に持ち、第六天魔王を後ろに構える。すると、ヤマモトの剣気はみるみると高まり、バルマードに匹敵するオーラを周囲に放ち始める。
一つ違うところは、バルマードに比べ、ヤマモトの剣気はとても安定しており、美しい清水のような波紋で伝わってくる。
バルマードは、ヤマモトに斬りかかりながらこう叫ぶ。
「さすがに戦闘経験の差が出ますな!! なんと美しきライトフォースの響き」
「強さにはあまり関係ないよ。勝負は勝たないと意味ないから、そういった綺麗さとか不要かなぁ」
二人が一言交わす間に、バルマードは一千回にも及ぶ剣撃を繰り出していた。
ヤマモトは涼しい顔をして、二本の剣でそれを受け流す。
バルマードはその速攻を繰り出す為に、剣撃を加えるラインの質量を0に変換して、空気抵抗などをなくしている。ヤマモトはそのラインの変化を瞬時に読み取り、剣が振り下ろされる前に、受け流しの姿勢に入っている。
ただ、これは『伝説の剣皇』であるヤマモトであるからこそ成しえる技で、並みの戦士なら、バルマードのこの攻撃速度に対応出来ず、ひたすらシールドで耐えるしかない。
その場合、あっという間にシールドは砕かれてしまうだろうが。
「さすが、我が師!! 我が神速剣を見事にかわされますなっ!」
「いや、結構、しんどいよ。・・・もう一万撃くらいくれてるでしょ。一回、流し損ねると致命傷だからね~」
ヤマモトはそう言いながらもバルマードに一撃を加えたが、バルマードのバトルアーマーは平然とそれを耐える。ヤマモトとしても、バルマードの神速の剣をかわしながら、鋭い一撃を放つのは至難である。
「ところでさ、バルマード。ウィルちゃんって、たしか10歳くらいまで中性だったよね?なんで男の子にしたのよ?」
「ハッハッハッ!! 簡単ですよ、師匠。女の子にしたら、嫁に出さなきゃならないでしょ? その点、王子ならその心配はありませんからなッ」
「今なら、女の子に戻せるでしょ。ちょうどワシ、あんな子を嫁に欲しかったりするのよ。・・・だめ?」
「師匠のパパ上になるなど、御免こうむりたいですなッ! 私が嫁にしたいくらいなのに」
二人はそうやって馬鹿げたやり取りをしているが、剣の方では人類最強を決めるような決戦をしている。
ウィルハルトの話に少し触れるが、ウィルハルトは極めて稀有とも呼べる中立の性を持って生まれてきた戦士である。
中性の戦士は、戦天使同様に貴重な存在で、生まれた時から戦士レベル限界値が最高の100と決まっている。戦士レベルは当人の容姿にも反映され、故にウィルハルト(女性時の名は、ウィルローゼ)は、戦天使セリカ(現・魔王ディナス)とも肩を並べる程の美形である。
戦士レベルが100に達するまでは、性の変更は可能な上、一定(16~18歳)の年齢に達すると老化すらしなくなる。
はるか昔、一人だけその中性の人物が存在したが、その人物を巡って、大陸を三分する帝国(アスレウス帝国・ホーヴレウス帝国・ミストレウス帝国)間で大戦が勃発した。
そして、その勝者であるミストレウス帝国・皇帝サードラルの妻として、その人物は迎え入れられた。
名を、『覇王妃・オーユ』という。セリカの姉である。
バルマードは、今一度、ヤマモトとの間合いを取り直し、その剣を鞘に収めた。
「これでは、埒が明きませんな、師匠」
ヤマモトはバルマードの次の手に気付いて、苦笑いをする。
「バルマード、それはないよ。これは、稽古だよ、け・い・こ」
「我が剣など、異界の神々すらをも畏怖せしめ、『剣神グランハルト』と恐れられた、トレイメアス剣皇陛下には、そよ吹く風でありましょうに」
ヤマモトの本名は、『グランハルト=トレイメアス=ミストレウス』である。
覇王サードラルの実弟として、その覇王の剣(つるぎ)であった時は『グランハルト』の名を用いていたが、覇王サードラル無き今では、字(あざな)である『トレイメアス』名の方を主に用いている。
覇王を継ぐ意思がまるで無い彼は、「グランハルト」や「ミストレウス」といった覇王家に連なる名を封印している。
古代の文書などに記述のほとんどない「トレイメアス」の名を名乗っているのも、古の大帝国・ミストレウス帝国の威光から、己を遠ざける意味合いもあった。
「グランハルト=ミストレウス」の名を名乗れば、それはミストレウス帝国の皇帝継承権第一位の名の人物を意味する。
もし自身が覇王として、大陸に君臨してしまえば、世界の進化は止まる。
絶対強者を前に大陸は安定し、群雄は鳴りを潜め、以後、強力な戦士の誕生は望めないだろうと彼は考えたのだ。
覇王サードラル時代の帝国には、十分に強力な戦士たちが多数存在し、異界の敵とも決戦し得る戦力があった。
が、覇王サードラルを失ったその過去の大戦により、エグラートの戦力は十分の一以下にまで衰退していた。
故にそんな状態の大陸を、覇王グランハルトの名で統一する事を彼は望まなかった。
世界の進化を止めてしまえば、次に来るであろう異界の神々との決戦の時に、人類の敗北は必至であろうと、激戦の中を生き抜いた彼はそう感じずにはいられなかったのだ。
そして、彼が約束された覇王の座を彼が捨てて、五千年もの時が流れた。
もし彼がその時、覇王となっていたならば、この稀代の剣王・バルマードも誕生することもなかったであろう。
現在ではさらに『ヤマモト』と名を変え、半隠居生活を送っている彼だが、彼自身の過去の実績があまりにも絶大過ぎて、その僅かな記述しか残されていないトレイメアスの名でさえ伝説化しており、その語頭や語尾には常に『剣皇』の名が付き纏っていた。
口伝いに勇名が知れ渡ったと推測される。
目の色を変えたバルマードに、ちょっとジジくさい口調でヤマモトは言う。
「バルマード、そりゃ、年老いたワシでは耐えられんて」
「フフッ、ご冗談を。実年齢はともかく、肉体年齢ハタチのピッチピチの師匠に、腰がどうのこうのとか、持病のシャクがなどとは言わせませんぞ。その無限の若々しさが羨ましいですな、顔はオッサンですがネ」
そう言って、バルマードは居合いの構えを取る。
バルマードのその構えから、それがただ事でない錬気の姿勢であることがヤマモトには分かる。
「おだてても駄目だからね。いくらワシでも、マスタークラスのお前さんの奥義なんて喰らったら、ただじゃすまないよ。それにワシ、攻撃型の戦士だからね、防御下手だからね!!」
バルマードは柄に右手の平をそえ、莫大な量のライトフォースを、鞘に納まるオメガ・レプリカへと圧縮していく。
「模擬戦とはいえ、ここまでの剣気を錬成したのは初めてですよ。鞘を握る手がちぎれそうな勢いです」
「だったら、やめとけって。お前さんがめちゃくちゃな強さなのは師匠であるワシが良くわかっとるからの。お前さんの勝ちでいいから、今からでもやめてくんない?」
一度、オメガ・レプリカを鞘に戻したのは、超絶な剣気の圧縮の為であり、刀身をさらした状態でここまでの力の集束は、バルマードにさえ難しい。
鞘の中のオメガ・レプリカには、マイクロブラックホールを形成するほどの高密度のエネルギーが蓄積され始めている。
鞘は周囲の光を限定的に喰らい、黒い、漆黒とも言える色をして、ギギッ、ギギッと鳴き始める。
「や、やばいな・・・。オメガを使いこなす事の出来るバルマードなら、ダーククリスタルの暗黒エネルギーすら剣気に変えておるな。この闘技場の狭さでは、かわすのは難しいぞ」
ヤマモトは攻撃型の戦士である。
彼は、戦士レベルを大きく凌駕する圧倒的攻撃力を有しているが、と同時に防御は紙のように薄く、脆い。それを神速の動きで回避することによって補っているのだが、この限られた空間ではその機動も生かせず、かといって防御するにも、超が付くほどの攻撃型のヤマモトが、その力を防御に回しても、大きくレベルダウンしたシールドしか形成することができず、同じ攻撃型のバルマードの、しかも奥義クラスとなればそれを耐えられるハズもない。
「バトルアーマーに遮蔽された分の力を、ワシに悟られずライトフォースの錬成に使いおったか。錬気があまりにも早すぎるからのう。それでいて、あの高速の剣撃を見せるとは、底が知れぬの。・・・バルマードよ、お前さん、ワシをはめたな」
「人聞きの悪い。ハンデをもらったって言ってたでしょうに。喰らうの嫌なら、今の、隙だらけの私を狙えばよいだけでしょう」
「で、出来るかッ!!! お前さんを倒せても、暴発に巻き込まれて、ワシは消し飛んでしまうわい! シールドで耐え得る範囲までも逃げれんし」
バルマードがその血管の浮き出た右手で、柄を強く握る!
抜刀のタイミングを誤れば、バルマードもバトルアーマーだけを残して、この世から消し飛ぶ。
清々しいほどにいい顔をするバルマードだが、内心はその緊張感で、柄を握る手にも汗がにじむ。
「いやぁ、この一瞬を味わえる相手など、私は師匠をおいて他を知りませぬ。戦士たるもの、一度は自分の限界というやつを試したくなるものじゃないですか、ねえ?」
「ねえ。って、知るかーーーッ!! こんなことなら、ティヴァーテくんだりまで、わざわざ来るんじゃなかった。とほっ・・・」
次の瞬間、バルマードは高らかに叫び声を上げ、ついにオメガ・レプリカを抜刀する!!!
「剣皇剣・烈空波、第五の太刀『常闇』ッ!!」
一閃、ヤマモトに向かってバルマードから光の筋が流れると、周囲は漆黒の闇に没した。
音はない。
そして、光もない
暫しの沈黙の後、その姿を現したのは、全力を出し切って膝を折り、青銅色をした石畳の床にオメガ・レプリカを突き立てた、バルマードであった。
バルマードは全身から大量の汗を流し、身に付けたそのバトルアーマーも随分重たそうにしている。
「・・・いやぁ、さすが師匠。無駄に永くは生きていませんな」
バルマードがそう呟くと、消え行く闇の隙間から、ケホッ、ケホッと咳をしながら、ボロボロになった作務衣姿のヤマモトが、二本の剣をクロスさせた状態で姿を現す。
「焦ったーッ!!! つか、常闇はねえだろ。ワシの技のまるパクリじゃんか!! 寿命が300年くらい縮んだぞッ!」
「まあ、結果オーライと言うことで」
「気軽に言うなッ!!」
ヤマモトは、バルマードの奥義を受ける瞬間に、オメガと第六天魔王をクロスさせ、内側に向かって奥義を放っていた。
バルマードよりも練気が十分でない分を二本の剣のダーククリスタルによって補い、奥義最弱の一の太刀『宵闇』を大量発生させ、マイクロブラックホールの矢となったバルマードの奥義を薄皮一枚の所で受け止め、それを数百億分の一単位で分解、開放を繰り返すことで、多少のダメージを受けながらも、それを中和する事に成功する。
この間、ヤマモトはコンマ1秒を体感300年に置き換え、延々と一の太刀を錬成しては、手数を稼ぐ為にギリギリの最短距離で、バルマードの五の太刀『常闇』へと打ち込んでいた。
このような荒業をやってのける人類の戦士など、後にも先にもヤマモト一人くらいであろう。
ヤマモトは目に大きなクマを作って、まるで徹夜明けで多数の原稿を仕上げた人気作家のような、まどろんだ瞳をバルマードの方に恨めしく向けていた。
対照的に、全てを出し切って、スッキリさわやかな笑顔を取り戻したバルマードは、徐にヤマモトの方へと近付き、彼の耳元でこう囁いた。
「そろそろウィルハルトが、得意のスウィーツを仕上げている頃です。今日一日、ウィルハルトを貸してあげますから、一緒に上へと参りましょう」
「ま、まぢかーーー!? ウィルちゃん貸してくれるの? いいの? 本当にいいの?」
現金な感じで、スタミナを一気に回復させたヤマモトは、まるで子供のようにグラサンの奥の瞳を輝かせて、バルマードに何度も確認する。
「いいですよ、師匠にはお世話になりっぱなしだし」
「やったー! 今日はウィルちゃんにご本を読んで聞かせて、天蓋付きのベットで添い寝なんかしちゃうぞ! うひょひょ、うひょうひょ!!」
バルマードは、師匠のやや危なげな発言に、少しだけその笑顔を歪ませたが、まあこのオッサンが、ウチの天使に手を出す勇気がないのは知っていたので、なんとなく、うんうんと自分を納得させた。
そう、彼にその甲斐性があれば、その彼の妻は、きっとこの名で呼ばれていただろう。
『剣皇妃・オーユ』と。














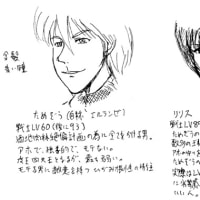

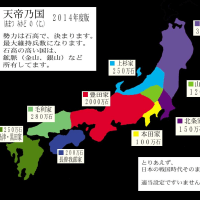



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます