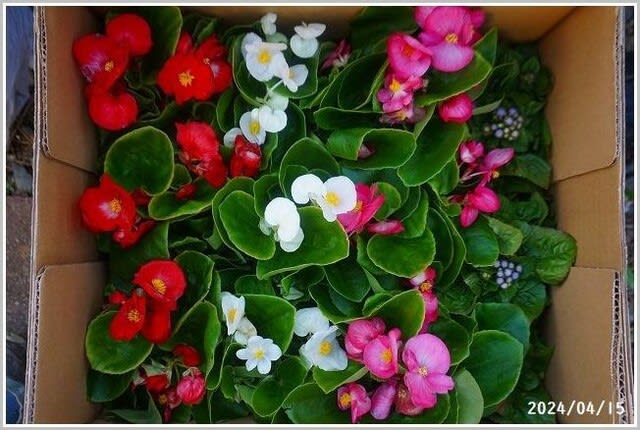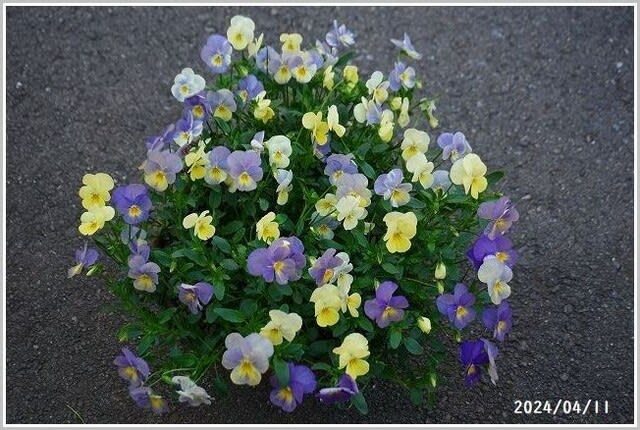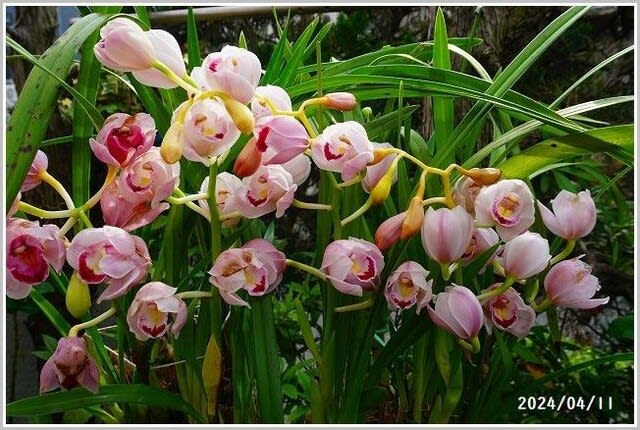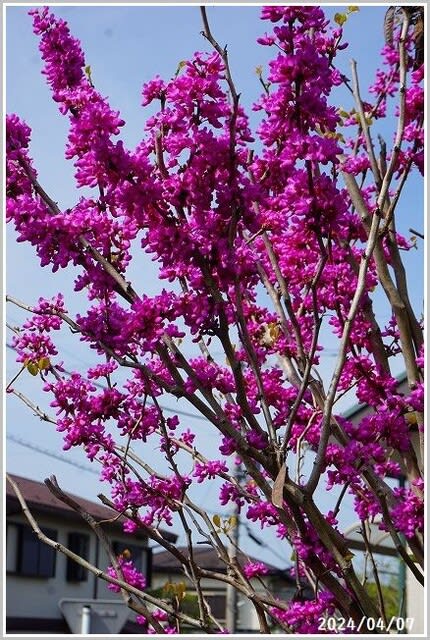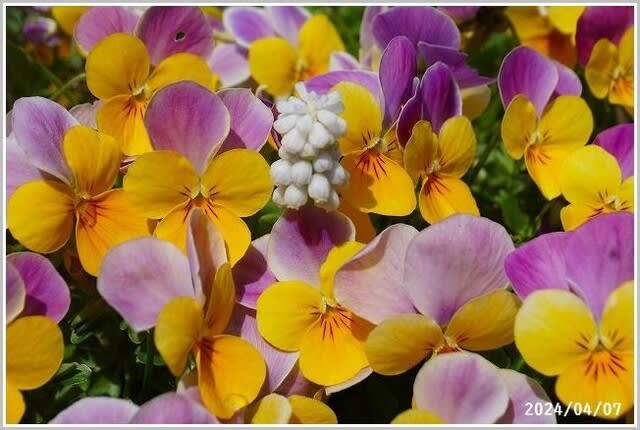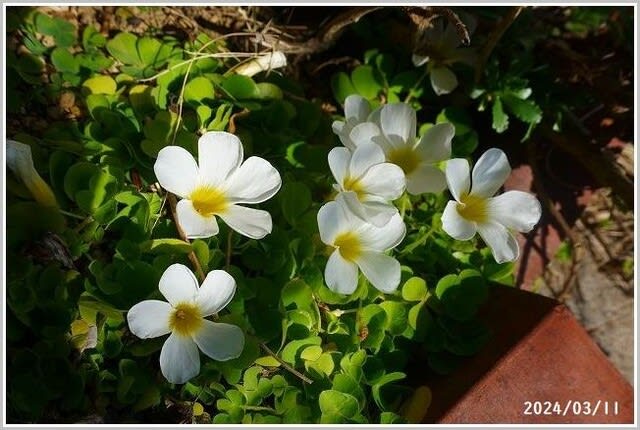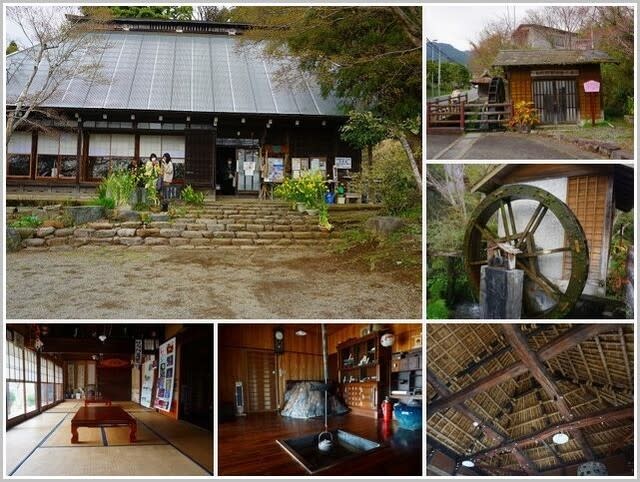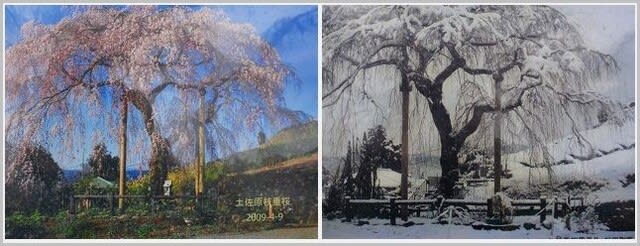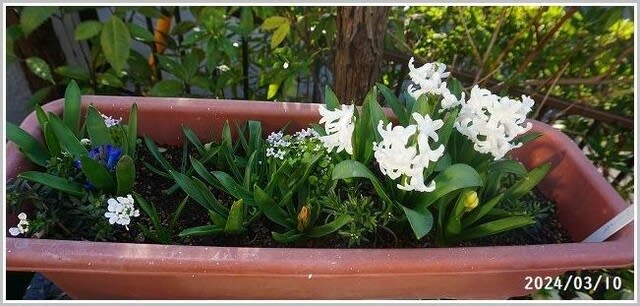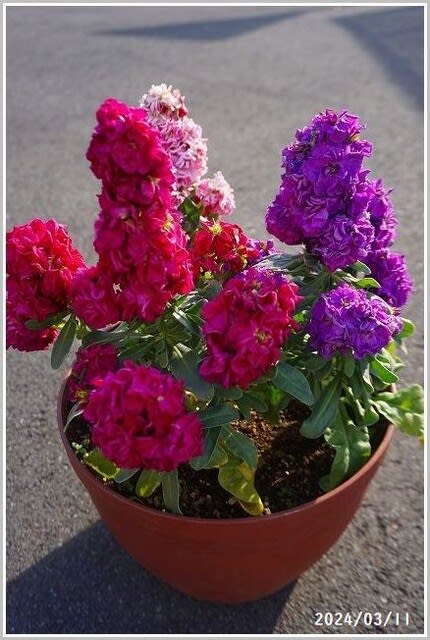高齢者になると自分の年齢をひたすら隠す人(女性に多い)と、
逆に聞きもしないのに自分から話される人がいます。
昨日は卓球教室があり、ボール拾いをしていると、
Nさん(男性)が「明日で喜寿になるんだよ」と話しかけてきたので、
「それはおめでとうございます」とこたえると、
傍にいた40代ぐらいの若い女性が、
「年寄り自慢している」と笑いながら茶化していました。
『年寄り自慢』?
ネットで調べると嫌味な意見も少しはありましたが、
年齢を自慢したいのではなくて、「○○才なのに」元気で頑張ってる
と思われたいだけではないかと考えている方が多いようでした。
私は明日、家族の方から喜寿のお祝いして頂けるので、
それがただ嬉しくて話されたのではないかと想像したのですが…。

寄せ植え①
ビオラとフランス小菊・マトリカリア
後ろの木はサラサウツギ
(画像は昨年11月末に植え付けた当時のもの)

フランス小菊は花が咲き終わった後、
休眠していましたが、4月中旬頃から、再び咲き始めました。
サラサウツギは小さな蕾を持っています。

ビオラの花が小さくなり、花びらが虫に食べられています。
ナメクジではないようですが、気になります。

サラサウツギの開花はこれだけ…。

こちら👆は昨年4月25日に購入したサラサウツギの画像すが、
今年はもっと咲くと期待していたので残念です。
寄せ植えに向かないのかしら…。

寄せ植え②
ナデシコ1p 葉ボタンp
(寄せ植えは昨年11月15日に作成)

昨年11月末に植え付けた時は小さな丸い葉ボタンでしたが、
薹が立ち菜の花のようなお花が咲きました。
現在、お花の部分は切り戻ししました。
ナデシコは冬になるとお花は一旦終わりますが、
春になると草丈が伸び、その先端に可憐なお花が沢山咲きます。

寄せ植え③
ギョウリュウバイ ナデシコ スィートアリッサム
プリムラ・ジュリアン
プリムラ・ジュリアンは枯れたのでナデシコに植え替え
(画像は昨年12月20日に植え付けた時のもの)


4月21日:ギョウリュウバイの剪定


2月15日に、デージー、ボリジ、クモマグサのポット苗を購入。
デージーとクモマグサは寄せ植えにし、写真を撮って
一度アップしましたが、ポリジは先延ばしになっていました。
お花を植え付けたのは4月7日でしたが、あっという間に大きくなり、
4月11日にはもうお花が咲いていました。

ポリジ、4月7日。まだ蕾です。

手前の勿忘草

ポリジ、4月12日の様子。

ポリジ、4月23日の様子。
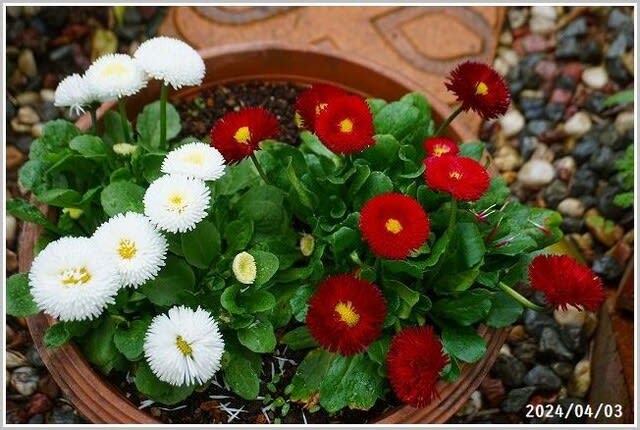
寄せ植え④ デージー2p
2月15日にポット苗2株を植えました。
30㎝の丸鉢には3ポット植えていたのですが、
今年は2ポットにしてみました。
今は花色が少し薄れましたが、鉢いっぱいに広がっています。

寄せ植え⑤ クモマグサ2p
クモマグサもデージーと同じ2月15日に、ポット苗2株を植えました。
2ポットでは鉢の隙間が多く、咲植えてからしばらくは
寂しい感じがしましたが、こちらも今は鉢いっぱいに咲いています。