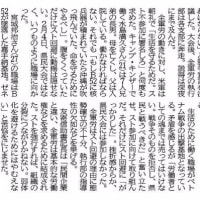給与生活というのは、長い間、労働の世界で最も不安定な身分のひとつだった。雇われ者の境涯に落ちるのは、食い詰めた農民や職人、親方になり損ねた徒弟と相場が決まっていた。第三共和制時代の1922年、政府の主翼だった急進党はマルセイユの党大会で、その選挙綱領に「奴隷制の遺物たる賃金労働制の廃止」を掲げていた。
『社会福祉問題の変容』の中でロベール・カステルは(1)、賃金労働がたどってきた長い足取りを分析している。賃金労働は、1950年代から70年代までの経済成長期(それは結局、資本主義としては例外的なものでしかなかった)の間に、上述の先入観を克服して現代社会の標準モデルとなるに至った。それはひいては我々の社会制度と意識を深く規定している。
70年代までとほぼ逆行する変化が、ここ30年間に進行した。この変化は、今や就業人口の89%を占める賃金労働関係そのものを危うくするまでには至らなかった。ところが、ここ最近、新規採用契約(CNE)や初採用契約(CPE)といった措置が打ち出されている。この措置は、失業者のうち特定の層が対象にされているが、そのじつ労働法そのものに対する侵害にほかならない。そこには、給与所得者の法的地位を揺さぶりかねない要素が含まれている。過去30年間にわたり、賃金労働に関わる規範が細分化され、労働者の分断が深められたあげく、賃金労働の核心部分そのものに雇用不安を注入することが目指されているのである。
無期限の雇用契約が、安定雇用という規範を体現するものとなるまでには、数度にわたるステップアップが必要とされた。現行法上の無期限契約の規定は、労使関係の長い歴史の末に到達した成果である。というのも、賃労働が成立した当初の時期には、むしろ職場を替えるということが、自分たちの生活を左右する雇い主に対して賃労働者が最初に表明できた抵抗だったからである(2)。19世紀の労働契約では、労働者の拘束は一定期間に限られなければならなかった(民法典1780条にあるように「役務提供の約束は一定期間に特定の事業に関して行うものに限定されなければならない」のである)。それは労働者が奴隷状態あるいは隷属状態に陥る危険を防ぐためだった。そこには、1791年のル・シャプリエ法によって同業組合が禁止された結果、雇用関係が両当事者の個人的な契約関係に限定され、一般法の下に置かれたという要素が働いている(3)。
賃労働者がより安定した法的地位を要求するようになるのは19世紀末になってからである。これに対する最初の答えが1890年、期限の定めのない役務貸借契約の規定が民法典に導入されたことである。しかしこの契約では、当事者のいずれかによる一方的な契約破棄は全面的に自由とされていた。そのため、現在の無期限契約の原形となる当時の労働契約は、当事者の拘束期間が対象業務の期間に限られる一般的な契約に比べ、はなはだ柔軟な性格のものという印象を与えた(歴史の皮肉)。
無期限契約(正社員契約)が安定雇用の保障となったのは、3つの重要な要素が導入されたことによる。事前通告の義務(1958年)、解雇時の補償金(1967年)、個別解雇か整理解雇かをとわず、現実かつ重大な解雇理由を示す義務(1973年法および1975年法)である。1973年以前には、馘になった従業員が雇用者側の権利濫用を立証しなければならなかった。1973年法が施行されると、雇用者の側が解雇理由を示し、その是非を裁判所が判断することになった。この違いは大きい。
長期的な雇用関係は、経済成長期の新たな要請に対応するものだった。成長を支えた労働の科学的組織化が、企業における労働力の安定を求めたからである。フランスでは、無期限契約という規範の一番徹底した形は大企業において見られた。大企業では、労働の分担と報酬に関する基本ルールが労働協約にもとづいて決められ、それが給与生活者のキャリアの枠組みとなって、社会人としての一生をおおむね決定した。同じ時期、労働に関わるさまざまなリスク(病気、事故、離職など)への対策が必要だとの気運が社会的に高まり、それらのリスクを考慮した労働法と社会保障制度の整備につながっていく。こうして労働契約は、単なる個人間の双務契約の域にとどまらない重要性を帯びる。その究極の形が完全雇用である。完全雇用は公共の責任として重要視され、その責務は企業が、また高度成長期のケインズ主義的な公共政策が担った。以上の一連の要素により、賃金労働者の地位に対し、社会の結束の礎としての強力な意味が付与されたのである。
非正規雇用は拡大の一途
大量の失業が、給与生活者を圧迫する直接の脅威として、またそれが社会に広める不安感によって、この地位を弱める第一の要因となるのは当然である。しかし、給与所得者の地位を弱める変化は、働き方そのもののうちにも根をおろしつつある。企業サイドにしてみれば、技術システムの急速な変化、市場の不安定さ、競争の熾烈化が、現在見られるような労働の柔軟化をますます必須のものとする。その際には二通りの論理が使われる。ひとつは社内での柔軟化で、従業員の位置付けの見直し(業務再編、多職能化など)をてことする。もうひとつは対外的な柔軟化で、特定業務の遂行に限定した契約を結ぶというものだ。これは、期間を限った労働契約、派遣会社や下請企業との契約、また独立で業務を請け負う労働者の利用などの形を取る。こうして、経済的リスクの一部あるいは全部が第三者に転嫁されてゆく。
この二つの論理は、企業により異なった組み合わせで用いられているが、全国的にみると雇用の柔軟化という大きな趨勢のもとに、第二の論理が促進されている。ますます勢いを強める自由主義的な分析の影響のもと、失業がなくならないのも何より労働力市場の「硬直性」のため、特に労働契約が法律と協約によって規制されているからだと診断されているのだ。臨時雇用、有期限契約、パートタイムといった、特殊な雇用の形が発達しはじめたのは、逆説的なことに、無期限契約が次第にいろいろな保護措置を整え、標準的な雇用形態になりつつあった70年代だった。しかも、これら非正規の雇用形態に関する規制は、無期限契約を基準にして作られている。
有期限契約と臨時採用は、企業の平常業務との関連性のない仕事にしか使えないことになっている。ところが、法制の変更によって、これらの雇用形態の対象範囲が大きく拡張されようとしている。それに、雇用者は必ずしも規制を守らない。いや、それどころではない。有期限契約はフランスの全雇用の中では13%を占めるにすぎないが(4)、新規採用では標準になっているのだから。従業員10名以上の民間企業では、2004年の新規採用者100人あたり73人が短期契約である(5)。この点についての国際比較は、契約形態が各国の特徴に根ざしているだけに、一概にはできない。例えば英国の場合、終身契約は雇用者にとって拘束的でも高コストでもなく、一時雇用の利用は欧州連合(EU)平均14%に対して6%と、きわめて限られている(6)。だからといって雇用不安がないとは決して言えない。それは安定雇用の内側に忍び込み(定職はあっても生活が苦しい)、あるいは終身契約の頻繁な破棄という形で広がっている(7)。
労働の柔軟化のもうひとつの手段が、雇用期間を生産期間に合わせて設定するパートタイムである。その地位は一様ではない。フランスではパートタイムの導入は、45%を占めるオランダ、26%の英国、22%のドイツなど一部のEU諸国に比べて「遅れて」いる。とはいえ、パート労働は過去10年間に毎年1ポイントの増加を見せており、今や17%に達している。
若者、女性、高齢者は、労働力市場の「周辺的存在」どころではないにもかかわらず、労組に代弁者がほとんどいないため、雇用形態の変容を大きく推進する要因となってきた。つまり、別枠としてあしらわれているせいで、これらの層の地位は極端に脅かされている。労働力人口の過半数を占め、現在進行中の変化の担い手となっている若者、女性、高齢者という層は、雇用形態の全般的な見直しという動きに一役かわされてしまっているのである。
労働力市場に新規参入する立場に置かれた若者は、一時雇用の最大の標的である。競争的な産業部門では、29歳未満の年齢層の3分の1が有期限契約で雇われている。非営利部門(補助金付きの雇用、派遣社員、契約社員など)ではもっと多く、40%に達する。たしかに、期限付き雇用の割合は年齢とともに下がっていく。しかし現在では、労働統計によって明らかなように、各世代が得られる定職の数は、最終的に前の世代より少なくなっている(8)。要するに、若い世代は社会の変化の最前線に置かれているのだ。第一に、雇用に関わる規範が崩れ、それとともに給与所得者としての法的地位に基づいた従来の保護、特に失業保険が風化していることの影響を真っ先に被っている(被保険者資格の基準から言って、若者で失業保険を受けられるのは、3人に1人がせいぜいだ)。第二に、こうした時流に直面した若者たちは、心底からこんなふうに望んでいる。時間をかけて自分を磨き、技術変化に迫られたときに仕事を替えられるようにしておきたい、自分の職業経験が転職の際に評価され、転職するなら追い込まれてではなく自分の選択として行いたい・・・。
質の低い雇用を増やすだけの政府
女性の場合、就職率が過去20年一貫して増大しており、平均学歴が今や男性を抜いているにもかかわらず、パートタイム労働の最大の標的にされている。15歳から59歳までの就業者に占めるパートの比率は、2004年現在、男性が5%に対して女性では30%にのぼる。たしかに、パートという労働形態の割合や影響は、年齢、仕事に必要な能力、労働契約の性格などによって異なる。しかし、大半はほとんど熟練を必要とせず、さらに大多数は時給ベースの細切れ仕事でしかない。収入、将来の年金、今後の職歴といったことを考えれば、パートの不利益はいっそう増す。しかも、もっと仕事をしたいと望む賃金労働者のうち120万人がパートの仕事しか得られていないため(9)、法定最低賃金による所得保障制度は大きく空洞化しつつある。時給ベースで設定される法定最低賃金では、もはや、勤労貧困層の増大を食い止められない。法定最低賃金を下回る給与で働く人の数は、2003年現在で350万人にのぼっており、その80%が女性である。彼女たちにも心からの望みがある。特に、仕事の時間と自分の時間の兼ね合いであり、それをうまくやりくりするのはパート労働ではむずかしい。
高齢者はどうかと言えば、これまで長いこと早期退職を奨励する政策がとられ、現役労働人口から排除されてきたのが、ここにきて年金制度改革の圧力のもと、なにか仕事に就くようにと言われている。しかし、その雇用形態は、パートタイム、不定期雇用、一時雇用といった特殊なものでしかない。さらに現在では、57歳以上の失業者を対象として、更新可能な18カ月のシニア向け有期限契約なる施策が打ち出されている。
対象者が200万人を超えるまでに補助金付き雇用を促進することによって、政府は不安定な雇用を広めるのに大きく加担した。しかも、新たな雇用形態の試行と制度化は、たんに法律上の労働契約の形式という面にとどまらない。社会保障費の企業負担分を免除する(2005年には総額240億ユーロ)との原則が打ち出されたことで、雇用者は社会保障の財源を分担する責任を免れるようになった。低賃金労働者の雇用には、特に大幅な減免措置が認められている。減免率は、雇用した労働者の賃金が法定最低レベルなら26%で、賃金レベルによって段階的に引き上げられ、法定最低賃金の1.7倍でゼロになる。非営利部門では、社会保障費のほぼ全額を政府が負担しているせいで、労働法が歪められている。雇い主にとってほとんどコストのかからない労働者に、いったいどれほどの価値が認められるというのか。
政府が進めている施策の問題は、さらに広く言えば、質の低い雇用の促進によって、長期的な失業対策のないまま一時的な解決に終始していることだ。2004年には850万人に交付された雇用手当もまた(10)、まともな賃金を払うという雇用者の義務を免除して、賃金が足りない分は政府の負担で補填するという仕組みでしかない。
これまでのところでは、雇用が極端に不安定になったとは言えない。フルタイムの無期限契約は、今も過半数であり、全雇用のうちに占める比率は減りつつあるとはいえ、2004年でもなお86%である(1975年には91%だった)。なにより、新規採用に占める比率が経済成長回復期に伸びた。こうして、1997年から2001年までの間に、企業は大量に無期限契約で採用した。このことから考えて、生産条件が変化したから雇用の柔軟化が企業にとって客観的に必要だという説は割り引いて考えた方がよい。
雇用の不安定化の影響をまず第一に受けているのは、企業の中で勤続年数が1年未満の社員である。最近入社したばかりで、一時契約の形がとられているからだ。彼らの場合、職を失うリスクは、他の条件は何も変わらない(個別の採用という点は変わらない)のに、1970年代以来ほぼ3.5倍に増大した。他方、勤続年数が10年を超える従業員の雇用は相変わらず安定している(11)。ある時点で期限付きで雇われていた従業員の1年後の正社員転換率が絶えず低下しているだけに、この両極の断絶は、ますます深まる一方である。
不安定雇用に追い込まれるという状況は、特殊な少数の現象どころではない。労働力人口の8~10%は過去3年以上にわたって失業しているか、不安定な職しか得られていない。欧州諸国を比較すると、フランスは失業者がすぐに代わりの職を得られる率が低い。2000年に失業中だった者のうち2001年に新しい働き口を見つけたケースは、当時のEU15カ国平均では41%だが、フランスは32%である(12)。
給与所得者の法的地位とは
こうした不平等の拡大と並行して、勤続年数の長い従業員に対する圧力も増加している。勤務時間の弾力的な延長、成果の要求、「顧客」からの圧力といったことだ。その一方で、失業はもはや他人事ではなくなり、それがまさしく職場における規律の手段として働いている。自主判断を求められ、多職能化への対応も迫られるという状況で、職場のストレスと苦痛は増すばかりだ。しかも、無期限契約による定職そのものが、整理解雇や個別解雇の増加によって危うくなっている。そのまま失業者となる者はたしかに少ないが、解雇の事実はその対象とされた従業員に深い傷跡として残っていく。
こうした動きがさらに決定的に強められそうな気配がある。2006年1月11日の破毀院(最高裁)判決は、予防解雇の合法化に向けて突破口を開くものだった。パージュ・ジョーヌ社が職能階級の見直しと解雇を実施した際の根拠は、たんに技術の変化に対処するため、あるいは競争力維持のために必要だということでしかなかったのに、この主張がなんと裁判で認められたのである(13)。
現在進められている労働契約改革は、零細企業には新規採用契約、若者には初採用契約、高齢者には有期限契約というふうに、一定の層に絞り込んで対策を講じるという古典的な政策の踏襲であって、「若者の4人に1人が失業している」と危機感を大げさに煽り立てようとするものだが、じつは在学中の者を計算に入れれば16歳から25歳までの者のうち13人に1人にすぎない。一連の政府の決定が中期的にねらっているのは、労働法の作り替えである。2つの公式報告によって推奨されているように(14)、有期限契約と無期限契約を一元化して、二本立てによる影響を断ち切ってしまおうというのは、一見魅力的な提案かもしれない。しかし第一に、それでも二元性は残る。新規採用者と長期勤続者はやはり区別されるだろう。第二に、有期限契約と無期限契約を統合しようとすれば、解雇に対する保護が大幅に切り下げられることは必至である。
企業が雇用を吸い込んでは吐き出すポンプにすぎないと考えるのは無理がある。雇用が実際にどれぐらいの柔軟性を示すかは、労働力市場の部門ごと、労働力の種類ごとに、個々ばらばらである。それを示しているのが、有能な従業員を維持・獲得するための戦略であり、企業の人事部長は相手に応じた契約を準備し、個別の交渉で給与を決めようとする。とはいえ、個別交渉モデルの場合、対象者は(どんなに有能であっても)自分の能力をもっぱら市場によって評価されるというリスクに迫られるのであり、頼るのは自分の交渉力だけ、労働協約による保護はほとんど望めないことになる。従来は給与所得者という法的地位によって保護されていたのが、たんなる個人間の契約に逆戻りすることで、この労働者はいっそうの危険に曝されてしまう。それに、いつ馘になるかもしれないのに、仕事に打ち込み、自己研鑽に努めようなどという気になれるものだろうか。
したがって、目下の争点は、給与所得者の法的地位を規定しなおすこと、つまり薄弱化が指摘されている労働契約を基準にするのではなく、一生の間ずっと同じ仕事を続ける可能性が低くなった個々の人間に付随した地位を規定することにある(勤務先の変更、教育訓練の期間、配置転換、長期の無給休暇など)。無数の提案が出されており、すでにあった言葉が別の意味のもとに提唱されているような例もある。たとえば「職業関連社会保障」は、労働総同盟(CGT)の新たな検討課題とされているものだが、先に述べた有期限契約と無期限契約の一元化の提唱者も同じ言葉を使っている。
こうした数々の提案は、将来への展望を開くものではあるが、多くの問題も提起している。それらをめぐる論争は、まだまだ決着がつくどころではない。もし労働契約と直接関係しないさまざまな権利を基準として、広い意味での(教育訓練なども含めた)社会保障を制度化するならば、企業は雇用や失業に関して公共的な責任を一切負わないことになる。企業はすぐさま、過去に障害者の採用を拒否したときと同じように、従業員の解雇に関しても政府に過料を納めることで「手打ちをする」ようになるだろう。給与所得者の法的地位を個人単位で規定しなおすためには、雇用そのものの再定義から始める必要がある。新たに定義される雇用は、競争を至上命令とした窮屈で一方的な労務管理の所産であってはならない。雇用は公共的に形づくられるものとして、その内容自体が、まさに社会的な規制の対象とされるべきである。
(1) ロベール・カステル『社会福祉問題の変容』(ファイヤール社、パリ、1995年;ガリマール社フォリオ評論叢書より再版、パリ、1999年)。
(2) ダミアン・ソーズ「雇用の安定:社会闘争の成果か、経営者のポリシーか」(『労働と雇用』103号、フランス国立統計経済研究所、パリ、2005年7-9月)。
(3) 労働に関する法制が特別法として登場したのは1910年の労働法典の成立による。
(4) 補助金付き雇用契約と労働研修契約を含めた数値。
(5) 研究調査統計推進局「2004年第四四半期における労働力動向」(『情報フラッシュ・統計フラッシュ』32-2号、パリ、2005年8月、http://www.travail.gouv.fr/)。
(6) 「ヨーロッパの雇用、2005年度」(欧州委員会雇用・社会問題総局、ブリュッセル、http://www.europa.eu.int/)。
(7) 「雇用の不安定化と労組の代表」(『経済社会研究所国際時報』97号、ノワジー・ル・グラン、2005年11月)。
(8) ヤニック・フォンドゥール、クロード・ミンニ「労働市場の力学の渦中に置かれた若年雇用」(『経済と統計』378-379号、フランス国立統計経済研究所、パリ、2005年7月)。
(9) パートタイム労働者の総数は420万人である。「不完全雇用の対象者が120万に」(『国立統計経済研究所フラッシュ』1046号、2005年10月、http://www.insee.fr/)参照。
(10) この手当は、所得税納付者の場合は税額控除の形をとり、それ以外の者(こちらの方が多い)の場合は実額が支給される。
(11) リュック・ベアゲル「雇用の不安定性:勤続年数の保護的役割は低下したのか」(雇用調査センター資料24号、2003年4月、http://www.cee-recherche.fr/)。
(12) 「雇用の安定-経済変容の課題を前に」(雇用・所得・社会的結束評議会報告5号、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2005年、http://www.cerc.gouv.fr/)。
(13) 電話帳会社パージュ・ジョーヌ社は、インターネットと携帯電話の普及による影響の先取りとして、2001年に社員9人を解雇するとともに、販売員930人との契約内容に変更を加えた。この変更を拒否した多数の販売員が経済的理由のもとに馘にされた。
(14) ミシェル・カムドゥシュ「飛躍、フランスのための新たな成長に向けて」(経済・財務・産業省への報告書、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2004年10月)、ピエール・カユク、フランシス・クラマルズ「雇用不安から流動性へ:職業関連社会保障に向けて」(経済・財務・産業省および雇用・労働・社会的結束省への報告書、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2004年12月、http://www.ladocumentationfrancaise.fr/)。
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2006年3月号)
『社会福祉問題の変容』の中でロベール・カステルは(1)、賃金労働がたどってきた長い足取りを分析している。賃金労働は、1950年代から70年代までの経済成長期(それは結局、資本主義としては例外的なものでしかなかった)の間に、上述の先入観を克服して現代社会の標準モデルとなるに至った。それはひいては我々の社会制度と意識を深く規定している。
70年代までとほぼ逆行する変化が、ここ30年間に進行した。この変化は、今や就業人口の89%を占める賃金労働関係そのものを危うくするまでには至らなかった。ところが、ここ最近、新規採用契約(CNE)や初採用契約(CPE)といった措置が打ち出されている。この措置は、失業者のうち特定の層が対象にされているが、そのじつ労働法そのものに対する侵害にほかならない。そこには、給与所得者の法的地位を揺さぶりかねない要素が含まれている。過去30年間にわたり、賃金労働に関わる規範が細分化され、労働者の分断が深められたあげく、賃金労働の核心部分そのものに雇用不安を注入することが目指されているのである。
無期限の雇用契約が、安定雇用という規範を体現するものとなるまでには、数度にわたるステップアップが必要とされた。現行法上の無期限契約の規定は、労使関係の長い歴史の末に到達した成果である。というのも、賃労働が成立した当初の時期には、むしろ職場を替えるということが、自分たちの生活を左右する雇い主に対して賃労働者が最初に表明できた抵抗だったからである(2)。19世紀の労働契約では、労働者の拘束は一定期間に限られなければならなかった(民法典1780条にあるように「役務提供の約束は一定期間に特定の事業に関して行うものに限定されなければならない」のである)。それは労働者が奴隷状態あるいは隷属状態に陥る危険を防ぐためだった。そこには、1791年のル・シャプリエ法によって同業組合が禁止された結果、雇用関係が両当事者の個人的な契約関係に限定され、一般法の下に置かれたという要素が働いている(3)。
賃労働者がより安定した法的地位を要求するようになるのは19世紀末になってからである。これに対する最初の答えが1890年、期限の定めのない役務貸借契約の規定が民法典に導入されたことである。しかしこの契約では、当事者のいずれかによる一方的な契約破棄は全面的に自由とされていた。そのため、現在の無期限契約の原形となる当時の労働契約は、当事者の拘束期間が対象業務の期間に限られる一般的な契約に比べ、はなはだ柔軟な性格のものという印象を与えた(歴史の皮肉)。
無期限契約(正社員契約)が安定雇用の保障となったのは、3つの重要な要素が導入されたことによる。事前通告の義務(1958年)、解雇時の補償金(1967年)、個別解雇か整理解雇かをとわず、現実かつ重大な解雇理由を示す義務(1973年法および1975年法)である。1973年以前には、馘になった従業員が雇用者側の権利濫用を立証しなければならなかった。1973年法が施行されると、雇用者の側が解雇理由を示し、その是非を裁判所が判断することになった。この違いは大きい。
長期的な雇用関係は、経済成長期の新たな要請に対応するものだった。成長を支えた労働の科学的組織化が、企業における労働力の安定を求めたからである。フランスでは、無期限契約という規範の一番徹底した形は大企業において見られた。大企業では、労働の分担と報酬に関する基本ルールが労働協約にもとづいて決められ、それが給与生活者のキャリアの枠組みとなって、社会人としての一生をおおむね決定した。同じ時期、労働に関わるさまざまなリスク(病気、事故、離職など)への対策が必要だとの気運が社会的に高まり、それらのリスクを考慮した労働法と社会保障制度の整備につながっていく。こうして労働契約は、単なる個人間の双務契約の域にとどまらない重要性を帯びる。その究極の形が完全雇用である。完全雇用は公共の責任として重要視され、その責務は企業が、また高度成長期のケインズ主義的な公共政策が担った。以上の一連の要素により、賃金労働者の地位に対し、社会の結束の礎としての強力な意味が付与されたのである。
非正規雇用は拡大の一途
大量の失業が、給与生活者を圧迫する直接の脅威として、またそれが社会に広める不安感によって、この地位を弱める第一の要因となるのは当然である。しかし、給与所得者の地位を弱める変化は、働き方そのもののうちにも根をおろしつつある。企業サイドにしてみれば、技術システムの急速な変化、市場の不安定さ、競争の熾烈化が、現在見られるような労働の柔軟化をますます必須のものとする。その際には二通りの論理が使われる。ひとつは社内での柔軟化で、従業員の位置付けの見直し(業務再編、多職能化など)をてことする。もうひとつは対外的な柔軟化で、特定業務の遂行に限定した契約を結ぶというものだ。これは、期間を限った労働契約、派遣会社や下請企業との契約、また独立で業務を請け負う労働者の利用などの形を取る。こうして、経済的リスクの一部あるいは全部が第三者に転嫁されてゆく。
この二つの論理は、企業により異なった組み合わせで用いられているが、全国的にみると雇用の柔軟化という大きな趨勢のもとに、第二の論理が促進されている。ますます勢いを強める自由主義的な分析の影響のもと、失業がなくならないのも何より労働力市場の「硬直性」のため、特に労働契約が法律と協約によって規制されているからだと診断されているのだ。臨時雇用、有期限契約、パートタイムといった、特殊な雇用の形が発達しはじめたのは、逆説的なことに、無期限契約が次第にいろいろな保護措置を整え、標準的な雇用形態になりつつあった70年代だった。しかも、これら非正規の雇用形態に関する規制は、無期限契約を基準にして作られている。
有期限契約と臨時採用は、企業の平常業務との関連性のない仕事にしか使えないことになっている。ところが、法制の変更によって、これらの雇用形態の対象範囲が大きく拡張されようとしている。それに、雇用者は必ずしも規制を守らない。いや、それどころではない。有期限契約はフランスの全雇用の中では13%を占めるにすぎないが(4)、新規採用では標準になっているのだから。従業員10名以上の民間企業では、2004年の新規採用者100人あたり73人が短期契約である(5)。この点についての国際比較は、契約形態が各国の特徴に根ざしているだけに、一概にはできない。例えば英国の場合、終身契約は雇用者にとって拘束的でも高コストでもなく、一時雇用の利用は欧州連合(EU)平均14%に対して6%と、きわめて限られている(6)。だからといって雇用不安がないとは決して言えない。それは安定雇用の内側に忍び込み(定職はあっても生活が苦しい)、あるいは終身契約の頻繁な破棄という形で広がっている(7)。
労働の柔軟化のもうひとつの手段が、雇用期間を生産期間に合わせて設定するパートタイムである。その地位は一様ではない。フランスではパートタイムの導入は、45%を占めるオランダ、26%の英国、22%のドイツなど一部のEU諸国に比べて「遅れて」いる。とはいえ、パート労働は過去10年間に毎年1ポイントの増加を見せており、今や17%に達している。
若者、女性、高齢者は、労働力市場の「周辺的存在」どころではないにもかかわらず、労組に代弁者がほとんどいないため、雇用形態の変容を大きく推進する要因となってきた。つまり、別枠としてあしらわれているせいで、これらの層の地位は極端に脅かされている。労働力人口の過半数を占め、現在進行中の変化の担い手となっている若者、女性、高齢者という層は、雇用形態の全般的な見直しという動きに一役かわされてしまっているのである。
労働力市場に新規参入する立場に置かれた若者は、一時雇用の最大の標的である。競争的な産業部門では、29歳未満の年齢層の3分の1が有期限契約で雇われている。非営利部門(補助金付きの雇用、派遣社員、契約社員など)ではもっと多く、40%に達する。たしかに、期限付き雇用の割合は年齢とともに下がっていく。しかし現在では、労働統計によって明らかなように、各世代が得られる定職の数は、最終的に前の世代より少なくなっている(8)。要するに、若い世代は社会の変化の最前線に置かれているのだ。第一に、雇用に関わる規範が崩れ、それとともに給与所得者としての法的地位に基づいた従来の保護、特に失業保険が風化していることの影響を真っ先に被っている(被保険者資格の基準から言って、若者で失業保険を受けられるのは、3人に1人がせいぜいだ)。第二に、こうした時流に直面した若者たちは、心底からこんなふうに望んでいる。時間をかけて自分を磨き、技術変化に迫られたときに仕事を替えられるようにしておきたい、自分の職業経験が転職の際に評価され、転職するなら追い込まれてではなく自分の選択として行いたい・・・。
質の低い雇用を増やすだけの政府
女性の場合、就職率が過去20年一貫して増大しており、平均学歴が今や男性を抜いているにもかかわらず、パートタイム労働の最大の標的にされている。15歳から59歳までの就業者に占めるパートの比率は、2004年現在、男性が5%に対して女性では30%にのぼる。たしかに、パートという労働形態の割合や影響は、年齢、仕事に必要な能力、労働契約の性格などによって異なる。しかし、大半はほとんど熟練を必要とせず、さらに大多数は時給ベースの細切れ仕事でしかない。収入、将来の年金、今後の職歴といったことを考えれば、パートの不利益はいっそう増す。しかも、もっと仕事をしたいと望む賃金労働者のうち120万人がパートの仕事しか得られていないため(9)、法定最低賃金による所得保障制度は大きく空洞化しつつある。時給ベースで設定される法定最低賃金では、もはや、勤労貧困層の増大を食い止められない。法定最低賃金を下回る給与で働く人の数は、2003年現在で350万人にのぼっており、その80%が女性である。彼女たちにも心からの望みがある。特に、仕事の時間と自分の時間の兼ね合いであり、それをうまくやりくりするのはパート労働ではむずかしい。
高齢者はどうかと言えば、これまで長いこと早期退職を奨励する政策がとられ、現役労働人口から排除されてきたのが、ここにきて年金制度改革の圧力のもと、なにか仕事に就くようにと言われている。しかし、その雇用形態は、パートタイム、不定期雇用、一時雇用といった特殊なものでしかない。さらに現在では、57歳以上の失業者を対象として、更新可能な18カ月のシニア向け有期限契約なる施策が打ち出されている。
対象者が200万人を超えるまでに補助金付き雇用を促進することによって、政府は不安定な雇用を広めるのに大きく加担した。しかも、新たな雇用形態の試行と制度化は、たんに法律上の労働契約の形式という面にとどまらない。社会保障費の企業負担分を免除する(2005年には総額240億ユーロ)との原則が打ち出されたことで、雇用者は社会保障の財源を分担する責任を免れるようになった。低賃金労働者の雇用には、特に大幅な減免措置が認められている。減免率は、雇用した労働者の賃金が法定最低レベルなら26%で、賃金レベルによって段階的に引き上げられ、法定最低賃金の1.7倍でゼロになる。非営利部門では、社会保障費のほぼ全額を政府が負担しているせいで、労働法が歪められている。雇い主にとってほとんどコストのかからない労働者に、いったいどれほどの価値が認められるというのか。
政府が進めている施策の問題は、さらに広く言えば、質の低い雇用の促進によって、長期的な失業対策のないまま一時的な解決に終始していることだ。2004年には850万人に交付された雇用手当もまた(10)、まともな賃金を払うという雇用者の義務を免除して、賃金が足りない分は政府の負担で補填するという仕組みでしかない。
これまでのところでは、雇用が極端に不安定になったとは言えない。フルタイムの無期限契約は、今も過半数であり、全雇用のうちに占める比率は減りつつあるとはいえ、2004年でもなお86%である(1975年には91%だった)。なにより、新規採用に占める比率が経済成長回復期に伸びた。こうして、1997年から2001年までの間に、企業は大量に無期限契約で採用した。このことから考えて、生産条件が変化したから雇用の柔軟化が企業にとって客観的に必要だという説は割り引いて考えた方がよい。
雇用の不安定化の影響をまず第一に受けているのは、企業の中で勤続年数が1年未満の社員である。最近入社したばかりで、一時契約の形がとられているからだ。彼らの場合、職を失うリスクは、他の条件は何も変わらない(個別の採用という点は変わらない)のに、1970年代以来ほぼ3.5倍に増大した。他方、勤続年数が10年を超える従業員の雇用は相変わらず安定している(11)。ある時点で期限付きで雇われていた従業員の1年後の正社員転換率が絶えず低下しているだけに、この両極の断絶は、ますます深まる一方である。
不安定雇用に追い込まれるという状況は、特殊な少数の現象どころではない。労働力人口の8~10%は過去3年以上にわたって失業しているか、不安定な職しか得られていない。欧州諸国を比較すると、フランスは失業者がすぐに代わりの職を得られる率が低い。2000年に失業中だった者のうち2001年に新しい働き口を見つけたケースは、当時のEU15カ国平均では41%だが、フランスは32%である(12)。
給与所得者の法的地位とは
こうした不平等の拡大と並行して、勤続年数の長い従業員に対する圧力も増加している。勤務時間の弾力的な延長、成果の要求、「顧客」からの圧力といったことだ。その一方で、失業はもはや他人事ではなくなり、それがまさしく職場における規律の手段として働いている。自主判断を求められ、多職能化への対応も迫られるという状況で、職場のストレスと苦痛は増すばかりだ。しかも、無期限契約による定職そのものが、整理解雇や個別解雇の増加によって危うくなっている。そのまま失業者となる者はたしかに少ないが、解雇の事実はその対象とされた従業員に深い傷跡として残っていく。
こうした動きがさらに決定的に強められそうな気配がある。2006年1月11日の破毀院(最高裁)判決は、予防解雇の合法化に向けて突破口を開くものだった。パージュ・ジョーヌ社が職能階級の見直しと解雇を実施した際の根拠は、たんに技術の変化に対処するため、あるいは競争力維持のために必要だということでしかなかったのに、この主張がなんと裁判で認められたのである(13)。
現在進められている労働契約改革は、零細企業には新規採用契約、若者には初採用契約、高齢者には有期限契約というふうに、一定の層に絞り込んで対策を講じるという古典的な政策の踏襲であって、「若者の4人に1人が失業している」と危機感を大げさに煽り立てようとするものだが、じつは在学中の者を計算に入れれば16歳から25歳までの者のうち13人に1人にすぎない。一連の政府の決定が中期的にねらっているのは、労働法の作り替えである。2つの公式報告によって推奨されているように(14)、有期限契約と無期限契約を一元化して、二本立てによる影響を断ち切ってしまおうというのは、一見魅力的な提案かもしれない。しかし第一に、それでも二元性は残る。新規採用者と長期勤続者はやはり区別されるだろう。第二に、有期限契約と無期限契約を統合しようとすれば、解雇に対する保護が大幅に切り下げられることは必至である。
企業が雇用を吸い込んでは吐き出すポンプにすぎないと考えるのは無理がある。雇用が実際にどれぐらいの柔軟性を示すかは、労働力市場の部門ごと、労働力の種類ごとに、個々ばらばらである。それを示しているのが、有能な従業員を維持・獲得するための戦略であり、企業の人事部長は相手に応じた契約を準備し、個別の交渉で給与を決めようとする。とはいえ、個別交渉モデルの場合、対象者は(どんなに有能であっても)自分の能力をもっぱら市場によって評価されるというリスクに迫られるのであり、頼るのは自分の交渉力だけ、労働協約による保護はほとんど望めないことになる。従来は給与所得者という法的地位によって保護されていたのが、たんなる個人間の契約に逆戻りすることで、この労働者はいっそうの危険に曝されてしまう。それに、いつ馘になるかもしれないのに、仕事に打ち込み、自己研鑽に努めようなどという気になれるものだろうか。
したがって、目下の争点は、給与所得者の法的地位を規定しなおすこと、つまり薄弱化が指摘されている労働契約を基準にするのではなく、一生の間ずっと同じ仕事を続ける可能性が低くなった個々の人間に付随した地位を規定することにある(勤務先の変更、教育訓練の期間、配置転換、長期の無給休暇など)。無数の提案が出されており、すでにあった言葉が別の意味のもとに提唱されているような例もある。たとえば「職業関連社会保障」は、労働総同盟(CGT)の新たな検討課題とされているものだが、先に述べた有期限契約と無期限契約の一元化の提唱者も同じ言葉を使っている。
こうした数々の提案は、将来への展望を開くものではあるが、多くの問題も提起している。それらをめぐる論争は、まだまだ決着がつくどころではない。もし労働契約と直接関係しないさまざまな権利を基準として、広い意味での(教育訓練なども含めた)社会保障を制度化するならば、企業は雇用や失業に関して公共的な責任を一切負わないことになる。企業はすぐさま、過去に障害者の採用を拒否したときと同じように、従業員の解雇に関しても政府に過料を納めることで「手打ちをする」ようになるだろう。給与所得者の法的地位を個人単位で規定しなおすためには、雇用そのものの再定義から始める必要がある。新たに定義される雇用は、競争を至上命令とした窮屈で一方的な労務管理の所産であってはならない。雇用は公共的に形づくられるものとして、その内容自体が、まさに社会的な規制の対象とされるべきである。
(1) ロベール・カステル『社会福祉問題の変容』(ファイヤール社、パリ、1995年;ガリマール社フォリオ評論叢書より再版、パリ、1999年)。
(2) ダミアン・ソーズ「雇用の安定:社会闘争の成果か、経営者のポリシーか」(『労働と雇用』103号、フランス国立統計経済研究所、パリ、2005年7-9月)。
(3) 労働に関する法制が特別法として登場したのは1910年の労働法典の成立による。
(4) 補助金付き雇用契約と労働研修契約を含めた数値。
(5) 研究調査統計推進局「2004年第四四半期における労働力動向」(『情報フラッシュ・統計フラッシュ』32-2号、パリ、2005年8月、http://www.travail.gouv.fr/)。
(6) 「ヨーロッパの雇用、2005年度」(欧州委員会雇用・社会問題総局、ブリュッセル、http://www.europa.eu.int/)。
(7) 「雇用の不安定化と労組の代表」(『経済社会研究所国際時報』97号、ノワジー・ル・グラン、2005年11月)。
(8) ヤニック・フォンドゥール、クロード・ミンニ「労働市場の力学の渦中に置かれた若年雇用」(『経済と統計』378-379号、フランス国立統計経済研究所、パリ、2005年7月)。
(9) パートタイム労働者の総数は420万人である。「不完全雇用の対象者が120万に」(『国立統計経済研究所フラッシュ』1046号、2005年10月、http://www.insee.fr/)参照。
(10) この手当は、所得税納付者の場合は税額控除の形をとり、それ以外の者(こちらの方が多い)の場合は実額が支給される。
(11) リュック・ベアゲル「雇用の不安定性:勤続年数の保護的役割は低下したのか」(雇用調査センター資料24号、2003年4月、http://www.cee-recherche.fr/)。
(12) 「雇用の安定-経済変容の課題を前に」(雇用・所得・社会的結束評議会報告5号、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2005年、http://www.cerc.gouv.fr/)。
(13) 電話帳会社パージュ・ジョーヌ社は、インターネットと携帯電話の普及による影響の先取りとして、2001年に社員9人を解雇するとともに、販売員930人との契約内容に変更を加えた。この変更を拒否した多数の販売員が経済的理由のもとに馘にされた。
(14) ミシェル・カムドゥシュ「飛躍、フランスのための新たな成長に向けて」(経済・財務・産業省への報告書、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2004年10月)、ピエール・カユク、フランシス・クラマルズ「雇用不安から流動性へ:職業関連社会保障に向けて」(経済・財務・産業省および雇用・労働・社会的結束省への報告書、ドキュマンタシオン・フランセーズ、パリ、2004年12月、http://www.ladocumentationfrancaise.fr/)。
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2006年3月号)