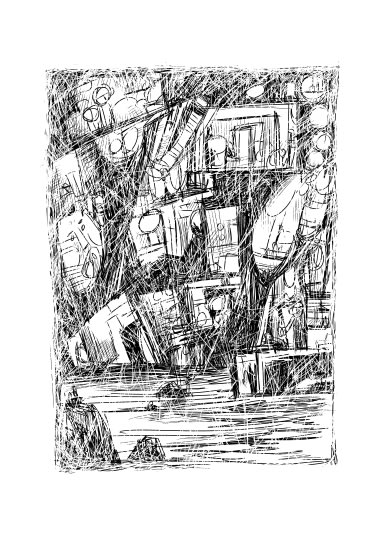どうもタブレットとPCの相性がわるいらしく、いつの間にかPCのやつが勝手に新入りタブレットのドライバーをアンインストールしてやがる(笑)。 これで3回目のインストール。 どうなる、このケンカ?
(先住猫と新入り猫のケンカみたいなものか? 仲良くやってほしい、それがわたしの望みだ。)
PC画にはインクがいらない、というのも利点だ。(欠点でもあるが。味わいがないという点で。)
実際にペンにインクを着けて描くと、途中でインクがなくなる。線を引く途中で急に終わったり。 だからといって、ペン先にたっぷりのインクをつけると、ドバっとインクが落ちて絵が台無しになったりする。
そういうところに注意しつつ描く、という緊張感はPC画では必要がなくなる。よくもわるくも。
PCではまた、ホワイト線も黒線と同じように引けるのがすばらしい。
実際にペンで描く時は、ホワイトは、ポスターカラーの白を溶いて使う。しかしこれがなかなか思うように紙に乗らなかったりする。 (なので僕は、ホワイトの場合には、ペンではなく筆を専ら使っていたものだ。)
 雪見猫。
雪見猫。
さて、小川洋子さんのこと。
図書館から『猫を抱いて象と泳ぐ』と一緒に小川さんのエッセイ集を一冊借りてきたのだけれど、その中に『盗作』というのがあった。
「エッセイというのはラクでいいよなあ。」と、ある漫画家の人が呟いていたことがあるんだけど、僕も、「そうだよな」と思う。 たしかに、小説書くとか、漫画を描くとかに比べると、格段にラクちんに思える。実際にそうだと思う。
あれが好きだ嫌いだとか品格がどうのとケチをつけておいて、それでお金をもらうというのは、妙なお仕事だ。
けども小説というのはそんなに売れないし、いい小説なんてそんなにポンポン生まれるものじゃないだろうし、それだけでは食べていけないのかもしれない。 そもそもエッセイに需要があるからお金になるわけだ。
僕自身も、小説よりもエッセイのほうを好んで読む、そういう時期があった。エッセイを読むほうがラクなのだ。
「小説を読む」にはそれなりにエネルギーがいる。
とすると、「小説(物語)」は、「エッセイ」よりも深い場所に潜らなければならない、ということか。
まあそれはいい。 小川洋子のエッセイ『盗作』のことについてしゃべらねば。これはでも、お気楽エッセイとはちがいますよ。 (スゴイです。)
このエッセイの冒頭は、ずっとボツになっていた小川洋子さんの原稿がやっと文芸誌に採用されて載ったその作品『バックストローク』が、実は‘盗作’だったということから始まっている。
そして読み進めると、びっくりするようなことが次々と書いてある。
たとえば、小川さんの付き合っていた同じ職場に勤める恋人(病院の研究室員)が、突然に横領の容疑で逮捕された、とか。まったくそんなことは知らなかった小川さんだが、あれが金を貢がせた女だとか噂され、彼女も辞めざるを得なくなった。
(付き合っている恋人が職場の金を横領し逮捕された、なんて経験をもつ人がこの世に何人いるだろう? )
その少し前、小川さんの弟が突然に亡くなった。病気や事故で…というのではない。不良グループの少年達に殴り殺されたというのだ。教会のバザーの手伝いをした帰りに。
(そんな死に方をした肉親をもつ人がこの世にどれほどいるだろう? )
その弟の葬儀から戻ってすぐ、浴室の水道を締め忘れて部屋を水浸しにしてしまい、弁償金を払い、アパートを引っ越さねばならなくなった。貯金も体力も使い果たした。
(そんな経験をした人…、そんなにはいないだろう。)
その次に起こったことが、恋人の「横領事件」なのである。
まだ続きがある。
小川さんはこの後、パン工場の自動車にはねられてしまう。
そのライトバンは小川さんを跳ね飛ばし、花屋に突っ込んだ。小川洋子の身体は道に横たわり、その周囲にはフランスパンと花びらが散っていたという。小川さんはその日、生活に困り家賃の相談に行くために外に出たのだそうだ。
全治3カ月の重症だった。両膝、肋骨、顎、右手首の骨が砕けた。見舞客は、運転手、パン工場の常務、警察官だけだった。(親とはケンカ中だった。)
ね。なんともすごい話でしょう?
(しかしここまでくると、あまりの密度の高さに笑いさえこみあげてくる。)
小川洋子さんは病室で目覚めたとき「自分は死んだんだ」と思ったそうである。だが、そうではなかった。
小川さんは退院し、それからしばらく松葉杖をついてリハビリのため病院に通った。顔の半分はプロテクターにガードされ、左膝と右手首にはギブス。
そんな姿で電車に乗って病院へ向かっていた途中、うっかり寝過ごしてしまったかと思い駅名を確かめようとしていたら、見知らぬ女性が「まだ二駅ありますよ」と声を掛けてきた。 その女性は「私も病院へ行くんです」と言った。それからこう言った。
「弟が、入院しているものですから。」
その女性の膝の上には紙袋が置かれ、そこから甘い匂いが漏れてきた。
「お土産のホットケーキ。弟の好物なんです。」
それで毎週火曜日は、小川さんはその女性と電車で会うことが重なった。
ある日、小川さんは勇気を出して、その女性にこう言った。
「お願いがあるんですけれど…。 弟さんのことを聞かせてくれませんか」
彼女の弟は水泳の背泳ぎの選手だったという。そのときに聞いたその話を、小川さんは小説にして書いた。書きながら小川洋子は回復していった。
その小説『バックストローク』が小川洋子のデビュー作となった。
その女性と会ったのは、彼女のその弟の話を聞いた時が最後だったという。
7年後に、小川洋子さんはその病院を訪れた。残っていた膝のボルトを除去する手術を受けるためだった。
“彼女”の姿がないかと捜してみた。彼女の弟は精神科病棟だったからそこを歩いてみた。見つからなかった。“弟さん”らしき人はいないだろうか。ホットケーキの匂いは…。突き当りの談話室は日当たりのいい場所だった。小川さんはふとサイドテーブルに目をやった。そこには『BACKSTOROKE』というタイトルの英語版のペーパーバックが置かれていた。古くて、表紙は擦り切れ、変色していた。
小川さんはそれを読んだ。そこには、自分が書いたのと同じ、あの女性が語ったのと同じ話が書いてあった。水泳の背泳ぎのの選手だった弟が、左腕から徐々に死に近づいていく話…。作者は1901年生まれの聞き覚えのない女性で、その名前のスペルはとても発音できそうにない綴りだった。
自分の書いたものが‘盗作’だったと知った時、小川洋子さんは、戸惑いよりも、むしろある確信が生まれたという。
「私を救い出すためにあの小説がどうしても必要だったのだ」と。
こんなディープなエッセイも、時にはある。
(先住猫と新入り猫のケンカみたいなものか? 仲良くやってほしい、それがわたしの望みだ。)
PC画にはインクがいらない、というのも利点だ。(欠点でもあるが。味わいがないという点で。)
実際にペンにインクを着けて描くと、途中でインクがなくなる。線を引く途中で急に終わったり。 だからといって、ペン先にたっぷりのインクをつけると、ドバっとインクが落ちて絵が台無しになったりする。
そういうところに注意しつつ描く、という緊張感はPC画では必要がなくなる。よくもわるくも。
PCではまた、ホワイト線も黒線と同じように引けるのがすばらしい。
実際にペンで描く時は、ホワイトは、ポスターカラーの白を溶いて使う。しかしこれがなかなか思うように紙に乗らなかったりする。 (なので僕は、ホワイトの場合には、ペンではなく筆を専ら使っていたものだ。)
 雪見猫。
雪見猫。さて、小川洋子さんのこと。
図書館から『猫を抱いて象と泳ぐ』と一緒に小川さんのエッセイ集を一冊借りてきたのだけれど、その中に『盗作』というのがあった。
「エッセイというのはラクでいいよなあ。」と、ある漫画家の人が呟いていたことがあるんだけど、僕も、「そうだよな」と思う。 たしかに、小説書くとか、漫画を描くとかに比べると、格段にラクちんに思える。実際にそうだと思う。
あれが好きだ嫌いだとか品格がどうのとケチをつけておいて、それでお金をもらうというのは、妙なお仕事だ。
けども小説というのはそんなに売れないし、いい小説なんてそんなにポンポン生まれるものじゃないだろうし、それだけでは食べていけないのかもしれない。 そもそもエッセイに需要があるからお金になるわけだ。
僕自身も、小説よりもエッセイのほうを好んで読む、そういう時期があった。エッセイを読むほうがラクなのだ。
「小説を読む」にはそれなりにエネルギーがいる。
とすると、「小説(物語)」は、「エッセイ」よりも深い場所に潜らなければならない、ということか。
まあそれはいい。 小川洋子のエッセイ『盗作』のことについてしゃべらねば。これはでも、お気楽エッセイとはちがいますよ。 (スゴイです。)
このエッセイの冒頭は、ずっとボツになっていた小川洋子さんの原稿がやっと文芸誌に採用されて載ったその作品『バックストローク』が、実は‘盗作’だったということから始まっている。
そして読み進めると、びっくりするようなことが次々と書いてある。
たとえば、小川さんの付き合っていた同じ職場に勤める恋人(病院の研究室員)が、突然に横領の容疑で逮捕された、とか。まったくそんなことは知らなかった小川さんだが、あれが金を貢がせた女だとか噂され、彼女も辞めざるを得なくなった。
(付き合っている恋人が職場の金を横領し逮捕された、なんて経験をもつ人がこの世に何人いるだろう? )
その少し前、小川さんの弟が突然に亡くなった。病気や事故で…というのではない。不良グループの少年達に殴り殺されたというのだ。教会のバザーの手伝いをした帰りに。
(そんな死に方をした肉親をもつ人がこの世にどれほどいるだろう? )
その弟の葬儀から戻ってすぐ、浴室の水道を締め忘れて部屋を水浸しにしてしまい、弁償金を払い、アパートを引っ越さねばならなくなった。貯金も体力も使い果たした。
(そんな経験をした人…、そんなにはいないだろう。)
その次に起こったことが、恋人の「横領事件」なのである。
まだ続きがある。
小川さんはこの後、パン工場の自動車にはねられてしまう。
そのライトバンは小川さんを跳ね飛ばし、花屋に突っ込んだ。小川洋子の身体は道に横たわり、その周囲にはフランスパンと花びらが散っていたという。小川さんはその日、生活に困り家賃の相談に行くために外に出たのだそうだ。
全治3カ月の重症だった。両膝、肋骨、顎、右手首の骨が砕けた。見舞客は、運転手、パン工場の常務、警察官だけだった。(親とはケンカ中だった。)
ね。なんともすごい話でしょう?
(しかしここまでくると、あまりの密度の高さに笑いさえこみあげてくる。)
小川洋子さんは病室で目覚めたとき「自分は死んだんだ」と思ったそうである。だが、そうではなかった。
小川さんは退院し、それからしばらく松葉杖をついてリハビリのため病院に通った。顔の半分はプロテクターにガードされ、左膝と右手首にはギブス。
そんな姿で電車に乗って病院へ向かっていた途中、うっかり寝過ごしてしまったかと思い駅名を確かめようとしていたら、見知らぬ女性が「まだ二駅ありますよ」と声を掛けてきた。 その女性は「私も病院へ行くんです」と言った。それからこう言った。
「弟が、入院しているものですから。」
その女性の膝の上には紙袋が置かれ、そこから甘い匂いが漏れてきた。
「お土産のホットケーキ。弟の好物なんです。」
それで毎週火曜日は、小川さんはその女性と電車で会うことが重なった。
ある日、小川さんは勇気を出して、その女性にこう言った。
「お願いがあるんですけれど…。 弟さんのことを聞かせてくれませんか」
彼女の弟は水泳の背泳ぎの選手だったという。そのときに聞いたその話を、小川さんは小説にして書いた。書きながら小川洋子は回復していった。
その小説『バックストローク』が小川洋子のデビュー作となった。
その女性と会ったのは、彼女のその弟の話を聞いた時が最後だったという。
7年後に、小川洋子さんはその病院を訪れた。残っていた膝のボルトを除去する手術を受けるためだった。
“彼女”の姿がないかと捜してみた。彼女の弟は精神科病棟だったからそこを歩いてみた。見つからなかった。“弟さん”らしき人はいないだろうか。ホットケーキの匂いは…。突き当りの談話室は日当たりのいい場所だった。小川さんはふとサイドテーブルに目をやった。そこには『BACKSTOROKE』というタイトルの英語版のペーパーバックが置かれていた。古くて、表紙は擦り切れ、変色していた。
小川さんはそれを読んだ。そこには、自分が書いたのと同じ、あの女性が語ったのと同じ話が書いてあった。水泳の背泳ぎのの選手だった弟が、左腕から徐々に死に近づいていく話…。作者は1901年生まれの聞き覚えのない女性で、その名前のスペルはとても発音できそうにない綴りだった。
自分の書いたものが‘盗作’だったと知った時、小川洋子さんは、戸惑いよりも、むしろある確信が生まれたという。
「私を救い出すためにあの小説がどうしても必要だったのだ」と。
こんなディープなエッセイも、時にはある。