
画像の記事(クリックで拡大できます)は、8月6日付の読売新聞2面に掲載された大井玄先生へのインタビュー記事です。
最近同紙が1・2面を表裏対で特集連載している「長寿革命」と題されたシリーズうちの1回で、すでにお読みになった方も多いかと思います。
大井先生には当会顧問として来る9月13日(日)の学習会で講演をしていただきますが、そのことについて前回の広告頁でご紹介したとおり、日本の環境問題研究の分野において国立環境研究所所長という重職を務められた一方で、医師・医学者として、公衆衛生学、老年医学、終末期医療等の第一人者でもあられます。
詳しくはもちろん記事をご覧いただくとして、ここで簡単にご紹介したいと思います。
大井先生は「認知症患者」と呼ばれる認知能力の低下したお年寄りについて、それは多くの場合、自然な老いの本来の過程にあるにもかかわらず、私たちの社会の根深い誤解が、本人や周囲の介護者の境遇を不幸で悲惨なものにしてしまっていると、ご自身の臨床経験を交えて語っておられます。
それは記憶力の低下に伴う認知能力の低下という「中心症状」と、徘徊する、奇声を上げる、うつ状態になる等の「周辺症状」――いわゆる「困った症状」――の混同・誤解です。
私たちは「痴呆」と聞くと、その両者をいっしょくたにイメージして考え「もうどうしようもない」と思ってしまいがちではいないでしょうか?
そしてそこには「そうなったら人間もうおしまい」といったような絶望のニュアンスが色濃くあります。
(大井先生は、「認知症」という言葉よりも、元来の「痴呆症」という言葉の方がより適切な表現だとも仰っておられます。)
しかし周辺症状=困った症状とは、認知症(痴呆症)の本質でもなければ必然でもない、と大井先生は指摘されます。
この区別はある意味でシンプルなようですが、しかしこのことについての私たちの誤解とは非常に根深く、まるで盲点のようにこれまでほとんど意識されることがなかったと思います。
それだけにきわめて重要なポイントだと思われます。
そしてそうした困った「周辺症状」とは、主として周囲の重要な人たちとの人間関係のまずさ、とくにお年寄りをせかせ、間違いを指摘し、叱責する、といったような周囲の接し方によって引き起こされがちだとのことです。
「『周辺症状』……こちらは患者の置かれた環境や心身の状態によって大きな差がでてくるのです。……ここで大事なことは、認知症が進んでも会社、家族など、周囲との「何らかのつながりを維持したい」という患者の気持ちを見落とさないことです。」
そう指摘されてみると当たり前のようなのですが、痴呆のお年寄りも「正常」である私たちも、同じく感情を持ち、人と世界とつながることで安心を求める人間であることには、まったく変わりないということです。たとえ記憶力が低下して現在の周囲の状況との関係・つながりをうまく持てなくなったとしても。
私たちはそこにとてつもない壁があると、そう強く思いこんできたのではないでしょうか。
(次回に続きます)













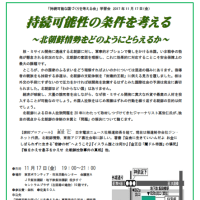
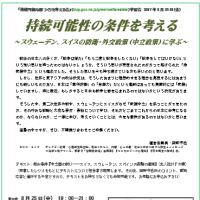

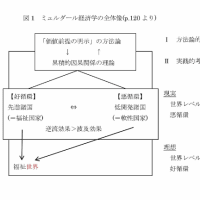



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます