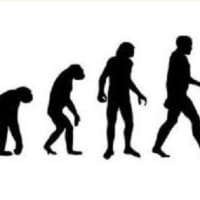本日のタイトルは小林秀雄のエッセーのパクリだが、パクリついでに彼の言葉「美しい花がある、『花』の美しさといふ様なものはない。」について、彼の真意は置いといて、哲学者ならこの言葉をどのように考えるかを簡単に説明したいと思う。それと、小林はカッコつきの「花」としている、これは世阿弥の造語としての「花」のことであるが、とりあえず植物の花の比喩として解釈するものとする。
小林が「花の美しさといふ様なものはない。」とわざわざ言うからには、一般的には「花の美しさ」というものがあると信じられているということだろう。つまり、花が美しさを持っている。美しい花には属性としての「美しさ」があるということなのだろう。赤い花は「赤い」色という属性を持っている。匂いの良い花は「良い匂い」という属性を持っている。それらと同様に、美しい花は「美しさ」という属性を持っている、と考えられているのではないだろうか? 小林の言葉はそのことに異議を唱えているように思われる。
下の左の写真をご覧いただきたい。ピンク色のバラである。このバラは「ピンク色」という属性を持っている。そのことを証明するのは簡単である。このバラの色以外の属性はそのままにして、「ピンク色」という属性だけを抜き取ったものが右の写真である。左右の写真を比較すれば、左のものには明らかに「ピンク色」が属性として備わっていることが分かる。つまり、この花には「ピンク色がある」のである。

さて次は、もしこのピンク色の花が「美しい」ということに異存がなければ、この花の他の属性はそのままで、「美しさ」だけがないというバラを想像してもらいたい。

多分、想像できないはずだ。というより、全く映像的には同じなのだから、やはり「美しい」と感じざるを得ないはずだ。このことから分かるのは、 「美しさ」はこのバラの側の属性ではなく、このバラを見る側の感性の中に存在しているのである。つまり、そのように考えてみると、「花の美しさなどというものはない」ということは当たり前で、美しい花はとにかく美しいということになる。
さて、もう少し突っ込んで小林の言葉を吟味しておきたい。「美しい花がある、『花』の美しさといふ様なものはない。」という言葉は、「当麻」というエッセーの中の言葉だが、小林は能を鑑賞した後で、世阿弥の「物数を極めて、工夫をつくして後、花の失せぬところを知るべし。」という言葉について考えている時に浮かんだ言葉である。ならば、この「花」は当然、世阿弥の造語による「花」と見なさなくてはなるまい。世阿弥は能における美を「花」と称したのである。現代に生きる日本人にはなかなか想像しにくいことだが、「美」という抽象概念が江戸時代までの日本には存在しなかったのである。そのことを以前、多和田葉子さんの「エクソフォニー」によって教えられた。つまり、世阿弥の頃には、「美」という抽象概念がまだ日本にはなかったのである。だから、能の美を表現する概念として、世阿弥は「花」という新概念をつくったのだ。つまり、「花」は「美」そのものかまたは「美」の一部である。
このように考えていくと、小林の言葉は的を外れているとも言える。その点について、多和田葉子さんは次のように指摘している。
≪また、『花伝書』の「花」という単語の使い方も面白いと思う。存在するのは「美しい花」か「花の美しさ」かなどといつまでも議論していないで、「美」を「花」と訳してしまってもよかったのではないか。≫
(「エクソフォニー」P.122)
私には彼女の指摘が当を得たもののように思える。