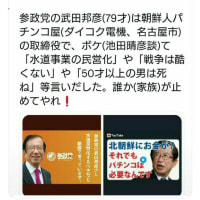認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
8/18(土) 11:00配信 文春オンライン
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
長谷川和夫氏(認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長) ©文藝春秋
2018年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第4位は、こちら!(初公開日:2018年5月6日)。
津川雅彦の長女が明かす「認知症の母、朝丘雪路と父の絆」
* * *
社会の高齢化に伴い、認知症患者が急増している。厚労省の発表によれば、2012年時点で国内の65歳以上の認知症患者数は462万人にのぼり、2025年には約700万人、高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されている。
精神科医の長谷川和夫氏(89)は、1974年に認知症診断の物差しとなる「長谷川式簡易知能評価スケール」を公表した、認知症医療の第一人者だ。認知症ケア職の人材育成にも尽力してきた長谷川氏は、昨年10月の講演で、自らも認知症であることを明かした。
半世紀にわたり認知症と向き合ってきた長谷川氏が、当事者となったいまの思いを率直に語った。
◆ ◆ ◆
私は50年以上、認知症を専門としてきました。認知症がどのようなものか、大体のことは分かっているつもりでした。
その私が認知症になって痛切に感じたのは、「確かさ」がはっきりしなくなったことです。
医師として、私は認知症は次のような段階を進んで「確かさ」が失われていく、と説明してきました。まず、今がいつなのかが明らかでなくなる。次に、今どこにいるかがはっきりしなくなる。最後に、目の前にいる人が誰なのか、分からなくなってしまう。
私の場合は、自分が話したことを忘れてしまうことから始まりました。話したと思うんだけれども、どうもそうでないような気もする。さらに、昨日の日付は分かっていたのに、翌日になると、今日が何日か分からなくなる。自宅を出るとき鍵を閉めても、鍵を閉めたことがはっきりしないから、来た道を戻って確認しなければ気が済まない。ひどいときは、一度確認したことを何度も確かめたくなる……。
こうしたことから、自分が認知症ではないかと疑いはじめました。
ありのままを受け入れる
私は当初、自分をアルツハイマー型認知症ではないかと考えました。アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞に「老人斑」というシミのようなものが広がることなどで起こる、認知症の中でも最も多いものです。
そこで、認知症専門病院である和光病院(埼玉県和光市)で、さまざまな検査をしてもらいました。
認知症の診断では、私が開発した「長谷川スケール」(1991年に改訂)を用います。長谷川スケールは、「お齢はいくつですか」「今日は何年の何月何日ですか、何曜日ですか」といった9つの質問によって構成されており、それぞれの得点を合計して、認知症の有無を診断します。しかし、開発者の私は、この質問項目を全て覚えているので、正しい診断ができない(笑)。なので、難しい心理テストをいくつも出してもらうことになりました。
その結果、私は「嗜銀顆粒(しぎんかりゅう)性認知症」と診断されました。
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
©iStock.com
60代から70代の患者が多いアルツハイマー型認知症とは違って、この認知症は80代以降の人に起こることが多いものです。特徴は、正常な状態と認知症の状態とを行ったり来たりすること。午前中はしっかりしているけれど、午後になって疲れてくると、認知症の症状が出てくる。80代、90代という、人生の晩節期に起こる認知症です。
ただ、認知症の中では、ひどい症状を引き起こすものではありません。忘れ物はたくさんするけれども、一晩寝れば治ってしまう。毎日がその繰り返しです。だから、診断を受けたときも、そんなに心配しなくて良いだろうと考えました。
認知症は、長生きすれば誰にでも起こり得ることです。だから、ありのままを受け入れるしか、仕方がありません。まずは、自分でできる範囲のことをやる。その上で、少しでも人の役に立つようなことができたら、それ以上嬉しいことはない――。そんなふうに考えながら、日々を送っています。
自分が認知症になって初めて体験したことの1つは、週に1回、デイケアに通うようになったことです。私はこれまで、患者さんに「ケア職の人に接するのはとても良いことだから、週に1度や2度でもいいから行ってごらんなさい」と勧めてきました。それが、いまでは勧められる立場になったわけです。
デイケアに通うようになって、まず驚いたのは、スタッフ一人ひとりが、利用者の情報をよく知っていることです。スタッフがそれぞれ何人かの利用者を受け持っている、というのではなく、スタッフ全員がみんなのことを把握している。こちらは馴染みのないスタッフでも、向こうは私のことをよく知っている。利用者としては、大きな安心感があります。
それに、こちらが少しでもボーッとしていると、「長谷川さん、どうしたの? 何か困ったことでもある?」「ちょっとこっちへ来て、こんな体操をやってみない?」と、すぐさま声がかかります。すれ違ったときにも「長谷川さん、お昼ご飯は美味しかった?」とかね。
簡単なゲームをする時間もあって、それがまた面白いものばかり。雰囲気は非常にゆったりとしていて、人と人とのつながりが温かい。デイケアというのは、すごいものだなと、本当に感心しました。
恥さらしとされた認知症
いま振り返れば、私はとても恵まれた境遇に置かれ、大いに学問的な刺激を受けてきました。
私は1929年、愛知県の東春日井郡牛山村で生まれました。祖父は村の庄屋で、終戦のときには祖父の家の大きなラジオで、村の人たちと一緒に玉音放送を聞いたものです。
戦後間もない1947年、私は東京慈恵会医科大学に入学し、そのまま精神神経科に入局しました。
私は18歳のころにキリスト教を信仰するようになったのですが、当時はキリスト教徒であれば、1年に10人ずつ、全国から選ばれて留学することができました。私はその試験に受かって、アメリカの東海岸にあるセント・エリザベス病院という大きな精神病院に留学しました。
当時の日本では、大きな病院といってもせいぜい700床でしたが、その病院は7000床。敷地面積はモナコ公国に匹敵するそうで、お医者さんが回診で別の病棟へ移動するのに、クルマに乗っていたのには驚かされました。そんなスケールの大きな病院で、私はとても刺激的な時間を過ごしました。
その後、2度のアメリカ留学を経て、慈恵医大の医局長を務めていたころのことです。私は新福尚武教授と一緒に、東京都内の老人ホームの利用者を対象とした、健康調査をすることになりました。このとき、私は初めて認知症の方の診断をすることになったのです。まだ「認知症」という言葉が一般的ではなく、「痴呆」と呼ばれていた時代でした。
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
©iStock.com
調査にあたり、教授がこう言いました。
「長谷川くん、君はこれから僕と一緒にお年寄りが痴呆であるかどうか、診断しなければならない。誰が診断しても同じ結果になるような尺度、スケールをつくりなさい」
こうして私は、診断のために必要な項目を作り、結果が数値化できるようなスケールを発案しました。当初は不安だったけれど、実際に使ってみると、誰が検査してもほぼ同じ結果になる。その後、いろいろな研究を重ね、1974年に「長谷川式簡易知能評価スケール」として発表しました。
スケール作りのために各地を回ったさいには、認知症の人がひどい扱い方をされているのを、たくさん目にしました。
ある家では「恥さらし」「役立たず」とされて、納屋に閉じ込められていました。家で面倒を見られなくなると、精神科病院や老人病院に入れられるのですが、入院したところで病棟では何もすることがないから、隔離するだけです。さらには、手や腰を縛られて、拘束される。いまでこそ在宅介護やグループホームが一般的となりましたが、当時はそういう時代だったのです。
戦争が終わってから歳月が経って、国民一人ひとりを大切にしようという理念が、日本の社会に少しずつ浸透していった。こうした風土が、今日の認知症ケアの土台となったのではないかと思います。
◆
2000年には、認知症ケア職の人材育成を目的とした高齢者痴呆介護研究・研修センター(現・認知症介護研究・研修センター)が東京、宮城県仙台市、愛知県大府市に新設され、長谷川氏は東京センター長に就任。それまでは認知症患者を診療する立場だった長谷川氏が、ケア職の育成に関わるようになった。
長谷川氏が考える、認知症ケアに必要なものとは何なのか。
◆
私が認知症ケアで大切にしてきたのは「パーソン・センタード・ケア」という考え方です。認知症の人を中心に考えるという理念で、イギリスのトム・キットウッドという臨床心理士が提唱したものです。
認知症の人を中心にすると言っても、ちやほやしたり、言いなりになるのが良い、というわけではありません。必要なのは「認知症の人と自分は同じだ」と考えること。同じ目線に立って話すことが、とても大切です。
また、衛生や食事、排泄などを援助する従来のケアに加えて、「その人らしさ」を尊重することも重要です。「その人らしさ」とは、明るい、几帳面、綺麗好きというような、単なる性格や性質のことではありません。それは、人生での経験や、周りの人々からの影響で作り上げられた、その人独自のユニークなものです。
表面的には同じ性格に見えても、それを形成した背景は、人それぞれ異なります。その背景を粘り強く推し量り、「その人らしさ」を理解して、お互いに代えがたい存在であることを認め合う。認知症ケアには、そんな姿勢が求められると思います。
では、認知症の人と接するとき、具体的にはどのようにしたら良いのでしょうか。
話をするときには、こちらから何か話しかけるのではなく、相手が話し始めるのを待って、何を欲しているのか、耳を傾けるのが原則です。
例えば、認知症の人が「今朝はとても寒いから、朝ごはんはいつものパン食じゃなくて、温かいお粥にしてもらいたいな」と思っているとしましょう。ところが、こちらが先に違う話を始めてしまうと、それに一生懸命答えようとして、自分が言おうとしていることを忘れてしまう。認知症の人は、頭のスイッチの切り替えがスムーズにできないのです。
だから、何か言いたいことがあるんじゃないかな、というときは「どうしたの?」「何がしたいの?」と問いかける。これで良いのです。
本人の願望を注意深く聞き取り、大切にしてあげること。これが本当の「パーソン・センタード・ケア」なのだと思います。
私は、こうした日本の認知症ケアを、世界に広めていくべきだと考えています。
日本はいま、世界有数の長寿国です。その分、認知症の有病率も、世界一高い。だからこそ、日本は認知症への対策が一番進んでいる国でもあり、世界中から注目を集めています。
特に日本に熱い視線を注いでいるのは、東南アジアの国々です。東南アジアでは、衛生環境の改善などで、社会の高齢化が加速度的に進んでおり、認知症対策が待ったなしの状況です。
日本ではこれまでも、東南アジアの認知症医療を支援するための取り組みをしてきました。現地の看護師やケア職の人を日本の介護施設などで受け入れ、働きながら訓練を受けてもらって、帰国させる。日本で得た知識を、現地の医療に生かしてもらう試みです。
ですが、この方法には無駄も多いように思います。日本で介護を学ぶには、「鬱病」や「褥瘡(じょくそう/床ずれのこと)」といった専門用語まで、覚えなければならない。でも、インドネシアやベトナムの人たちが、こんな難しい日本語を覚えたところで、母国では何の役にも立ちません。
むしろ、日本にいる専門の医師やケア職の人を、現地へ派遣するのが良いと思います。派遣された日本人は、その国の事情を勉強しながら、「日本ではこういうことをやっています」ということを現地の人に教える。その国の実情にあわせて、日本の認知症ケアを輸出するのです。そうすれば、難しい言葉を覚える必要もない。現地の人々もずいぶん助かるのではないでしょうか。
「認知症の人も私と同じ」
これからの認知症ケアには、専門職や家族だけではなく、地域の人たちの理解や接し方もとても大切になると思っています。
高齢者の数が多くなったいまでは、どこの地域でも、必ず近所に認知症の方が何人かいらっしゃるはずです。少しずつでもいいから、認知症とはどのようなものか、みんなが学ぶ。そして、「認知症の人の心は、私の心と同じ。あの人も私と同じように、楽しみたい、幸せになりたいと思っているんだ」という気持ちをもって、本人に接してみる。
こうして、認知症になっても安心して暮らせる社会をつくっていくことが、これからの日本に求められているのではないでしょうか。
私はいま、子どもたちに認知症のことを理解してもらうための絵本を作りたいと考えています。海外には、すでにそうした絵本があります。認知症の症状が進んでいくおじいちゃんを目の当たりにした孫が、いろいろな工夫をしながら、一緒に生活していく様子を物語にしたものです。僕はそれを真似して、おじいちゃんのところをおばあちゃんに変えて作ろうとしているんだけど(笑)、なかなかはかどりません。なんとか、今年の夏ごろまでには完成させたいと思っています。
◆
長らく適応薬がなかった認知症だが、1999年には製薬会社のエーザイが開発した認知症治療剤「アリセプト」が認可されている。アルツハイマー型認知症の進行を抑制する薬だ。長谷川氏は、臨床治験が始まった1989年から治験統括医に任命され、治験を成功裡に導いた人物でもある。
認知症を根治させるための薬の開発を願う患者や家族は多いだろう。しかし、長谷川氏はいまの新薬開発に対する懸念を口にした。
◆
かつての認知症は、診断しても、医師にできることがほとんどない病気でした。それが、アリセプトの登場で、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせることができるようになった。医師が「一緒に考えていきましょう」と声をかけられるようになったのは、大きな出来事でした。
アルツハイマー型認知症は、本人にとっても家族にとっても辛い病気です。
発症すると、まず「時間」の見当がつかなくなります。先ほど私の症状として申し上げたように、今日が何月何日か、いつも確認しなければならないような状態です。
さらに症状が進むと「場所」、さらには「人間」についても、はっきりしなくなります。
場所の見当がつかなくなると、近所で買い物をするために外出しても、自宅に帰ることができなくなります。自宅を探して大慌てで走り出し、あっという間に遠いところまで行ってしまう。山林に分け入って、そのまま行方不明になってしまうこともあります。
さらに、人間が分からなくなると、自分の奥さんの顔さえも忘れてしまいます。
こうして、時間、場所、人間についての記憶が、それぞれ約3年ずつかけて失われていく。そんな症状の進行を遅らせることができるアリセプトは、たいへんメリットの大きい薬でした。
ただし、症状の原因を取り除く「原因療法」になるような薬ではありません。状況を元に戻すことはできない。それで満足するしか、いまのところは仕方がないのです。
そのために、原因療法のための新薬の開発が期待されています。それに近い薬が発表されると、新聞で取り上げられることもあります。ですが、こうした新薬の副作用については報じられません。これは、非常に危ないことだと思っています。
アルツハイマー型認知症を発症させる犯人は、脳に蓄積されたアミロイドβというタンパク質です。これを取り去るような薬ができれば、認知症を根治できるかもしれませんが、副作用も必ず起こります。ですから、それを抑える薬も、同時に必要になるはずです。
しかし、原因療法のための薬ばかりが求められ、副作用を抑えるための薬が蔑ろにされている。いまの日本には、そんな風潮があるような気がしてなりません。これは、いまのアルツハイマー型認知症の治療をめぐる大きな問題点だと思います。
笑いを絶やさず、前向きに
長谷川氏は2010年に刊行した 『認知症ケアの心』 (中央法規出版)の中で、認知症とともに生きるオーストラリア人女性、クリスティーン・ブライデンさんの言葉を引用している。
〈認知症の人はそれぞれがかつて自分を定義した複雑な認知の表層や、人生を経験するなかでつくられた感情のもつれから離れて、自分の存在の中心へ人生の真の意味を与える魂の核に向かって進んでいく旅の途上にいる。この旅を支えてください〉
この「旅」をよりよいものにするためには、何が必要なのだろうか。そう尋ねると、長谷川氏はゆっくりと語りだした。
◆
一言で言うのは難しいけれども、私が認知症の人やその家族とたくさん語り合ってきた中で、1つ、感銘を受けた出来事があります。
それは、ある講演会でのこと。自分は認知症だという男性が、こう言ったのです。
「笑いましょう。笑うということがとても大切なのです」
それを聞いて私は、本当にその男性は「笑い」を大切にしているのか、知りたくなりました。住所を教えてもらい、了解をとりつけて、自宅にお邪魔したんです。その男性とは面識もなかったのに、いまになって考えると、ずいぶん大胆なことをしたものです。
はっきり覚えていませんが、その家は確か、東京の下町のほうにあったと思います。実際に伺うと、男性は本当によく笑っていた。「先生がわざわざ来てくれたんだから、コーヒーでも淹れようか、ハッハッハ!」という具合です。奥さんも「ああ、そうだね。アハハハハ」と、こちらもよく笑っている。そうやって、夫婦で明るく楽しい時間を過ごしていたのです。これは、と思いましたね。
認知症になっても、本人やその家族が笑いを絶やさず、前向きに生きていく。そのことが、とても素敵に感じられた出来事でした。
長谷川 和夫



8/18(土) 11:00配信 文春オンライン
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
長谷川和夫氏(認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長) ©文藝春秋
2018年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第4位は、こちら!(初公開日:2018年5月6日)。
津川雅彦の長女が明かす「認知症の母、朝丘雪路と父の絆」
* * *
社会の高齢化に伴い、認知症患者が急増している。厚労省の発表によれば、2012年時点で国内の65歳以上の認知症患者数は462万人にのぼり、2025年には約700万人、高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されている。
精神科医の長谷川和夫氏(89)は、1974年に認知症診断の物差しとなる「長谷川式簡易知能評価スケール」を公表した、認知症医療の第一人者だ。認知症ケア職の人材育成にも尽力してきた長谷川氏は、昨年10月の講演で、自らも認知症であることを明かした。
半世紀にわたり認知症と向き合ってきた長谷川氏が、当事者となったいまの思いを率直に語った。
◆ ◆ ◆
私は50年以上、認知症を専門としてきました。認知症がどのようなものか、大体のことは分かっているつもりでした。
その私が認知症になって痛切に感じたのは、「確かさ」がはっきりしなくなったことです。
医師として、私は認知症は次のような段階を進んで「確かさ」が失われていく、と説明してきました。まず、今がいつなのかが明らかでなくなる。次に、今どこにいるかがはっきりしなくなる。最後に、目の前にいる人が誰なのか、分からなくなってしまう。
私の場合は、自分が話したことを忘れてしまうことから始まりました。話したと思うんだけれども、どうもそうでないような気もする。さらに、昨日の日付は分かっていたのに、翌日になると、今日が何日か分からなくなる。自宅を出るとき鍵を閉めても、鍵を閉めたことがはっきりしないから、来た道を戻って確認しなければ気が済まない。ひどいときは、一度確認したことを何度も確かめたくなる……。
こうしたことから、自分が認知症ではないかと疑いはじめました。
ありのままを受け入れる
私は当初、自分をアルツハイマー型認知症ではないかと考えました。アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞に「老人斑」というシミのようなものが広がることなどで起こる、認知症の中でも最も多いものです。
そこで、認知症専門病院である和光病院(埼玉県和光市)で、さまざまな検査をしてもらいました。
認知症の診断では、私が開発した「長谷川スケール」(1991年に改訂)を用います。長谷川スケールは、「お齢はいくつですか」「今日は何年の何月何日ですか、何曜日ですか」といった9つの質問によって構成されており、それぞれの得点を合計して、認知症の有無を診断します。しかし、開発者の私は、この質問項目を全て覚えているので、正しい診断ができない(笑)。なので、難しい心理テストをいくつも出してもらうことになりました。
その結果、私は「嗜銀顆粒(しぎんかりゅう)性認知症」と診断されました。
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
©iStock.com
60代から70代の患者が多いアルツハイマー型認知症とは違って、この認知症は80代以降の人に起こることが多いものです。特徴は、正常な状態と認知症の状態とを行ったり来たりすること。午前中はしっかりしているけれど、午後になって疲れてくると、認知症の症状が出てくる。80代、90代という、人生の晩節期に起こる認知症です。
ただ、認知症の中では、ひどい症状を引き起こすものではありません。忘れ物はたくさんするけれども、一晩寝れば治ってしまう。毎日がその繰り返しです。だから、診断を受けたときも、そんなに心配しなくて良いだろうと考えました。
認知症は、長生きすれば誰にでも起こり得ることです。だから、ありのままを受け入れるしか、仕方がありません。まずは、自分でできる範囲のことをやる。その上で、少しでも人の役に立つようなことができたら、それ以上嬉しいことはない――。そんなふうに考えながら、日々を送っています。
自分が認知症になって初めて体験したことの1つは、週に1回、デイケアに通うようになったことです。私はこれまで、患者さんに「ケア職の人に接するのはとても良いことだから、週に1度や2度でもいいから行ってごらんなさい」と勧めてきました。それが、いまでは勧められる立場になったわけです。
デイケアに通うようになって、まず驚いたのは、スタッフ一人ひとりが、利用者の情報をよく知っていることです。スタッフがそれぞれ何人かの利用者を受け持っている、というのではなく、スタッフ全員がみんなのことを把握している。こちらは馴染みのないスタッフでも、向こうは私のことをよく知っている。利用者としては、大きな安心感があります。
それに、こちらが少しでもボーッとしていると、「長谷川さん、どうしたの? 何か困ったことでもある?」「ちょっとこっちへ来て、こんな体操をやってみない?」と、すぐさま声がかかります。すれ違ったときにも「長谷川さん、お昼ご飯は美味しかった?」とかね。
簡単なゲームをする時間もあって、それがまた面白いものばかり。雰囲気は非常にゆったりとしていて、人と人とのつながりが温かい。デイケアというのは、すごいものだなと、本当に感心しました。
恥さらしとされた認知症
いま振り返れば、私はとても恵まれた境遇に置かれ、大いに学問的な刺激を受けてきました。
私は1929年、愛知県の東春日井郡牛山村で生まれました。祖父は村の庄屋で、終戦のときには祖父の家の大きなラジオで、村の人たちと一緒に玉音放送を聞いたものです。
戦後間もない1947年、私は東京慈恵会医科大学に入学し、そのまま精神神経科に入局しました。
私は18歳のころにキリスト教を信仰するようになったのですが、当時はキリスト教徒であれば、1年に10人ずつ、全国から選ばれて留学することができました。私はその試験に受かって、アメリカの東海岸にあるセント・エリザベス病院という大きな精神病院に留学しました。
当時の日本では、大きな病院といってもせいぜい700床でしたが、その病院は7000床。敷地面積はモナコ公国に匹敵するそうで、お医者さんが回診で別の病棟へ移動するのに、クルマに乗っていたのには驚かされました。そんなスケールの大きな病院で、私はとても刺激的な時間を過ごしました。
その後、2度のアメリカ留学を経て、慈恵医大の医局長を務めていたころのことです。私は新福尚武教授と一緒に、東京都内の老人ホームの利用者を対象とした、健康調査をすることになりました。このとき、私は初めて認知症の方の診断をすることになったのです。まだ「認知症」という言葉が一般的ではなく、「痴呆」と呼ばれていた時代でした。
認知症医療の第一人者が語る「みずから認知症になってわかったこと」――2018上半期BEST5
©iStock.com
調査にあたり、教授がこう言いました。
「長谷川くん、君はこれから僕と一緒にお年寄りが痴呆であるかどうか、診断しなければならない。誰が診断しても同じ結果になるような尺度、スケールをつくりなさい」
こうして私は、診断のために必要な項目を作り、結果が数値化できるようなスケールを発案しました。当初は不安だったけれど、実際に使ってみると、誰が検査してもほぼ同じ結果になる。その後、いろいろな研究を重ね、1974年に「長谷川式簡易知能評価スケール」として発表しました。
スケール作りのために各地を回ったさいには、認知症の人がひどい扱い方をされているのを、たくさん目にしました。
ある家では「恥さらし」「役立たず」とされて、納屋に閉じ込められていました。家で面倒を見られなくなると、精神科病院や老人病院に入れられるのですが、入院したところで病棟では何もすることがないから、隔離するだけです。さらには、手や腰を縛られて、拘束される。いまでこそ在宅介護やグループホームが一般的となりましたが、当時はそういう時代だったのです。
戦争が終わってから歳月が経って、国民一人ひとりを大切にしようという理念が、日本の社会に少しずつ浸透していった。こうした風土が、今日の認知症ケアの土台となったのではないかと思います。
◆
2000年には、認知症ケア職の人材育成を目的とした高齢者痴呆介護研究・研修センター(現・認知症介護研究・研修センター)が東京、宮城県仙台市、愛知県大府市に新設され、長谷川氏は東京センター長に就任。それまでは認知症患者を診療する立場だった長谷川氏が、ケア職の育成に関わるようになった。
長谷川氏が考える、認知症ケアに必要なものとは何なのか。
◆
私が認知症ケアで大切にしてきたのは「パーソン・センタード・ケア」という考え方です。認知症の人を中心に考えるという理念で、イギリスのトム・キットウッドという臨床心理士が提唱したものです。
認知症の人を中心にすると言っても、ちやほやしたり、言いなりになるのが良い、というわけではありません。必要なのは「認知症の人と自分は同じだ」と考えること。同じ目線に立って話すことが、とても大切です。
また、衛生や食事、排泄などを援助する従来のケアに加えて、「その人らしさ」を尊重することも重要です。「その人らしさ」とは、明るい、几帳面、綺麗好きというような、単なる性格や性質のことではありません。それは、人生での経験や、周りの人々からの影響で作り上げられた、その人独自のユニークなものです。
表面的には同じ性格に見えても、それを形成した背景は、人それぞれ異なります。その背景を粘り強く推し量り、「その人らしさ」を理解して、お互いに代えがたい存在であることを認め合う。認知症ケアには、そんな姿勢が求められると思います。
では、認知症の人と接するとき、具体的にはどのようにしたら良いのでしょうか。
話をするときには、こちらから何か話しかけるのではなく、相手が話し始めるのを待って、何を欲しているのか、耳を傾けるのが原則です。
例えば、認知症の人が「今朝はとても寒いから、朝ごはんはいつものパン食じゃなくて、温かいお粥にしてもらいたいな」と思っているとしましょう。ところが、こちらが先に違う話を始めてしまうと、それに一生懸命答えようとして、自分が言おうとしていることを忘れてしまう。認知症の人は、頭のスイッチの切り替えがスムーズにできないのです。
だから、何か言いたいことがあるんじゃないかな、というときは「どうしたの?」「何がしたいの?」と問いかける。これで良いのです。
本人の願望を注意深く聞き取り、大切にしてあげること。これが本当の「パーソン・センタード・ケア」なのだと思います。
私は、こうした日本の認知症ケアを、世界に広めていくべきだと考えています。
日本はいま、世界有数の長寿国です。その分、認知症の有病率も、世界一高い。だからこそ、日本は認知症への対策が一番進んでいる国でもあり、世界中から注目を集めています。
特に日本に熱い視線を注いでいるのは、東南アジアの国々です。東南アジアでは、衛生環境の改善などで、社会の高齢化が加速度的に進んでおり、認知症対策が待ったなしの状況です。
日本ではこれまでも、東南アジアの認知症医療を支援するための取り組みをしてきました。現地の看護師やケア職の人を日本の介護施設などで受け入れ、働きながら訓練を受けてもらって、帰国させる。日本で得た知識を、現地の医療に生かしてもらう試みです。
ですが、この方法には無駄も多いように思います。日本で介護を学ぶには、「鬱病」や「褥瘡(じょくそう/床ずれのこと)」といった専門用語まで、覚えなければならない。でも、インドネシアやベトナムの人たちが、こんな難しい日本語を覚えたところで、母国では何の役にも立ちません。
むしろ、日本にいる専門の医師やケア職の人を、現地へ派遣するのが良いと思います。派遣された日本人は、その国の事情を勉強しながら、「日本ではこういうことをやっています」ということを現地の人に教える。その国の実情にあわせて、日本の認知症ケアを輸出するのです。そうすれば、難しい言葉を覚える必要もない。現地の人々もずいぶん助かるのではないでしょうか。
「認知症の人も私と同じ」
これからの認知症ケアには、専門職や家族だけではなく、地域の人たちの理解や接し方もとても大切になると思っています。
高齢者の数が多くなったいまでは、どこの地域でも、必ず近所に認知症の方が何人かいらっしゃるはずです。少しずつでもいいから、認知症とはどのようなものか、みんなが学ぶ。そして、「認知症の人の心は、私の心と同じ。あの人も私と同じように、楽しみたい、幸せになりたいと思っているんだ」という気持ちをもって、本人に接してみる。
こうして、認知症になっても安心して暮らせる社会をつくっていくことが、これからの日本に求められているのではないでしょうか。
私はいま、子どもたちに認知症のことを理解してもらうための絵本を作りたいと考えています。海外には、すでにそうした絵本があります。認知症の症状が進んでいくおじいちゃんを目の当たりにした孫が、いろいろな工夫をしながら、一緒に生活していく様子を物語にしたものです。僕はそれを真似して、おじいちゃんのところをおばあちゃんに変えて作ろうとしているんだけど(笑)、なかなかはかどりません。なんとか、今年の夏ごろまでには完成させたいと思っています。
◆
長らく適応薬がなかった認知症だが、1999年には製薬会社のエーザイが開発した認知症治療剤「アリセプト」が認可されている。アルツハイマー型認知症の進行を抑制する薬だ。長谷川氏は、臨床治験が始まった1989年から治験統括医に任命され、治験を成功裡に導いた人物でもある。
認知症を根治させるための薬の開発を願う患者や家族は多いだろう。しかし、長谷川氏はいまの新薬開発に対する懸念を口にした。
◆
かつての認知症は、診断しても、医師にできることがほとんどない病気でした。それが、アリセプトの登場で、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせることができるようになった。医師が「一緒に考えていきましょう」と声をかけられるようになったのは、大きな出来事でした。
アルツハイマー型認知症は、本人にとっても家族にとっても辛い病気です。
発症すると、まず「時間」の見当がつかなくなります。先ほど私の症状として申し上げたように、今日が何月何日か、いつも確認しなければならないような状態です。
さらに症状が進むと「場所」、さらには「人間」についても、はっきりしなくなります。
場所の見当がつかなくなると、近所で買い物をするために外出しても、自宅に帰ることができなくなります。自宅を探して大慌てで走り出し、あっという間に遠いところまで行ってしまう。山林に分け入って、そのまま行方不明になってしまうこともあります。
さらに、人間が分からなくなると、自分の奥さんの顔さえも忘れてしまいます。
こうして、時間、場所、人間についての記憶が、それぞれ約3年ずつかけて失われていく。そんな症状の進行を遅らせることができるアリセプトは、たいへんメリットの大きい薬でした。
ただし、症状の原因を取り除く「原因療法」になるような薬ではありません。状況を元に戻すことはできない。それで満足するしか、いまのところは仕方がないのです。
そのために、原因療法のための新薬の開発が期待されています。それに近い薬が発表されると、新聞で取り上げられることもあります。ですが、こうした新薬の副作用については報じられません。これは、非常に危ないことだと思っています。
アルツハイマー型認知症を発症させる犯人は、脳に蓄積されたアミロイドβというタンパク質です。これを取り去るような薬ができれば、認知症を根治できるかもしれませんが、副作用も必ず起こります。ですから、それを抑える薬も、同時に必要になるはずです。
しかし、原因療法のための薬ばかりが求められ、副作用を抑えるための薬が蔑ろにされている。いまの日本には、そんな風潮があるような気がしてなりません。これは、いまのアルツハイマー型認知症の治療をめぐる大きな問題点だと思います。
笑いを絶やさず、前向きに
長谷川氏は2010年に刊行した 『認知症ケアの心』 (中央法規出版)の中で、認知症とともに生きるオーストラリア人女性、クリスティーン・ブライデンさんの言葉を引用している。
〈認知症の人はそれぞれがかつて自分を定義した複雑な認知の表層や、人生を経験するなかでつくられた感情のもつれから離れて、自分の存在の中心へ人生の真の意味を与える魂の核に向かって進んでいく旅の途上にいる。この旅を支えてください〉
この「旅」をよりよいものにするためには、何が必要なのだろうか。そう尋ねると、長谷川氏はゆっくりと語りだした。
◆
一言で言うのは難しいけれども、私が認知症の人やその家族とたくさん語り合ってきた中で、1つ、感銘を受けた出来事があります。
それは、ある講演会でのこと。自分は認知症だという男性が、こう言ったのです。
「笑いましょう。笑うということがとても大切なのです」
それを聞いて私は、本当にその男性は「笑い」を大切にしているのか、知りたくなりました。住所を教えてもらい、了解をとりつけて、自宅にお邪魔したんです。その男性とは面識もなかったのに、いまになって考えると、ずいぶん大胆なことをしたものです。
はっきり覚えていませんが、その家は確か、東京の下町のほうにあったと思います。実際に伺うと、男性は本当によく笑っていた。「先生がわざわざ来てくれたんだから、コーヒーでも淹れようか、ハッハッハ!」という具合です。奥さんも「ああ、そうだね。アハハハハ」と、こちらもよく笑っている。そうやって、夫婦で明るく楽しい時間を過ごしていたのです。これは、と思いましたね。
認知症になっても、本人やその家族が笑いを絶やさず、前向きに生きていく。そのことが、とても素敵に感じられた出来事でした。
長谷川 和夫