「うん、わかった。・・心配しなくてもいいよ、大丈夫・・じゃあね、うん、メリー・クリスマス」
受話器を置いてアレクサンドルが居間に戻ってきた。そのまま無言でソファに座り込む。
「ご両親から?」 クリストファーが聞いた。
「あれで親っていえるならね。子供一人留守番させといて、メリー・クリスマスもないと思わない?」と肩を竦める。「まあいつものことでもう慣れてるけどね」
「お仕事なんだろ?」
「うん、今年はデュッセルドルフでの公演。この時期は稼ぎ時なんだよね」
アレクサンドルの両親にはソ連ヴォルショイ・バレエ団の花形ダンサーだった過去がある。スウェーデンに亡命した後はコーチ、振付師として成功を収め、西欧を中心としたバレエ公演にコーディネーターとして従軍することも多かった。家族で親交を深めるはずのクリスマスを両親不在で迎えることも、そういう事情でアレクサンドルにはよくあることだったのだ。
「埋め合わせに、新年にはユーテボリのリスベリに連れてってくれるって。ほーんといつまでも子ども扱いなんだから・・」
「はは、ぼやくなぼやくな。そんなこと言って、実は結構楽しみって顔してるぞ」
「へへ、まあね」 漸く気を取り直したらしく、アレクサンドルは笑顔になった。「あそこのジェット・コースター半端ないからね」
「・・・・・」 クリストファーは無言で微笑み返した。
それではっとしたように「考えてみればパパとママが帰って来なくて良かったんだよね。帰ってきたら君のこと説明するのが大変なところだった」
『ならその前に旅立っていたさ』との思いを呑み込んで、クリストファーはただ微笑み続ける。
「でも29日には帰ってくるから、それまでに巧い言い訳考えとかないと」
「・・・・・」
「クリストファーも一緒にユーテボリに行けるよね?」
少年の無邪気な表情がわけもわからず眩しい。年上の男はふっと視線を逸らして話題を変えた。
「腹が空いたな。ディナーの時間にしない?」
近くのレストランから取り寄せた二人分のクリスマス料理のアラカルトをテーブルに広げ、アーモンドと干しぶどうを入れてコンロに乗せてあったグロッグ(温ワイン)をマグに分け入れる。「メリークリスマス」と言って乾杯した後は、ただ黙々とフォークを口に運ぶだけだった。なんとも侘しい限りのイブだ。
食事の合間にクリストファーはアレクサンドルを眺める。
少年の才能を知って以来、例のカード読みを始めとする数々のテストを試みた。どれも結果は上々だった。ことによるとアドリアンさえも上回る逸材なのではないか・・クリストファーの胸は高鳴った。
『アドリアンの代わりになってくれるのでは?』
暗闇に一条の光が射したかのように一瞬希望がほの見えた。
『しかし・・』
これから新たに一から訓練し直すのは時間的にも、また環境的にも無理というしかなかった。
やはり、アドリアンこそぎりぎりで見出した最初で最後の頼みの綱だったのだ。今更ながらにそれが自覚された。彼を見出した頃には、時がこれほど差し迫っているとは知る由もなかったのだが・・
その唯一の希望に裏切られた、いや、見捨てられたと言ったほうが当たっている気がする。
クリストファーは再び底知れぬ絶望感に押し潰されそうになって唇をかんだ。
そもそも札付きの不良少年がこちらの信頼に都合よく応えて見返りのない犠牲の道を選ぶなんてこと自体、はなからあり得ない話だったかも知れない。ドハニーが何度も懸念を漏らすのを聞いてきた。しかし、クリストファーはどういうわけか、会った瞬間からこの不良少年の中に理屈抜きに信頼できる何かを感じた。なんのかんの言っていても、いざとなったら必ず共に闘ってくれる。ものごころついた頃からずっと独りで引き摺ってきた重荷・・それも彼なら理解してくれる、そんな気がしたのだ。母とも慕うドハニーや唯一の親友であるスティラーにさえ明かせずにきた心情も、彼となら分かち合えそうだ。なぜなら二人は同じ種類の人間だから・・。一見これほどないというくらいタイプの違う相手にどうしてそんなことを感じたのか、思えば不思議な話ではあった。
ともあれクリストファーはアドリアンを信じた。頭から信じ切った。それ自体が理不尽な話だったのだが・・実を言うと未だに裏切られたことを信じ切れないでいる自分がどこかにいて、今も『何故?』と問い続けている。それが尚更無念だった。
「ねえ、考えてくれた?」
食後のコーヒーを淹れる準備をしながらアレクサンドルが問いかけ、クリストファーを現実に引き戻した。
「え?」
さり気なさを装っているが、明らかにかなり決意して問いかけたんだとわかる表情がアレクサンドルの顔には浮かんでいた。
「考えとくって言ってただろう?僕を・・訓練してくれるかどうか」
「あ・・う、うん」
「僕の、その・・才能・・いや、その」 巧い言葉が見つからず、少年は言いよどんだ。「つまりさあ、僕に将来性ありそう?」
「将来性・・?」
アレクサンドルの顔には今やあからさまに子供っぽい期待感が溢れていた。「そう、エスパーとしてやってけるだけの才能・・僕にあると思う?」
クリストファーは思わず笑った。「よせよ、まさか君までスーパー・ヒーローでキャリア積みたいなんて言いだすんじゃないだろうな」 が、言ったとたんそういう会話を交わした過去の記憶が蘇えり、その時のもう一人の後輩の顔が脳裏に浮んで彼の心を沈ませた。
「やっぱり・・駄目?」 相手の顔が急に曇ったのを別な意味に解釈したアレクサンドルが落胆の表情で言った。
「いや」
「ん?」 再び少年の顔に希望の光が射す。
クリストファーはしばらく躊躇ってから静かに口を開いた。
「君には並々ならぬ才能がある、それは間違いない」
「じゃあ・・」
「だけど、コーチしてあげることは・・出来ない」
「どうして?!」 納得のいかない顔つきだ。
クリストファーは困ったように「僕は・・僕にはこれから、やるべきことがあるんだ」
そもそも、お尋ね者である彼がのんびりとストックホルム市内でうろうろしていられると思うこと自体、アレクサンドルの子供っぽさなのだが・・。たとえそれがなくとも、いつまでもここに滞在出来ない事情がクリストファーにはあった。
「・・急ぎの仕事?」
クリストファーは頷いた。
「じゃあ・・僕も連れて行って!」
「えっ?!」
「大切なことなんだろう?そして・・とっても難しいことなんだ」
「え?・・・!」
「僕に手助けさせてよ。道すがらコーチしてくれればいい。すぐものになるよ、これでも呑み込みは早いほうなんだ」 アレクサンドルはそこで一息切り、駄目押しするかのように続けた。「アドリアンの代わりになりたいんだ」
クリストファーは驚きを通り越し、呆然として相手を見つめた。
「どうして・・」 -そんなに悟りがはやいのか-
無言の問い掛けにアレクサンドルが答えた。「ジェネシス社にまつわるスキャンダルが出回り始めた頃から、不思議な夢をみるようになったんだ。君とアドリアンの顔、新聞で見るより先に知っていたよ」
「・・・・・」
「触れられたくないみたいだったから出来れば言わないで置こうと思ってたんだけど・・」
「・・どういう夢だよ?」
「象徴的な絵巻物、でもちゃんと現実を表している、いつもそうなんだ。・・なんちゅうか地球全体を覆う巨大な暗雲がたちこめた感じで・・絶望的状況だとわかるんだ。で、もう駄目だと思ったとき・・」
「ウルトラマンでも飛んできた?」
「ウ・・?・・茶化さないでよ!」
「わるい」
「光に包まれた勇者の一群が登場するんだ。剣で暗雲を切り裂いて・・」
「なんだ、ウルトラマンとあまり変わらんな」
アレクサンドルは無視して続けた。「彼らの周りから光がどんどん拡大していく。世界を滅亡から救う唯一の希望だとわかるんだ」
「・・・・・」
「その先頭に立っているのが・・」
「僕ってわけか」
「そういうこと」 やっと判ってくれたかというようにアレクサンドルは満足げに頷いた。
「ふーん・・」
「キラキラ光る黄金の鎧に身を包んでてね、すげえかっこよかったよ」
「・・そう?」
「うん、まるで少女漫画の王子様・・」
「え?なんだよそれ、酷いな!」と不本意な顔。
「いや、それでも何故か強くてさあ。・・あ、本気にしてないね?」 相手の不真面目な表情に気付き、アレクサンドルは憤然とした。「ただの夢だろうなんて言って誤魔化そうと思ってるんだろ?駄目だよ。正夢はよく見るんだ、わかるよ。あれは本物だ」
「いや・・誤魔化すつもりはない」 クリストファーは考え深い面持ちになって言った。「そうか、君には予知能力まであったんだな・・」
そういう相手の様子を観察しながら、アレクサンドルは興奮を隠しきれなかった。「・・やっぱりそうなんだ。君はこれから世界を救いにゆくんだね!」
「・・・・」
「連れてってよ、絶対役に立つから!」
少年の脳裏にはクリストファーと共に悪に立ち向かう己が雄姿が、既にありありと浮んでいるらしかった。
「アレクサンドル」 相手の興奮ぶりとは裏腹な静かな声でクリストファーが制した。
「え?」
「仲間がいたって言ったね。夢の中では・・僕は一人ではなかったんだね」
少年は首を横に振った。
「・・何人ぐらい?」
「うーん、見えたのは・・10人ぐらい、でももっといたかも」
「・・そう」
「彼も君の直ぐ傍にいた」
「彼?」
「アドリアンだよ、もちろん」
クリストファーはびくっとして相手を見直した。
「彼はさしずめ白銀の騎士だな、クールでかっこいいったらない。二人並ぶと凄い絵になってたよ」 相手の動揺には気付かず、アレクサンドルはうっとりとした表情で物語り続けた。恐らく二人の隣には黒金の鎧を身に纏った己が姿もちゃっかりインサートしているのだろう。
「・・・・・」
-どういうことだ?この子は既に失われた選択肢の一つを見たとでもいうのか?-
人間には自由意志があり、一人々々が瞬間ごとに無限の選択をし続けている。だから絶対的予言など神にも不可能な業であろう。が、可能性を予言するだけなら多分出来る。アレクサンドルが垣間見たという未来にはどれほどの実現性があるのだろうか。
答えは知りようもなかったが、アドリアンの件を始めとしてかなり差し引いてみても、希望的予言なのは変わりなさそうだ。何も達成しないうちに無念の死を遂げるという、彼が最も恐れていた最悪シナリオの可能性はこれでかなり減ったように思われ、それだけでも随分慰められた。
「ありがとう」 クリストファーの顔に静かな笑みが広がった。
「え、なに?」 アレクサンドルには意味がわからない。
「未来の僕は一人じゃないんだな・・。これで安心して旅立てるよ」
「今でも一人じゃないだろ?僕がいるもの」
「君を連れて行くわけにはいかない」
「どうして?!」
「君はまだ未成年だ」
「アドリアンだって未成年だろ!」
「彼は・・別だ」
「な、なんだよ、それ?」
「君には気遣ってくれるご両親がいるだろう」
「パパとママはいつも仕事第一だ。僕のことなんか・・」
「馬鹿をいうな!」
「・・・・・」 クリストファーの思わぬ語気の強さに押されてアレクサンドルは黙った。
「・・愛してくれる人のいる幸せを軽んじてはいけない」
「でも・・」 ちょっと間を置いてからためらいつつ再び口を開く。「なら、僕はどうして・・こんな能力を持って生まれてきたっての?」
「アレクサンドル・・」
「偶然じゃない、そうだろう?」
「・・・・・」 今度はクリストファーが黙る番だった。
「君と同様僕にもきっと使命があるんだ」
クリストファーは途方にくれた表情になって、強情そうな相手の顔を見つめた。
その27へ















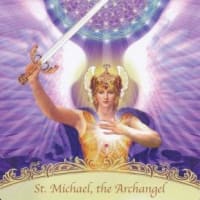





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます