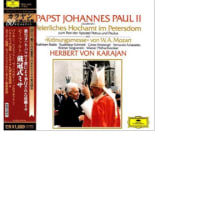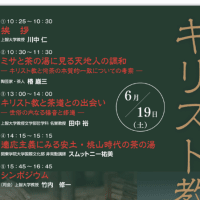神谷美恵子の戦中日記(「遍歴」 神谷美恵子著作集9 169頁)によると、当時の長島愛生園では、療養所内部でも、「有毒地帯」と「無毒地帯」が截然と分かれており、その境界を越える場合には、次のような厳格な消毒作業が義務づけられていた。
戦前の国立療養所の管理方式の特徴の一つは、絶対隔離・終生隔離の原則であるが、隔離は、療養所の内と外にとどまらず、療養所の内部においても、「有毒地帯」を「無毒地帯」から差別隔離したうえで、その二つの地域を往還するさいの消毒の実施である。消毒を徹底的に行うことによって、職員や医者・看護婦への感染を防止するという思想がそこにあるが、このようなペストやコレラにも比すべき消毒と隔離が、はたして、医学的に必要であったのかという事に対する批判的な視点、また、強制隔離が患者の人権をいかに抑圧するものであるかという視点は、神谷の手記には全く見られない。
我々は「小笠原登の医療思想」において、1930年代において既に小笠原が、「らいは強烈な伝染病である」という思想を医学的な根拠のない迷信として斥けたことを知っているし、夫婦間でらいが伝染した統計的事例がいかに少なかったという事も知っている。そういう視点から見ると、国立のらい療養所で、このような極端な消毒と差別的な隔離が徹底されていたことの当否は、当然、問題とされるべき事であった。
医学生として戦時中の愛生園を見学に行った神谷は、病院の医師達による患者の遺体解剖にも立ち会う。当時、(そして敗戦後、かなりしばらくの間もそうであったが)国立のらい療養所に入所する患者は、すべて、入所時に、死後、遺体解剖されることに同意することが義務づけられていた。そして、神谷は、当時の療養所では、結婚の条件として、断種手術が義務づけられていたことにも言及している。つまり、戦前の日本の公立のらい療養所においては
この戦中日記を、60年という歳月を経た上で読み直すと、未だ充分に論議されているとは言い難い様々な問題が伏在していることに気づく。
そのひとつは、前に述べたように、「健常者」と「患者」との間の極端な院内隔離と、強制収容・断種という当時の「救癩」政策の根本原則に対して、神谷が全く批判的な視点を持っていないと云うこと、そして、毎日、患者の遺体が次々と荼毘に付されるという異常なまでの患者死亡率の高さについても、それを強制収容のもとでの患者作業の過酷さと結びつける視点を全く欠いていると云うことである。それに対して、神谷の「戦中日記」を貫く基本的なトーンは、所長の光田健輔にたいする彼女のほとんど絶対的と言っても良いほどの信頼・帰依の感情である。日記の中には、遺体解剖に立ち会ったときの記述のような、医療の客体としての患者に対する記述ばかりがめだち、主体として語るのは療養所の医師達ばかりである。そして光田やその門下生がいかに賞賛すべき医師達であったかという記述に満ちあふれている。
ところで、この戦中日記が公開されたのは昭和18年当時ではなく、それから20年も経過した後である。このように、わざわざ20年後に昔の記録を出版することになった事情については、神谷自身が理由を述べているが、要するに、戦争中の愛生園の状況、とくにそこで勤務していた医師達がいかに献身的で素晴らしい人物であったかと言うことを伝えたいという意図があったということであろう。
20年の歳月、そのあいだには、患者自身による「らい予防法」に抗する闘いがあり、戦前と戦後人権無視の政策に対する抗議と共に、光田健輔とその門下の医師達の「救癩」政策に対する批判が行われるようになったが、そういう人権の問題に対する神谷自身の考え方は怖ろしく冷ややかである。たとえば彼女は次のように云う。
こういう私の意見に対して、「それは現在の価値観をもって過去を断罪することだ」という批判が寄せられるかも知れない。なによりも神谷自身がそういう意見の持ち主であった。彼女は次のように云う。
全国ハンセン病患者協議会元事務局長の鈴木禎一さんの近著「ハンセン病ー人間回復へのたたかいー神谷美恵子氏の認識について」(岩波出版サービスセンター 2003)は、このような神谷美恵子の考え方を含めて、光田イズムを、強制収容された入所者の視点から批判したものであるが、それは、基本的には、松本馨さんの「らい予防法に抗する闘い」と同じく、安直な歴史的な相対主義にたつことなく、戦前戦後の日本の「救癩」政策の主流を形成してきた「光田イズム」に対する根源的な批判である。私は鈴木さんの本から、多くのことを教えられた。強制収容された当事者自身から為された、このような批判を踏まえて、今一度、神谷美恵子の思想と実践を、再検討することが必要であろう。たんにハンセン病の問題だけでなく、神谷自身の精神医療に対する考え方、さらに一般的にはごく最近まで日本の精神医療に存在していた人権抑圧の問題点に対しても、同時に検討しなければなるまい。
ここ(昭和18年の愛生園)では、健康者の活動する区域と患者のいる区域が判然と分けられており、両者の間には厳重な消毒網が設けられている。その順を示すとつまり、患者達の生活空間と医師や職員達の生活空間とは完全に隔離されており、一方から他方へ移動するときには、(1)から(10)のような煩雑な手続きーそれが果たして充分な医学的根拠に基づいていたかは別途に考察したい-が要求されていたことが判る。
はいるとき--
(1)本館から風呂場の脱衣所に行って衣服を脱ぎ、次室でモンペをはく
(2)次室で上衣、帽子、マスクを付ける(3)試験室を出て診察棟および患者の住居区域に至る
出るとき――
(1)消毒液に浸された靴拭きマットで靴を拭く(2)準備室で手を洗って消毒(3)次室で上衣、帽子をとる(4)次室でマスクを籠の中に投げ入れる(5)次室で足袋、靴を脱ぐ(6)次室で足を消毒液に浸す(7)次室で顔を昇汞ガーゼで拭く(8)次室でモンペを脱ぎ、足をリゾール液につける(9)風呂に入って衣類を全部取り替える(10)消毒液でうがい
医師も、看護婦も、この「出入り」を日に二回繰り返す。
戦前の国立療養所の管理方式の特徴の一つは、絶対隔離・終生隔離の原則であるが、隔離は、療養所の内と外にとどまらず、療養所の内部においても、「有毒地帯」を「無毒地帯」から差別隔離したうえで、その二つの地域を往還するさいの消毒の実施である。消毒を徹底的に行うことによって、職員や医者・看護婦への感染を防止するという思想がそこにあるが、このようなペストやコレラにも比すべき消毒と隔離が、はたして、医学的に必要であったのかという事に対する批判的な視点、また、強制隔離が患者の人権をいかに抑圧するものであるかという視点は、神谷の手記には全く見られない。
我々は「小笠原登の医療思想」において、1930年代において既に小笠原が、「らいは強烈な伝染病である」という思想を医学的な根拠のない迷信として斥けたことを知っているし、夫婦間でらいが伝染した統計的事例がいかに少なかったという事も知っている。そういう視点から見ると、国立のらい療養所で、このような極端な消毒と差別的な隔離が徹底されていたことの当否は、当然、問題とされるべき事であった。
医学生として戦時中の愛生園を見学に行った神谷は、病院の医師達による患者の遺体解剖にも立ち会う。当時、(そして敗戦後、かなりしばらくの間もそうであったが)国立のらい療養所に入所する患者は、すべて、入所時に、死後、遺体解剖されることに同意することが義務づけられていた。そして、神谷は、当時の療養所では、結婚の条件として、断種手術が義務づけられていたことにも言及している。つまり、戦前の日本の公立のらい療養所においては
(1)「健康地区」と「汚染地区」との療養所内に於ける分離と両地区を出入りするときの消毒の徹底という顕著な特徴があり、諸外国のそれとは截然と異なっていたのである。そして、らい予防法に依れば、隔離は強制的であり、入所規定のみがあって退所規定がなく、軽快退所は例外的であって、原則として死ぬまで療養所に隔離することがめざされていた。療養所に宗教地区があり、納骨堂が設置されたのはその間の事情を物語るものである。
(2)入所者全員に、死後遺体解剖に付されることを承諾させる
(3)結婚を認める条件として断種手術を行う
この戦中日記を、60年という歳月を経た上で読み直すと、未だ充分に論議されているとは言い難い様々な問題が伏在していることに気づく。
そのひとつは、前に述べたように、「健常者」と「患者」との間の極端な院内隔離と、強制収容・断種という当時の「救癩」政策の根本原則に対して、神谷が全く批判的な視点を持っていないと云うこと、そして、毎日、患者の遺体が次々と荼毘に付されるという異常なまでの患者死亡率の高さについても、それを強制収容のもとでの患者作業の過酷さと結びつける視点を全く欠いていると云うことである。それに対して、神谷の「戦中日記」を貫く基本的なトーンは、所長の光田健輔にたいする彼女のほとんど絶対的と言っても良いほどの信頼・帰依の感情である。日記の中には、遺体解剖に立ち会ったときの記述のような、医療の客体としての患者に対する記述ばかりがめだち、主体として語るのは療養所の医師達ばかりである。そして光田やその門下生がいかに賞賛すべき医師達であったかという記述に満ちあふれている。
ところで、この戦中日記が公開されたのは昭和18年当時ではなく、それから20年も経過した後である。このように、わざわざ20年後に昔の記録を出版することになった事情については、神谷自身が理由を述べているが、要するに、戦争中の愛生園の状況、とくにそこで勤務していた医師達がいかに献身的で素晴らしい人物であったかと言うことを伝えたいという意図があったということであろう。
20年の歳月、そのあいだには、患者自身による「らい予防法」に抗する闘いがあり、戦前と戦後人権無視の政策に対する抗議と共に、光田健輔とその門下の医師達の「救癩」政策に対する批判が行われるようになったが、そういう人権の問題に対する神谷自身の考え方は怖ろしく冷ややかである。たとえば彼女は次のように云う。
過去に於いて強制的に隔離されたという意識は、患者の多くのもののなかに、社会及び政府当局に対する深い恨みの一念を植えつけたようにみえる。これに対する代償として終生、医療と生活保護を受ける権利があるとの主張がここから生まれている。この特権意識は、時折強い個人攻撃性や特定の要求を主張するための手段的デモの形であらわれた」(神谷の論文「日本に於けるらい患者の精神症状」)この文にあらわれている認識は、神谷のみならず、療養所の医師の多くに共有されていたものであり、戦前戦後のみならず敗戦後になっても持ち越された「光田イズム」の信奉者達には特に顕著なものであった。強制的な終生隔離の推進者であり、戦後になってもその態度を改めようとしなかった光田は「日本のシュバイツアー」として文化勲章を受章したが、戦後のらい予防法の改正を求める患者自身の人権闘争の挫折の後という時点で、神谷が、このような文章を公表したことに対する社会的責任は免れないであろう。
こういう私の意見に対して、「それは現在の価値観をもって過去を断罪することだ」という批判が寄せられるかも知れない。なによりも神谷自身がそういう意見の持ち主であった。彼女は次のように云う。
戦後、サルフォン剤でらいが治るようになってみると、患者さんを強制的に隔離収容するという政策がにわかに非人道的なものに見えてきた。光田先生が主張された方針が、園内からも外国からも非難されるようになった。いったい、人間のだれが、時代的・社会的背景から来る制約を免れ得るであろうか。何をするにあたっても、それは初めから覚悟しておくべきなのであろう。私はむしろ、歴史的制約の中で、あれだけの仕事をされ、あれだけのすぐれた弟子達を育てた光田先生という巨大な存在に驚く。研究と診療と行政と。あらゆる面に超人的な努力を傾けた先生は、知恵と慈悲とを一身に結晶させたような人物であった。先生との出会いは、生涯消えることのない刻印を、多くの人の心に刻みつけたのだと思う」(神谷美恵子著作集2 「人間を見つめて」より「光田健輔の横顔」)神谷自身の個人的な感慨は別として、光田イズムの信奉者達が定年で療養所の所長を辞めた後で、入所者の人権回復が軌道に乗ったというのが歴史的事実である。
全国ハンセン病患者協議会元事務局長の鈴木禎一さんの近著「ハンセン病ー人間回復へのたたかいー神谷美恵子氏の認識について」(岩波出版サービスセンター 2003)は、このような神谷美恵子の考え方を含めて、光田イズムを、強制収容された入所者の視点から批判したものであるが、それは、基本的には、松本馨さんの「らい予防法に抗する闘い」と同じく、安直な歴史的な相対主義にたつことなく、戦前戦後の日本の「救癩」政策の主流を形成してきた「光田イズム」に対する根源的な批判である。私は鈴木さんの本から、多くのことを教えられた。強制収容された当事者自身から為された、このような批判を踏まえて、今一度、神谷美恵子の思想と実践を、再検討することが必要であろう。たんにハンセン病の問題だけでなく、神谷自身の精神医療に対する考え方、さらに一般的にはごく最近まで日本の精神医療に存在していた人権抑圧の問題点に対しても、同時に検討しなければなるまい。