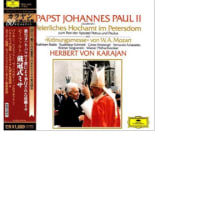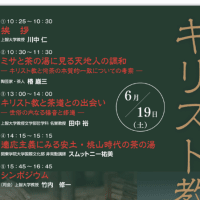一 「自然」と「恩寵」
前節では「野の花」に寄せて、専ら詩的言語において「自然」が「恩寵」の如く働く事例を考察した。しかしながら、自然について哲学的な考察をする場合には、野の花や朝顔のような、(普通の意味でも)美しいと認められている事物だけに限定するわけには行かない。高尚と卑賤、美と醜、価値的なるものと反価値的なるものの差別をこえて働くと言うところが、自然の探求の内には存しているからである。プラトンの対話編「パルメニデス」において、老パルメニデスが、善美のイデアにのみ固執する若き日のソクラテスの理想主義を戒め、善悪の価値的対立を越えて物そのものを捉えることを哲学の道としたことには理由があるかかる考え方は、希臘哲学においてのみならず、東洋の諸思想においても見られる。荘子が「道」を一切の事物に認めて差別せずという立場に徹底したこと、道元が、一切存在(悉有)は仏性において捉えられたことが想起される。
「自然」という言葉は、哲学・科學・宗教・文藝の諸領域に於いて、様々な意味で使用されてきた。それは決して一義的な語ではない。そこで、多義的なものを統一性を全く欠いた偶然的な多義性として放置するのではなく、ある基底的・焦点的な意味を定め、そこから、様々なる「自然」の意味を系統的に整序したうえで、それらを批判的に考察することを試みたい。
まず、さまざまな自然概念に共通して「ものの自体的なあり方」が含意されることに注意したい。列子の張湛の注に「自然とは、外より資らざるなり」とあるが、そこでは「自然とは他の力を借りないで、自ずからそうなること、もしくはそうであること」が含意されている。この意味での「自然」は、ギリシャ語のphysis の用法に近い所がある。アリストテレスは「自己自身の内に運動の原因をもつもの」としてphysisを定義したが、そういう意味での自然概念には、運動ないし変化の原因を、外に求めずに内在化する考え方が現れている。
しかしながら、こういう哲学的議論は、我々の具体的なる経験の現場を離れて次第に抽象化され、やがては、我々自身の経験の現場を離れて、自然が対象化され、実体化されていく傾向性があることに注意しなければならない。そのように対象化された議論の枠組みにおいて、両立しがたい様々な体系-形而上学的なるものと反形而上学的なる物の双方がある-が構築されるからである。
たとえば、荘子の注釈者として著名な郭象の「無因自然」論をとってみよう。そこでは、「万物には主宰者は存在せず、個々の事物は、それぞれに存在根拠をもち、他者の介入を許さない」という意味での「自然」が強調される。これは、単に、万物の主宰者の存在を否定するという意味での無神論であるだけでなく、そもそも事物には原因なるものは存在しないと言う意味で因果を撥無する議論でもあった。これは形而上学を拒否する自然主義の一事例である。
それとは対照的に、単なる個物の感覚的認識ではなく、ものの原理と原因の認識を持って学的認識の特徴とするアリストテレスにおいては、いわゆる四原因論こそが自然学の基本となる。因果性を撥無するところには科學は生まれない。そして、自然界の全体的な認識のためには、第一の原因・原理の探求こそが要求されるのであって、かかる原因の’探求は、究極するところでは、形而上学において完結する。それゆえにアリストテレスの伝統を継承する自然学は、最終的には、自己自身を越える根拠としての第一哲学=神学(テオロギケー)を必要とするのである。こちらのほうは形而上学に対して開かれた自然主義の事例である。
哲学的な思索においては、事物の原因の探求、あるいは事物の本来的なありかた、生成消滅の根拠と言う文脈において「自然」が語られるが、宗教においては、それと同時に、我々の救済の根拠を求めるという文脈で、「自然」という言葉が語られる。
仏教に於いては、「自然」という語は、良い意味でも悪い意味でも使われると言う点で両義的な用語である。救済の究極的な根拠を表現する場合にも使われるが、救済が実現されるためには否定されるべきものとして語られる場合もある。 中国仏教に於いては、無因自然のごとき考え方は、仏教の基本にある縁起説、因果の理法とは相容れぬものと扱われた。道教のいわゆる「無為自然」は「自然外道」と等値され、から、仏教的な「空」の立場との混同を戒める議論も行われた。他方に於いて、親鸞の晩年の言葉を筆録した『末燈抄』では、「自然法爾」が、絶対他力の信心の究極を表す言葉として使用されている。
『歎異抄』にも「わがはからはざるを自然とまうすなり。これすなはち他力にまします」ということばがあり、ここでは、自然は、人為のはからいを捨てて絶対他力に帰依信心のありかたを指しているのである。
キリスト教の場合、カトリックとプロテスタントの神学の相違点の一つは、啓示神学にたいする自然神学の位置づけである。バルトに於いて典型的に見られるように、聖書原理を重視するプロテスタントの神学は、基本的な傾向として、自然神学というものの価値を認めない。聖書の啓示こそが神学の与件であり、その与件に基づいて神学体系を組織する啓示神学のみが、本来の意味での神学である。その他に神学なるものはない。あるとすれば、それは神学の装いのもとに展開された世俗の哲学に過ぎない。
これに対し、カトリシズムの伝統に於いては、基本的に、自然神学の価値を承認する。それは、さしあたっては特定の経典に立脚せずに、異教徒にもキリスト者にも共通するもの、いわば両者が共に認める自然なる与件としての世界から議論を組み立てる。それは、古くはプラトンやアリストテレスのこころみた哲学的な神学(テオロギケー)の系譜を引くものであって、キリスト者と非キリスト者とが、ともに共通の場において論議可能な地平をもつ神学である。
すなわち、自然を重視し、そこから神学的な思索を行うことは、自己と異なる伝統に由来する他宗教との対話のために必要なことがらであり、自己の宗教のもつ特殊性、独自性を越える普遍性を獲得するために、必要な営みなのである。
自然の概念は、このように、仏教に於いてもキリスト教に於いても両義的である。このような両義性の由来を追尋することは、キリスト教的な創造論や救済論の文脈で自然を語る場合に於いても、あるいは大乗仏教に於ける仏性論との関係で自然を語る場合においても避けて通ることのできぬものであろう。さらに、如何なる宗教的な価値にたいしても中立的な自然科学的な意味での「自然」概念があり、これは宗教的な自然概念と如何に関係するかと言うことも、考察されるべき問題である。
「恩寵は自然を破棄せずに、却ってこれを完成する」というトマス・アクィナスの言葉がある。
歴史的に見れば、この言葉は、キリスト教が自然を学問的に研究するアリストテレスの哲学を受容したあとで、信仰と理性という相反する二つの立場を、信仰の側から統合する立場を表明したものである。これは、カトリシズムに於ける啓示神学と自然神学との根本的な関係を表明したものとして良く引用される。この言葉は、単に西欧のキリスト教の歴史のある段階に於いて発せられた特殊な命題であるにすぎないものではない。およそ、恩寵という言葉が宗教的な救済の出来事を表すものであり、自然という語が、我々の本性に由来する物を表すとするならば、この言葉は、宗教の成立する根幹にかかわる問題を指示している。いいかえれば、それは現在に於いても、我々に対して、思索を促すだけの普遍性をもっているのである。
この言葉は、トマスの言う意味での「普遍の信仰」の立場を述べたものであるから、それを単に、中世西欧のキリスト教的思惟という歴史的な文脈で理解するだけではなく、時代と思想の風土も異なる現代の日本において、我々の思索を促すものとして採り上げよう。すなわち、我々は、あらためて、次のように問うのである。
「恩寵は自然を破棄せずに、却って完成させる」という、そのことは、如何にして可能となるのであろうか。
さしあたっては、我々が事物を経験するときの、そのものの「自然なありかた」、および経験する主体である我々の「自己のありかた」の様態を形容するものとして、すなわち「ものはどのように生成するのか」、「私はどのように生きているのか」を言い表す語としての「自然」に焦点を定めたい。そういう考察に於いては、経験する主体を捨象したうえで対象化された事物の総体としての自然ではなく、対象と経験する主体との間の不可分なる具体的な関係性そのものが問題となろう。
このような「生成の<如何に>」を表現する「自然」は、「しぜん」というよりも「じねん」と言う、より古い読み仮名で表現する方が適切であるかもしれない。今日、「自然(しぜん)」は、主体抜きの純然たる客体、ないし客体の総体としての世界、即ち近代以後の自然科学の対象世界を指す意味で使われることが多くなったからである。しかし、自然科学が扱う自然の概念を如何に位置づけるかと言うことも我々の議論の射程に入る。現代に於いては、自然科学で言う意味での自然概念が如何にして生まれるかという問題を追尋することなくして、自然一般を論じるだけでは不充分である。自然科学で対象化された自然も又「生成の<如何に>」を表示する基底的な自然概念から派生するものとして議論することが出来るものでなければならない。
「生成の<如何に>」を表す意味での自然を第一義とする場合、それは、神と世界という二元的な対立図式の片方のみ、すなわち神から区別された世界のあり方のみを指すと固定して考えるべきではない。「自然(じねん)」を専ら神と区別された世界に限定することは、ひとつの先入主である。それは、神と世界をそれぞれ別個の「もの」として実体化した後で、時間的生成という働きを世界の側に帰し、神を自然的世界から峻別された非時間的なる存在として捉える考えを既に前提してしまっているからである。しかるに「生成する神」の概念は受肉と歴史が本質的な意味を持つキリスト教にとって必要不可欠である。
ここで、現代に於ける自然神学の一つの試みとして、神学に於ける「自然」概念の根柢は、「世界の自然」にではなく、「神の自然」にあるという考え方を提唱したい。
この提唱は、直接的には、先程提示した「恩寵は自然を破棄せずに、却ってこれを完成する」いうトマスの言葉の可能根拠を指し示すものである。すなわち、恩寵とは「神の自然」に他ならず、普通言われる意味での「世界の自然」を完成するという意味である。
もちろん、こういったからといって、トマスの命題の意味するところ、その意味の全幅的な射程を覆い尽くしたなどと主張するつもりはない。そうではなくて、トマスの命題を受容し、そこから、形而上的なるもの(神的なるもの)へと開かれた自然主義の、新しい形態を出きる限り明晰に述べること、そのために必要な概念を提示するひとつの試みなのである。
そういう概念の適合性ないし有効性を判定する基準は、あくまでも我々自身の直接経験の現場以外にはない。各自が、自己自身の宗教的経験が、はたして有効に解釈され照明されるか、それを判定していただかなければならない。
「神の自然」は、「自然」というそのありかたにおいて「世界の自然」と通底している。そのゆえに、かかる「世界の自然」のありかたを深く捉えることが、「神の自然」を捉えることに繋がり、かかる「神の自然」を捉えることによって、始めて「世界の自然」の捉え方が完成する――これが、「神の自然」という概念の意味するところである。
もし、このような言い方が許されるとするならば、「恩寵」とは、まさに、かかる「神の自然」の働きに他ならず、この「神の自然」の働きこそが、「世界の自然を破棄せずに、これを完成させる」ことの可能なる所以を与えるのではないか。
しかしながら、この問題はさらに突き詰めて考察する必要があろう。神と世界の「自然」について論ずることは、両者の区別と関係性を如何に語るかという問題の考察を要求するからである。
世界の「自然」が、単に「自己自身のうちに生成の根拠を持つ」ことにつきるのであるならば、「恩寵」はそのような自己を否定するという意味を持つはずである。仏教徒の表現を借りるならば、「自力作善」の立場が根柢から否定されると言うことが、「恩寵」には本来含まれる。神の「自然」には、世界の「自然」の自己充足性を突破するものが含まれているのでなければならない。したがって、我々は、神と世界との区別と関係性を、如実に述べるために必要にして適切なる範疇とは何であるか、それを省察することを求められるのである。我々にとっては「世界の自然」の方が先立つものであるが、事柄自体としては、「神の自然」こそが「世界の自然」に先行し、それを可能ならしめるものである。しかし、そのことは、我々にいかに如実に経験されるのか、それが経験される場というのはいかなるものであるのかが指示されなければならない。
前節では「野の花」に寄せて、専ら詩的言語において「自然」が「恩寵」の如く働く事例を考察した。しかしながら、自然について哲学的な考察をする場合には、野の花や朝顔のような、(普通の意味でも)美しいと認められている事物だけに限定するわけには行かない。高尚と卑賤、美と醜、価値的なるものと反価値的なるものの差別をこえて働くと言うところが、自然の探求の内には存しているからである。プラトンの対話編「パルメニデス」において、老パルメニデスが、善美のイデアにのみ固執する若き日のソクラテスの理想主義を戒め、善悪の価値的対立を越えて物そのものを捉えることを哲学の道としたことには理由があるかかる考え方は、希臘哲学においてのみならず、東洋の諸思想においても見られる。荘子が「道」を一切の事物に認めて差別せずという立場に徹底したこと、道元が、一切存在(悉有)は仏性において捉えられたことが想起される。
「自然」という言葉は、哲学・科學・宗教・文藝の諸領域に於いて、様々な意味で使用されてきた。それは決して一義的な語ではない。そこで、多義的なものを統一性を全く欠いた偶然的な多義性として放置するのではなく、ある基底的・焦点的な意味を定め、そこから、様々なる「自然」の意味を系統的に整序したうえで、それらを批判的に考察することを試みたい。
まず、さまざまな自然概念に共通して「ものの自体的なあり方」が含意されることに注意したい。列子の張湛の注に「自然とは、外より資らざるなり」とあるが、そこでは「自然とは他の力を借りないで、自ずからそうなること、もしくはそうであること」が含意されている。この意味での「自然」は、ギリシャ語のphysis の用法に近い所がある。アリストテレスは「自己自身の内に運動の原因をもつもの」としてphysisを定義したが、そういう意味での自然概念には、運動ないし変化の原因を、外に求めずに内在化する考え方が現れている。
しかしながら、こういう哲学的議論は、我々の具体的なる経験の現場を離れて次第に抽象化され、やがては、我々自身の経験の現場を離れて、自然が対象化され、実体化されていく傾向性があることに注意しなければならない。そのように対象化された議論の枠組みにおいて、両立しがたい様々な体系-形而上学的なるものと反形而上学的なる物の双方がある-が構築されるからである。
たとえば、荘子の注釈者として著名な郭象の「無因自然」論をとってみよう。そこでは、「万物には主宰者は存在せず、個々の事物は、それぞれに存在根拠をもち、他者の介入を許さない」という意味での「自然」が強調される。これは、単に、万物の主宰者の存在を否定するという意味での無神論であるだけでなく、そもそも事物には原因なるものは存在しないと言う意味で因果を撥無する議論でもあった。これは形而上学を拒否する自然主義の一事例である。
それとは対照的に、単なる個物の感覚的認識ではなく、ものの原理と原因の認識を持って学的認識の特徴とするアリストテレスにおいては、いわゆる四原因論こそが自然学の基本となる。因果性を撥無するところには科學は生まれない。そして、自然界の全体的な認識のためには、第一の原因・原理の探求こそが要求されるのであって、かかる原因の’探求は、究極するところでは、形而上学において完結する。それゆえにアリストテレスの伝統を継承する自然学は、最終的には、自己自身を越える根拠としての第一哲学=神学(テオロギケー)を必要とするのである。こちらのほうは形而上学に対して開かれた自然主義の事例である。
哲学的な思索においては、事物の原因の探求、あるいは事物の本来的なありかた、生成消滅の根拠と言う文脈において「自然」が語られるが、宗教においては、それと同時に、我々の救済の根拠を求めるという文脈で、「自然」という言葉が語られる。
仏教に於いては、「自然」という語は、良い意味でも悪い意味でも使われると言う点で両義的な用語である。救済の究極的な根拠を表現する場合にも使われるが、救済が実現されるためには否定されるべきものとして語られる場合もある。 中国仏教に於いては、無因自然のごとき考え方は、仏教の基本にある縁起説、因果の理法とは相容れぬものと扱われた。道教のいわゆる「無為自然」は「自然外道」と等値され、から、仏教的な「空」の立場との混同を戒める議論も行われた。他方に於いて、親鸞の晩年の言葉を筆録した『末燈抄』では、「自然法爾」が、絶対他力の信心の究極を表す言葉として使用されている。
「自然といふは、自はおのづからと言ふ、行者のはからひにあらず、しからしむといふ言葉なり。然といふは、しからしむといふことば、行者のはからひにあらず、如来のちかひにてあるがゆゑに、しからしむるを法爾といふ。…..すべて、人のはじめてはからざるなり。このゆゑに、他力には義なきを義とす、としるべきなり」
『歎異抄』にも「わがはからはざるを自然とまうすなり。これすなはち他力にまします」ということばがあり、ここでは、自然は、人為のはからいを捨てて絶対他力に帰依信心のありかたを指しているのである。
キリスト教の場合、カトリックとプロテスタントの神学の相違点の一つは、啓示神学にたいする自然神学の位置づけである。バルトに於いて典型的に見られるように、聖書原理を重視するプロテスタントの神学は、基本的な傾向として、自然神学というものの価値を認めない。聖書の啓示こそが神学の与件であり、その与件に基づいて神学体系を組織する啓示神学のみが、本来の意味での神学である。その他に神学なるものはない。あるとすれば、それは神学の装いのもとに展開された世俗の哲学に過ぎない。
これに対し、カトリシズムの伝統に於いては、基本的に、自然神学の価値を承認する。それは、さしあたっては特定の経典に立脚せずに、異教徒にもキリスト者にも共通するもの、いわば両者が共に認める自然なる与件としての世界から議論を組み立てる。それは、古くはプラトンやアリストテレスのこころみた哲学的な神学(テオロギケー)の系譜を引くものであって、キリスト者と非キリスト者とが、ともに共通の場において論議可能な地平をもつ神学である。
すなわち、自然を重視し、そこから神学的な思索を行うことは、自己と異なる伝統に由来する他宗教との対話のために必要なことがらであり、自己の宗教のもつ特殊性、独自性を越える普遍性を獲得するために、必要な営みなのである。
自然の概念は、このように、仏教に於いてもキリスト教に於いても両義的である。このような両義性の由来を追尋することは、キリスト教的な創造論や救済論の文脈で自然を語る場合に於いても、あるいは大乗仏教に於ける仏性論との関係で自然を語る場合においても避けて通ることのできぬものであろう。さらに、如何なる宗教的な価値にたいしても中立的な自然科学的な意味での「自然」概念があり、これは宗教的な自然概念と如何に関係するかと言うことも、考察されるべき問題である。
「恩寵は自然を破棄せずに、却ってこれを完成する」というトマス・アクィナスの言葉がある。
歴史的に見れば、この言葉は、キリスト教が自然を学問的に研究するアリストテレスの哲学を受容したあとで、信仰と理性という相反する二つの立場を、信仰の側から統合する立場を表明したものである。これは、カトリシズムに於ける啓示神学と自然神学との根本的な関係を表明したものとして良く引用される。この言葉は、単に西欧のキリスト教の歴史のある段階に於いて発せられた特殊な命題であるにすぎないものではない。およそ、恩寵という言葉が宗教的な救済の出来事を表すものであり、自然という語が、我々の本性に由来する物を表すとするならば、この言葉は、宗教の成立する根幹にかかわる問題を指示している。いいかえれば、それは現在に於いても、我々に対して、思索を促すだけの普遍性をもっているのである。
この言葉は、トマスの言う意味での「普遍の信仰」の立場を述べたものであるから、それを単に、中世西欧のキリスト教的思惟という歴史的な文脈で理解するだけではなく、時代と思想の風土も異なる現代の日本において、我々の思索を促すものとして採り上げよう。すなわち、我々は、あらためて、次のように問うのである。
「恩寵は自然を破棄せずに、却って完成させる」という、そのことは、如何にして可能となるのであろうか。
さしあたっては、我々が事物を経験するときの、そのものの「自然なありかた」、および経験する主体である我々の「自己のありかた」の様態を形容するものとして、すなわち「ものはどのように生成するのか」、「私はどのように生きているのか」を言い表す語としての「自然」に焦点を定めたい。そういう考察に於いては、経験する主体を捨象したうえで対象化された事物の総体としての自然ではなく、対象と経験する主体との間の不可分なる具体的な関係性そのものが問題となろう。
このような「生成の<如何に>」を表現する「自然」は、「しぜん」というよりも「じねん」と言う、より古い読み仮名で表現する方が適切であるかもしれない。今日、「自然(しぜん)」は、主体抜きの純然たる客体、ないし客体の総体としての世界、即ち近代以後の自然科学の対象世界を指す意味で使われることが多くなったからである。しかし、自然科学が扱う自然の概念を如何に位置づけるかと言うことも我々の議論の射程に入る。現代に於いては、自然科学で言う意味での自然概念が如何にして生まれるかという問題を追尋することなくして、自然一般を論じるだけでは不充分である。自然科学で対象化された自然も又「生成の<如何に>」を表示する基底的な自然概念から派生するものとして議論することが出来るものでなければならない。
「生成の<如何に>」を表す意味での自然を第一義とする場合、それは、神と世界という二元的な対立図式の片方のみ、すなわち神から区別された世界のあり方のみを指すと固定して考えるべきではない。「自然(じねん)」を専ら神と区別された世界に限定することは、ひとつの先入主である。それは、神と世界をそれぞれ別個の「もの」として実体化した後で、時間的生成という働きを世界の側に帰し、神を自然的世界から峻別された非時間的なる存在として捉える考えを既に前提してしまっているからである。しかるに「生成する神」の概念は受肉と歴史が本質的な意味を持つキリスト教にとって必要不可欠である。
ここで、現代に於ける自然神学の一つの試みとして、神学に於ける「自然」概念の根柢は、「世界の自然」にではなく、「神の自然」にあるという考え方を提唱したい。
この提唱は、直接的には、先程提示した「恩寵は自然を破棄せずに、却ってこれを完成する」いうトマスの言葉の可能根拠を指し示すものである。すなわち、恩寵とは「神の自然」に他ならず、普通言われる意味での「世界の自然」を完成するという意味である。
もちろん、こういったからといって、トマスの命題の意味するところ、その意味の全幅的な射程を覆い尽くしたなどと主張するつもりはない。そうではなくて、トマスの命題を受容し、そこから、形而上的なるもの(神的なるもの)へと開かれた自然主義の、新しい形態を出きる限り明晰に述べること、そのために必要な概念を提示するひとつの試みなのである。
そういう概念の適合性ないし有効性を判定する基準は、あくまでも我々自身の直接経験の現場以外にはない。各自が、自己自身の宗教的経験が、はたして有効に解釈され照明されるか、それを判定していただかなければならない。
「神の自然」は、「自然」というそのありかたにおいて「世界の自然」と通底している。そのゆえに、かかる「世界の自然」のありかたを深く捉えることが、「神の自然」を捉えることに繋がり、かかる「神の自然」を捉えることによって、始めて「世界の自然」の捉え方が完成する――これが、「神の自然」という概念の意味するところである。
もし、このような言い方が許されるとするならば、「恩寵」とは、まさに、かかる「神の自然」の働きに他ならず、この「神の自然」の働きこそが、「世界の自然を破棄せずに、これを完成させる」ことの可能なる所以を与えるのではないか。
しかしながら、この問題はさらに突き詰めて考察する必要があろう。神と世界の「自然」について論ずることは、両者の区別と関係性を如何に語るかという問題の考察を要求するからである。
世界の「自然」が、単に「自己自身のうちに生成の根拠を持つ」ことにつきるのであるならば、「恩寵」はそのような自己を否定するという意味を持つはずである。仏教徒の表現を借りるならば、「自力作善」の立場が根柢から否定されると言うことが、「恩寵」には本来含まれる。神の「自然」には、世界の「自然」の自己充足性を突破するものが含まれているのでなければならない。したがって、我々は、神と世界との区別と関係性を、如実に述べるために必要にして適切なる範疇とは何であるか、それを省察することを求められるのである。我々にとっては「世界の自然」の方が先立つものであるが、事柄自体としては、「神の自然」こそが「世界の自然」に先行し、それを可能ならしめるものである。しかし、そのことは、我々にいかに如実に経験されるのか、それが経験される場というのはいかなるものであるのかが指示されなければならない。