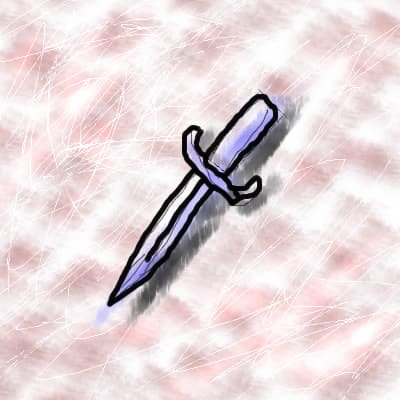
イギリス人の女 ―短いゴシック・ロマン―
199*年の秋から冬にかけて、ぼくは長い休暇を取って東欧を旅行した。それが生まれて初めての一人旅だったが、ある時乗換駅で列車をつかまえそこね、どことも知れない田舎町で立ち往生してしまった。あたりは寒く、暗い。ぼくはパニックに陥った。もう列車はないと繰り返すだけの無愛想な駅員と押し問答をしたり、ぼろぼろになった電話帳を調べたり、通りがかりの泥まみれの子供を呼び止めたりしてなんとか目的地へ向かおうとつとめたが、結局諦めざるを得なかった。ふと見ると、空には見渡す限り灰色の雲が垂れこめている。すでに夕刻を過ぎ、空気は冷たかった。こうしたあれこれがすっかりぼくの気分を滅入らせ、今日は多少無理をしてでも心地よい部屋で眠りたいという気にさせた。ぼくは陰険な目つきをした駅員から、このあたりで一番上等というホテルの場所を聞き出した。それは徒歩で十分ほど歩いたところにあるレンガ造りのホテルで、外から眺めるとロマネスク風のファザードが優雅と言えないでもなかったが、中に入るとすっかり失望させられた。壁には汚れが目立ち、絨毯は擦り切れていた。フロントの若い男がどんよりした目でぼくを眺め、何も言わずに宿帳らしきものを突き出した。ホールを横切る時、柱の影にうずくまっている灰色の猫が首を回してぼくを見た。大きな音を立てる年代もののエレベーターに乗り、四階へと上がった。ぼくにあてがわれた部屋はエレベーター乗り場から一番遠いところにあった。部屋に入って荷物を降ろすと、もう一歩も歩けないほどの疲労を感じた。荷物をクローゼットの中に押し込み、下着だけになってベッドに横たわった。部屋の中は薄暗く、赤くくすんだ色の絨毯の上に花柄のソファーが置かれていた。晩飯は抜くことにして、しばらくぼんやりと、何を喋っているのか判然としないテレビを眺めた。それから部屋の灯りを消し、眠りに落ちた。
何時ごろか分からないが、ふと目がさめた。暗い部屋の中では目を凝らしても家具のシルエットしか見えなかった。ぼくはまだ自分が眠っているに違いないと思ったが、それは天井のあたりからぶつぶつ呟く女の声が聞こえてきたからだ。はっきりそれと分かるイギリス英語で、おそらく二十代から三十代くらいの女の声だった。こんなことを喋っていた。
あの人と一緒にこの部屋に入ってきた時、私は感激して声をあげてしまったわ。なぜならソファーとカーテンお揃いの花柄の刺繍がとってもロマンティックだったから、そしてそのロマンティックな部屋のしつらえがあの人の私への心遣いを表しているように思えたから。気に入ったかい、とあの人は尋ねた。ええとても、と私は答えた。ここで一週間過すなんて夢みたいよ。あの人は笑っていた、最初に出会った頃いつもそうだったように。でも悲しいことに、時とともにその笑顔はだんだん消えていった。そして私は、仮面のような彼の沈黙をたびたび恐れるようになった。でもそれはまだ後のこと、このホテルで過した一週間は素晴らしかった。二人とも幸福の海に漂い、陶酔の午前に寄り添った。私はあの人とずっと一緒にいられるのが嬉しかった。夜中に目を覚ました時、彼の寝息が聞こえると心が安らいだ。毎日私たちはこの部屋で愛し合い、それから外へと出かけていった。お洒落なレストランやブティックは一軒もない田舎町だったけれど、何もかもが美しかった。お年寄りばかりが集うまどろむような簡易食堂で食事をとり、町に一軒しかない映画館でモノクロ映画を観て、ひと気のない小さな公園をぶらついたわ。ちょっと足を伸ばすと森があって、私たちは柔らかい草の上に腰を下ろし、卵とレタス入りのサンドイッチを食べたりもした。そんな時、あの人の視線は私から離れようとはしなかった。私はこれからずっとこんな日が続くものと信じて、幸福のあまり気絶しそうだったわ。
声は休みなく喋り続けた。
とろけるような一週間はあっという間に過ぎ、私たちはロンドンに戻った。それぞれの仕事、それぞれのアパートに帰っていった。けれどもそのうち一緒に住めると思っていたから、それも苦にはならなかった。でもあの人の顔から笑いが消えていき、かわりに冷淡な憂鬱がすべてを覆い隠すようになると、すべてが変わってしまった。最初は気のせいかと思ったけれど、やがて彼は私と会うのを避けるようになった。たまに会ってもその視線は冷たかった。私はどうすれば良いのか分からなかった。ただ手をこまねいて、何かの奇跡によってすべてが元に戻ることを願うばかりだった。あの人の裏切りを知ったのは、それからしばらくしてのことだったわ。あの人の心が私から離れてしまっているのはもう分かっていた。だからあんな日にあんな場所に出かけていったのも偶然なら、大勢の群集の中からあの人を見つけ出したのも偶然だった。あの人はとても幸福そうだった。私にはもう見せなくなった、あの子供みたいな笑みを浮かべていた。そしてあの人の隣にはあの女がいた。なんということでしょう、よりによってあの女が。心臓が止まり、その場に倒れてしまわなかったのが不思議なくらいだった。すぐにその場を立ち去り、自分のアパートに戻った。目の奥にキリを差し込まれたような痛みを感じ、ソファーに身を投げて泣き崩れた。あんな女に、よくも手を出せたものね! でもその時はまだ、怒りを感じる余裕はなかった。ただ消えてしまいたいだけだった。私は母親が来ると嘘をついて、あの人との約束を全部キャンセルした。あの人は疑いもせず、ああそう、とだけ言って電話を切ったわ。その時だった、私の中に憎しみがどっと溢れ出してきたのは。
ぼくは暗闇の中でじっと耳を傾けていた。声はさらに喋り続けた。
私はアパートの部屋から出かけることもせず、苦しみのあまり痩せ細っていったけれど、目だけは憎悪にぎらついていた。部屋の中をハツカネズミみたいにグルグル歩き回りながら、復讐の方法を考えた。そしてふと思った、もうあの人を殺すしかないって。それ以外に私の苦しみを和らげる方法はないって。他人が聞けば笑うかも知れないけれど、私は真剣だった。すぐに殺人手段の研究を始めた。計画が固まるまで一ヶ月かかったわ。あの人の習慣を知り尽くしている私は、機会の選定も慎重に行った。あの人が日曜日の夜、タバコを買いに行く時に通る裏道。ひと気もなく、隠れる場所も多い。あそこならあの人を確実に殺せそうな気がしたわ。こうしてすべての準備が整った。凶器も手に入れた。返り血を浴びても大丈夫なように上着も用意した。マスクとサングラスも用意した。カレンダーを手に取り、ある日付をマルで囲んだ。これが決行日。その瞬間、体中の血が煮立ったトマトソースみたいに熱くなるのが分かった。罪悪感のせいじゃなく、あの人の死をこの手でつかめるような気がしたから。計画があまりにも完璧で、失敗するなんて考えられない。私はベッドにもぐりこんで、夢も見ずにぐっすり眠ったわ。目をさました時、生まれ変わったような気分だった。憑き物が落ちたようなさっぱりした気分で、爽快だった。コーヒーとパンの朝食をとって、それからあのカレンダーの印を見た時、自分でも驚いたことに、殺意や憎悪がきれいさっぱり消えてしまっていることに気づいた。あんなに憎しみをたぎらせていたのが嘘のよう。きっと、殺害計画を立てたことで気持ちの整理がついたのだわ。私はそう考えた。神に感謝の祈りを捧げ、マスクもサングラスも刃物も全部捨ててしまった。そうやって久しぶりに普段の自分を取り戻し、本来の生活に戻ってから一週間たった月曜日、朝刊を読んで、あの人の死を知った。日曜の夜、タバコを買いに出た帰り道に誰かに刺殺されたことを。犯人は分からず、手掛かりも目撃者もなかった。私は新聞を両手で持ったまま立ちすくんだ。自分自身の声が、頭の中で鳴り響いた。これは偶然なんかじゃない、私のせいだ、私が立てた計画は完璧だった、だからあの人は死んだ。私が彼を殺したんだわ。
声は尚も、憑かれたように喋り続けた。
私はベッドの中で丸くなり、ただひたすら眠ろうとした。すべてを忘れ、考えることをやめ、感じることをやめたかった。食事も喉を通らなかった。体がどんどん衰弱していくのが分かった。鏡を見ると目が落ち窪み、十歳も老けて見えた。私はどうしたというのだろう。あの人が死んだからどうだというのか。殺したからなんだというのか。あの人を殺したいと願ったのは誰? でもそんなことを言って自分を騙そうとしても、もう何の役にも立たなかった。自分があの人なしでは生きていけないこと、それはあの新聞記事を読んだ時から分かっていた。私はその喪失に耐えられなかった。それは鈍い痛みとひりつくような渇きをもたらした。だから私はあの人と一緒に過した時間を思い出し、その記憶があたかも柔らかい毛布であるかのように自分を包み込み、私のベッドを満たそうとした、世界を満たそうとした。しかしそうすればするほど、鏡の中の私は痩せ細り、私の絶望は深くなっていった。この喪失に耐える力は私にはない、それは最初から分かっていた。私は身の回りのものを片付け、小さなスーツケースだけ持って再びこのホテルにやってきた。このホテルの、この部屋に。私たちが幸せだった場所、かつて私たちの希望と笑い声が日没時の海と太陽のようにとろけた場所、それをシャボン玉のように包み込んで二人で宙に浮かべた場所に。それから致死量の睡眠薬を水で飲み下し、ベッドに横たわった。目を閉じてあの人のことを思い出そうとしたけれど、もうそれもできなかった。私に残されたのは、冷たい空っぽの空間だけだった。私を中心にぐんぐんとどこまでも遠く広がっていく、あの孤独と呼ばれる灰色の虚空だけだったわ。
そこで声がふっつり聞こえなくなったので、ぼくはようやく眠ることができた。翌朝、ホテルを出て行く時にフロントの若い男に尋ねてみた。「このホテルに、幽霊が出るって噂はないかい?」
若い男はあきれたようにぼくの顔を眺めて言った。「さあ、知らないね」
「じゃあ昔、ここで自殺したイギリス人の女性はいなかった?」
「いないね、そんな女」
ぼくは列車に乗るためにホテルを出た。列車に乗り込んで一息ついたあと、地図を広げ、予期せぬ一夜を過した町の名を探してみたけれども、どうしても見つけることができなかった。
199*年の秋から冬にかけて、ぼくは長い休暇を取って東欧を旅行した。それが生まれて初めての一人旅だったが、ある時乗換駅で列車をつかまえそこね、どことも知れない田舎町で立ち往生してしまった。あたりは寒く、暗い。ぼくはパニックに陥った。もう列車はないと繰り返すだけの無愛想な駅員と押し問答をしたり、ぼろぼろになった電話帳を調べたり、通りがかりの泥まみれの子供を呼び止めたりしてなんとか目的地へ向かおうとつとめたが、結局諦めざるを得なかった。ふと見ると、空には見渡す限り灰色の雲が垂れこめている。すでに夕刻を過ぎ、空気は冷たかった。こうしたあれこれがすっかりぼくの気分を滅入らせ、今日は多少無理をしてでも心地よい部屋で眠りたいという気にさせた。ぼくは陰険な目つきをした駅員から、このあたりで一番上等というホテルの場所を聞き出した。それは徒歩で十分ほど歩いたところにあるレンガ造りのホテルで、外から眺めるとロマネスク風のファザードが優雅と言えないでもなかったが、中に入るとすっかり失望させられた。壁には汚れが目立ち、絨毯は擦り切れていた。フロントの若い男がどんよりした目でぼくを眺め、何も言わずに宿帳らしきものを突き出した。ホールを横切る時、柱の影にうずくまっている灰色の猫が首を回してぼくを見た。大きな音を立てる年代もののエレベーターに乗り、四階へと上がった。ぼくにあてがわれた部屋はエレベーター乗り場から一番遠いところにあった。部屋に入って荷物を降ろすと、もう一歩も歩けないほどの疲労を感じた。荷物をクローゼットの中に押し込み、下着だけになってベッドに横たわった。部屋の中は薄暗く、赤くくすんだ色の絨毯の上に花柄のソファーが置かれていた。晩飯は抜くことにして、しばらくぼんやりと、何を喋っているのか判然としないテレビを眺めた。それから部屋の灯りを消し、眠りに落ちた。
何時ごろか分からないが、ふと目がさめた。暗い部屋の中では目を凝らしても家具のシルエットしか見えなかった。ぼくはまだ自分が眠っているに違いないと思ったが、それは天井のあたりからぶつぶつ呟く女の声が聞こえてきたからだ。はっきりそれと分かるイギリス英語で、おそらく二十代から三十代くらいの女の声だった。こんなことを喋っていた。
あの人と一緒にこの部屋に入ってきた時、私は感激して声をあげてしまったわ。なぜならソファーとカーテンお揃いの花柄の刺繍がとってもロマンティックだったから、そしてそのロマンティックな部屋のしつらえがあの人の私への心遣いを表しているように思えたから。気に入ったかい、とあの人は尋ねた。ええとても、と私は答えた。ここで一週間過すなんて夢みたいよ。あの人は笑っていた、最初に出会った頃いつもそうだったように。でも悲しいことに、時とともにその笑顔はだんだん消えていった。そして私は、仮面のような彼の沈黙をたびたび恐れるようになった。でもそれはまだ後のこと、このホテルで過した一週間は素晴らしかった。二人とも幸福の海に漂い、陶酔の午前に寄り添った。私はあの人とずっと一緒にいられるのが嬉しかった。夜中に目を覚ました時、彼の寝息が聞こえると心が安らいだ。毎日私たちはこの部屋で愛し合い、それから外へと出かけていった。お洒落なレストランやブティックは一軒もない田舎町だったけれど、何もかもが美しかった。お年寄りばかりが集うまどろむような簡易食堂で食事をとり、町に一軒しかない映画館でモノクロ映画を観て、ひと気のない小さな公園をぶらついたわ。ちょっと足を伸ばすと森があって、私たちは柔らかい草の上に腰を下ろし、卵とレタス入りのサンドイッチを食べたりもした。そんな時、あの人の視線は私から離れようとはしなかった。私はこれからずっとこんな日が続くものと信じて、幸福のあまり気絶しそうだったわ。
声は休みなく喋り続けた。
とろけるような一週間はあっという間に過ぎ、私たちはロンドンに戻った。それぞれの仕事、それぞれのアパートに帰っていった。けれどもそのうち一緒に住めると思っていたから、それも苦にはならなかった。でもあの人の顔から笑いが消えていき、かわりに冷淡な憂鬱がすべてを覆い隠すようになると、すべてが変わってしまった。最初は気のせいかと思ったけれど、やがて彼は私と会うのを避けるようになった。たまに会ってもその視線は冷たかった。私はどうすれば良いのか分からなかった。ただ手をこまねいて、何かの奇跡によってすべてが元に戻ることを願うばかりだった。あの人の裏切りを知ったのは、それからしばらくしてのことだったわ。あの人の心が私から離れてしまっているのはもう分かっていた。だからあんな日にあんな場所に出かけていったのも偶然なら、大勢の群集の中からあの人を見つけ出したのも偶然だった。あの人はとても幸福そうだった。私にはもう見せなくなった、あの子供みたいな笑みを浮かべていた。そしてあの人の隣にはあの女がいた。なんということでしょう、よりによってあの女が。心臓が止まり、その場に倒れてしまわなかったのが不思議なくらいだった。すぐにその場を立ち去り、自分のアパートに戻った。目の奥にキリを差し込まれたような痛みを感じ、ソファーに身を投げて泣き崩れた。あんな女に、よくも手を出せたものね! でもその時はまだ、怒りを感じる余裕はなかった。ただ消えてしまいたいだけだった。私は母親が来ると嘘をついて、あの人との約束を全部キャンセルした。あの人は疑いもせず、ああそう、とだけ言って電話を切ったわ。その時だった、私の中に憎しみがどっと溢れ出してきたのは。
ぼくは暗闇の中でじっと耳を傾けていた。声はさらに喋り続けた。
私はアパートの部屋から出かけることもせず、苦しみのあまり痩せ細っていったけれど、目だけは憎悪にぎらついていた。部屋の中をハツカネズミみたいにグルグル歩き回りながら、復讐の方法を考えた。そしてふと思った、もうあの人を殺すしかないって。それ以外に私の苦しみを和らげる方法はないって。他人が聞けば笑うかも知れないけれど、私は真剣だった。すぐに殺人手段の研究を始めた。計画が固まるまで一ヶ月かかったわ。あの人の習慣を知り尽くしている私は、機会の選定も慎重に行った。あの人が日曜日の夜、タバコを買いに行く時に通る裏道。ひと気もなく、隠れる場所も多い。あそこならあの人を確実に殺せそうな気がしたわ。こうしてすべての準備が整った。凶器も手に入れた。返り血を浴びても大丈夫なように上着も用意した。マスクとサングラスも用意した。カレンダーを手に取り、ある日付をマルで囲んだ。これが決行日。その瞬間、体中の血が煮立ったトマトソースみたいに熱くなるのが分かった。罪悪感のせいじゃなく、あの人の死をこの手でつかめるような気がしたから。計画があまりにも完璧で、失敗するなんて考えられない。私はベッドにもぐりこんで、夢も見ずにぐっすり眠ったわ。目をさました時、生まれ変わったような気分だった。憑き物が落ちたようなさっぱりした気分で、爽快だった。コーヒーとパンの朝食をとって、それからあのカレンダーの印を見た時、自分でも驚いたことに、殺意や憎悪がきれいさっぱり消えてしまっていることに気づいた。あんなに憎しみをたぎらせていたのが嘘のよう。きっと、殺害計画を立てたことで気持ちの整理がついたのだわ。私はそう考えた。神に感謝の祈りを捧げ、マスクもサングラスも刃物も全部捨ててしまった。そうやって久しぶりに普段の自分を取り戻し、本来の生活に戻ってから一週間たった月曜日、朝刊を読んで、あの人の死を知った。日曜の夜、タバコを買いに出た帰り道に誰かに刺殺されたことを。犯人は分からず、手掛かりも目撃者もなかった。私は新聞を両手で持ったまま立ちすくんだ。自分自身の声が、頭の中で鳴り響いた。これは偶然なんかじゃない、私のせいだ、私が立てた計画は完璧だった、だからあの人は死んだ。私が彼を殺したんだわ。
声は尚も、憑かれたように喋り続けた。
私はベッドの中で丸くなり、ただひたすら眠ろうとした。すべてを忘れ、考えることをやめ、感じることをやめたかった。食事も喉を通らなかった。体がどんどん衰弱していくのが分かった。鏡を見ると目が落ち窪み、十歳も老けて見えた。私はどうしたというのだろう。あの人が死んだからどうだというのか。殺したからなんだというのか。あの人を殺したいと願ったのは誰? でもそんなことを言って自分を騙そうとしても、もう何の役にも立たなかった。自分があの人なしでは生きていけないこと、それはあの新聞記事を読んだ時から分かっていた。私はその喪失に耐えられなかった。それは鈍い痛みとひりつくような渇きをもたらした。だから私はあの人と一緒に過した時間を思い出し、その記憶があたかも柔らかい毛布であるかのように自分を包み込み、私のベッドを満たそうとした、世界を満たそうとした。しかしそうすればするほど、鏡の中の私は痩せ細り、私の絶望は深くなっていった。この喪失に耐える力は私にはない、それは最初から分かっていた。私は身の回りのものを片付け、小さなスーツケースだけ持って再びこのホテルにやってきた。このホテルの、この部屋に。私たちが幸せだった場所、かつて私たちの希望と笑い声が日没時の海と太陽のようにとろけた場所、それをシャボン玉のように包み込んで二人で宙に浮かべた場所に。それから致死量の睡眠薬を水で飲み下し、ベッドに横たわった。目を閉じてあの人のことを思い出そうとしたけれど、もうそれもできなかった。私に残されたのは、冷たい空っぽの空間だけだった。私を中心にぐんぐんとどこまでも遠く広がっていく、あの孤独と呼ばれる灰色の虚空だけだったわ。
そこで声がふっつり聞こえなくなったので、ぼくはようやく眠ることができた。翌朝、ホテルを出て行く時にフロントの若い男に尋ねてみた。「このホテルに、幽霊が出るって噂はないかい?」
若い男はあきれたようにぼくの顔を眺めて言った。「さあ、知らないね」
「じゃあ昔、ここで自殺したイギリス人の女性はいなかった?」
「いないね、そんな女」
ぼくは列車に乗るためにホテルを出た。列車に乗り込んで一息ついたあと、地図を広げ、予期せぬ一夜を過した町の名を探してみたけれども、どうしても見つけることができなかった。



















