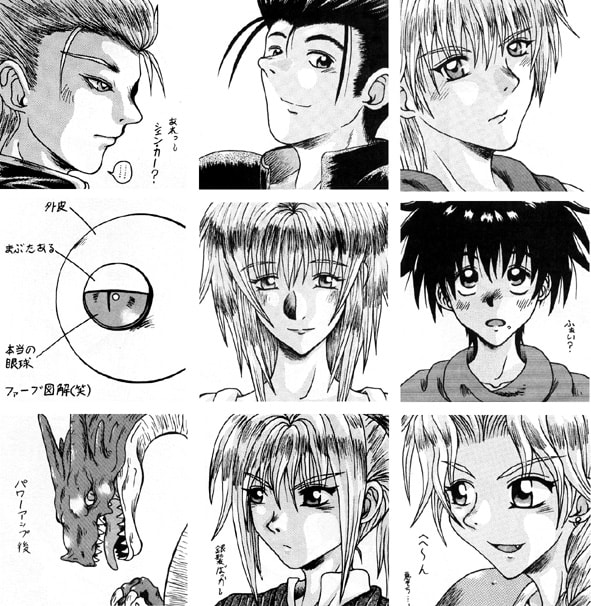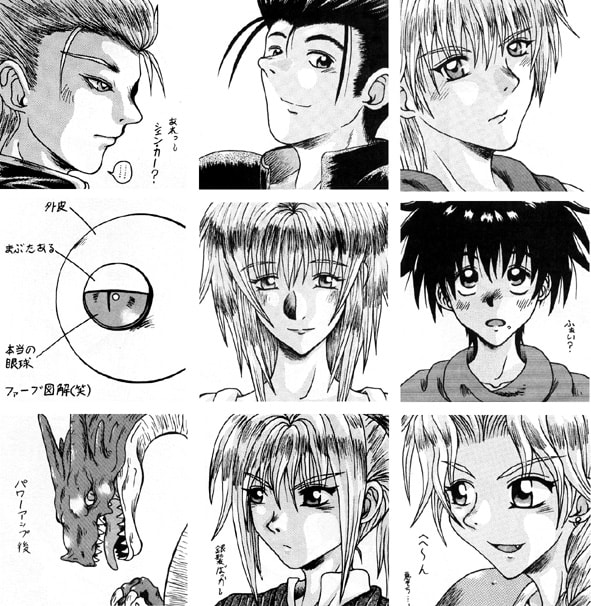※最初(もしくは他の回)から読みたい人はカテゴリーの目次か、右のリンクをご利用下さい→
目 次。
―終わり無き危機―
「ひょっとして、ケガで動けないのか?」
ベーオルフはベルヒルデが重傷の所為で返答できないのだと勝手に納得した。まさかシカトを決め込まれているとは夢にも思わなかったであろう。だが、実際に彼女がかなりの重傷を負っていることは間違いなく、戦闘の疲労もあって暫くは起き上がれそうにもない。
「仕方ないな。ほれ、これをやるよ」
ベーオルフは突っ伏したままのベルヒルデの前に、小さな小瓶をコトリと置く。彼女はわずかに顔を上げ、不審そうに小瓶を見遣った。
「…………何これ?」
「なんだ、ちゃんと口きけるじゃねえか。薬だよ、薬。それを飲めば、かなり楽になるはずだぜ」
「……………………」
ベルヒルデは渋面として薬と睨めっこをしている。どうしてもその薬を口にすることに抵抗を感じるのだ。王族が故に、平時より暗殺の危険に晒されていた彼女は、『得体の知れない食物を口にしてはいけない。毒物が混入されている可能性がある』と、幼い頃から教え込まれていた。だが、もう背に腹はかえられない。
(……この際、仕方がないか……。いつまでも寝ている訳にはいかないものね)
この薬が質の良い魔法薬ならば、立ち上がって歩き回れるくらいには回復できるはずだ。まあ、実はこの薬が眠り薬で飲んだら最後、完全に自由を奪われて拉致監禁、その上で口では言えないようないかがわしいことをされてしまう可能性も無きにしも非ずだが、この男ほどの能力があれば薬などという回りくどい真似をする必要もないだろうし、そもそも今のベルヒルデには何をされても抵抗出来るような余力も残っていないのだから、薬で動きを封じる必要も無い。
それに命を救ってもらっておいて、なおその人物を疑うのはどう考えても失礼だった。それでもベルヒルデはたっぷり1分近い時間をかけ、色々と覚悟を決めた上でようやく薬に手を伸ばした。この獣のような用心深さが彼女を『銀狼姫』と呼ばせしめている要因の1つとなっている。一説によれば貴族の男達がどんなに恋のアプローチをしても、彼女は野性の狼のように心を許そうとしなかったらしく、それが故に狼に例えられるようになったという話もあるほどだ。
ベルヒルデはおずおずと薬を口にした。銀狼姫の餌付けに成功した瞬間である。
「グッ……!?」
ベルヒルデは慌てて口を両手で塞いだ。そんな彼女の顔は、紅潮しているのか蒼白となっているのか判断に苦しむような複雑な顔色――紫色に近い――をしている。
そんなベルヒルデの様子を見たベーオルフは問う。
「『良薬、口に苦し』って言葉知っているよな?」
ベルヒルデは涙目になりながらコクコクと頷く。
「なら、吐くなよ。効き目が無くなるからな。我慢して飲みこめ」
(そんなことを言われてもっ!)
口の中の薬は、なかなか喉を通ろうとはしなかった。まるで身体が拒絶している――というか、実際にしているのだろう。それほどまでに凄まじい味であった。しかし、このまま口内にこの劇物を泳がせ続ければ、味を感じる味蕾細胞が死滅して味覚が駄目になってしまうという最悪の事態が想定される。
だからベルヒルデは、ともすれば火蜥蜴との戦闘時よりも決死の想いで、無理やりに薬を飲み込んだ。
「――っ、何なのよこの無茶苦茶な味はっ!? 一瞬、お花畑が見えたわよ!? なんか、亡くなった父様と母様もいたしっ!!」
「……臨死体験するほど不味いかあ? まあ、仕方がねーだろ。その薬は効能だけを追求した物らしいからな。味にまで手が回らなかったんだろ。その代わり効果は絶大だ。もうかなり良くなったはずだぜ?」
「馬鹿言わないでよ! いくら良薬だからって、そう簡単に傷が治っていたら、治癒魔法なんていらな………………治ってる?」
ベルヒルデは傷の痛みがかなり薄らいでいることに気が付いた。腕の傷を確認してみると、完治こそしてはいないが、もはや重傷でもない。通常、薬よりもはるかに癒しの力がある治癒魔法でも、並みの魔法ではこれほど早く癒せるような傷ではなかったはずなのだが……。
「凄い! これなら、もう一戦くらいいけるかしら?」
「おいおい、いくらなんでも、もう戦うのはよしておけ。その薬、痛み止めの効果もあるから、自分で思っているよりも治っていないぞ、きっと」
「そうなの……? なんだぁ。でも、やっぱりまだ戦わなくちゃ。早く皆を助けに行かないと……」
「……俺が来たのは、お前のところで最後だぞ……」
「えっ? ってことは、他の竜はもうあなたに全部倒されているの? それじゃあ皆は無事なのね……?」
一瞬、安堵しかけたベルヒルデであったが、ベーオルフの次の言葉が、彼女を絶望の谷底へと突き落とす。
「……半分以上…駄目だった……」
「え?」
「言い訳になるが……何故か邪竜の奴らがどうしても俺を城に入れようとしなかったんだ。結局、俺が城に入った頃には騎士達の半分以上駄目だった」
「そんな……っ!」
ベルヒルデはワナワナと唇を震わせた。その表情は何処か茫然としている。
「……それでも数百人がかりとはいえ、中位の竜が4匹も倒されていた。それに避難していた住民には全く被害が出ていなかったみたいだしな。それだけに住民を守護していた騎士には、かなりの被害が出ていたみたいだが……。
大したもんだよ……。正直、俺はもっと被害が大きいと思っていた。それこそ全滅に近いくらいにな……。この国の騎士達はよっぽど有能みたいだな……」
「当たり前よっ! 私の自慢の部下達だものっ!」
うつむきつつ喚くベルヒルデのその声は、既に涙声だった。
「そうか……お前の部下か。それじゃあ、後で沢山褒めてやるんだな……。立派だったってさ……」
(褒めてあげたいわよ……。あなた達を私はの誇り思うって。でも……、でも死んじゃったら……!)
騎士団の――特に戦乙女騎士団の者達の死がベルヒルデの上に重くのしかかってくる。戦いに死は付きものだ。それは彼女も理解している。しかし、頭で理解しているからといっても、どうしても感情では納得できないものが、耐えられないものがある。しかも今回の戦いの指揮を執り、騎士達を死地へ赴かせたのは彼女自身に他ならない。
また、戦乙女騎士団の者達に至っては、彼女達が騎士を志し、戦いに身を投じるようになった切っ掛けはベルヒルデである。やはり自身の責任だろうと彼女は思う。彼女は母を失った時と同様に、再び自らを責めようとしていた。
「しかしこの国にはいい騎士が揃そろっているな……。あいつらが竜相手にあれだけ戦えたのは、国と民を護る使命に信念と誇りを持っているからなんだろうな。そうじゃなきゃ、立場とか全部かなぐり捨ててでも逃げ出しているさ。やっぱ立派だよ……」
「う……ん……」
ベーオルフのその言葉は、『騎士達は自らの意志で、自らの誇りの為に戦ったのだ。だからお前が責任を背負う必要はない』と、言っているようにベルヒルデには思えた。自らにとっての都合のいい解釈かもしれないが、それでも随分と救われた気がする。
「さ、いつまでも悲しんでないで元気だしな。いや……まあ、すぐには無理かもしれないけどさ。生き残った奴らも沢山いるんだ。死者に対してはもう想うことしかしてやれないけどさ、生きている奴には沢山してあげられることがある。死者の為に生者を蔑ろにしちゃいけないと思わないか?」
「……うん……そうだね。早く皆の所にいってあげなきゃ。救護とか沢山やることがあるものね……」
ベルヒルデ指で涙を拭いつつ、はわずかに微笑んだ。ベーオルフの言うことは尤もだ。『死者の為に生者を蔑ろにしてはいけない』そのことに気付いたからこそ、母の死にひたすら悲しみ、自らを責め続けることを幼い頃の彼女はやめたのだ。
(そうだ。やれることがある内は悲しんでいる暇なんか無いんだ……!)
「ありがと、少し元気が出たわ。うん、そういえばまだ助けてもらったお礼もちゃんと言ってなかったわよね。アースガル神聖王国を代表して礼を言うわ。この恩にはどう報いたらいいのか分からないくらい……。いいえ、多分どんなことをしても報い切れないと思うわ」
「んー、別に礼なんて別にいいぜ? 俺だってやりたいようにやっただけだ。それに結構面白いものも見せてもらったしな。報いなんてそれで充分だ」
「面白いもの?」
(そんな面白いものなんてこの国にあったっけ?)と、ベルヒルデは怪訝そうに眉根をよせた。
「ああ、お前の戦いぶりは本当に凄かったわ。あれはちょっと他ではなかなか見られないだろうな」
「…………あなた、私が戦っているところを見ていたの? それならもっと早く助……け……に…………」
ベルヒルデはその言葉の語尾をゴニョゴニョと有耶無耶にした。『助けて欲しかった』と言うのはなんとなく屈辱的に思えたのだ。それに、実際助けてもらいたかったかというと、そうでもなかったような気もする。
「あの時は助けなんか必要なかっただろ? 俺の見立てでは、火蜥蜴とお前のどちらが勝つかは五分五分だった。勝敗も決まっていない内に、しかもまだ勝機のある勝負を邪魔されたくはないだろう?」
「うん……まあね……」
ちょっと戸惑い気味にベルヒルデは頷く。確かにベーオルフがもっと早く助けに入っていれば、彼女はあれほどの重傷を負う必要も無かったし、仲間の所へとすぐさま駆けつけることができた。だが、自分自身の力で戦いに決着をつけたいという想いも間違いなくあり、もしも全力を出し切らない内に横槍を入れられて不完全燃焼となっていたら、彼女は一生心にしこりを残したかもしれない。
「だろ? やっぱり戦士としての矜持(プライド)を持っている奴はそうだよな。それにお前って超一流の戦士だしさ。あの火蜥蜴は殆ど上位竜並みの能力を持っていたんだぜ? それと互角に戦うなんてやっぱ、すげーよ。あの火蜥蜴じゃねーけど、尊敬に値するな、お前のその強さは」
そんな絶賛とも言えるベーオルフの言葉にベルヒルデは不機嫌そうな表情を作る。
「なんか……竜を一撃で倒す人に『凄い』とか言われても嫌味に聞こえちゃうな……」
「あ? 別に嫌味なんかじゃ無いぜ。確かに俺は竜をもあっさりと倒せるだけの能力がある。だけど俺の場合、力(パワー)に頼り過ぎているんだよな。多分……技術の面ではお前の足下にも及ばないだろうさ。お前の戦いぶりを見ていて自分の未熟さを痛感したよ。正直言って、技の指導を願いたいくらいだ。そうすれば俺はもっと強くなれるかもしれない」
「そんなこと……」
さすがにベルヒルデもそこまで言われると悪い気はしない。思わず照れて頬を紅潮させた。それに山を吹き飛ばし、竜を一撃で倒すようなこの男が自身に技の指導を乞いたいと言う。これはちょっと痛快なことかもしれない。
(私の技と、この男の力が合わされば、一体どれほどの強さになるのかしらね……?)
それを見たく無いと言えば嘘になる。
「そうね。あなたが本気ならば、その話、考えてあげてもいいわよ。助けられた恩も返さないといけないしね」
「おおっ、本当か!?」
ベーオルフは本当に嬉しそうな表情を浮かべる。そんな彼に対してベルヒルデは、
(フフ……この人、ただ純粋に強くなりたいみたいね)
と、好感を覚えた。それは彼女も同じように強さを求めたからこその、共感からくる物だったのかもしれない。
「まあ、その辺は後でじっくり話合いましょ。今は皆の様子を見に行きたいわ」
「ああ、そうしてやりな。他の連中もお前の無事を知ったら喜ぶだろうぜ。結構慕われているみたいだしな」
「えへへ……」
ベルヒルデは小さく照れ笑いし、皆の元へと小走りに駆け出した。その瞬間――、
ズゴオォォォォォォッ!!
「なっ!?」
突然、辺りに爆音が響き渡る。それと同時に城を覆っていた結界が霧散した。
「お、王座の間が……!!」
茫然とした顔で、王座の間があったはずの場所をベルヒルデは見上げた。結界が消失したのは結界装置の中枢たる王座の間に何かがあった為だろうと判断してのことだ。しかし、彼女の見上げたその先は、原形を留めぬほどに吹き飛んでいた。
「……しまった! こっちが本命だったのか。それじゃあ、あの水竜はあそこに……!?」
ベーオルフが吐き捨てるように叫ぶ。しかし、ベルヒルデにはその声が殆ど聞こえていない。あまりの精神的衝撃によって、ただひたすらに呆然としている。
(お……王座の間が……。それじゃあ……あそこに居たはずの……)
ようやく最悪の可能性に思考が追いついた瞬間、ベルヒルデは叫ばずにはいられなかった。
「兄様、シグルーンーっ!?」
王座の間にいたはずの兄と妹を呼ぶその声は半ば絶叫であり、そんな彼女の声が響く中、2匹の竜が王座の間の跡に降り立とうとしている姿が見て取れた。
この国を襲う危機は、未だ終わらない…………。
第4巻へと続く
あとがきへ続く(※更新は不定期。更新した場合はここにリンクを張ります)。