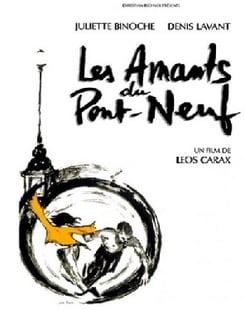(原題:Tschick )観ている間はまあ退屈はしないが、取り立てて良くもない。少年達のロード・ムービーとしては「マイ・フレンド・フォーエバー」(95年)よりも幾分マシだが、「スタンド・バイ・ミー」(86年)にはとても及ばない。有り体に言えば“中の下”の出来であろう。
ドイツの地方都市に住むマイクは、周囲から変人扱いされている冴えない中学生。クラスのマドンナ的存在の女生徒の誕生日パーティにも、絶対に呼ばれない。ある日、その学校に中央アジア出身のロシア系移民の子であるチックが転校してくる。彼はマイク以上の問題児で、誰も相手にしない。夏休みに入ってもヒマを持て余すだけのマイクの家に、チックがいきなり乗り込んできてドライブに誘う。盗んだディーゼル車で一緒にルーマニアのワラキアまで行こうというのだ。
無理矢理にチックに付き合わされることになったマイクだが、途中で知り合ったチェコ出身の若い女イザを加えての道中は、けっこう楽しめるものになる。だが、思わぬ事故により彼らの旅は唐突に終わる。ドイツ国内で220万部以上を売り上げたというベストセラー児童文学の映画化だ。
笑える場面やホノボノとするシークエンスもあるのだが、あまり楽しめないのは主人公達の振る舞いが完全に犯罪行為だからだ。無断で車を拝借したのを皮切りに、警察官の公務を妨害し、勝手に畑に入って農作物を荒らす。ヨソのトラックから燃料を盗み、果ては迷惑運転で検挙される。もちろん、2人とも車の免許なんてものは持ち合わせていない。マイクは今までは単なる変人だったのが、旅が終われば札付きの不良になって皆をビビらせる存在になったと・・・・つまり、そういうことだろう。
そもそも、マイクの母親はアル中で、父親は家庭を顧みず若い愛人とよろしくやっているという設定は、息子が非行に走ってもおかしくないものだ。で、その図式通りストーリーが進んでもらっても、観ている側としては鼻白むしかない。監督のファティ・アキンは以前「ソウル・キッチン」(2009年)という快作を手掛けたが、この映画では後退しているような印象を受ける。主演のガキ2人は良い演技はしているが、作品自体が気勢が上がらないので評価は差し控えたい。
ただ、ライナー・クラウスマンのカメラがとらえたドイツの自然や田園風景はキレイだった。そして個人的にウケたのが、彼らのドライブのBGMとして流れるリチャード・クレイダーマンの「渚のアデリーヌ」(爆)。音源がカセットテープだが、テープが絡まって再生不能になると2人が“クレイダーマンが死んだ!”と言ってのけるのが妙におかしかった。