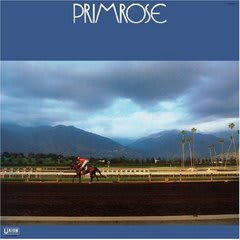(原題:Resident Evil )2002年作品。同名のテレビゲームを映画化したサバイバル・スリラー。シリーズ化され、現時点で(実写版は)4本が作られているが、私が観たのは最初のこの映画だけである。
バイオ兵器を開発していた巨大企業で、人間をゾンビ化させる新種のウイルスが蔓延。内部調査のため送り込まれた特殊部隊とゾンビ軍団との死闘が延々と続くといった内容だ。まあ、ちょっと面白かった「イベント・ホライゾン」のポール・W・S・アンダーソンが監督なので、そこそこ観られる映画にはなっている。
元ネタになったゲームの“本編”を描くのではなく、その“前日談(?)”を扱っているせいで、一本の作品としての製作コンセプトを獲得することには成功しているようだ。少なくとも同じくゲームの映画化である「ファイナルファンタジー」や「トゥームレイダー」みたいな居心地の悪さは希薄だ。
しかし、映画のウリである“特殊部隊とゾンビ軍団の死闘”が脚本の段取りが悪いせいか、ほとんど盛り上がらない。舞台の地理関係が十分映像で示されていないのが原因かと思われる。それより前半の、地下世界を制御するコンピュータとの戦いが断然面白い。特に人間を切り刻む“レーザー攻撃”のシーンは出色。こっちの方をメインに持ってくるべきだった。ヒロイン役のミラ・ジョヴォヴィッチは今回も露出度全開(笑)。その手のファンには喜ばれよう。




バイオ兵器を開発していた巨大企業で、人間をゾンビ化させる新種のウイルスが蔓延。内部調査のため送り込まれた特殊部隊とゾンビ軍団との死闘が延々と続くといった内容だ。まあ、ちょっと面白かった「イベント・ホライゾン」のポール・W・S・アンダーソンが監督なので、そこそこ観られる映画にはなっている。
元ネタになったゲームの“本編”を描くのではなく、その“前日談(?)”を扱っているせいで、一本の作品としての製作コンセプトを獲得することには成功しているようだ。少なくとも同じくゲームの映画化である「ファイナルファンタジー」や「トゥームレイダー」みたいな居心地の悪さは希薄だ。
しかし、映画のウリである“特殊部隊とゾンビ軍団の死闘”が脚本の段取りが悪いせいか、ほとんど盛り上がらない。舞台の地理関係が十分映像で示されていないのが原因かと思われる。それより前半の、地下世界を制御するコンピュータとの戦いが断然面白い。特に人間を切り刻む“レーザー攻撃”のシーンは出色。こっちの方をメインに持ってくるべきだった。ヒロイン役のミラ・ジョヴォヴィッチは今回も露出度全開(笑)。その手のファンには喜ばれよう。