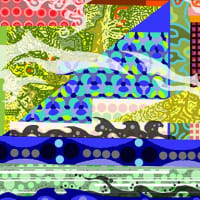7・混沌の海を越えて
香奈恵はドラコにしがみついたまま、手を伸ばした。
「ジンさん!」
(ダメにょ!精一杯にょ!)
ドラコはにべもない。(デモンバルグは大丈夫に決まってるのにょ)
ドラコはヒレで意識のない鈴木真由美を支えている。
(それににょ、この場所の底に沈むのは危険だとドラコは思うにょ。とりあえず、上に上がるのがいいにょ!)
「上に上がったって、どうなるのよ?」
(窓から脱出するにょ)
「あの穴?、変な女が見張ってたじゃない!」
(ドラコには~どうにかなると思うのにょ~)
デモンバルグは遠ざかるドラゴンを見上げていた。
ドラゴンに掴まる香奈恵の姿がどんどん遠ざかって行く。ジンの目には真由美の膨らんだ腹部が光り輝くのが見える。今はあそこにある、似たような魂。
光は遠ざかって行く。まんまと騙された。ジンの唇が笑う。
そして反対にジンの体は沈んで行く。
『ちくしょう、俺としたことが!』何一つ、触るものもない無限の混沌が重く暗く広がっている。目に入るものもなくなった、無限の闇。
(混沌に溶けて消えるがいい!)黒皇女のあざけるような声が頭に響いてくる。
『冗談じゃない!』ジンはそれを振り払う。
『溶けてたまるか!俺は天下のデモンバルグさ!世界の創世から生き残って来た魔族さ。剣と盾を併せ持つドウチなんさ!』
おそらく、この死んだ肉体に入っている限りはデモンバルグの意識が混沌に流れ出す、それはありえない。黒皇女の言葉が正しければだ。
「肉を持たぬものが溶ける混沌だとっ、くそっ!」思わず叫ぶ。「そんな馬鹿な!」
この肉を捨て去れば、ひょっとして活路が開ける可能性はある。
しかし。
この重く淀んだ混沌と呼ばれるものが、自分にどういう作用を及ぼすかはデモンバルグにも自信がなかった。『ゼリーいや、融かした片栗粉のようなものか。熱くも寒くもない・・・でも、あの魔族の女は焼かれて半死半生になったんだった・・・酸に溶かされたみたいになってさ・・・どういう理屈なんだか。まったく、陰気くさい場所だぜ。」しかしそうなると、うかつに外へ出るわけにはいかなくなる・・・と、いうことは嫌な予感が浮かんだ。この肉に永久に閉じ込められたままになってしまうというのか。重い死人の肉は下へ下へと沈んで行く。
浮上することは叶いそうもない。
沈むとともに水圧のように更に重い空間が回りから迫ってくる。肉が回りから圧迫されてしまっていくのを感じた。骨がギシギシとなる音を聞きながら、デモンバルグは絶望的な予想を巡らせた。まさかこのまま、押しつぶされて行くのか?
彼を乗せた肉の船は終いには圧縮された肉の塊に成り果てる可能性が過った。
すると死体のではない悪魔の目に真下の方から見覚えのある装束を纏った人体が漂うように近づいて来るのが見えた。「こんなところにひとがた?女か?」
圧縮されてないということは生きた人体なのか。ジンが近づこうと努力するまでもなく、ジンの乗った肉塊はなんなく側へと落ちて行った。
やがて、広がった髪の中に仰向いた白い顔が見える。
それを見た瞬間、デモンバルグは電撃に打たれた思いがした。
「盾の巫女・・・!?」
いや、そんなはずはなかった。これは・・・すぐに合点する。
色のない混沌のなかでは濃淡にしかわからないが、女の纏っている衣装はおそらく白い着物に緋の袴。巫女の装束に間違いない。
「あはは、なるほどこりゃね。巫女は巫女でも・・・」
ジンは縮んで行く肉の船の上で、混沌を飲み込みながらもむせび笑った。痙攣に似た衝動がデモンバルグをジンの肉体と微妙にぶれさせた。
「こんなところにあったとはな。見つからないはずだ。」
はみ出した悪魔の本体は尚も船にしがみつきながらも、声を詰まらせる。
「これが・・渡の大大叔母さんの遺体ってわけだ・・!なるほどさね・・・盾の魂を持っていたのがこの叔母さんだったと。遺体はここに、混沌に沈められていた・・・だから、魂魄の片方が彷徨っていたってことなのか・・・剣の魂が竹本の血縁に惹かれたってのも・・・あがなちあの蒼い光のせいだけじゃなかったってわけさね・・・こりゃ、おかしいや!」
はみ出した本体の口から、声を放つと多数の泡と共に血のようにエネルギーが溢れ出る。しまった、早くまた肉体に入らなくては。しかし、随分と縮んだ肉塊はデモンバルグ自体の容積を超えてしまいそうだ。デモンバルグは小さく潜り込んで尚も肉塊にとどまろうと試みる。俺も溶けてしまうのだろうか。次第に意識がぼんやりとして来るのを叱るように引き締める。自分と言う認識がぼやけ、輪郭を失い丸くなって行くようだ。そこは自分がかつていた場所。遥か、遥か古代のどこかで・・・自分が産声を上げた場所なのか。聳える輝きわたる塔。白い船。
走馬灯のように過去が頭に溢れるのは人間だけではないのか。
『ちくしょう・・・まさか・・・いや、一か八かさっ!』
デモンバルグは追い越しざまに大大叔母の身体に飛び移った。
ジンの面影を失い、人体の形も崩れつつある醜い塊が真下へと落ちて消えた。
「この叔母さんは沈まないし、縮まないみたいさね・・・?なんでなんだろう・・・盾の魂が入っていた容れ物だ・・・丈夫らしいさ。」
デモンは居心地悪く、女の身体に潜り込んだ。
『なんだ?この違和感は・・・』
悪魔たるもの女の体に入ったことがないわけはない。正確には彼等には性別などない、と言うのが基本である。男悪魔であったり女悪魔であったりすることは、完全にそれぞれの嗜好が関係している。この世界への出現の仕方というならば魔族や天使族の親から産まれ落ちるというものは少ない。突如、意識を持ってこの世界に存在していたことを認識するのだとでも言えばいいだろうか。勿論その瞬間は彼等は無性であり、同時に両性でもあると言えるのがこの『果ての地球』独自の次元生物であるとアギュレギオンが推定している彼等だった。
デモンバルグは細心の注意力で自分が仮宿として選んだ体を内側から探っていった。
そして今は冷たく凍えた子宮の片隅に遂にその違和感の原因を発見した。
しばしジンはその固いしこりを当惑を持っていじくり回していた。
『なるほどさぁね・・・。』結果、それがパンドラの箱であるのかもしれないとデモンバルグは結論ずける。『この体が沈みもせず、混沌に壊されもしない理由がわかったぜ。盾の魂が鈴木真由美の胎児に移った後なのにさ。この巫女の女はすげぇな。寛大と言うか、本家の盾の巫女にも匹敵するお人好しぶりさね・・・こんなものまで内に飼っていたとは。こいつは・・・・こいつがこの体を守っていたわけか。』
寝た子は起こすな。ましてこの狭い体の中でこいつと共存するなんて言うのはまっぴら御免だった。デモンバルグはその存在は無視を決め込むことにする。
生きた細胞であったならデモンバルグのエネルギーに感応させて彼の思いのままに配列を変えることもできる。そうやって今まで彼は神興一郎というアジア人を作り出してきた。しかし、細胞のひとつ1つが呼吸を止めた死体では外観を選ぶ事などはできない。この巫女の外観のままでいるしかなかった。
『まったく因縁話だぜ。俺も忘れかけたぐらいの古代に・・・盾の巫女の自滅を静観していた俺がさ・・あの巫女に酷似したさ、こんな体に押し込められるとは。しかも、ありがたくもない居候がいるときた・・・』
デモンバルグには己の膨大な過去を振り返る時間が今やたっぷりある。
無限といってもよい。そのことはさすがにデモンバルグを少し落ち込ませた。
その時だった。レイコと呼ばれた肉体を纏ったばかりのデモンバルグであったが、彼の超魔族としてのアンテナが遥か下から浮上してくる何かを認識し始める。
『まさかな・・・遥か底まで溶け出した俺の意識が俺に何かを伝えようとしている・・・なんてわけはあるまいが・・・こんなところに何がいるっていうのか?。今度こそ・・・敵か味方か・・・一難さってまた一難さね。』
そう思うと、デモンバルグは広がる黒髪を両手で分けて見開いた巫女の目をきびしく凝らした。しかし、暗闇があるばかりで何も視界には写らなかった。随分と。悪魔にとっても随分と長い時間が経過したように感じられた。
やがてやっと、揺れる不透明なうねりの底が微かに判別できるようになり辺りがぼんやりとわずかに蒼く光り始めた。その光は次第に強くなっていく。
悪魔に動悸があるとしたらその心臓はそれは激しく振動していたことだろう。
『あの屋敷に入った瞬間から、俺の感覚は狂わされていたみたいだが・・・まだ、戻らないのか? そんな・・まさか・・・この気配・・・?』
デモンバルグは近づいて来るものが蒼い光体であることを認めた。
自分が深く安堵したことに思わず、デモンは笑っている。
『さっきからまったくさ・・・まさか、まさかの連続さねぇ。こんなに生きているっていうのに・・まったく退屈しないさね。だから悪魔は辞められないってかさ。』
ほどなくデモンバルグの意識は巫女の肉体ごと蒼い光に包まれていた。
「これは、これは。」
アギュレギオンの口調はひどく驚いた為におどけた口調になってしまった。
「デモンバルグ・・・ですよね。そんな身体で・・・どうしてここにいるのです? その姿は、いつもよりは趣味がいいですね。」
アギュはかつて知る面影に似通うレイコの顔を複雑な気持ちで見下ろす。
「・・・おまえこそ、なんでここに。」
レイコの肉体は戸惑いを隠すこともできずにアギュを見上げた。
二人の視線が再び合致する。
いまや巫女の体はアギュの腕にしっかりと抱かれている。その体と放つ光にしっかりと包まれた安心感、凍えた死体の中に納まった悪魔の体をも暖める体温をジンは触れた掌から感じている。癒されたなどとは口が裂けても言えない。
ジンは色の褪せた唇を噛み、切れ長の瞳で睨みつけた。
「俺だって好きでこんな身体に入ってる訳じゃないんさ。」
「じゃあ、どういうわけで?」
ジンはその質問は無視した。悪魔にも言いたくない、恥ずかしい時もあるのだ。
「そんなことより、蒼い光野郎。お前は宇宙人なんだろうが?。それが、どうしてここにいるんだ? まず、それを答えろ。」
「それがあまりにも荒唐無稽で・・・話しても到底信じてもらえるかどうか。」
アギュはジンとの顔の近さに閉口していた。愛するユウリに酷似する顔。かつて知る顔よりは老成し、揺るぎのない意志を刻んでいるがまだ若々しく美しい。
小柄ではあったが、子供を産んだことのある成熟した豊満な肉体は薄い夏物の着物一枚に包まれてアギュの体に密着しているのだ。
ジンも状況に苛立っている。なんだよ、これ。傍目には恋人同士の抱擁じゃないか?。ジンの口調は思わず噛み付くようになる。
「お前さ、ここが『混沌』だと知っているんだろうな?!」
アギュの口調が変わる。
「フン!今、オマエの記憶を読んだぞ。」口元はバカにしたように歪んだ。
「ムカシのオンナに足下をすくわれたな。黒幕はもう一人のマゾクのオンナだな。戦前からこの辺りに巣食っていたマモノだ。ソイツの陰険なやり口はじっくりと拝見してきたぞ。手出しができないことがはがゆいばかりだ。」アギュの蒼い瞳が暗い深みを増す。「ソイツがナグロスとレイコを陥れたヤツだ。」
デモンバルグはよくわからず沈黙していたのだが、驚いたことに別の声が答えた。
「それよりもです、ここは混沌と呼ばれるのですか・・・興味深いところですね。あまり健康に良さそうな場所ではないけれど。・・・ああ、カナエもここにいるんですか。でも、ドラコが付いてるから大丈夫でしょう。アトで見つけに行きましょう。それとも、もう脱出しましたか?・・」「うまく脱出したようだな。」「それは良かったです。ここでは肉体が容れ物として機能しているようですからね、もう一人の女性もおそらく後遺症はないのでしょうね。ただ・・・戦前からここにいるというその魔族の女が今だに上で見張ってるとしたら・・・結構、やっかいなことになっている可能性があります。加勢にいかなくては・・・ですね?。」
「すぐに引き返して、オレが助けにいくさ。」アギュは息を吐いた。
「おまえは・・・おまえはいったい・・・なんなんだ?」
アギュに包まれ支えられた今、すべてを言い当てられたデモンバルグは少し、本来の不遜な態度を失ったようだ。しかも、その言葉を放つのは今は流れる黒髪も美しい、たおやかな巫女姿なのだからまったく迫力がない。
恐怖を司るデモンバルグとしては、面目丸つぶれの思いだった。
「ここはさ・・万物が産まれ来る場所、混沌なんさ。まず普通に来れる場所ではないはずなんだが。いったい、あんたはどこから来たのさ?」
「フフン、これもジゲンの一種だからな。」アギュは嘯く。「イマは見つけられなくてもオレのリンカイが進めば、いずれはジリキで探知したはずだ。このホシのジンルイ達の集合意識が作り上げたジゲンのソコがここだ。ここは一番波長の低い、ソコの方に当たるな。」
底?デモンは内心当惑する。自分は確かに上から沈んで来たのではないのか?
アギュよりも、もうちょっとだけ親切な418が説明を始める。たとえ相手がデモンバルグであってもかつて愛した相手の親の肉体に入ったからには,邪見にできないらしい。
「私達は過去から来たんですよ。60年前の記憶から。渡の大大叔母さんの死体がここにあるのがわかったんで回収に来たんです。これがあれば、彷徨う叔母さんの魂を分離できるんじゃないかと思いましたんで。」カプートと呼ばれた418が微笑む。
「ここが混沌と呼ばれることは始めて知りました。」4大天使の記憶が最終的にここに繋がっていたとは彼としても驚きであった。彼等、天使達にとってもここは産まれいずる場所なのだろうか。
「まあ、そんなわけでずっと・・・色んな過去を見て来たわけです・・・」
デモンバルグの歴史をというところは割愛した。
「さすがにちょっと疲れましたけどね。」
「そうか?オレは全然、疲れてないぞ。」アギュが口を挟んだ。「疲れたなら奥で寝ていろ。外へ出たら、何かありそうだからな、オマエだって感じるだろ、もめ事の気配だ。そのマゾクとかいう奴らをぶっ飛ばせばすべて解決するじゃないか。ワクワクするぞ。」
腕の中のレイコの身体をぐっと引き寄せる。
「気色悪いけど、オマエも助けてやる。レイコの体に入ってるから、仕方なくだ。恩に着ろ、アクマ。」
「おまえは・・・光・・」デモンは確信した。「やっぱり1人じゃないんだな。」
「今頃、わかったか。バカめ、ニブいアクマだ。テンシの方がずっとものわかりが良かったぞ。」
「天使?」ハッとした。「まさか、おまえら天使にあったのか?・・・4大天使か?」
「まあな。」
「はあ、なるほど。過去を司る奴ら・・・ってか。あいつらいつの間にそんな力を得たのか。」
「何千年も高カロリー食を食べたからじゃないですかね。」
「引っ込んでろ、カプート。」
再びデモンバルグにはあずかり知らぬ名前を口にする。
アギュはレイコの肉体を抱えて上昇を・・・いや、底に向かっての下降なのかどちらかを始める。
「見ろ、ナグロスがいるぞ。」
「権現山の仙人さ・・・。ナグロスというのか・・と、言うことはこいつもやっぱり宇宙人なんさな・・・」レイコが呟く。かつて御堂山で遊民ギャングに宇宙人呼ばわりされた時に仙人は無言でいたが、あえて否定しなかったことを思い出す。
「こいつまでここに沈んでいたとは。」
「生きてる体はそんなに沈まないんだな。」
アギュは取り合わず、無造作に身体を引き寄せた。
「壊れることもない。レイコとナグロス。本物の恋人同士だ。」
仙人と呼ばれた男の目はもはや虚ろであり、蒼白の顔色は土気色に近い。
死体の方がまだ生きがいいとジンは顔を顰めレイコの体を仙人から遠ざけた。それに構わないアギュは男の体も抱えるとやつれた顔をしげしげと眺めた。
「老けたな。」アギュが容赦なく断定する。
「さっきまで若いのを見てたから余計に感じるんですよ。」
「仕方ないだろ。人間は年を取るんだ。」自分でも思いがけず、デモンが反論した。「すぐ、死んじまうんだから仕方ないさ。」
「・・・ホントにそうだな。」
アギュが大きなため息を付いたので、デモンバルグはレイコの口をつぐんだ。
哀しみが籠っていたからだ。臨海進化体の事情を悪魔は知らない。
「とりあえず、コレも連れて行くか。」
「おい、どっちに行くんさ?」悪魔ですらぐるぐると感覚が麻痺して来る。
「上がってるのか、下がってるのか、今はいったいどっちなんだ?俺にも頭がこんがらがって来たさ。」
アギュレギオンは仙人とレイコの体をまとめてグイと引き上げる。仙人のひげ面とと肌が触れ合ったデモンバルグはレイコの体の中であがいた。
「もっと丁寧に扱え!」
「お前らは元フウフだ。引き裂かれたフタリがキセキの再開だ。仲良く、大人しくくっついてろ。」
「冗談じゃないぞ! こいつ、髭をちゃんと剃ってないじゃないか!」
「スコシのアイダぐらい我慢しろ!」
デモンバルグが抗議するが、それに構わずアギュは光度をあげる。混沌のうねりが潮流のように流れる以外は何も見えない、感じられなくなる。
「面倒くさいモノを二つも抱えて、悶着はごめんだ。」
アギュがデモンバルグに聞かせるでもなく言葉を吐く。
「オマエは知っているか?この中はジカンが流れてないんだ。」
動いている実感はほとんどない。しかし、混沌は次第に澄み色が変わって行く。それと半比例するように辺りには、何かわからない金属音が高まっていった。テープの早回しのように流れて行くものは音であるのか、映像であるのか。辺りはどんどん騒がしくなり、手に触れられそうなほど濃い密度の喧噪がいくつも現れもつれ、解けるように渦巻いてあっと言う間に後方に遠ざかって行く。
「アクマ、面白いものを見せてやる。オマエが落ちたとこに戻るのも楽しいが、もっともっと面白いデグチがあるぞ。多分、いくら長生きのオマエでも始めてのケイケンだろうよ。楽しみだな。オレに感謝するがいい。」
アギュは呵々かと笑ったが、その声は音の洪水の中で悪魔の地獄耳でも聞き取るのがやっとだった。