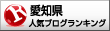その中にいると当たり前のように感じられたり、特に違和感を感じないことはあるものだ
現在の社会の弱い者いじめ的なバッシング(眞子さんのパートナーに対する)や
長いものに巻かれろ的なものは、一部の意識高い系の人には批判されていても
現実にはそれらを喜んで受け入れている大衆の多さから、それは日本社会に内在する問題
かもしれない(と思えたりする)
自分たちの考えや行動が世界的に見てどのように評価されているか?
を知ることは、自分たちの組織の中で想像力を用い自分たちだけで評価するだけで駄目で
客観的に外の評価と比較することによって初めて明らかになるかもしれない
去年読んだ「歴史の終わり」(フランシス・フクヤマ著)の中に日本のことが
書かれていた部分があり、とても気になったので書き残しておいた
それは日本社会のあり方とか優先順位に関することで
この本が書かれた時代と今とは少し変わっているかもしれないが
それでも大枠のところで今でも十分通用しそうな内容だ
以下がその抜粋
ほとんどのアジアの諸国では政治的権威の起源が欧米の場合とは異なっており、リベラルな民主主義についての解釈も、歴史的にそれが誕生してきた国々とはかなり違っている。 儒教的な社会においては集団と言うものが労働倫理を維持する上で重要なばかりでなく、政治的権威の基盤としても決定的な意味を持つ。ある一個人が地位を得るのは、当人の持っている個人的な能力や価値のおかげというより、もっぱら彼が数珠つなぎになった一連の諸集団にその1つに属しているためだ。 例えば、日本の憲法や法体系はアメリカと同様に個人の諸権利を認めているかもしれないが、一方で日本の社会はまずもって集団を認めようとする傾向がある。
このような社会における個人は、当人が既存の集団の一員であってその規則を遵守する限りにおいて尊厳を持つ。しかし、彼がその集団に対して自己の尊厳や権利を主張するやいなや、伝統的な専制支配の公然たる暴政にも劣らないほどの手ひどい社会的村八分に遭い、地位を失う羽目になる。このことが協調性を要求するための計り知れない圧力を生み出し、そのような社会に暮らすものは幼い子供をうちからこの協調性を植え付けられていく。 言い換えればアジア社会における個人は、トクヴィルの「多数者の専制」―あるいはむしろ、大小問わず個人の生活と関わりのあるあらゆる社会的集団の中の多数者の専制―の餌食となっているのである。
このような専制については日本社会の中から2、3の例を挙げることができるだろうし、東アジアのどの文化にも似たようなところはある。日本において個人がまず第一に敬意を払うべき社会集団は家族であり、 子供に対する父親の慈愛に満ちた権威は、支配者と非支配者との関係を含めて社会全般の力関係の原型であった(ヨーロッパでも家父長的権威が政治的権威のモデルだったが、近代自由主義はその伝統に対して明確な決別を表明した)
アメリカでも子供たちは、 幼いうちは両親の権威への服従を要求される。だが成長するにつれて彼らは親に反抗して自分自身のアイデンティティーを主張し始める。親の価値観や希望に子供が公然とそむく10代の反逆という行為は、1人の大人の人間としての個性を作り上げていく過程でほとんど欠かせないものなのだ。なぜなら反逆という行為によってのみ子供は自立と自活への精神的心構えを養っていく。同時に自分を守ってくれる家庭という傘を捨てる能力、 そしてのちには1人の大人としての人格を支える能力に基づいた、1個の人間としての「気概」に満ちた自己価値観を磨いていくのだ。この反逆の時期をくぐり抜けて初めて彼は両親と互いに尊重し合う関係に戻れるが、それはもうかつてのような従属関係ではなく対等な付き合いなのである。
これに対して日本は異なる。幼い頃の年長者への服従は、成人してからも一生続いていくのが当然とされる。人の「気概」は、個人の資質に誇りを抱く自分自身にではなく、むしろ、個々の構成員以上に全体としての評判を優先する家族その他の集団へと結びついていく。怒りが生じるのは、他人が自分自身の価値を認めてくれなかった時ではなく、こうした集団が軽視される時である。逆に、最大の羞恥心は、 個人的な失敗からではなく自分の属する集団が被った不名誉から生じる。
したがって日本の多くの親たちは、結婚相手を選ぶ子供たちにとって重要な決断に対しても、自尊心のあるアメリカの若者なら誰ひとり許さないようなことをところまで差し出がましく口を挟むのである。
日本での集団意識の表れの第2番目のものは、従来からの西欧流の民主主義的な「政治」と言うものが沈黙しているところにある。というのも西洋の民主主義は善悪についての「気概」にもとづいた対立意見のぶつかり合いの上に成り立ち、その対立はマスコミでの論戦となって現れ、最終的には各種レベルの選挙によって利害や主張の異なる政党が政権交代を繰り返していくのである。この対立意見のぶつかり合いは当然至極で、民主主義の正常な機能にとって不可欠な 付随物であると考えられている。
対照的に日本では、社会全体が単一かつ安定した経営の源泉を持っているただ1つの大集団とみなされがちだ。そして集団の調和を強調することによって、開かれた対立は政治の外縁部へと追いやられてしまう傾向にある。だから日本には政治問題での衝突による政権交代は皆無で、むしろ自由民主党の支配が数十年にわたって続いているのである。
もちろん、自由民主党と野党の社会党や共産党の間にはあからさまな論争もあるが、これらの野党は、主張が急進的すぎるために時流から取り残されているのが実情だ。そしてまともな意味での政治の駆け引きは、おおざっぱに言えば中央官僚制度の内部や自民党の密室など大衆の目が届かないところで取り行われているのである。自民党の中では、政治は個人的な親分子分の関係に基づいた派閥の絶え間ない奸策の周りをぐるぐるめぐっており、西欧なら誰もが政治の中身として理解しているものがそこには全く欠けているのだ。
(これが書かれたのは、社会党が存在していた頃)
西欧と同じ民主主義的な社会を実現しているようでも、他所から見れば日本はこのような見方をされている
個の確立がされれば必然的に起き上がる問題意識も、日本社会では集団的な秩序と相反するものと思われた時点で
感情的に排除されたり無視されたりする
また憲法でも個人間の同意のもとに法的に認められる結婚も、今回の大騒ぎのような外野が小姑の様に
そしてそれは正しいことのように思い込んで批判をし、その行為自体になんの罪悪感も違和感も感じないでいる
そして西欧社会では意見のぶつかり合いは至極当然で、それにより切磋琢磨されると認識されているが
日本では「批判ばかり」と言葉を妙な方向に捻じ曲げられた報道が社会全体の空気をつくる
残念ながら「歴史の終わり」での指摘は、そのとおりだと実感する
だが一番残念なのは、このように実感している人が数多くないと思えてしまうことだ
本来ならば政治家なり教授なりが率先して日本社会の問題点として掲げる問題を
安易な昔からの伝統といったような言葉で認め、それが制度疲労していても
現状を変えようとしないでいること(それどころか過去に戻ろうとさえしている)は大いに不満だ
人の社会の正解は実際には誰もわからない
時が経過してからのみ、その選択が良いものだったかどうかがわかる
だが人にできる確率的に正しいと思われる選択をするには
少しづつ気づいた欠点は修正していくことだと思われる(それは保守の考え方の基本らしい)
今日と同じような明日があるということは、同じことの繰り返しをしていることではなくて
実は微妙な修正のうえに成り立つものだと思う
ただ微妙な修正は誰が指摘して行っていくかは、意識高い系の人に頼らざるを得ないところは
あるかもしれない
この意識高い系の人々の存在とその行動(発言)が社会にうまく認められば良いのだが
これがなかなか難しそう、、
さて、田舎のおっさんはここで何をすべきか
最新の画像[もっと見る]
-
 文化会館の「ランチタイムコンサート」
2週間前
文化会館の「ランチタイムコンサート」
2週間前
-
 9月も暑い
2週間前
9月も暑い
2週間前
-
 しょうがないことかもしれない
3週間前
しょうがないことかもしれない
3週間前
-
 8月の気温と木瓜(ボケ)の花
4週間前
8月の気温と木瓜(ボケ)の花
4週間前
-
 8月の気温と木瓜(ボケ)の花
4週間前
8月の気温と木瓜(ボケ)の花
4週間前
-
 枕草子 清少納言の挑戦状
4週間前
枕草子 清少納言の挑戦状
4週間前
-
 枕草子 清少納言の挑戦状
4週間前
枕草子 清少納言の挑戦状
4週間前
-
 委託業者はせざるを得ないのだろうか
4週間前
委託業者はせざるを得ないのだろうか
4週間前
-
 委託業者はせざるを得ないのだろうか
4週間前
委託業者はせざるを得ないのだろうか
4週間前
-
 「なぜ、子どもはあのような絵を描くのか」
4週間前
「なぜ、子どもはあのような絵を描くのか」
4週間前