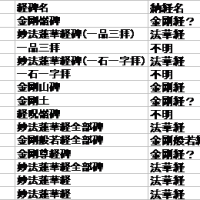考古学者とは、比喩的に定義すれば「モノ」に「語らせる」ことで一つの「物語」をつくりあげる作家のようだ、というのが最初の読後感である。とはいえ、即座に付記しておかなければならない。彼の手法はどこまでも科学的=実証的でなければならず、「作品」はフィクションであってはならない、と。
「物語」の発端は1972年、東京都教育委員会が無人となった小笠原諸島で実施した遺跡分布調査である。大学で考古学を専攻した著者は、この年同教育委員会に採用されたばかりであった。この調査で産地不明・由来不明の「無釉焼締陶器」(大甕)類が発見された。この陶器類は、引き続き調査が行われた伊豆大島の八丈島でも大量に発見された。島では「南蛮カメ」と呼ばれ、「島焼酎」や水貯蔵として多用されたという。
この陶器類は、当時産地不明として調査報告書にも記載されないままに推移したが、1991~1993年の東京都港区汐留遺跡(仙台藩伊達家上屋敷跡)から発掘された「無釉焼締徳利」の調査・分析結果から、いずれも那覇市壺屋で焼かれた「壺屋焼」であることが判明した。小笠原での発見から20年が経過したことになる。言い換えれば著者は、20年間この陶器の出所と来歴を尋ね歩いてきたということだ。本書の出だしは、その旅程を「考古学的」に縷々述べることから始まる。
どの「科学」も特定の対象と特定の方法を持っている。考古学の場合、まずは「発掘」という方法がある。対象はモノ。出土したモノ=物的資料の比較・分析・分類が行われる。そのための指針は、それまでに発掘された同類の資料の分布と編年である。問題は出土した資料が、ラベル名がはっきりした「引き出し」に入れられない「新発見」の場合だ。この発見が従来の研究に新たな一ページを加えるか、あるいは従来の説を覆すかする可能性を予期させる場合は研究者の注目を集めるが、そうでないと判断された場合は「その他」のラベルがついた引き出しに収められ、眠って(眠らされて)しまう。
本書が対象とする「無釉焼締」の陶器とは、結論から言えば「壺屋焼」のそれである。したがって著者は、長年引き出しの中で「無視」されてきた「その他」の陶磁器類を比較=分析することによってその中から一つの共通項を見つけ出し、「壺屋焼」というもう一つの引き出しを作り上げることに成功したのである。この方法を「科学的=学問的」と言わずして何と言おうか。
この種の調査研究=作業がどれだけの労苦を求めるものか。著者は述懐している。「(本土の)近世遺跡から発掘される膨大な陶磁器類の中から、壺屋焼を探す作業は大変な労力と時間、それに幸運(偶然)を必要とした」。その理由の一つは「近世陶磁器研究の主流は産地が著名で文様による判定が容易な」「磁器」類であり、もう一つは「大型でかつ素焼・無文のため産地判定などの難しい」「陶器・瓦器」類は「あまり注目されることもなく収納されてしまうことが多かった」からである。
いわゆる「壺屋焼」は、地元の言葉で「ジョーヤチ(上焼)」と「アラヤチ(荒焼)」に大別される。前者は釉薬を施した陶器類で、後者が「無釉焼締」の陶器類を指す。前者には碗や皿、土瓶などの日常食器類が多く、後者は壺や甕などの貯蔵用具・酒器などが多くつくられた。近年観光土産品店にならぶのはジョーヤチで、アラヤチ製品はほとんど見られない。著者らのこの間の調査研究によって、「アラヤチ」を中心とする「壺屋焼」が出土した(本土の)遺跡は東京都内で23箇所、他に京都・堺・金沢・博多湾・長崎などで7箇所、鹿児島県内で40箇所を超えるという。
出土した「壺屋焼」の器種は、「ウニヌティー」と呼ばれるアラヤチの徳利とアラヤチの「カーミ(甕)」に大別される。だとして、これらはどのような用途を伴って「本土」に運ばれたのだろうか。結論から言えば、泡盛の容器としてである。そこで著者の関心はその経路と経緯に広がって行く。ここからは通常の考古学的手法を越えて、歴史学的方法すなわち文献渉猟の旅と、民俗学的手法すなわちフィールドワークの旅に移る。文献探索の旅程は、近世にあっては琉球王府による「江戸上り」の旅に焦点が当てられる。王府派遣の一行は旅宿の大名や将軍に泡盛その他を献上ないし進呈したが、泡盛の容器がアラヤチ陶器である。その物証が発掘調査で確認されたのである。著者のフィールドワークは、近代においては糸満漁民や移民の足跡を追ってマリアナ諸島にまで及ぶ。
これらの行路は、「黒潮圏の壺屋焼」を追い、「泡盛の道」をたどる追跡=研究の道筋と言い換えることもできよう。モノの移動を追う旅は同時に、そのモノを運んだヒトの軌跡を訪ね、関連する情報を収集する旅でもある。
一連の記述は冒頭の表現を使えば、ノンフィクション作品を読むときにも似たときめきをおぼえさせる。その根拠は、繰り返すことになるが何よりも科学的=実証的=資(史)料的な裏打ちが施された説得的な記述にある。壺屋焼の記述にしても、アラヤチに限定しない。専門の考古学的検証と研究史を踏まえた上で、沖縄における土器=焼物の出現から始まる一連の「沖縄のやきもの史」の中で「壺屋焼」を正統=正当に位置づけようとするスタンスや、いわゆる大交易時代に始まるとされる泡盛のルーツとその後の「泡盛(焼酎)の道」全行程を「黒潮圏」全体を視野に入れながら記述しようとする著者のスタンス=方法が、読者の信頼感を高めるのである。「部分」をたえず「全体」の中で捉えなおそうという視角である。
「大変な労力と時間」を割きながら辛抱強く続けてきた調査研究の道筋を支えてきたのは、旅程の長さと広さをものともせず渉猟する著者の熱意、換言すれば考古学者としてのモノとその軌跡へのこだわりであったのは十分にうかがえる。また、著者がいうように、その「発見の旅」は運に恵まれていたという側面もあるだろう。しかし、度重なる「偶然」の積み重ねがこの著作を生む幸運=必然に転化したということも、確かであると思われる。( 2008/11/04 21:05)(2535字)
「物語」の発端は1972年、東京都教育委員会が無人となった小笠原諸島で実施した遺跡分布調査である。大学で考古学を専攻した著者は、この年同教育委員会に採用されたばかりであった。この調査で産地不明・由来不明の「無釉焼締陶器」(大甕)類が発見された。この陶器類は、引き続き調査が行われた伊豆大島の八丈島でも大量に発見された。島では「南蛮カメ」と呼ばれ、「島焼酎」や水貯蔵として多用されたという。
この陶器類は、当時産地不明として調査報告書にも記載されないままに推移したが、1991~1993年の東京都港区汐留遺跡(仙台藩伊達家上屋敷跡)から発掘された「無釉焼締徳利」の調査・分析結果から、いずれも那覇市壺屋で焼かれた「壺屋焼」であることが判明した。小笠原での発見から20年が経過したことになる。言い換えれば著者は、20年間この陶器の出所と来歴を尋ね歩いてきたということだ。本書の出だしは、その旅程を「考古学的」に縷々述べることから始まる。
どの「科学」も特定の対象と特定の方法を持っている。考古学の場合、まずは「発掘」という方法がある。対象はモノ。出土したモノ=物的資料の比較・分析・分類が行われる。そのための指針は、それまでに発掘された同類の資料の分布と編年である。問題は出土した資料が、ラベル名がはっきりした「引き出し」に入れられない「新発見」の場合だ。この発見が従来の研究に新たな一ページを加えるか、あるいは従来の説を覆すかする可能性を予期させる場合は研究者の注目を集めるが、そうでないと判断された場合は「その他」のラベルがついた引き出しに収められ、眠って(眠らされて)しまう。
本書が対象とする「無釉焼締」の陶器とは、結論から言えば「壺屋焼」のそれである。したがって著者は、長年引き出しの中で「無視」されてきた「その他」の陶磁器類を比較=分析することによってその中から一つの共通項を見つけ出し、「壺屋焼」というもう一つの引き出しを作り上げることに成功したのである。この方法を「科学的=学問的」と言わずして何と言おうか。
この種の調査研究=作業がどれだけの労苦を求めるものか。著者は述懐している。「(本土の)近世遺跡から発掘される膨大な陶磁器類の中から、壺屋焼を探す作業は大変な労力と時間、それに幸運(偶然)を必要とした」。その理由の一つは「近世陶磁器研究の主流は産地が著名で文様による判定が容易な」「磁器」類であり、もう一つは「大型でかつ素焼・無文のため産地判定などの難しい」「陶器・瓦器」類は「あまり注目されることもなく収納されてしまうことが多かった」からである。
いわゆる「壺屋焼」は、地元の言葉で「ジョーヤチ(上焼)」と「アラヤチ(荒焼)」に大別される。前者は釉薬を施した陶器類で、後者が「無釉焼締」の陶器類を指す。前者には碗や皿、土瓶などの日常食器類が多く、後者は壺や甕などの貯蔵用具・酒器などが多くつくられた。近年観光土産品店にならぶのはジョーヤチで、アラヤチ製品はほとんど見られない。著者らのこの間の調査研究によって、「アラヤチ」を中心とする「壺屋焼」が出土した(本土の)遺跡は東京都内で23箇所、他に京都・堺・金沢・博多湾・長崎などで7箇所、鹿児島県内で40箇所を超えるという。
出土した「壺屋焼」の器種は、「ウニヌティー」と呼ばれるアラヤチの徳利とアラヤチの「カーミ(甕)」に大別される。だとして、これらはどのような用途を伴って「本土」に運ばれたのだろうか。結論から言えば、泡盛の容器としてである。そこで著者の関心はその経路と経緯に広がって行く。ここからは通常の考古学的手法を越えて、歴史学的方法すなわち文献渉猟の旅と、民俗学的手法すなわちフィールドワークの旅に移る。文献探索の旅程は、近世にあっては琉球王府による「江戸上り」の旅に焦点が当てられる。王府派遣の一行は旅宿の大名や将軍に泡盛その他を献上ないし進呈したが、泡盛の容器がアラヤチ陶器である。その物証が発掘調査で確認されたのである。著者のフィールドワークは、近代においては糸満漁民や移民の足跡を追ってマリアナ諸島にまで及ぶ。
これらの行路は、「黒潮圏の壺屋焼」を追い、「泡盛の道」をたどる追跡=研究の道筋と言い換えることもできよう。モノの移動を追う旅は同時に、そのモノを運んだヒトの軌跡を訪ね、関連する情報を収集する旅でもある。
一連の記述は冒頭の表現を使えば、ノンフィクション作品を読むときにも似たときめきをおぼえさせる。その根拠は、繰り返すことになるが何よりも科学的=実証的=資(史)料的な裏打ちが施された説得的な記述にある。壺屋焼の記述にしても、アラヤチに限定しない。専門の考古学的検証と研究史を踏まえた上で、沖縄における土器=焼物の出現から始まる一連の「沖縄のやきもの史」の中で「壺屋焼」を正統=正当に位置づけようとするスタンスや、いわゆる大交易時代に始まるとされる泡盛のルーツとその後の「泡盛(焼酎)の道」全行程を「黒潮圏」全体を視野に入れながら記述しようとする著者のスタンス=方法が、読者の信頼感を高めるのである。「部分」をたえず「全体」の中で捉えなおそうという視角である。
「大変な労力と時間」を割きながら辛抱強く続けてきた調査研究の道筋を支えてきたのは、旅程の長さと広さをものともせず渉猟する著者の熱意、換言すれば考古学者としてのモノとその軌跡へのこだわりであったのは十分にうかがえる。また、著者がいうように、その「発見の旅」は運に恵まれていたという側面もあるだろう。しかし、度重なる「偶然」の積み重ねがこの著作を生む幸運=必然に転化したということも、確かであると思われる。( 2008/11/04 21:05)(2535字)