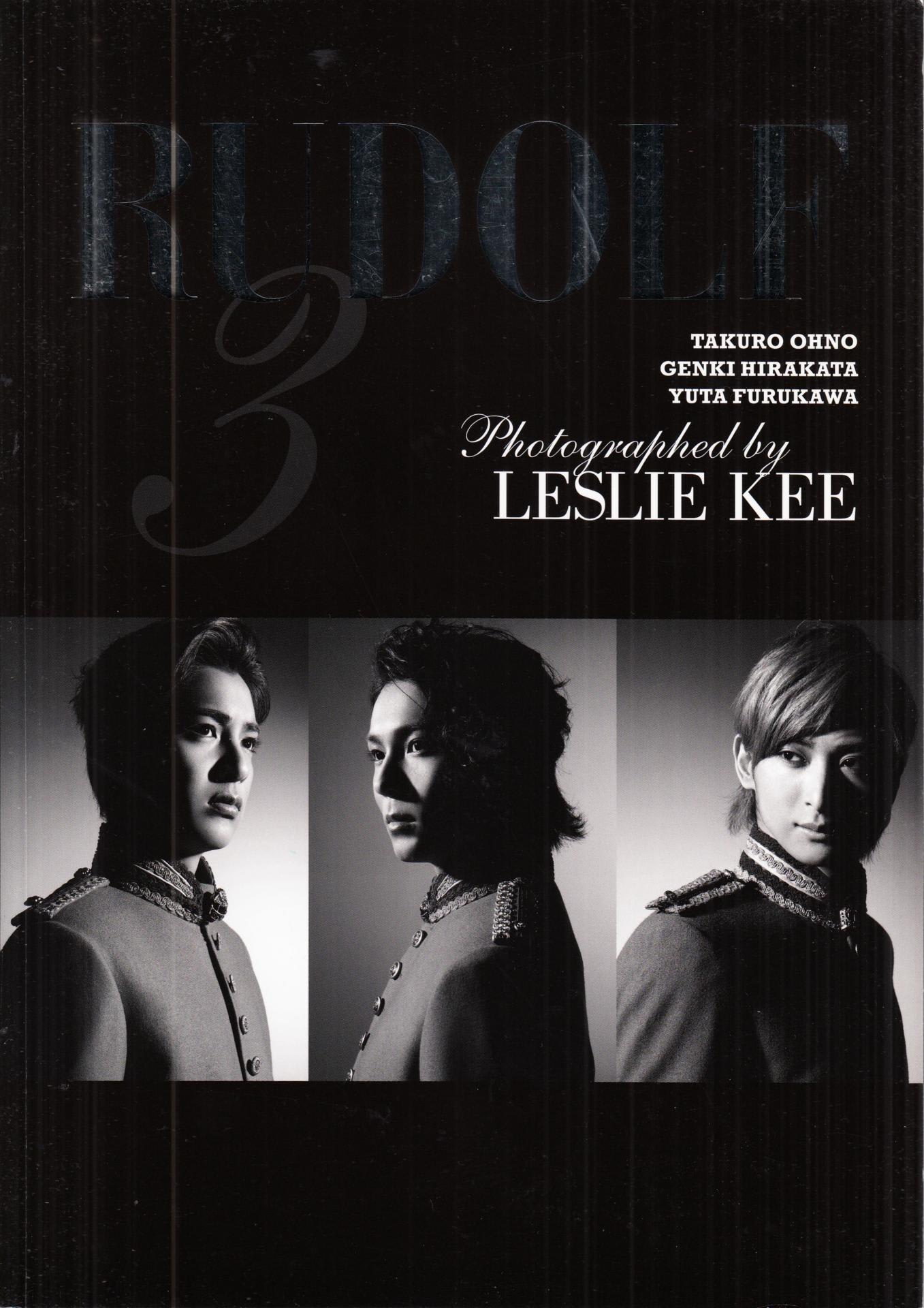
2000年東宝『エリザベート』プログラムより、
「=ハプスブルク家と皇妃エリザベート-東洋英和女学院大学長塚本哲也=
歴史上、古今東西を通じてもっとも美しい女性はエジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃ということになっている。最近ではハプスブルク帝国の皇妃エリザベートがこれに加わった。クレオパトラも楊貴妃も伝説の美女で、その美しさは確かめようもないが、エリザベートには写真も肖像画も残っており、まごうかたなき美しい女性であることは、伝説ではなく、誰しも認めることであろう。
それは19世紀の有名なドイツ人宮廷画家ヴィンターハルターが描いた、若き日の皇妃エリザベートの全身像の絵が物語って余りある。40年近く前、ウィーンの王宮ではじめて見たこの大きなエリザベートの肖像画は美しさの極致で、これほど美しい女性がいるのかと圧倒され、深い感動を覚えた。エーデルワイスの花と星の形のダイヤモンドをちりばめた腰まで届く長い栗色の髪、同じような星型の刺繍のある白い豪華なドレスに身を包んだ皇妃エリザベートの美しさは、典雅、気品、端麗、威厳、魅惑、孤高、静寂、ロマンティシズム、いかなる言葉を並べても表現できない存在感と迫力をもって、見るものを金しばりにする。それはこの世のものとも思われぬ、妖精のような幻想的な魅力をたたえている絵であった。
彼女は中部ヨーロッパに広大な領土を持ち六百数十年もの長い間君臨してきたハプスブルク帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフの皇妃で、その優雅な気品ある姿は、いかにも王朝にふさわしい象徴のように思われがちだが、実際は儀礼づくめで堅苦しいウィーンの宮廷生活を嫌い、地中海やアドリア海、イオニア海などを旅から旅へと渡り歩く「さすらい人」だった。宮廷の公務をおざなりにし、宮廷の生活を嫌ったのは、孤独を愛する彼女の性格なのだが、それは生まれ育った環境からきていた。
エリザベートは1837年12月24日クリスマス・イヴにミュンヘンで生まれた。南ドイツ一帯を支配してきたヴィッテルスバッハ家のバイエルン王国の王族の一人であった。父親のマクシミリアン侯爵は王族としての儀礼的な生活を嫌い、南ドイツの山の中に別荘をつくり、ここでえ狩猟や乗馬、釣り、山歩きを好み、同時に作曲や詩作に耽けり、イタリアなど地中海地域を旅行して歩く自由な芸術家気質の貴族であった。うわべだけの社交界や俗っぽい権力、政治外交から遠ざかり、広大な庭園に動物園のように多くの動物を飼い、家族と共に花咲き乱れる大自然の中で人生を楽しんだ。別荘といっても小さな山小屋ではなく、大きな居城といった方がふさわしい。近くに青い澄んだ湖があり、アルプスの峰々が見える。映画の「サウンド・オブ・ミュージック」のような雄大な大自然の中で、エリザベートは育った。
兄弟姉妹6人の中で父親の性格をもっとも強く受け継いだのがエリザベートで、子供の時の愛称はシシィといい、父親にもっとも可愛がられた。彼女はいつも泥んこになって野山を飛び歩き、特に乗馬が好きでうまく乗りこなし、一方文学少女で小説を読み、詩作に耽り、メルヘンの世界をただよう夢見がちな野生の少女に成長していった。
父親のマクシミリアン公爵は南ドイツの村祭りや年の瀬の市に、変装して農民風の服装でチターを片手に、お忍びで街頭や酒場を流して歩くのが大好きだった。父親がチターを弾くかたわらで、シシィがお下げの髪を振りながらミュンヘンの民族衣装にエプロンを拡げ、農民が投げてくれる銅貨を受け取って、お礼にぴょこんとお辞儀をした。農民たちは公爵親子だと知りながら、知らんぷりしてたが、内心は「風変わりな型破りの王族だ」と思っていた。エリザベートはこの時もらった銅貨の一つを、少女時代の思い出として皇妃になっても持ちつづけ、女官や侍女たちに「かつて私が正当に働いて稼いだただ一つのお金よ」といって驚かせた。こんな破天荒な経験を持った皇妃はまずいないだろう。
こんな型破りの野生の公爵令嬢だから、自ら進んで皇妃になったわけではなかった。三歳年上の姉ヘレーネがオーストリア帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフとお見合いする時、相手側が一家そろって大勢でやってくるというので、母親がこちらも少し出席者を増やさなければと思い、たまたま付き添いにシシィを連れていっただけのことだった。姉ヘレーネはしつけのよい礼儀作法も心得た女性だったが、皇帝の方は本命でない妹のシシィの方を気にいってしまったのである。彼女にはそれまで皇帝が見たこともない野生的な魅力があったからだが、それでいて犯しがたい気品と神々しい美しさがあった。皇帝の結婚申し入れに対し、シシィはいやだといって泣きじゃくったが、母親と育ての乳母から「断ることはできない」と恫喝されて、何が何だか分からないうちに承諾せざるをえず、彼女の運命は決まった。母親が姉妹同士だったから、二十二歳の皇帝と十六歳の皇妃は従兄妹同士の結婚だったのである。
しかしこの結婚は必ずしも幸福ではなかった。お互いに愛し合ってはいたが、きびしい礼儀作法づくめの宮廷生活は、自由にのびのびと暮らしてきた若き乙女にとって拷問にひとしかった。皇妃としての威厳を保つために、面倒で複雑な宮廷儀礼を仕込んでやろうと待ちかまえていた皇帝の母ゾフィー大公妃とそりが合わず、シシィは心身のバランスを失い、神経もずたずたに引き裂かれていった。彼女にとtって宮廷生活は牢獄であった。まだフロイトの精神分析学が確立される前であったが、恐らく極度の鬱病に陥ったのだろう。野生動物が檻に入れられ、行動の自由を失ってもがき苦しむように、彼女は世紀を失った病人のようになってしまったのである。この当時の写真を見ると、暗い病的な表情をしている。
医者から転地療養をすすめられたエリザベートは、これを口実に息苦しい宮廷から逃亡しようと決心し、自ら保養先をなんとマデイラ島に選んだのである。マデイラ島は大西洋の孤島で、リスボンから1200キロ、アフリカ大陸から500キロも離れているポルトガル領の島で、当時はヨーロッパから見るともっとも遠い最果ての地であった。それほど遠い離れ孤島に行ったのは、ウィーン宮廷への嫌悪だけでなく、永遠なるものへの憧れも重なっていた。遠くへ行きたいというのは、夢見がちな彼女の根源的な願望で、それは心の奥底で永遠なるものとつながっていた。
マデイラ島は花咲き鳥歌う、陽光に満ちた楽園であった。身も心も生き返ったエリザベートは、スペイン各地や地中海の島々を渡り歩き、帰国したのは半年後だった。しかしウィーンに戻ると条件反射のようにたちまち調子が狂い出し、またウィーンを離れたいという衝動にかられ、旅から旅へと放浪を続ける渡り鳥のような生涯が始まる。
はじめは宮廷生活への反逆と絶望からの旅だったが、さすらうことによって彼女の魂は甦り、さすらいの旅は彼女の安らぎと心の再生のためのものとなった。彼女は公務を平然と拒絶し、自らの孤独な世界に閉じこもった。野性的でありながら内面的かつロマンティックな性格で、自ら詩をつくっていたが、彼女は非難や批判を承知しながらも、さすらいの旅をやめることがなkった。自らの自由と孤高を保つためには、王室の権威させも無視する勇気があった。
彼女は皇妃というよりは芸術家気質の女性で、19世紀後半ヨーロッパで女性解放の象徴ともなったノラの先駆者でもあった。ノラは1878年に初演されたノルウェイの作家イプセンの戯曲「人形の家」の主人公で、女性の人格を認めない因習にとらわれた封建的な社会に反抗し、夫と子供を置いたまま家出する女性解放を象徴するヒロインであった。「人形の家」の主人公ノラの名前は世界中に広まったが、シシィはその10年前に、一人で宮廷革命ともいうべきノラの先駆者となっていた。宮廷への反逆は大変勇気のある大胆な行為であった。
エリザベートが皇妃の地位に何の執着も未練もなかったことは、末娘に言った言葉でよく分る。
「あなたは煙突掃除人夫と結婚してもいいのですよ。結婚とは不合理な制度です。十五歳で結婚が決まり、何やらわけのわからない誓いを交わし、30年あるいはそれ以上たって後悔しても、もうどうにもならないのです。」
皇帝と結婚したことを後悔している彼女の本心がよく出ている。ただ皇帝を毛嫌いしているのではなかった。儀礼にがんじがらめの形式的な宮廷生活がいやであり、耐えられなかったのである。皇帝から結婚を申し込まれたとき、彼女は、「あの方が皇帝でなければよかったのに。仕立て屋さんでも何でもほかの仕事なら・・・」と言ったのは、生涯変わらなかった彼女の考えだった。
そんな彼女の拠り所は自分の美しさであった。自分だけが頼りであり、自ら頼りになるのは美しさであった。もともとスタイルがよく美しかった彼女は、その美しさを保つことにあらゆる努力を惜しまなかった。特に彼女の長い髪の美しさはたとえようもなく、くるぶしまである長い房々とした毛の手入れと洗髪に毎日2時間、3時間もかけ、自ら「私は髪の奴隷よ」と周囲に漏らしていた。
またスタイルをよくするために、当時まだあまり普及していなかったダイエットを自ら実行するだけでなく、スポーツ、特に競歩と体操と乗馬に打ち込んだ。宮廷内に体操道具を設置し、競歩も暑い夏の日に20キロ、30キロとスピードをあげて歩き回り、女官はとてもついていけなかった。乗馬も安全第一というおっとりした軽い趣味のものではなく、野や林を全力をあげて疾走する競馬のように激しいもので、まかりまちがえば命を落としかねないような激しさであった。彼女は何か内部から噴き上げてくる火山のような衝動にかられているようだだった。その内なる激しさは何だったのだろうか。美しさを保つだけではなく、永遠への激しい憧れがいつも湧き出ていた。それは死へのいざないにうながされていたようであるといえよう。彼女の詩集がそれを物語っている。
エリザベートは古代ギリシアの時代と文化に憧れ、ギリシャ語を学び、イオニア海の島に別荘をつくり、海を見遥るかす庭園にはギリシャ神話のアキレウスの像を置いていた。地中海やエーゲ海、イオニア海をヨットで航行し、沿岸の地をふらりとお忍びでふらつくのが好きであった。船の上からはいつも果てしなく青い海の地平線を一人でじっといつまでも見つめていた。
旅から旅へとさすらい、ウィーンの王宮に寄りつかない皇妃の不在は、子供たち、特に長男のルドルフには深い精神的な傷を与える結果になってしまった。ルドルフは母親に似て、感受性が鋭く、頭の回転の早い知的な青年に育っていたが、母親の愛情に餓えている孤独な青年だった。いつの間にか、父親の皇帝と政治外交問題で対立が深まり、父と子の相克は次第に抜き差しならないものになっていった。ベルギー王室から嫁いできた皇太子妃との関係もうまくいかず、二人の関係は冷え切ったものになり、たった一人の息子で、ハプスブルク帝国の後継者であるルドルフ皇太子が心身ともに疲れ果て追いつめられていることに、エリザベートは気づかなかった。
1888年のクリスマスの夜、さすらいの翼を休めにウィーンの王宮に戻った時、30歳にもなる大の男のルドルフ皇太子が突然、母親であるエリザベートに抱きつき、大声をあげて泣き出した。あまりにも激しく、しかもいつまでも泣き止まないので、周囲の人々は感動し、もらい泣きした。
エリザベートも思わず涙ぐんだ。それが永遠の別れの涙であることはそのとき誰も分からなかった。
明けて1889年1月末、皇太子ルドルフが若い未婚の18歳の男爵令嬢と心中し、命を絶ったという凶報がエリザベートを襲う。エリザベートは激しい衝撃と後悔の中で、はじめてルドルフ皇太子の心中を察したが、後の祭りだった。皇帝の配慮で彼女はルドルフの葬儀には出席しなかったが、深夜ルドルフ葬られたばかりのハプスブルク代々の人々が眠る霊廟を訪れ、暗闇の中にろうそくを灯し「ルドルフ、ルドルフ」と叫ぶエリザベートの声が暗い地下の墓所にこだまする光景は鬼気迫るものがあったと、霊廟の修道僧は書き残している。
旅に明け暮れて一人息子の身近にいることができなかったエリザベートは深い後悔に苛まれたが、ルドルフ亡き後、彼女の魂にはどうにも埋めようもない孤独感と絶望感が深まり、この苦悩を断つためにさらに強く死を望むようになった。こうして彼女のさすらいの旅への衝動はさらに激しさを増していった。居ても立ってもいられなくなったのである。アフリカやイタリア、ギリシャに上陸すると、焼けつくような熱い太陽の照りつける血を素足で何時間もぶっつづけに歩きつづけた。死に向かっての自虐的な逃避行であった。
息子ルドルフの死の後、彼女は公式行事にさえも黒の喪服で出席した。「ルドルフの死は私の信仰を打ち砕きました。これからまだ長い年月、生きつづけるなんて、気が狂いそうです」と、末娘につぶやくような悲しみと無力感、自己嫌悪の中で、彼女はいつも死を身近に感じていた。死神が訪れることを彼女は絶えず待ち望んでいた。死こそ安らぎの時であった。
安らぎの時は思いがけなく、ある晴れた日に訪れてきた。
1898年9月10日のさわやかな秋の日の午後1時40分、スイス、ジュネーブのレマン湖で蒸気船に乗ろうとした時に、突然傍観に襲われ、心臓を一突きに刺され、67歳の生涯を閉じた。犯人は25歳の無政府主義者のイタリア人、ルイジ・ルケーニだった。「高位高官の人物だったら、誰でもよかった」とうそぶいていた。あまりにも突然のドラマティックな死で、まるで死神がつかわした宿命の死者のように思われた。彼女は高位高官の人であったが、テロリストの対象になるような暴君ではなかった。むしろ宮廷の封建制に反旗を翻し、デモクラティックでリベラルな皇妃であった。
19世紀末のこの時代、ハプスブルク王朝のオーストリア・ハンガリー二重帝国は世紀末の文化が花開いていた。当時多民族国家のハプスブルク帝国は政治的には斜陽落日の一途をたどっていた。支配下にあった北イタリアとの戦いに破れ、イタリアは独立、北方の雄プロイセンとの戦いにも大敗して圧倒され、きびしい試練にさらされていたが、文化的には音楽、絵画、文学、建築、都市計画、法学、経済学、医学と多方面の分野に天才たちが輩出し、アルプス山脈のような蛾々たる多様な高度の文化を築き上げていた。
エリザベートの美しく典雅な気品ある姿はこの絢爛たる王朝文化の象徴のようであったが、その死の20年後の1918年、第一次大戦の終結とともに、700年近く中欧に君臨してきたハプスブルク帝国は崩壊した。彼女の死はその弔鐘であった。
1953年にできた米国映画『ローマの休日』のオードリー・ヘップバーン演ずる王女は何となくエリザベートを思い出させる。すらりとしていて上品で美しく、自由になって一人ローマの街を遊ぶが、最後は王家の「籠の鳥」になっていくヒロインの哀愁と悲しみをたたえた瞳は、エリザベートの人生そのものだった。エリザベートが死後百年以上たって今なお世界中で語られるのは、50年近く前の『ローマの休日』が主演女優亡きあとも世界中から親しまれているのと同じように、美しさとロマンティシズムと哀愁を帯びたドラマティックな人生だったからだろう。
暗殺者のルイジ・ルケーニは犯行後も悪びれることなく、昂然としていたが、1910年牢獄で自殺した。すでに20世紀になっていたが、1917年にはロシア革命が起り、ロマノフ王朝一家は惨殺され、滅亡し、同時にハプスブルク王朝も700年近い栄華の後に、地上から消えた。20世紀は血なまぐさい階級闘争の時代に突入していった。そのあとにスターリン、ヒトラーが続く。
こうして見ると、エリザベートの暗殺は20世紀の荒々しい時代の予兆ともいうことができよう。エリザベートに突然訪れた暗殺というドラマはあまりにもドラマティックで、なにか歴史の運命の力だったようにも思える。」

















