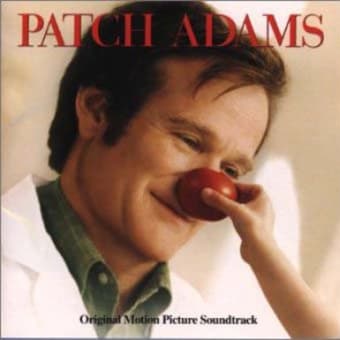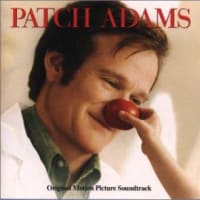●『旧約聖書』の「創世記」第9章24節から27節に、大洪水を無事に乗り越えたノアが、ブドウ畑を作って収穫したブドウ酒に酔いつぶれ、丸裸で寝ている情景が出てきます。
そして、それを見たノアの3人の息子のうち、セムとヤペテは父親の裸を見ないようにしてそっと着物をかけてやるのですが、そうしなかったハムにノアは目が覚めてから激怒し、まだ誕生していないハムの子のカナンに対して「カナンは呪われよ! カナンは兄弟たち(セムとヤペテのこと)の奴隷のそのまた奴隷となれ!」と言いました。
●これは「創世記」、いや聖書全体を通じて、最も深い謎に包まれている一節といえましょう。なぜ、ノアは彼の孫のカナンに、これほどの怒りをぶつけなければならなかったのでしょうか。合理的な説明は、聖書では与えられていません。
で、カナン族にかけられた呪聿は、彼らの住んだ土地カナンにも浸透したわけですが、このカナンの土地が今のパレスチナ地方であります。この地とカナンの末縺は、人類全体に対する最大の呪いとなり、今に及んでいるという見方もあります。(ヘブライの館より)
五千年来、人類は「カナンの呪い」にたたられてきたとマリンズはいう。『旧約聖書』「創世記」の中に、かなりよく知られている次の場面がある。ノアが酒に酔いつぶれて裸で寝込んでしまった。ノアに3人の息子(セム、ハム、ヤペテ)があり、ハムの息子がカナンである。そのカナンが、ノアの裸を見た。目が覚めたあとノアは、カナンに激怒し、「カナンは呪われよ。汝は、奴隷として仕えよ」と叫んだとある(文中より)。
衝撃のユダヤ5000年の秘密
ユダヤはなぜ文明に寄生し破壊させたか?
ユースタス・マリンズ・著 太田龍・解説 日本文芸社 1995年刊
序文 ● 日本の読者の皆さまへ
本書が日本の皆さまに読まれることは、私の名誉であります。大日本帝国が第二次世界大戦へと巻きこまれていく背後にあった事実を、日本民族は本書ではじめて発見することになるでしょう。
フランクリン・デラノ・ルーズヴェルト政権は、貿易等の経済制裁をもちいた日本に対する一連の挑発行為を通して、むりやり日本に太平洋地域のアメリカ保有財産を攻撃させようと謀りました。ルーズヴェルトが日本軍の暗号を解読ずみであったため、ホワイトハウスには敵対行為がいよいよ勃発するのに先立って日本側の交信をすべて秘密裡に明かされていました。
1941年12月6日夜、サンヘドリン、すなわちユダヤ最高法院のホワイトハウス駐在員バーナード・バルークは、合衆国陸軍参謀総長ジョージ・C・マーシャル将軍およびルーズヴェルト大統領と同席していました。何時間か経つうちに、3人はパニックにおちいりました。暗号解読された通信によって、日本の作戦部隊がパールハーバーに接近中であることが判明しましたが、同時に、攻撃前にアメリカ側に探知されたら攻撃を中止して日本に引き返せとの厳しい命令を、日本側の作戦司令官は受けていたからです。
日本軍は果たして攻撃するであろうか? もし日本軍の暗号電文がホワイトハウスによって解読追跡されていることが知れたら、攻撃は取り止めになり、日本と合衆国を第二次世界大戦へ巻きこむという世界ユダヤの計画は水泡に帰すことになります。しかし日本軍は、監視下に置かれていることに気づくことなく、全力でハワイに向かって近づき、攻撃を開始しました。
ルーズヴェルト、バルーク、マーシャルは、近づきつつある攻撃に関するすべての情報を米国太平洋方面軍指揮官に洩れないよう入念な措置を講じました。
はっきりしていることは、もし彼らがパールルハーバーの艦隊に警告を発していたら、日本は攻撃しなかったということです。沈黙をつづけることにより、ルーズヴェルトは日本のパールハーバー攻撃を奨励したのです。そしてこのことが、大統領自身の国の何千人という若い兵士船員たちが警告も受けず死んでゆく運命を決したのです。まさにレオン・トロツキーが口ぐせにしていたとおり、「卵を2、3個割らなければ、オムレツはつくれない」であったのです。
それからなんとルーズヴェルトは、パールハーバーの司令官だったキンメルとショートとを、攻撃に対する準備ができていなかったという「重過失」の嫌疑で軍法会議にかけたのです。後日、キンメルの息子は、任期切れ寸前のジョージ・ブッシュ大統領に父親の特赦を嘆願しました。ブッシュは、「私には歴史を書き換えることはできかねる」といって、そっけなく断わりました。
戦後、ダダラス・マッカーサー将軍が日本占領連合軍最高司令官となったとき、新たな経済の絶対支配者としてウィリアム・ドレイパー将軍を帯同しました。ドレイパーはウォール街の銀行ディロン・リード社の共同経営者であり、同社は1924年に1億2000万ドルの債券を発行することによりドイツを再軍備へと踏みださせ、第2次世界大戦への道を避けられないものとしました。
紳士達の終わりなき夜の夢
Dillon,Read &co
ドレイパーの会社ディロン・リードを率いていたのはクラレンス・ラポウスキーでしたが、彼は自分の名前をディロンと改名したのです。ディロンはテキサスのユダヤ入で、その息子C・ダグラス・ディロンはケネディ大統領の財務長官となりました。C・ダグラス・ディロンの娘は結婚してヨーロッパの貴族となっています。第2次世界大戦後、ドレイパー将軍の指揮のもとで日本経済は、ドレイパーのほんとうの主人ロスチャイルド家が策定した路線に沿って再編されました。
当時、イギリスのジャーナリストのコンプトン・ペイカナムは「ニューズ・ウィーク」誌の通信員をしていました。ペイカナムはまた天皇ヒロヒトの親友の一人でもありました。私はペイカナムを訪ねたことがあります。彼が私に語ってくれたのは、天皇はユダヤ陰謀家たちの悪辣さを絶対に理解できない、なぜなら天皇は即位以来まったく信義というものをもたない人間と接触したことが一度もないからだ、ということでした。
日本民族は、ユダヤ人のもつ血への欲望のゆえに、第2次世界大戦中、信じがたいほどの残虐非道すなわち東京大規模爆撃、広島・長崎への原爆攻撃などを耐え忍びました。これら大量殺人は軍事的にはなんらの影響をともなわず、ただただ、あらゆる歴史においてもっともおぞましい大量虐殺にすぎなかったのです。日本がユダヤによって原子爆弾の標的として選ばれたのは、原子爆弾のユダヤ人開発者らがユダヤの地獄爆弾を非白人系の民族にテストしてみたかったからにほかなりません。
ハリー・トルーマン大統領は原爆の使用については疑念を抱いていたのですが、サンヘドリンのもっとも邪悪な使用人の一人ジェームス・ブライアント・コーナントが原爆の使用を熱心に説き、とうとう説得させられてしまいました。コーナントはハーバード大学総長になった化学者ですが、ウィンストン・チャーチルに依託されて、ドイツに対して使用するための炭疸(たんそ)爆弾を開発しました。
この爆弾は、ドイツに生存するすべての生物を殺戮し、長期間にわたってそこには誰も住むことができないようにするはずでした。しかしコーナントが開発したときには、すでにドイツに使用する時期を失していました。彼は炭疸爆弾を日本に使用するよう求めたのですが、ユダヤ陰謀家たちは日本民族に対して彼らの地獄爆弾をテストすることを決めたのです。
私は公式の法廷記録のなかで、ジェームス・ブライアント・コーナントこそが「第2次世界大戦の最大の戦争犯罪人」であると繰り返し述べてきました。彼はのちに敗戦国ドイツの高等弁務官となり、1955年にドイツ語に翻訳された連邦準備制度の歴史に関する私の著作の焚書を命じました。彼の補佐官はベンジャミン・ブッテンワイザーで、西半球におけるロスチャイルド権益の秘密アメリカ代理人であるニューヨークのクーン-ロエブ商会の共同経営者でした。ブッテンワイザーの妻、レーマン銀行一族のヘレン・レーマンは、アルジャー・ヒスの名高いスパイ事件の裁判で弁護人でした。ブッテンワイザーは、アルジャー・ヒスが刑務所に収監されていた期間、ヒスの息子のトニーを100万ドル相当のマンハッタンの邸宅で養育しました。
この情報をお伝えすることによって日本の皆さまが、ユダヤが日本民族に対して負わせてきた極悪陰険な国際的勢力についてのよりよき理解を得る一助にされることを私は心から希望します。
1994年11月25日
ユースタス・マリンズ
◎衝撃のユダヤ5000年の秘密/目次 (第1章のみ全文掲載)
第 1 章 ◎ ユダヤはなぜ文明に寄生したか?
第 2 章 ◎ 特異な生物学的特性をもつユダヤ
第 3 章 ◎ 誰も明かさなかったユダヤ民族の起源
第 4 章 ◎ 古代四大帝国を崩壊させたユダヤ
第 5 章 ◎ ユダヤの正体を見破ったイエス・キリスト
第 6 章 ◎ ユダヤの恐るべき宗教儀式の秘密
第 7 章 ◎ ヨーロッパを乗っ取ったユダヤ
第 8 章 ◎ 共産主義はユダヤ・タルムードの所産
第 9 章 ◎ ユダヤに完全支配されたアメリカ合衆国
第10章 ◎ ユダヤの地球支配最終戦略
第1章 ◎ ユダヤはなぜ文明に寄生したか?
つねに激しい敵意を引き起こす唯一の民族
文明の歴史のあらゆる時期を通して、人類のある特殊な問題が一貫してわだかまりつづけてきた。平和と戦争、また戦争の風聞の膨大な記録を調べると、帝国が次々に誕生するごとにおなじ窮地に追いこまれてきたことがわかる――それはユダヤ人の問題である。
この問題は執拗に持続しているにもかかわらず、また、これを主題にあつかった文献が山とあるにもかかわらず、賛否を問わず誰ひとりとして、その窮地の根源にまで踏みこんで対決した者はいなかった。すなわち、ユダヤ人とは何者か、彼らはどうしてこの世に存在するのか? という根源的な問いがなおざりにされたのである。
もし人間が全知を傾けてあたりさえすれば、この問いに答えることができる。
この問題には、キリストの愛というもっとも深い動機、なかんずく人間とはなにか、人間はなにに根ざしているか、あるいは人間はなにを目指しているのかという、人間自身に対する最大の敬意を払いつつ、最高の霊的な水準において立ち向かわなければならない。
人間の歴史は、もてる者ともたざる者との闘争と戦争、人間による人間の搾取、そして殺戮の歴史である。しかしながら、血ぬられた記録を調べると、どの地に居住しようとも、もっとも激しい敵意をつねに引き起こしつづけてきた民族がただ一つだけあることがわかる。
ただ一つの民族のみが、文明社会のあらゆる部分に寄生しては徹底的に宿主の国民をいらだたせ、ついには宿主が彼らと対立し、彼らを殺し、あるいは放逐するまでにいたることになる。
この民族を、人はユダヤ人と呼ぶ。この問題は、ユダヤ人以外でも、集団同士の対立抗争が1国にとどまらず起こるため、誤解されてきた。
トルコ人によるギリシャ人の大量殺害は、何千年にもわたって散発的に発生し、たかだか一世代前にもそのような事件が起こって、今日生存している人びとにも影響を及ぼしている。
数百年前にフランスで起こったユグノー派の大量殺害(1562年~1592年にフランスでカルビン派キリスト教徒ユグノー派とカトリック教徒とのあいだに宗教戦争が発生、大量のユグノー派が殺された)は、おなじ人種であっても、宗教上の違いから互いに対立し合い、異なる人種間の対立に劣らぬほどの、血で血を洗う抗争に発展しうることを示した。
しかしながら、これらの殺戮ののちには、対立した集団はふたたび平静な生活の営みにもどるのが常であった。対立が解消されるか、あるいは犠牲者の生き残りがどこかよそへ去るかしたものである。ユグノー派の例では、難民たちのなかからのちにアメリカ独立戦争を指導する思想家たちが数多く生まれることになった。
2000年以上にわたって存在しつづけてきた「ユダヤ問題」
和解も他の国への永住も絶対にしない例が1つだけある。
ユダヤ人の歴史は、そうした2つの事実を示している。
第1に、ユダヤ人と寄生先の宿主とのあいだに和解がもたらされたことはいまだかつてなかった。
第2に、いかなる国家もユダヤ人の永久追放に成功したことはなかった。
さらに驚くべき事実は、ユダヤ人はある国からしばしばたいへん厳しい状況のもとに追放されても、そのつどたかだか数年足らずのうちにもどってくるということだ。
ライオンの口になんども繰り返して自分の頭を突っこむような、この奇妙な衝動、この信じがたい執念深さは、他の集団の歴史上の記録に見いだすことはできない。
なぜそうであるのか、ユダヤ人の異様で強情な性格、みずから進んで苦難を耐え忍ぼうとする傾向で説明できる、とこれまでいわれてきた。
だが、集団マゾヒズムという解釈では、ユダヤ問題の他の多くの側面を説明できない。
人類の他の多くの問題と同様、実はユダヤ問題は2000年以上にわたってわれわれの前に横たわりつづけ、解決策が求められつづけてきた。われわれは、この問題に正直に直面することを拒んできたために、真相が見えなくなっているのだ。
ユダヤ問題は、キリスト信仰の重要な一面にかかわり、2000年前キリストがわれわれに範を示し、人間としての生命を捨てたキリストのあの解決策を受け入れることによってのみ解決することができるのである。キリストの物語は人類の物語であり、贖罪を発見するという戦慄すべき体験、つまり魂の救済の物語である。
ユダヤ人は、われわれがこの世にとどまるあいだに超克するよう求められている動物的な誘惑のすべてを代表している。ユダヤ人のために、救済は、無自覚あるいは偶然に左右されるのではなく、われわれ自身が意識的に選びとることになった。ユダヤ人と彼らが体現する悪がなければ、人は、目の前に黒白の選択を突きつけられることはなかったかもしれない。人は、よくどちらを選んだらよいのかわからなかったと言い訳をする。けれども、ユダヤ人が存在するからには、そのような言い訳はできないのである。
文明世界では、生涯のある時期に、誰でも極度の誘惑にさらされ、サタンに山頂に連れられていき、肉の喜びを目の前に広げられ、そしてサタンにささやかれる。「おまえがわしのいうことを聞くなら、これはみんな、いや、これ以上のものがおまえのものになる」と。
【参考】悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、「もし、ひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう」と言った。するとイエスは言われた。「退け、サタン。『あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ』と(聖書に)書いてある」。そこで悪魔は離れ去った。(マタイによる福音書)
カエサルはローマをユダヤ人に売ったために殺された!
今日の文明社会で富と権力を操る者の大多数は、サタンの申し出を受け入れた者であり、イエス・キリストを通じて魂が救済される可能性を放棄した者だ。
これらの人間はユダヤ人のために働いている。
バーナード・バルーク(1870~1965年、アメリカにおけるユダヤの黒幕、ウィルソン、ル―ズヴェルト両大統領の経済顧問)の哀れな道具ウィンストン・チャーチル、ベラ・モスコヴィッツのぶざまな召使フランクリン・D・ルーズヴェルト、カガノヴィッチ(1893年~1991年、クレムリン最大の謎の人物といわれてきた)の悪魔の手先スターリン――こうした入間たちはすべて、山の頂きに連れられていき、この世の成功という架空の栄華と富を見せつけられ、サタンに従うよう要求された者たちだ。
これらの者たちはサタンに同意した。そして彼らがまさにサタンに同意したがために、何百万という人びとが無惨に殺戮され、大戦争が悪疫のように世界中に広がり、地上の人類をことごとく恐怖におとしいれたユダヤの爆弾を炸裂させたのである。
チャーチルとルーズヴェルトとスターリンは死んだ。だが、ユダヤの恐怖という彼らの遺産は今日なお残っている。「すべての権力をユダヤへ!」。これがルーズヴェルトとチャーチルの署名したサタンとの条約であった。このために、この2人の男はどちらも地獄の業火に永遠にさらされることになり、ユダヤを呪いながら死んだ。すべては身から出たさびなのである。
そして彼らは、数人の若い女と数本の酒と引き換えに、自国民をユダヤに売りわたして奴隷としたことを慄然と悟って、永遠と向き合ったのである。
このことは、人類の歴史を知る者には、目新しくもショッキングでもない。5000年の長きにわたって、政治指導者たちはユダヤ人のおべっかを聞き入れてきた。
そして、指導者たちはことごとくおなじ暗礁に乗り上げて、その国民を難破させたのである。
文明社会の師であるユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が、当時のローマ国民をユダヤに売ったがために、みずからの元老院議員たちに殺された、というほとんど知られていない驚くべき事実を、われわれはユダヤ人自身の出版物のなかに見いだす。
そして何週間かのちにユダヤは、ルーズヴェルトを、チャーチルを、ジョン・F・ケネディを哀悼するために集会を催したように、カエサルが刺殺された場所で哀悼集会を開いたのである。
「サタンのもとを離れ去って、私についてきなさい」
歴史を通じて、そうした下劣な話はなんども繰り返されてきた。したがって歴史を通じて、指導者にも指導される者にもイエス・キリストのメッセージはずっと同一であった。すなわち、「サタンのもとを離れ去って、私についてきなさい」である。
この魔法のメッセージはとても単純ではあるが、人類にすべてを与えてくれているのに、何百万という人びとはその意味を理解することができず、救われることなく死んでいった。
これはなぜなのか?
なによりもまず、ユダヤ人が問題を混乱させる張本人として生きのびてきたからだ。
キリストが十字架に磔刑(たっけい)になってから、イエスの救いのメッセージが何千という人びとを引きつけはじめると、ユダヤは彼らに典型的な動きを開始した。イエスに反対するのではなく、イエスを乗っ取ろうとした。彼らは世界に向かって、「イエスはユダヤ人」であると主張したのである。そうなると、キリスト教徒となるには、ユダヤ人が命ずるままになんでも従うほかなくなる。
こうすることによって、ユダヤは「イザヤ書」第5章20節に次のように示されていることを無視したのである。
「わざわいなるかな、悪を善と呼び、善を悪と呼ぶ者は。闇を光となし、光を闇となす者、苦きを甘しとなし、甘きを苦しとなす者は、わざわいなるかな」
信じられないことだが、幾百万という人びとがユダヤのこの策略に引っかかった。あらゆる文書記録が、イエス・キリストの身体的特徴は、ガリラヤ生まれの青い目で亜麻色の髪の非ユダヤ人であったと明らかにしているにもかかわらず、何千というキリスト教聖職者が、「ユダヤ人キリストを礼拝しよう]と会衆に語りかけるのだ。
このことは、われわれの救世主に対するはなだしい冒涜であるばかりでなく、人間常識の根本をもことごとく冒涜するものだ。
もしもイエスがこのような善良なユダヤ人であるならば、どうしてユダヤ人はイエスを十字架にかけろと要求したのか? なぜシオンの長老たちはサタンの会堂に秘密のうちに集まり、イエスの肉体を死にいたらしめる計画を練ったのか? 驚くべきことに、会衆を前にしてこの問題を提起しようという聖職者は合衆国にただの一人もいない。それどころか、今日では人びとをユダヤ化する計画を遂行しているキリスト教聖職者さえいる。宗教指導者のなかには、イエス・キリストの傑刑にあらゆる面で荷担したユダヤ人の罪を許すために、聖なる枢機卿会議を開催する者たちさえいるのである。ユダヤは、この目的を達成するために何百万ドルものカネを事前にわたしている。その功あって宗教指導者が集まるこの聖職者会議では、世界に向かって神ご自身の記録である『聖書』はウソであると宣言する。
このことは、なにを意味するのか?
それは明白である。聖職者もまた人間にすぎない。サタンの誘惑で山の頂きに連れられていくことはありうる。つまるところ、個々人の最後の審判の日には誰も仲介に立つことはできず、人は一人で神と直面しなければならないのだ。
聖職者の真の使命とは、われわれの魂の贖罪をして下さるキリストのメッセージを、われわれに力強く説くことにあるはずである。
世界的な真実失墜の時代に、頭を高くかかげよ!
記録は改竄(かいざん)や隠滅することができ、人びとにニセの神を信じさせることもできる。しかし真理が決して曲げられない個所が1カ所だけある。それは魂のなかである。それゆえに、心奥の声なき声に耳を傾け、みずからに正直であれという教えに従う者は正しい選択をすることができるのだ。
この地上のユダヤ人の存在によって、われわれの選択は単純になっている。ユダヤ人の虚偽どおりに生き、救われることなく死するか、それとも、イエス・キリストの真理を抱いてイエスの御腕のなかで栄光に包まれるかのどちらかである。
われわれの文明の偉大な画家と音楽家や哲学者たちが霊感を得たのは、イエスによる贖罪を知っていたからである。
ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽の天かける楽節、何百というルネッサンス芸術家たちの作品、あまたのキリスト教哲学者たちの著述には、イエスの教えに従って生きる者の輝きが明らかに示されている。が、ここでもユダヤ人は、またしても闘いを挑んできた。ユダヤ人は、ゴイ[豚]すなわち非ユダヤ人のだまされやすさを徹底的にあざ笑うかのように、ときには犬や猿に塗りたくらせたような意味のない愚作を絵画の世界に氾濫させてきた。ユダヤ人は音楽の世界を、神経をいらだたせる自動車の警笛の金切り声やドラムを愚かにガンガン叩く騒音に一変させた。そしてユダヤ人は、文学の世界さえ、人間の放蕩三昧を繰り返す物語に変えてしまった。
われわれは、次のように問うてしかるべきだろう。どうしてユダヤ人はこういうことができるのか、どうしてユダヤ人は人間の感性をここまで蹂躙(じゅうりん)することができるのか? と。
答えはこうだ、ユダヤ人の生活は憎悪と復讐よりほかにありようがないからだ。
というのもまさにその本性のゆえにユダヤ人は、キリストが提供する魂の贖罪を受け入れることができないのだ。彼らは、永遠に地上界にとどまるよう宣告された唸る獣である。
天国は彼らを拒む。これがユダヤのほんとうの悲劇である。
今日の若者は、圧倒的なユダヤ的堕落にのぼせ上がって、イエス・キリストのメッセージを聞く耳をもたなくなっている。だが、偉大な詩人バイロン卿がいったように、「逆境にあることは真理への道」である。この世界的な真実失墜の時代に、頭を高くかかげることができ、なおかつイエス・キリストのメッセージを聞くことができる現代の若者にとって、その報いは大きい。
私は、まだ心がイエス・キリストに向かって開かれていない人びとのために、本書を執筆した。本書はユダヤ人の事実に即した歴史であり、もし読み終わって、なおもキリストを否定する人がいるなら、その人は真底から破滅しているのである。
解説 ◎ キリストの中に生きる現代アメリカ精神界の巨人 ―――――― 太田 龍
FBIとADLの苛烈な迫害を撥ねのけ厖大な創造的著作を刊行
マリンズの伝記・経歴を知ると、本当に彼が1994年末現在、いまだに無事で生きていられることが奇蹟のようにしか思えない。
FBI長官フーバーじきじきの全FBI最優先事項として、「マリンズを破滅させよ」という全米的作戦が1948年から1970年代まで30年以上にわたって実施された。
マリンズの父も、母も、2歳の時の自動車事故による重度身体障害の姉も、FBIによって事実上いじめ殺された。
この筆舌につくしがたいFBIとADL(名誉毀損防止同盟)などの圧迫の中で、マリンズは「自分がキリストの中に生きているがゆえに、普通ならとっくの昔に精神の異常を来すか、暴発して投獄ないし殺害されるか、すべての生計の道を断たれて野垂れ死にするしかない状況下で、calm(静かな、穏やかな、落ち着いた)で、serene(乱すものがない、のどかな、晴れた、澄み渡った、悠然とした)さを保ち、厖大な創造的著述活動を続けることができた。そして、そのことに多くの人びとが驚いていた」と記している。
マリンズはキリスト教の牧師でもなく、神父でもなく、神学者でもない。キリスト教会の通常の用語で言えば、世俗の人間(平信徒)に属する。どこかのキリスト教の教会に日曜日ごとに礼拝に行くような人並みに熱心な信者でもなさそうだ。
けれども彼は、もしも今この地上(マリンズが言うように、まさに悪魔の支配する帝国)に、本当の、本物のイエス・キリストの弟子が生きているとしたら、疑いもなくその本物の一人であるに違いない。キリスト教徒ではない私の目には、そのように見える。 私は少年時代(敗戦占領下)から、『古事記』、『法華経』とともに『聖書』(とくに『福音書』)を座右の書としてきたにもかかわらず、マリンズを発見するまでは、日本の内外でイエス・キリストに値するようなキリスト教徒の現物にお目にかかったことがなかった。
イエス・キリストがこの2千年を通じて、現に生き続けておられることを認識し得たのである。
本物の日本人と西洋人とは、何の困難もなく友好関係が結べる
かくしていま日本民族は、ペリー艦隊以後、日本に与えられたアメリカ像が本物とは似ても似つかない、ユダヤによって意図的に偽造されたものであることに気づいた。本物のアメリカを、そして自動的に本物のキリスト教を、本物の西洋、本物のアメリカとは、われわれ日本民族は何の困難もなく友好関係を結ぶことができるもののようだ。
これはありがたいことだ。まことに、心が晴れ晴れとする。
たとえば、あのダグラス・マッカーサー元帥である。マリンズは、『ジェネラル・マッカーサー~その内側の物語』という6ページほどの論文を書いている。
ユダヤは、大恐慌と大失業の真っ只中の1932年7月、首都ワシントンで在郷軍人のデモ隊に米軍を発砲させ、米国の内乱を挑発する陰謀を企図した。
しかしこの時、米陸軍参謀総長マッカーサー将軍は、ユダヤ・フリーメーソンの挑発を毅然として抑え、発砲厳禁の命令を下した。
ちなみにこの時、警備に出動した舞台の指揮官はパットン少佐(のちに第2次世界大戦時、ヨーロッパ戦線の米軍司令官。ユダヤの戦争指導策と衝突して暗殺された)であったという。
この時からマッカーサーは、ユダヤ・フリーメーソンの怒り(怨み)を買い、ついに1950年~1951年の朝鮮戦争で両者の正面衝突に発展してゆくありさまが、マリンズによってなまなましく描かれている。
日本民族はマリンズを糸口として、そして本書『新ユダヤ史』を皮切りに、フランシスコ・ザビエル以来のユダヤにかけられた黒魔術を断ち切るべく、いま猛然と一から学習し始めようとしている。この百数十年来、まっくらやみの暗黒の中に閉じ込められていた日本民族は、ここに一条の光を見いだした。
光は次第に、輝きを増してくるようだ。
「人類が直面する危機についての40年にわたる辛抱強い研究ののち、私は、きわめて単純な結論――すべての陰謀は悪魔的である――に到達した」
とマリンズは書いている。(『カナンの呪い――歴史の悪魔学』序文)
イエスがユダヤパリサイ派を「汝ら、悪魔の子」と弾劾された通り、ユダヤと悪魔ないし悪魔崇拝教は切っても切れない仲のようだ。
けれども両者は全くの同一物というわけでもなさそうだ。
人類を苦しめるすべての悪の要素は「カナン族」から出ている
マリンズは本書で、ユダヤの根本的特徴を「寄生性」と定義している。
英語では、パラサイト(Parasite 生物学では寄生生物、寄生虫、宿り木の意。古代ギリシャでは太鼓持ち的食客と辞書にはある)。つまり、ユダヤは次の2つの傾向を持っているということになる。
(1) 悪魔性
(2) 寄生性
この2つをどんな具合に結びつけたらよいのであろう。この五千年来、人類は「カナンの呪い」にたたられてきたとマリンズはいう。
『旧約聖書』「創世記」の中に、かなりよく知られている次の場面がある。
ノアが酒に酔いつぶれて裸で寝込んでしまった。ノアに3人の息子(セム、ハム、ヤペテ)があり、ハムの息子がカナンである。そのカナンが、ノアの裸を見た。目が覚めたあとノアは、カナンに激怒し、「カナンは呪われよ。汝は、奴隷として仕えよ」と叫んだとある。
マリンズは、現在ユダヤ(タルムード、カバラ)教徒として現れている人びとは、実はセム人の子孫ではなくて、カナン人の系統であることを突き止めた、という。
カバラも、フリーメーソンも、共産主義も、そのほか人類を苦しめるもの、そして人類を神から引き離し、神に反逆させるすべての悪の要素は、このカナン族から出てくる。
カナン人の信条は「世俗的人間至上主義(secular humanism)」であり、そしてそのヒューマニズムへの原動力は「憎悪」である、とマリンズは見た。
カナンの呪いとは、ノアがカナンにかけた呪いなのか、それともノアに呪われたカナンのノアに対する呪いなのか、それとも別のことなのか。そもそもノアは、なぜあれほど激しくカナンを怒ったのであろう? 「創世記」の数行の記述からは、いろいろな解釈が可能である。
ここで言われていること、そしてわれわれが理解しなければならない要点は、神が選んだセム→アブラハムの系統ではない、つまり彼らはセム系を詐称しているにすぎない、という命題である。恐らく西洋でこれほど明確に、そして体系的にユダヤの素性について迫ったのは、マリンズが初めてであろう。
彼らの世界権力は、ゆっくりと崩壊しつつある
マリンズのいちばん新しい著作『世界権力』の巻頭に献辞が印刷されている。
「世界権力」の寵児たちの巨大物偏執狂的計画にとって不幸なことは、彼らは負け戦を戦いつつある。彼らの時間は尽きかけている。彼らの世界権力は、ゆっくりと崩壊しつつある」
というのがマリンズの見方であるが、それは本当か。彼らの世界権力とは、つまるところ、寄生者の覇権であるが、そもそも寄生者が宿主に対して覇権を打ち立てるとは、何のことであろう。
しかしながら、そもそも悪魔とは、被造物の分際でありながら創造者たる神に反逆し、神に寄生して、神の上に立とうとする存在のようにも受け取りうる。
そんなことは、土台、無理な注文というものではなかろうか。つまり、それは最初から根拠のない計画、つまり早い話、幻想であり、妄想にすきないのではないか。
悪魔が、そしてユダヤが一時この地上で勝利するように見えることがあっても、それは錯覚であって、いざとなって悪魔の帝国はそれ自身の重みによって崩壊し、跡形もなく消滅する定めである。「創世記」のバベルの塔の物語が教えるものはそれである――という展望は、単なるロマンチックな楽観主義ではない、これは長年にわたる研究の結論である、とマリンズは記している。

人類の苦悩はその過剰な「攻撃性」にあるのではなく,その並外れた狂信的な「献身」にある。Arthur Koestler著A Summing Upより
アーサー・ケストラー(松岡正剛)
『ユダヤ人とは誰か』
1990 三交社
Arthur Koestler : The Thirteenth Tribe 1976
宇野正美 訳
転載開始
第842夜のスピノザ『エチカ』に出しておいたユダヤ人マラーノをめぐる宿題について、その続きを予告しておいたので、今夜はその宿題を書くために本書を選んだ。ついでに第693夜のベルント・レックの『歴史のアウトサイダー』も引き連れる。
著者のアーサー・ケストラーは20世紀後半の最もラディカルなジャーナリストの一人で、とくにスペインの内乱に向けた眼の先鋭性は、第941夜のダニエル・ゲランに匹敵するものがある。最初の話題作『スペインの遺書』は読む者の胸をえぐった。一方、『サンバガエルの謎』や『ホロン革命』をはじめとする代表著作があるように、ケストラーは科学にもシステム思考にも強かった。一貫してヒエラルキーに代わる「ヘテラルキーの社会化」を主張しつづけた思想者でありつづけた。90歳前後だったと思うが、最期はかねてからの計画通りに夫人と安楽死を遂げた。
ぼくは工作舎で『ホロン革命』の翻訳編集出版(このタイトルはぼくがつけた。原著は『ヤヌス』=両顔両面神という)にかかわったため、ケストラーにはとくに親しみをもっているが、本書のようなユダヤ人問題をめぐる著作があるとはしばらく知らなかった。
本書の原題はなかなか意味深長である。『第十三支族』となっていて、アシュケナージ(アシュケナージーム)のユダヤ人、すなわちカザール(ハザール)系のユダヤ人の動向を解明している。邦題『ユダヤ人とは誰か』から予想されるような、“あのユダヤ人”をめぐる全般史ではない。とりわけスファルディ(セファルディーム)を扱ってはいない。アシュケナージだけである。
しかし第693夜・第842夜にも書いておいたように、近代以降のユダヤ人問題を理解するには、このアシュケナージをこそ見る必要がある。これまであまり議論されてこなかったにもかかわらず、最も重要な動向を秘めている。
ただし、ケストラーの本書だけではこの動向の全貌は見えない。そこでごく最近刊行されたハイコ・ハウマンの詳細な『東方ユダヤ人の歴史』(鳥影社)をこれに交差させ、これらを補うためにシーセル・ロスの『ユダヤ人の歴史』(みすず書房)やマックス・ディモントの『ユダヤ人』上下巻(朝日新聞社)などを下敷きにした。
簡単におさらいをしておくと、今日のユダヤ人には大きく2種類あるいは3種類がある。日本人のわれわれはこの相違がよくわかっていない。
ひとつは「スファラディ」(スファルディ)のユダヤ人で、旧約聖書にアブラハム、イサク、ヤコブの子孫として歴史に登場する「モーセの民」である。スペインを意味するヘブライ語「スファラッド」を語源とする。
これがふつうは“本来のユダヤ人”だとみなされている。しかし、かれらは数度にわたるディアスポラ(離散)にあって、1492年までは主としてイベリア半島に定住していた。ここでかれらはスペイン語を改竄した「ラディノ語」をつくる。が、イスパニアでカトリックの力が強くなると(いわゆるレコンキスタ)、主要部族は北アフリカ、オランダ、フランス南部に移動した。
この移動部隊の多くはキリスト教徒と融合しながら生き延びた。この部隊の“隠れユダヤ人”たちが「マラーノ」である。スピノザやレンブラントはポルトガル系のマラーノの直系だった(第842夜)。
もうひとつは「アシュケナージ」のユダヤ人で、その多くは東ヨーロッパで多数のコミュニティをつくっていたのだが、ロシアのポグロムやドイツのホロコーストで迫害され、西ヨーロッパあるいはアメリカに移住した。
アシュケナージとは、ドイツを意味するヘブライ語の「アシュケナズ」から派生した呼称である。
このアシュケナージはもともとはカザール人と重なっていた。かれらはやがて東欧に動いてドイツ語を改竄して「イディッシュ語」をつくった。
いま、世界中のユダヤ人は1500万人ほどいるというが、そのうちの約90パーセントはアシュケナージだといわれる。しかし、アシュケナージは本来のユダヤ人なのかという問題がある。
さらに「ミズラヒ」と呼ばれるユダヤ人がいる。しばしばスファラディに含まれて語られることも多いのだが、その一部がアジアに流れていったことに特徴がある。もっとも今日のイスラエルにはスファラディとミズラヒがほぼ半分すづ居住する。
ぼくは長らく、「さまよえるユダヤ人」の歴史や動向や思想に関心をもってきた。最初は高校時代に読んだ石上玄一郎の『彷徨えるユダヤ人』(いまはレグルス文庫に入っている)からだったろうか。
その後、ユダヤの歴史と思想に惹かれてずいぶんいろいろな書物を渉猟してきたが、この「さまよえるユダヤ人」が今日の世界の大多数を占めるユダヤ人ではなかったということは、ケストラーを読むまでは知らなかった。
モーセの出エジプト以来、ダビデも預言者エレミアもハスモン王朝も、「タルムード」もカバラ神秘主義も「ゾハール」も、マホメッドもマイモニデスらの地中界ユダヤ人も、これらはセム系の「モーセの民」としての動向だった。これらは総じてユダヤ思想とかユダヤ主義とよばれてきたものである。その黄金期はだいたい11世紀までのことだった。
やがて「さまよえるユダヤ人」はいったん歴史の主舞台から姿を消し、やがてスファラディと呼ばれるようになった。なぜそうなったかといえば、度重なる十字軍の動きとキリスト教社会の矛盾に満ちた波及とともに、ロシアを含む全ヨーロッパでユダヤ人に対する追放や弾圧が始まった。多くのスファラディがスペインやポルトガルに逃げのびたことは上に述べたとおりだが(強制的に改宗させられた者も多く、そのため隠れユダヤとしてのマラーノが生まれた)、15世紀にはその逃げのびたユダヤ人がまたイベリア半島からも、フランスからも追放された。
16世紀になると、イタリア、ドイツ、中央ヨーロッパの各地に次々にゲットーができ、それが許容できないユダヤ人は集団でイギリスやアメリカに渡った。なかで比較的寛容なオランダ移民派のスピノザが『エチカ』を書いたのは、まさにこの時期である。そのスピノザを、ヨーロッパは冷たい沈黙で迎えたものだ。
こうしてスファラディは、むろんやむなくというべきだが、一方では改良主義に走り(モーゼス・メンデルスゾーンの改革派ユダヤ主義など)、他方ではゲットーを出て過激に走らざるをえなかった(ハシディズムの再燃など)。
近代に向かった「モーセの民」を待っていたのは、さらに複雑な動向である。
フランス革命がヨーロッパの精神を塗り替え、ついでナポレオンがヨーロッパの地図を塗り替えると、ユダヤ人を抱きこむ国があらわれて、いったんユダヤ人の“はかない春”がおとずれそうにもなったのだが、同時にユダヤ教など認めないという複雑骨折が次々におこっていった。
つづくナポレオンのロシアでの決定的敗北以降は、ヨーロッパ各国は「国民国家」の形成にむけて動き出して、ユダヤ人という人種問題などまったく顧みられることがなくなっていく。そういうときに、ロマノフ朝が支配を確立したロシアで、ユダヤ人の大量虐殺(ポグロム)が断行された。
かくして、もはやスファラディの純血はこれを守るすべがないほどに攫き乱され、アシュケナージとの交じり合いもおこりはじめた。実はマルクスやバクーニンが登場してきた時代は、こういう時期だった。ということは、これでおよその見当がつくと思うけれど、コミュニズムやアナキズムは、資本制社会や国民国家や人種差別に対する総合的なアンチテーゼだったのである。
20世紀はユダヤ人がどのように現代社会にユダヤを定着させるかという政治行動と哲学思想の時代になる。
たとえばシオニズムが吹き荒れ、マルティン・ブーバーのユダヤ実存主義が生まれ(第588夜)、フロイトやアインシュタインによる意識革命のプランや科学革命のプランが噴き出してきた。
ここにいたって、スファラディによって創意されてきたユダヤ主義は、大量のアシュケナージと混成していくことになった。
1948年にイスラエルが建国されたとき、その原動力になったのはほとんどアシュケナージだった。建国後、スファラディがイスラエルに入ってきた。しかし、スファラディとアシュケナージは全く別の“人種”だったのである。
では、今日のユダヤ人の90パーセントを占めるアシュケナージとは何なのか。
ケストラーによると、アシュケナージとカザール(ハザール)人の歴史は重なっている。そして、この歴史こそがヨーロッパの裏側のシナリオの解読にとって最も重要なものだという。
375年をさかいに、フン族をはじめとする民族大移動がユーラシアを動きまわった。このときビザンチン帝国の使節はフン王アッチラに親書を送り、戦士部族としてのカザール人の存在を報告した。歴史上、初のカザール人の登場である。
フンの王国が崩壊すると、カザール人はコーカサス北部を中心にしだいに勢力を拡大していった。首長はカガンと呼ばれた。ついで広大な草原にトルコ民族の突厥(チュルク)が出現すると、カザールの民はいったん突厥の支配下に入り、アバール・ハーン王国を名のった。そのうちビザンチン帝国の版図の拡大にともなって、ビザンチンとカザールとのあいだに軍事同盟ができ、コンスタンティヌス5世がカザールの王女を娶り、その息子レオン4世が“カザールのレオン”としてビザンチン帝国の皇帝の座についた。
その直後の740年ころ、カザールはユダヤ教に集団改宗した。理由ははっきりしない。ともかくカザールの民はいっせいにユダヤ化してみせたのだ。ノアの3番目の息子のヤペテを始祖とする“血の伝承”に関する見方もこのころにつくられた。
しかし、その血統は実際にはセム系ではなく、白色トルコ系であり、その気質はあきらかに遊牧民族系だった。
カザール国
こうして、カール大帝が西ローマ帝国を治めたときは、ロシア・トルコ地域には、キエフ王国とユダヤっぽいカザール王国(首都イティル)の二つの勢力がが相並んでいたということになる。
そのカザール王国の盛衰に終止符が打たれたのは、1236年にモンゴル軍が侵攻し(いわゆる「タタールのくびき」)、1243年にキプチャク・ハーン国が成立したときである。カザール人はバトゥ・ハーンの支配となって、ここに王国は滅亡した。
しかしケストラーは、このあとにカザール人がロシアから東欧に移動して、のちにアシュケナージとよばれる親ユダヤ的な中核をつくったと推理して、そこにブルガール人、ブルタ人、マジャール(ハンガリー)人、ゴート人、それにスラブ人が交じっていったと判断した。ケストラー自身がハンガリー生まれだったのである。
黒海とカスピ海に囲まれた地域を中心に広がった半径のなかにいたカザール人が、しだいにマジャールやブルガールと交じっていったことは、その後のユダヤの歴史をひどくややこしくさせている。
まずカザール・ディアスポーラは、東欧にかなり高密度な集落をつくっていった。これはゲットーではない。自主的なコモンズで、もっぱら「シュテトゥル」と呼ばれた。この集落がロシアの地からの拡張にともなってしだいにポーランドのほうにも移行して、やがて「ユーデンドルフ」(ユダヤ村)と総称された。そのユーデンドルフに、それまで離散していたユダヤ人が少しずつ加わった。そこには”本来のユダヤ人”(セム系ユダヤ人)やスファラディも交じっていた。
ここからはハウマンの記述が詳しいのだが、こうして、ポーランドが東方ユダヤ人の原郷とされていったのだ。これこそ、モーセ以来のセム系ユダヤの十二支族にもうひとつが加わることになった「第十三支族」なのである。
けれども、そのポーランドこそは近現代史の悲劇の舞台であった。ポーランドはたえず分割された。そしてそのたびに「第十三支族」が影のシナリオを担わされていった。これはかつての「さまよえるユダヤ人」ではなく、新たな近現代の「さまよえる複合ユダヤ人」の物語なのである。
これでおおざっぱなことは展望できたとおもう。ともかくも、こうして地球上をしだいに占めるようになったアシュケナージの動向は、「モーセの民」をも巻きこんだまま、今日の今日にいたるまで、イスラエルの中でも、イスラエルの内外でも、血統・勢力・宗旨・言語・風習をめぐる重大なキーをもったまま、国際政治の荒波での浮沈をくりかえす一団というふうになったのである。
ふりかえってみると、スピノザもマルクスも、カフカもブーバーもサルトルも抱えた“ユダヤ人問題”には、いくつもの難解な特徴があった。
3点だけ、ここではあげておく。
第1に、「モーセの民」と「タルムードの民」は必ずしも一致していないということだ。本来のユダヤ教は「旧約聖書」と「ゾハール」と「タルムード」が聖典であるが、アシュケナージは「タルムード」しか読まない。
第2に、言語の問題がある。「モーセの民」はヘブライ語の民である。ところがディアスポラのユダヤ人は各地でその地域の言語を編集して、新たな“ユダヤ風の言語”をつくった。それが10世紀ごろに確立されたイディッシュ語である。ドイツ語を基盤に、そこに「タルムード」の単語や句を交ぜた。これが大流行した。アシュケナージは主としてイディッシュ語をマメ・ロシュン(母語)とした。さきほどのユダヤ・コモンズ「シュテトゥル」もイディッシュ語である。
いまではイディッシュ文学という独自の領域もある。日本でも森繁久弥がテヴィエに扮して当たったミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』の原作者ショーレム・アレイヘムはその一人だった。ウクライナ生まれのアシュケナージだった。
ちなみに『屋根の上のヴァイオリン弾き』の舞台写真を最初に見たとき、ぼくはマルク・シャガールの絵をふいに思い出していた。のちに知って驚いたのだが、シャガールは20世紀で最も有名なアシュケナージの画家だったのだ。
第3にハシディズムやシオニズムの問題がある。ハシディズムはポーランドのバアル・シェーム・トーヴ(略称ベシュト)によって提唱された。18世紀である。神との交流による恍惚を謳った。
トーヴの活動はやがてハシディズム(敬虔主義)とよばれ、南ポーランド全体に広がっていく。が、ポーランド分割の悲劇がこの活動に終止符を打たせた。
シオニズムは選民思想である。しかし、そこにはシオニズムが投入されざるをえなかった苛酷な前段がある。
1855年にジョセフ・ゴビノーの『人種の不平等』がユダヤ人であること自体を悪とする人種差別思想をまきちらし、1881年にキリスト教社会党を組織したアドルフ・シュテッカーが「ドイツのユダヤ化」を激しく非難したパンフレットを連打、1903年にセルゲイ・ニールスが『シオンの議定書』を書いてユダヤ人が世界支配の計画と陰謀をもっているというデッチアゲをして、これらが流布された。
こうした異常な反ユダヤ主義(アンチセミティズム)がヨーロッパを席巻した。
この悪影響はわれわれの想像を絶するもので、心あるユダヤ人たちにいわゆる「ユダヤ人の自己嫌悪」をもたらし、このアンビバレンツな感情はハインリッヒ・ハイネを嚆矢に、オットー・ヴァイニンガー、フロイト、フッサールに及んだものだった。
この反ユダヤ主義に対して、レオン・ビンスケルが『アウト・エマンツィパツィオーン』(自力回復)を提唱する。ユダヤ人は同化されえず、自らも民族的ホームを求めるべきだというものだ。
モーゼス・ヘスも『ローマとエルサレム』でユダヤ倫理にもとづいたユダヤ人国家をつくるしかないと説き、ヒルシェ・カーリッシュが『シオンを求む』でイスラエルの地での再民族化の機会をもつべきではないかと説いた。
そこへドレフェス事件やエミール・ゾラの勇気ある活躍があって、ユダヤ人を認めるべきだという西ヨーロッパにおける機運がわずかに盛り上がってきた。テオドール・ヘルツルがシオニスト会議を提案した背景には、以上のような流れが渦巻いていた。
ヘルツルのシオニズム運動は挫折するけれど、その方針は受け継がれて結局はイエラエル建国に結びつく。それがどういうものであったか、どんな問題が積み残されたかについては、第398夜の『ユダヤ国家のパレスチナ人』や、立山良司がポスト・シオニズムの動向をまとめた『揺れるユダヤ人国家』(文春新書)などを読んでもらいたい。
以上、わずか3点だけ取り上げてみたが、これらはいずれもアシュケナージの奥にスファラディの歴史的宿命を窺うというていの問題ばかりである。
ユダヤ人問題というのは、とうていわれわれが観測しきれるものではない。しかし、ときどきはこの問題にひそんでいる壮絶な意味を覗いてみることは、日本や日本人を考えるときのヒントになることがある。
たとえば数年前、WJC(世界ユダヤ人会議)の会長ナフム・ゴールドマンが「ユダヤ人にとって良い時は、ユダヤ教にとって悪い時になる」と発言していたことは、強烈な暗示力をもっていた。
その後、イスラエルの良心とも呼ばれるヨッシ・ベイリン労働党議員がWJC60周年記念シンポジウムで、「ユダヤ人が個人として活動が自由になっているとき、ユダヤという民族は縮んでいるのだ」と発言していた。何かものすごいことをメッセージされていると思ったことである。
ユダヤ人の個人と、ユダヤ人という民族と、ユダヤという国家とは別なのだ。そこにはホッブズのリヴァイアサンはあてはまらない。いや、別なのではなく、それを一緒にしようとすると、歴史が必ずそこで逆巻くのである。
その理由がどこにあったのか、たとえばエドワード・サイードにも答えを出してほしかったことである。
PS:この本と,ユースタス・マリンズ著:カナンの呪いの二冊は読んでおこう。ちなみにユースタス。マリンズさんは1922年生まれ。現在老人ホームに軟禁状態であるが,時々Rense.comなどでラジオインタビューをして存在感をアッピールしている。