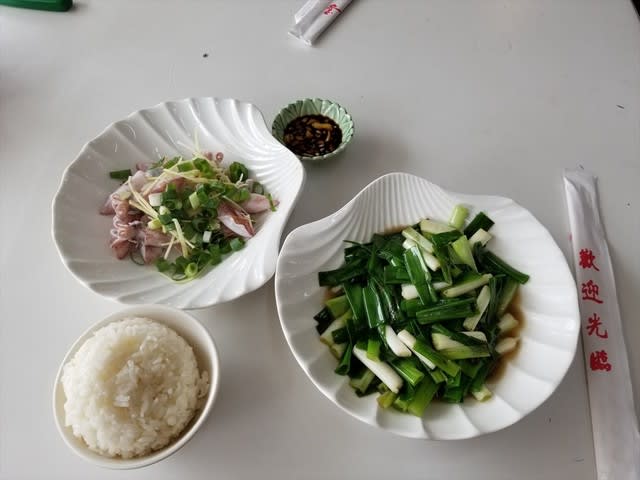陽明山国家公園は台北郊外の緑豊かなエリア。活火山である大屯山がもたらした自然の恵みと美しさに溢れた素晴らしい場所です。台北の市街からちょっと足を伸ばすだけで大都市近郊とは思えない景色が広がっており、いつ訪れても台湾の自然の豊かさを実感させてくれます。さて、火山活動が随所で現れているこのエリアには、野湯もあちこちに存在しており、拙ブログでもそのいくつかを既に取り上げておりますが、近年は立入制限が厳しくなり、実際にパトロールが実施されて、罰金を科せられた人もいるようです。

たとえば拙ブログで2014年に取り上げた磺渓温泉の入口には、上画像のように罰金3000元というリアリティのある罰金額が記載された立入禁止の看板が建てられ、強固なバリケードが張られるようになりました。
ここのみならず、台湾の野湯では屈指の知名度を誇る八煙温泉でも同様の看板が立てられ、違反して侵入する者を取り締まる様子がメディアで報道されたこともありました。
そんな中にあって、エリア内にもかかわらずこの規制の網から外れている野湯がありますので、行ってみることにしました。

まずは上磺渓駐車場(無料)にレンタカーを駐め、歩いて陽金公路(台2甲線)へ戻ります。

上磺渓駐車場付近は、台北市と新北市(旧台北県金山郷エリア)との境界なんですね。陽金公路にはそのことを示す看板が立っていました。

陽金公路を陽明山方向へ歩き、上画像の場所で右の未舗装路へ逸れます。
なお路線バスで当地を訪れる場合は、台北から士林や陽明山を経由して金山を結ぶ皇家客運1717バスの大油坑バス停と上磺溪橋(魚路古道)バス停の中間にこの脇道の入り口がありますので、台北方面からアクセスする場合は大油坑バス停で下車して金山方面を目指して歩けば良いですし、金山方面から乗車するなら上磺溪橋バス停で下車すれば良いでしょう。

砂利道を森へ向かってどんどん進んでゆくと・・・

やがて赤土が露出した杣道になります。

私が訪れた時には小雨が降っていたため、赤土の下り道はとても滑りやすく、途中何度か足元をすくわれそうになりました。慎重に歩みを進めます。

草をかき分けながら下っていった先には、上画像に写っている乳白色の小さな池が姿を見せていました。お察しの通りこの白い池は温泉なのですが、入浴するには小さく、しかもぬるいので、ここには入りません。

小さくて白い池の先には沢が流れており、雨にもかかわらずその川岸では野湯を楽しむ人々の歓声が響いていました。今回の目的地である下七股温泉に到着です。

強い日差しを遮ってのんびり湯浴みするためか、日除けのネットまで張られていました。

目の前を流れる沢はとっても綺麗。実に清冽です。

沢に沿っていくつか湯溜まりがあるのですが、今回私が入ったのは上画像に写っているこの湯溜まりです。一見すると野湯を楽しむに適したサイズであり、深さもそこそこあるように思えるのですが、なぜか先客たちはこの湯溜まりを避けているのです。

なぜこの湯溜まりに人がいないか、すぐにわかりました。入浴するにはちょっと熱いのです。温度計を差し込んだところ46℃と表示しました。他の湯溜まりは適温だったのですが、それらは既に先客が占有しているため、私が入れるのはここだけ。でも日頃の鍛錬で熱い風呂に入ることができる私は・・・

その場で水着に着替え、この熱い湯溜まりに入浴してしまいました。確かに熱いので長湯できませんが、はっきりと硫化水素臭が漂うなかなか良いイオウの濁り湯です。おそらく温泉は湯溜まりの底で湧出しているようです。なおお湯はグレーに濁っていますが、これは砂が混じるためであり、ビニルシートが敷かれている別の湯溜まりでは乳白色を呈していました。

ここの砂は鉄分を含んでいるらしく、硫化鉄で手が黒くなってしまいました。お湯がグレーに濁る原因のひとつはこの硫化鉄でしょう。従いまして、ここで野湯を楽しむ際、肌を汚したくない方は注意してくださいね。
立入規制が厳しくなった陽明山エリアにおいて、下七股温泉は野湯を合法的に楽しめる数少ない場所のひとつ。
湯溜まりが多くないので、週末には混んでしまうかもしれませんが、興味がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
台北市士林区某所
路線バスでアクセスする方法は本文中にて説明しております。
野湯につき無料。いつでも入浴可。
水着着用のこと
私の好み:★★+0.5
.

たとえば拙ブログで2014年に取り上げた磺渓温泉の入口には、上画像のように罰金3000元というリアリティのある罰金額が記載された立入禁止の看板が建てられ、強固なバリケードが張られるようになりました。
ここのみならず、台湾の野湯では屈指の知名度を誇る八煙温泉でも同様の看板が立てられ、違反して侵入する者を取り締まる様子がメディアで報道されたこともありました。
そんな中にあって、エリア内にもかかわらずこの規制の網から外れている野湯がありますので、行ってみることにしました。

まずは上磺渓駐車場(無料)にレンタカーを駐め、歩いて陽金公路(台2甲線)へ戻ります。

上磺渓駐車場付近は、台北市と新北市(旧台北県金山郷エリア)との境界なんですね。陽金公路にはそのことを示す看板が立っていました。

陽金公路を陽明山方向へ歩き、上画像の場所で右の未舗装路へ逸れます。
なお路線バスで当地を訪れる場合は、台北から士林や陽明山を経由して金山を結ぶ皇家客運1717バスの大油坑バス停と上磺溪橋(魚路古道)バス停の中間にこの脇道の入り口がありますので、台北方面からアクセスする場合は大油坑バス停で下車して金山方面を目指して歩けば良いですし、金山方面から乗車するなら上磺溪橋バス停で下車すれば良いでしょう。

砂利道を森へ向かってどんどん進んでゆくと・・・

やがて赤土が露出した杣道になります。

私が訪れた時には小雨が降っていたため、赤土の下り道はとても滑りやすく、途中何度か足元をすくわれそうになりました。慎重に歩みを進めます。

草をかき分けながら下っていった先には、上画像に写っている乳白色の小さな池が姿を見せていました。お察しの通りこの白い池は温泉なのですが、入浴するには小さく、しかもぬるいので、ここには入りません。

小さくて白い池の先には沢が流れており、雨にもかかわらずその川岸では野湯を楽しむ人々の歓声が響いていました。今回の目的地である下七股温泉に到着です。

強い日差しを遮ってのんびり湯浴みするためか、日除けのネットまで張られていました。

目の前を流れる沢はとっても綺麗。実に清冽です。

沢に沿っていくつか湯溜まりがあるのですが、今回私が入ったのは上画像に写っているこの湯溜まりです。一見すると野湯を楽しむに適したサイズであり、深さもそこそこあるように思えるのですが、なぜか先客たちはこの湯溜まりを避けているのです。

なぜこの湯溜まりに人がいないか、すぐにわかりました。入浴するにはちょっと熱いのです。温度計を差し込んだところ46℃と表示しました。他の湯溜まりは適温だったのですが、それらは既に先客が占有しているため、私が入れるのはここだけ。でも日頃の鍛錬で熱い風呂に入ることができる私は・・・

その場で水着に着替え、この熱い湯溜まりに入浴してしまいました。確かに熱いので長湯できませんが、はっきりと硫化水素臭が漂うなかなか良いイオウの濁り湯です。おそらく温泉は湯溜まりの底で湧出しているようです。なおお湯はグレーに濁っていますが、これは砂が混じるためであり、ビニルシートが敷かれている別の湯溜まりでは乳白色を呈していました。

ここの砂は鉄分を含んでいるらしく、硫化鉄で手が黒くなってしまいました。お湯がグレーに濁る原因のひとつはこの硫化鉄でしょう。従いまして、ここで野湯を楽しむ際、肌を汚したくない方は注意してくださいね。
立入規制が厳しくなった陽明山エリアにおいて、下七股温泉は野湯を合法的に楽しめる数少ない場所のひとつ。
湯溜まりが多くないので、週末には混んでしまうかもしれませんが、興味がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
台北市士林区某所
路線バスでアクセスする方法は本文中にて説明しております。
野湯につき無料。いつでも入浴可。
水着着用のこと
私の好み:★★+0.5
.