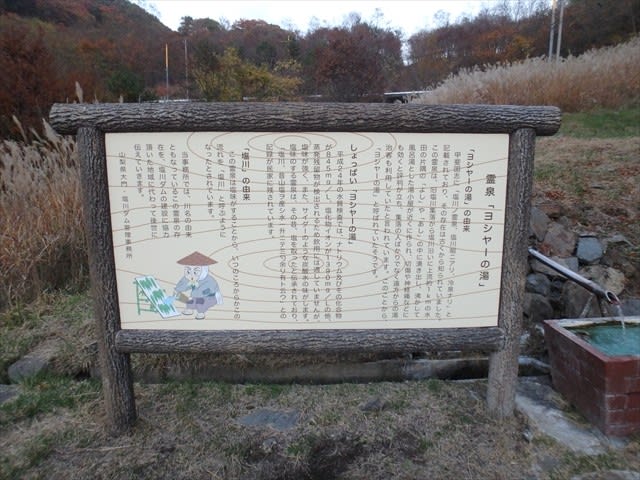久しぶりに埼玉県のネタを投稿させていただきます。埼玉県平野部の地中深くには、古東京湾の化石海水やそれに由来する地下水が大量涵養されており、地中で温められたそれらの地下水をボーリングで汲み上げることにより、温泉として利用されています。
今回取り上げる「埼玉スポーツセンター天然温泉」もそんな温泉施設の一つであり、温泉ファンから折り紙が付けられるほどお湯が良いことでも有名です。

まずは埼玉県民の一大集積地である池袋から東武東上線に乗り、みずほ台駅で下車。そして西口の駅前ロータリーから路線バスに乗り継ぎます。このロータリーから発着してる路線バスは1本しかなく、それゆえバス停も1つしかありませんので迷うことは無いでしょう。ライフバスという会社が運行しているのですが、会社の規模が小さい為か、運賃支払いは現金のみで交通系ICカードは使用不可。でも時刻はナビタイムで検索できます。地方の小さな路線まで網羅するナビタイムってすごいですね!

広大な農村風景の中に、住宅、工場、倉庫といった統一感の無い建物がモザイク状に建つ、埼玉県の郊外らしい車窓を眺めながら約5分ほど乗車して「埼玉スポーツセンター」停留所で下車。バスが来た道を若干戻る感じで歩いてゆくと・・・

今回の目的地である「埼玉スポーツセンター天然温泉」に到着です。

スポーツセンターという名前の通り、広大な敷地の中には温泉浴場のほかに、ゴルフの打ちっぱなし、テニスコート、フットサルコート、ボウリング場など、体を動かして楽しむ様々な施設が併設されていますが、今回私は温泉のみ利用しました。ちなみにこの「埼玉スポーツセンター」は、東上沿線の県内各地に広告看板を立てていますので、私も以前からその存在は知っておりました。おそらく地元の方には相当知名度が高い施設なのかと思います。
館内は撮影しておりませんので、ここから先はパンフレットに掲載されている写真を使わせていただきつつ、文章を中心にレポートさせていただきます。
玄関を入り、靴用ロッカーに下足を預け、受付で下足箱のカギと引き換えに脱衣室のロッカーキー付きリストバンドを受け取ります。なお料金は後払いです。正直なところを申し上げますと、田舎臭いネーミングや立地などから、あまりホスピタリティには期待していなかったのですが、受付の方の丁寧な接客にまず良い意味で期待を裏切られました。
受付を済ませたら、薄暗くシックな内装が施されている通路を歩いて浴場へ。たしかに落ち着いた大人な雰囲気を醸し出しているのでしょうけど、とはいえ安普請な感じは否めず、いささか背伸びをしちゃっているような感を受けます。また、話が前後しますが、湯上がり後にゆっくり寛げるような休憩スペースがあまり広くないので、せっかく作りだしたその雰囲気を活かせないのもちょっと残念なところ。

脱衣室を抜けて浴場に入りますと、正面に掛け湯が設けられており、そこから左右に通路が分かれています。
左側を進んだ先にあるのは、洗い場と2つの浴槽です。洗い場には、左右の壁に計14、中央の島に計12、そして奥の壁に4、合計30ヶ所のカランが設置されています。一方、洗い場の向かいには内湯の主浴槽である「静」と泡風呂の「舞」が隣り合っており、前者は石板張りの7~8人サイズで、後者は寝湯のようなスタイルで利用します。いずれも循環された温泉が張られており、露天を眺める大きな窓からは陽光が降り注ぐので、明るく気持ち良い入浴環境が保たれています。さらに、洗い場の奥へ延びる通路を進めば、ドライとミストの両サウナや水風呂へと続きます。
露天ゾーンの中央にはこの施設の主役と言うべき浴槽「和」や「極」があり、それらを取り囲むように多種多様な浴槽がありますので、簡単にご説明します。

内湯に近い方には循環した温泉を加温して熱めの湯加減にしている浴槽「熱」と、その隣に井水加温循環で円形浴槽の「蘇」が隣り合っています。

そして、ちょっと高いところに設置されている「極」へ登る階段の途中には寝湯の「夢」、一人用浴槽の「独」(2つ)が据え付けられています。「夢」の浴槽は石造で4人用。「夢」も「独」も循環した温泉が張られています。

露天ゾーンの中央に盛られた築山の上に設けられた浴槽は「極」。10人サイズの岩風呂なのですが、その名が示すようにこの浴場では極め付けのお風呂とでも言うべき存在であり、加温された源泉がかけ流されていて、赤茶色に染まった湯口から源泉のお湯が絶え間なく供給されていました。また源泉が持つ個性をなるべく損なわないようにするためか、加温は必要最低限に抑えられているため、人によってはかなりぬるく感じるかもしれませんが、ぬる湯好きな方にとっては体への負担が軽い状態でじっくりと長湯することができるでしょう。
この「極」を満たしたお湯は、その下にある浴槽「和」へと流れてゆきます。「和」は見た感じが優しい8人サイズの木の浴槽で、屋根が立てられていますから多少の雨なら凌げるでしょう。「和」のお湯は「極」以外の各浴槽と同じく加温循環されていますが、「極」から流れ込んでくるお湯もありますから、他の浴槽よりはお湯の状態が良いかと思います。

↑画像は各浴槽の湯使いに関する表示です。
井水加温循環の「蘇」と水風呂以外は温泉水を使用しており、温泉水を使っている浴槽は、「極」を除けば全て加温・循環・消毒が行われています。注目すべきは「極」の湯使い。源泉温度が31~32℃なので加温は仕方ないにせよ、それ以外の循環や消毒は行われておらず、しかも上述したように加温が程々に抑えられているので、とてもよいコンディションの温泉を掛け流しで楽しむことができるのです。
具体的に「極」のお湯について申し上げますと、湯口を赤茶色に染めるお湯は、浴槽では琥珀色を呈しつつも透明。湯口のお湯を口に含むと、重曹味と弱い金気味、そして弱いながらもモール臭が感じられます。特筆すべきは浴感であり、湯中ではヌルヌルを伴うツルスベ浴感が強く、しかも全身にしっかりと気泡が付着します。東京近郊という立地でありながら、こんなヌルツルスベで強力な泡付きのお湯に入れるだなんて、驚きとしか言いようがありません。加温を程々に抑えていることが、泡付きの良さに一役買っているものと思われます(加温を強くすると気泡が失われます)。
一方、加温循環されている各浴槽では、見た目は淡い山吹色となって色付きが薄くなり、泡付きもなく、ヌルツルスベ浴感もパワーダウンしていました。でも湯加減はちょうど良いので、私は「極」を中心に入浴し、それに飽きたり、あるいはもう少し体を温めたくなったら「和」など他の浴槽に入って、各浴槽を使い分けながら湯あみを愉しみました。
埼玉県平野部の温泉を大雑把に分類すると、ストレートな化石海水系のしょっぱいお湯と、その化石海水が長い年月をかけて成分を変えていったと思しき重曹泉系の2つに分けることができ、こちらの温泉は後者に属するものと思われます。また、知覚的特徴という点で捉えるならば、私が大好きな山梨県甲府盆地や熊本県人吉盆地のお湯にも近いタイプだと言えるでしょう。あるいは関西の阪神間に点在する温泉銭湯のお湯に似ているかもしれませんね。
通勤電車で行ける本格的な温泉。下手に遠くへ出かけて体力と時間とお金を費やすぐらいなら、こうした近場の温泉に入った方が良いかもしれません。

当記事の冒頭で、私はみずほ台駅から路線バスで当施設へアクセスしましたが、実は無料送迎車が運行されているんですね。館内でそのことを知った私は、帰りに無料送迎車を利用させていただきました。お客さんの利用状況により、ハイエースにするかバスにするか使い分けており、私が帰るときにはハイエースからバスへチェンジして運行されました。ハイエースでは運びきれないほどの利用客があるんですよ。
みずほ温泉
アルカリ性単純温泉 31.6℃ pH8.7 300L/min(動力揚湯) 溶存物質0.5903g/kg 成分総計0.5913g/kg
Na+:154.1mg(96.88mval%),
Cl-:55.6mg(22.29mval%), Br-:0.2mg, HCO3-:309.1mg(71.99mval%), CO3--:11.4mg,
H2SiO3:47.5mg,
(平成17年6月8日)
東武東上線・みずほ台駅より無料送迎バスを利用。もしくはみずほ台駅西口より路線バス(ライフバス)の5系統で「埼玉スポーツセンター」下車すぐ
埼玉県所沢市南永井1116
04-2946-4126
ホームページ
10:00~25:00
平日770円・土日祝870円
ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり
私の好み:★★+0.5
今回取り上げる「埼玉スポーツセンター天然温泉」もそんな温泉施設の一つであり、温泉ファンから折り紙が付けられるほどお湯が良いことでも有名です。

まずは埼玉県民の一大集積地である池袋から東武東上線に乗り、みずほ台駅で下車。そして西口の駅前ロータリーから路線バスに乗り継ぎます。このロータリーから発着してる路線バスは1本しかなく、それゆえバス停も1つしかありませんので迷うことは無いでしょう。ライフバスという会社が運行しているのですが、会社の規模が小さい為か、運賃支払いは現金のみで交通系ICカードは使用不可。でも時刻はナビタイムで検索できます。地方の小さな路線まで網羅するナビタイムってすごいですね!

広大な農村風景の中に、住宅、工場、倉庫といった統一感の無い建物がモザイク状に建つ、埼玉県の郊外らしい車窓を眺めながら約5分ほど乗車して「埼玉スポーツセンター」停留所で下車。バスが来た道を若干戻る感じで歩いてゆくと・・・

今回の目的地である「埼玉スポーツセンター天然温泉」に到着です。

スポーツセンターという名前の通り、広大な敷地の中には温泉浴場のほかに、ゴルフの打ちっぱなし、テニスコート、フットサルコート、ボウリング場など、体を動かして楽しむ様々な施設が併設されていますが、今回私は温泉のみ利用しました。ちなみにこの「埼玉スポーツセンター」は、東上沿線の県内各地に広告看板を立てていますので、私も以前からその存在は知っておりました。おそらく地元の方には相当知名度が高い施設なのかと思います。
館内は撮影しておりませんので、ここから先はパンフレットに掲載されている写真を使わせていただきつつ、文章を中心にレポートさせていただきます。
玄関を入り、靴用ロッカーに下足を預け、受付で下足箱のカギと引き換えに脱衣室のロッカーキー付きリストバンドを受け取ります。なお料金は後払いです。正直なところを申し上げますと、田舎臭いネーミングや立地などから、あまりホスピタリティには期待していなかったのですが、受付の方の丁寧な接客にまず良い意味で期待を裏切られました。
受付を済ませたら、薄暗くシックな内装が施されている通路を歩いて浴場へ。たしかに落ち着いた大人な雰囲気を醸し出しているのでしょうけど、とはいえ安普請な感じは否めず、いささか背伸びをしちゃっているような感を受けます。また、話が前後しますが、湯上がり後にゆっくり寛げるような休憩スペースがあまり広くないので、せっかく作りだしたその雰囲気を活かせないのもちょっと残念なところ。

脱衣室を抜けて浴場に入りますと、正面に掛け湯が設けられており、そこから左右に通路が分かれています。
左側を進んだ先にあるのは、洗い場と2つの浴槽です。洗い場には、左右の壁に計14、中央の島に計12、そして奥の壁に4、合計30ヶ所のカランが設置されています。一方、洗い場の向かいには内湯の主浴槽である「静」と泡風呂の「舞」が隣り合っており、前者は石板張りの7~8人サイズで、後者は寝湯のようなスタイルで利用します。いずれも循環された温泉が張られており、露天を眺める大きな窓からは陽光が降り注ぐので、明るく気持ち良い入浴環境が保たれています。さらに、洗い場の奥へ延びる通路を進めば、ドライとミストの両サウナや水風呂へと続きます。
露天ゾーンの中央にはこの施設の主役と言うべき浴槽「和」や「極」があり、それらを取り囲むように多種多様な浴槽がありますので、簡単にご説明します。

内湯に近い方には循環した温泉を加温して熱めの湯加減にしている浴槽「熱」と、その隣に井水加温循環で円形浴槽の「蘇」が隣り合っています。

そして、ちょっと高いところに設置されている「極」へ登る階段の途中には寝湯の「夢」、一人用浴槽の「独」(2つ)が据え付けられています。「夢」の浴槽は石造で4人用。「夢」も「独」も循環した温泉が張られています。

露天ゾーンの中央に盛られた築山の上に設けられた浴槽は「極」。10人サイズの岩風呂なのですが、その名が示すようにこの浴場では極め付けのお風呂とでも言うべき存在であり、加温された源泉がかけ流されていて、赤茶色に染まった湯口から源泉のお湯が絶え間なく供給されていました。また源泉が持つ個性をなるべく損なわないようにするためか、加温は必要最低限に抑えられているため、人によってはかなりぬるく感じるかもしれませんが、ぬる湯好きな方にとっては体への負担が軽い状態でじっくりと長湯することができるでしょう。
この「極」を満たしたお湯は、その下にある浴槽「和」へと流れてゆきます。「和」は見た感じが優しい8人サイズの木の浴槽で、屋根が立てられていますから多少の雨なら凌げるでしょう。「和」のお湯は「極」以外の各浴槽と同じく加温循環されていますが、「極」から流れ込んでくるお湯もありますから、他の浴槽よりはお湯の状態が良いかと思います。

↑画像は各浴槽の湯使いに関する表示です。
井水加温循環の「蘇」と水風呂以外は温泉水を使用しており、温泉水を使っている浴槽は、「極」を除けば全て加温・循環・消毒が行われています。注目すべきは「極」の湯使い。源泉温度が31~32℃なので加温は仕方ないにせよ、それ以外の循環や消毒は行われておらず、しかも上述したように加温が程々に抑えられているので、とてもよいコンディションの温泉を掛け流しで楽しむことができるのです。
具体的に「極」のお湯について申し上げますと、湯口を赤茶色に染めるお湯は、浴槽では琥珀色を呈しつつも透明。湯口のお湯を口に含むと、重曹味と弱い金気味、そして弱いながらもモール臭が感じられます。特筆すべきは浴感であり、湯中ではヌルヌルを伴うツルスベ浴感が強く、しかも全身にしっかりと気泡が付着します。東京近郊という立地でありながら、こんなヌルツルスベで強力な泡付きのお湯に入れるだなんて、驚きとしか言いようがありません。加温を程々に抑えていることが、泡付きの良さに一役買っているものと思われます(加温を強くすると気泡が失われます)。
一方、加温循環されている各浴槽では、見た目は淡い山吹色となって色付きが薄くなり、泡付きもなく、ヌルツルスベ浴感もパワーダウンしていました。でも湯加減はちょうど良いので、私は「極」を中心に入浴し、それに飽きたり、あるいはもう少し体を温めたくなったら「和」など他の浴槽に入って、各浴槽を使い分けながら湯あみを愉しみました。
埼玉県平野部の温泉を大雑把に分類すると、ストレートな化石海水系のしょっぱいお湯と、その化石海水が長い年月をかけて成分を変えていったと思しき重曹泉系の2つに分けることができ、こちらの温泉は後者に属するものと思われます。また、知覚的特徴という点で捉えるならば、私が大好きな山梨県甲府盆地や熊本県人吉盆地のお湯にも近いタイプだと言えるでしょう。あるいは関西の阪神間に点在する温泉銭湯のお湯に似ているかもしれませんね。
通勤電車で行ける本格的な温泉。下手に遠くへ出かけて体力と時間とお金を費やすぐらいなら、こうした近場の温泉に入った方が良いかもしれません。

当記事の冒頭で、私はみずほ台駅から路線バスで当施設へアクセスしましたが、実は無料送迎車が運行されているんですね。館内でそのことを知った私は、帰りに無料送迎車を利用させていただきました。お客さんの利用状況により、ハイエースにするかバスにするか使い分けており、私が帰るときにはハイエースからバスへチェンジして運行されました。ハイエースでは運びきれないほどの利用客があるんですよ。
みずほ温泉
アルカリ性単純温泉 31.6℃ pH8.7 300L/min(動力揚湯) 溶存物質0.5903g/kg 成分総計0.5913g/kg
Na+:154.1mg(96.88mval%),
Cl-:55.6mg(22.29mval%), Br-:0.2mg, HCO3-:309.1mg(71.99mval%), CO3--:11.4mg,
H2SiO3:47.5mg,
(平成17年6月8日)
東武東上線・みずほ台駅より無料送迎バスを利用。もしくはみずほ台駅西口より路線バス(ライフバス)の5系統で「埼玉スポーツセンター」下車すぐ
埼玉県所沢市南永井1116
04-2946-4126
ホームページ
10:00~25:00
平日770円・土日祝870円
ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり
私の好み:★★+0.5