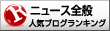5)恋文
冬休みに入ると、行雄は百合子との関係をなんとか打開しなければと焦ってきた。しかし、妙案があるわけではない。 電話で話しても、自分の気持を十分に伝えることは極めて難しい。 思い切って彼女の自宅を訪れようかと考えたが、そうする勇気もないし、彼女だって自宅に来られるのは断るに違いない。
どうしてよいか分からず、行雄は悶々たる気持で数日を過ごしたが、そのうちにある考えが固まってきた。 百合子に心から謝罪し、自分の真心を伝える手紙を出すということだった。それ以外に良い方法はないだろう。 行雄は決意を固め、クリスマスの二日後に百合子宛の手紙を書いた。それは敗軍の将が全面降伏し、勝った敵将の許しと憐れみをひたすら懇願するような内容のものとなった。
「・・・ 十一月七日、僕は登校時に君の天使の微笑みを見てから、頭がフラフラになった。 その時から君のことが片時も忘れられなくなり、なんとしても君と付き合えないものかと、そればかり考えるようになった。
でも、僕の臆病な性格が災いして、君に自分の気持を素直に伝えることができなかった。 僕は自分の不甲斐なさに、どれほど嫌気がさしたことだろう。僕自身を何度も叱ってみたが、どうすることもできなかった。
君は僕の臆病な性格を軽蔑して、嘲笑うならいくらでも笑ってほしい。現実の僕は、本当に意気地のない哀れな男なのだから。 それでも僕は、なんとかして君と仲良くなりたいと、そればかり考えるようになった。
早稲田祭の始まる前日、僕は意を決して君の家に電話をかけた。そうしたら、君のお母さんが出てきて、とても気持良く君を電話に出してくれた。 あの時、僕はどんなに嬉しく感じたことか。そして、君と話していてどれほど幸せを感じたか。 いま君に、正確に伝える言葉が見当たらないくらいだ。
そのあと僕は幸福感で一杯になり、歌舞伎の入門書を買ってきて、君と楽しく話しができるよう“にわか勉強”をしたくらいだった。 そしてあの日、僕は勇気凛々、君がいる歌舞研のサークル会場に向った。
ところが、会場に近づくにつれて、どういうわけか僕の気持は重苦しくなり、憂うつになっていった。その原因がいまでも分からないのだ。 君にあれほど会いたいと思っていたのに、サークル会場に入ったら逃げ出したい気持に変ってしまった。
君の姿が見えた時は、もう緊張のあまり、どうしてよいのか分からなくなってしまった。 そして、君が話しかけてきた時、僕はあんなに不様で失礼な態度をとってしまった。どうしてあのようになってしまったのか、その原因がいまでも分からない。 僕は自分自身がほとほと嫌になった。 本当にごめんなさい。あやまります。
僕は他の人がいると、何もできなくなるようだ。自意識過剰なのか、内気で病的な性格なのか知らないが、他の人がいると何もできなくなるのです。 こういう僕を許して下さい。心からあやまります。 もう二度と、あのような不様で失礼なことはしないつもりです。
君から逃げ出した時、僕は身体中が熱くなり、全身に汗をかいたように感じました。この奇妙で臆病な性格の男を許して下さい。 あれから僕は、なんとしても君にあやまらなければと、そのことばかり考えてきました。そして今、こういう手紙を書いているわけです。
もう二度とあのようなことがないように注意し、努力していきます。重ねて、どうかお許し下さい。 来年になったら、僕はもう少し利口になって、君と仲良くやっていけるように一所懸命努力します。本当に失礼しました。
どうぞ、良い年を迎えて下さい。僕にとっても、来年が良い年であるように頑張ります。 それでは、新学期にお会いしましょう。
中野百合子様 村上行雄 」
乱れた文章で手紙を書き終えると、行雄は少しばかり安堵感を覚えた。彼は手紙を読み直した後すぐに自宅を出て、近くの郵便ポストにそれを投函した。 ところが、百合子に謝罪の手紙を出した後、行雄はもう一通手紙を書こうという強い衝動に駆られた。
それは、百合子を完全に自分のものにしてしまおうという、激しい情念から生まれたものである。この衝動に彼は逆らうことができなかった。 いま出してきたばかりの手紙は、単なる謝罪のものでしかない。それだけでは足りないのだ。謝罪をしたのだから、あとは開き直って百合子を手に入れるだけである。
行雄は全身全霊を打ち込んだ愛の手紙を書こうと思った。彼は百合子をなんとしても“征服”しようと思ったのだ。 彼女を必ず圧倒する、誰にも書けないような凄まじいものを書かなければならない。そう決意すると、行雄は全身に力がみなぎるのを感じた。
その夜、彼は張り詰めた感情が狂おしいまでに高ぶるなか、あたかも“宣戦布告”をするような気持で筆を執った。
「百合子さん 僕の一生の感謝 一生の幸福になって下さい。 ワセダで最も美しい人 僕はあなたなしでは生きていくことができない。 あなたは僕の幸福の泉であり 感謝の源なのだ。 あなたの暖かい懐の中で死ねたら なんという感激! なんという愉悦!
夕陽にさらに赤らむ君の頬の美しさ 朝ごとの微風にほほえむ君の瞳の麗しさ ああ 乙女よ 乙女よ 心から君を愛す。 君は その白く美しく輝く身体を開いて たおやかに僕を迎え入れてくれるだろう。
君のいる街 君のいる家 君のいる部屋に射し込む日の光! ああ 僕の抱擁に 接吻に 愛撫に 君はぐったりする 僕は勝った! 僕は嬉しい! 君は僕のものだ そして 僕は君のものだ。
二人は完全に溶け合い 一体となって空の彼方 宇宙の果てに昇華していくだろう 愛が一つになった時 この世には他になにもない 愛があるだけだ ああ 百合子 僕の百合子 君は永遠に僕のものだ。
この世には君と僕しかいない 他になにもないのだ 二人だけの世界がいま開かれ 太陽が君と僕を祝福してくれる 光と熱が二人を一体のものとし その契りを永遠のものとするだろう。
僕はいま 幸福の絶頂に泣いている その涙で 君の香しい全身を潤そう 僕はもう狂いそうだ いや 君の前に狂い立っている 君になんと思われようともよい 君は僕のものだ!
そして 僕は全身全霊をあげて 君のものとなる 君の足元に 永遠にひれ伏す ありがとう 僕はこの運命に感謝する 二人を結びつけた神に 栄光のあらんことを! ・・・ 」
行雄は物に憑かれたように書き続けた。彼は宇宙の始原的な熱と力を放出しているように感じ、頭に思い浮かぶことをそのまま書いていった。十数枚の便せんに書きなぐった後で、彼はようやく我に返った気持になったのである。
翌日、行雄は二通目の手紙を郵便局から速達で出した。百合子の手元に、前の手紙とほぼ同時に届いて欲しいと願ったからである。 彼は自己満足をしていた。これで百合子を完全に“征服”できると思ったからである。
そこには、自己を捧げる愛情よりも、征服欲を満たした荒々しい満足感があった。行雄は、勝ち誇ったバッカスのような気分になっていたのである。 そして、自分に征服された百合子から、いずれ何らかの返事が来るだろうと考えていた。
新しい年、昭和三十七年が明けると、行雄はこの年が素晴らしい年になるに違いないと思った。 それと同時に、百合子からの返事が早く届くことを願った。彼女を征服したという思いは次第に薄れ、その返事を待ち焦がれるようになっていった。
三箇日が過ぎても百合子からの便りがないので、年賀状の配達との関係で他の郵便物が遅れているのかと行雄は思ったが、だんだん不安が高じてくる。 百合子から本当に返事が来るのだろうか、もし来なかったらどうしようかと思いあぐねるようになった。
しかし、自分はやるだけのことはやったのだ、後は天命を待つのみであるという心境にもなった。 不安と期待が高まる中で、行雄は四日、五日を過ごしたが、努めて明るい見通しを持つべきだと自分に言い聞かせ、百合子とのデートや、一緒にお茶を飲んだり映画を見に行くことなどを想像した。
そして、一月六日、百合子から待望の手紙が届いた。行雄が押し頂くようにして開封すると、七枚の便せんに大らかで読みやすい文字が整然と綴られている。
「・・・ 私は貴方の二通の手紙を読んで、驚きと恐怖の思いに満たされています。どうして、あのような手紙を書いて送ってきたのですか。 貴方は大学で私と一緒にいる時は、ほとんど何も話しかけて下さらなかったではありませんか。
現実の私に対して、何もしようとはされなかったのに、手紙を通しては、恐ろしいまでに色々のことを述べておられるのですね。 貴方は現実の私をほとんど無視していたのに、幻覚の中の私にだけ語りかけているのです。
貴方の考えていること、述べていることは全て幻覚です。それは現実とはまったく異なります。 私が貴方の幻覚の中で勝手に踊らされ、弄ばれていることに非常な憤りを感じています。
・・・ 私はいま、歯を食いしばっています。 貴方はなぜ現実の私に対して、何もしようとはされないのですか。なぜ、幻覚を現実のものにしようとされないのですか。 貴方は幻覚の中で勝利を味わっているだけで、現実には何も得ているわけではありません。
貴方が私に好意を持っておられるのなら、なぜそれを現実の生活の中で示そうとなさらないのですか。 貴方の二通の手紙が、好意の証しとでもいうのでしょうか。私にはそうは思えません。 貴方は幻覚の中で夢を見ているだけです。私を幻覚の中で弄んでいるだけです。
・・・ 新学期が始まりましたら、どうか現実の生活の中で、貴方なりの好意を示して頂きたいと思います。 それまで、私も歯を食いしばって我慢します。新しい年が、貴方にとって良い年でありますようお祈り致します。 それでは、お元気で。
村上行雄様 中野百合子 」
百合子の返事を行雄は食い入るように読んだ。「幻覚」と「現実」の文字が余りに多いが、彼はその後何十回も手紙を読み返したので、その内容をほとんど暗記してしまったほどである。
行雄は百合子の心を征服したとは思ったが、それ以上に、申し訳ないという罪悪感で胸が一杯になった。 彼女が繰り返し言っているように、自分は百合子を幻覚の中で勝手に弄んでいたのだろう。それについては、彼女の非難めいた文は当然だと思う。 しかし、彼女は行雄の好意を現実に示して欲しいとも言っている。それは、こちらの情愛を望んでいる証明ではないか。
熱い想いが込み上げてきて、行雄は一日も早く百合子に会いたいと願った。 彼女に非難されたとはいえ、彼は相変らず百合子の幻影を朝から晩まで追い求め、それがあの美しいヴィーナスに結び付いていく。 彼女の白い肉体・・・ふくよかな腰、長くて盛り上がった大腿部などが露わに脳裏に浮かんでくる。
行雄は初めて、百合子の肉体を想像してオナニーをする。そこにはほとんど罪悪感はなかった。これも“必然”だと思う。 理屈っぽい彼は、全てのことは必然なのだと自分に言い聞かせ、しびれるようなオナニーに陶然とする。
また、行雄は煮えたぎる想いを紛らすために、毎日毎日ベートーヴェンの交響曲第五番「運命」を聴いた。 百合子と自分の運命はここに定まったという思いである。「運命」の力強く圧倒的な調べは、二人の行く末を決定付けるように響き渡るのである。
三学期が始まると、行雄は一年ぶりに茶色の分厚いコートを着て大学に行った。一年前の学期末試験の時、まったく受験準備をしていなかった彼が、開き直ってこのコートと角帽を身に付け試験会場に乗り込んだことを思い出した。
あの時と同じように気持が高ぶっているが、行雄の今度の相手は試験ではなく百合子本人である。 最初の授業は一般教養課目の心理学で、大教室で行なわれることになっている。彼は中程に座って、百合子が来ていないかどうか室内を見回した。
すると、左側の後方の奥に、彼女がクラスメートの渡辺悦子と並んで座っているのが見えた。行雄の所から二十メートル近く後ろである。 百合子は行雄の視線に気が付いているのか分からないが、頬を少し紅潮させている。
講義の合間に、彼は幾度も百合子の方に視線を投げかけたが、彼女はそれに気付いていないような素振りである。 やがて講義が終った。学生達が一斉に大教室から出ていく中を、行雄は足早に後方の出口へ向った。
教室の外に出ると、廊下の隅で壁に背をもたれるようにして、百合子と渡辺が立ち話しをしている。 行雄が二人に近づくと、渡辺の方から声をかけてきた。「まあ、村上さん。久しぶりね、お元気ですか?」 「うん、まあね」 行雄は彼女にあいまいな返事をしてから、百合子を正面から見据えた。
「中野さん、こんにちは」 彼は努めて気軽に声をかけたつもりだが、百合子は戸惑った表情を見せると、驚いたように口を少し開けたまま行雄の顔を凝視している。 彼は緊張していなかったが、次に何と言ってよいものやら思いあぐねた。
暫くして行雄が語りかけた。「今度、中野さんの家に遊びに行ってもいいですか?」 彼は彼女に親愛の情を示したつもりである。ところが、百合子の驚きの表情がさっと青ざめ、彼女は左に顔をそむけて叫んだ。「困ります!」 その白い首筋がピクピクと震えている。
行雄は冷水を浴びせかけられたような気持になり、言葉を継ぐことができなかった。 困惑して渡辺の方に目を向けると、彼女もあいまいな笑みを浮かべているだけである。すっかり居たたまれなくなった行雄は、やけくそになって叫んだ。
「どうもすみませんでした! 失礼します!」 吐き捨てるように言って一礼すると、百合子はまた驚愕の表情を見せて彼の方を振り向いた。 行雄は憤然とした気持でその場を立ち去るしかなかった。
自分は好意を持って語りかけたのに、百合子はどうしてあのような“取りつく島もない”態度を取るのか。 彼女の家に伺いたいと言ったのは、出過ぎたことだったのだろうか。自分の言い方が唐突だったかもしれない。 それにしても、百合子に「困ります!」と拒絶されたことは、行雄にとってショックである。
情感に満ち誠意のこもった彼女のあの手紙は、一体なんだったのか。 彼女はあれほど希望を抱かせる返事を自分に寄越してくれたのに、今日の態度はどういうことなのか。 自分は口下手でぶっきら棒で、今日は不しつけな言い方をしたかもしれないが、百合子の方ももっと優しく対応してくれてもいいではないか。彼女の今日の仕打ちは残酷ではないのか。
行雄は屈辱と悔しさを感じていた。 百合子が手紙の中で「歯を食いしばる」と言っていたように、自分も“歯がみ”をするしかないと思う。 この日以降、彼は意気消沈して百合子に言葉をかけることができなかった。あれほど熱烈なラブレターを書いたというのに、現実生活では怖じ気づいて彼女に近寄れない日々が続くのである。
行雄が百合子に何もできないうちに、学期末試験の時がきた。 一年前とは打って変って、彼は十分に勉強していたので今回の試験には自信があった。果たせるかな、結果は上々の出来で、十五以上の課目のうち「良」はわずか三課目で、残りは全て「優」という成績で終った。
試験の方は堂々たるものがあったのに、百合子との関係についてはどうしても神経質で臆病になってくる。 行雄は絶えず彼女を窺っていたが、近づくことができないのだ。いつもジメジメした気持で百合子を見詰めている。 彼女に「困ります!」と拒絶されたことが尾を引いているとはいえ、自分の不甲斐なさに行雄は情けなく思うことがある。
彼がいつも百合子を凝視しているので、その関係を察したのか、クラスメートの剽軽(ひょうきん)な宮部進が「君は中野さんを“観賞”しているのか?」と、冷やかしてきたことがある。 行雄は百合子を観賞しているわけではないが、クラスメートにはそう思われたのだろう。
百合子に対し何もできないまま一ヵ月半以上が経ち、春休みに入った。 彼女の姿が見られないのは非常に寂しい。悶々たる気持になった行雄は、ついに電話をかけようと“決意”した。会いたいという願望を伝えようと思ったのである。
以前と同じように、行雄は緊張と不安で心臓がドキドキする中で受話器を取った。恐る恐るダイヤルを回す。 すると、これも以前と同じように、百合子の母親が感じの良い明るい声で電話口に出てきて、すぐに百合子を呼び出してくれた。
行雄は少しどぎまぎしながらも、端的に用件を述べた。「君とゆっくり話し合いたいんだけど、どうですか」 「いいですよ、いつがいいですか」 百合子の快活な声が返ってくる。「できれば、明日かあさって会いたいと思っているんだけど・・・」「それでは、あさってにしませんか。明日はわたし、ちょっと別の用事がありますので」
「ああ、勿論いいですよ。それじゃ、あさっての午後がいいかしら」「あさっては午後に、歌舞伎研究会の集まりがあるので、正午に学生会館でどうでしょうか」 「ああ、いいですよ。それじゃ、あさっての十二時に学生会館の一階に行きますから、それでいいですね」 「分かりました。その時間に学生会館の一階に行っています」「ありがとう、それではよろしく」
電話を切ると行雄は安堵した。今回は全てが順調に進んでいくようである。 大学の学生会館には各文化サークルの部室があり、一階は生協の食堂や面会所があって学生達の溜まり場になっている。 百合子とはその面会所で会うことになり、他にも学生が多数いるかもしれないが、行雄はそれでもいいと思った。
本当はゆっくり話せる喫茶店で会いたいと思っていたが、百合子の都合で学生会館で落ち合うのも仕方がない。 二日後、行雄は気もそぞろに家を出た。三月初旬だというのに、その日は比較的温かく穏やかな日和である。彼は高田馬場駅から徒歩で大学に向った。
学生会館に近づくと、以前の早稲田祭の時のように胸の高なりと緊張感を覚えたが、今回は足取りも軽く面会所に入る。 予想していたように、中には大勢の学生がいる。ぐるりと見渡すと、左奥の隅の方に百合子がいた。彼女は緑色のカーディガンを着て、くつろいだ感じで座っている。
行雄の緊張感がほぐれ、彼はテーブルを挟んで百合子の真正面に座った。「やあ、お待たせ。でも、十二時を少し回ったところかな」 行雄が語りかけると彼女は口元に微笑を浮かべたが、彼を見ることもなく「どうも」とつぶやいた。
座席に深々と座った行雄は、さも余裕ありげな態度で「今日は会える機会をつくってくれて、ありがとう」と礼を言ったが、百合子は無言である。 彼はやや気まずく感じたが尋ねる。「今日は何時ぐらいまでいいのかしら。君は歌舞研の集まりがあると言ってたけど」
「一時間ほどでしたら大丈夫です」 百合子が顔を上げてはっきりと答えた。 一時間とは短い。それでは喫茶店にも誘い出せないではないか、と行雄は思う。暫く沈黙が続いたが、彼の方から切り出した。
「君とこうやって話せるように、僕は以前から想っていたんだ。でも、何を話してよいのか分からない。 僕は面白い話しが出来るような器用な人間じゃないし、君と楽しく話せるかどうか自信がないんだ。 だけど、こうして会ってもらえるだけでも有り難い。 いろいろ話しているうちに、きっと楽しい話しが出来るようになると思っているんだけど・・・」
行雄が丁寧に控え目な口調で語る。百合子はうつむいたまま彼の話しを聞いているが、時折チラリと視線を上げる。暫くしてまた沈黙が続いた。 今度は百合子が、行雄の視線をしっかりと捕まえて切り出す。「どうして、去年の暮れにあんな手紙を書いてきたのですか」
彼女の口調には詰問するような厳しさがあった。行雄は返答に窮し、逆に挑むような眼差しで百合子を見返す。 彼女は彼の視線にトゲがあるように感じたのか、目を伏せると甲高い声で続けた。
「わたし、怖かったんです! どうしてあんな手紙を書いたのですか!? あの二通の手紙はほとんど読んでいません。とにかく怖かったんです。 あなたは何かにすぐ“没入”する人なんですね。わたし、そういうのが怖いんです」
没入? そうか、自分は確かに何事にも没頭してしまう人間だ。 森戸敦子の時も全学連の時も、俺はとことん没入、没頭する生き方をしてきた。それが善いか悪いかの問題ではなく、そういう生き方しかできないのだ。 百合子の言うことは当たっている。それに対して、自分はなんの抗弁もできない。 行雄はそう思うしかなかった。彼はやや申し訳ない気持になって、ようやく口を開く。
「すまなかったね、僕はそういう男なんだ。君が言うように、何かにすぐ没頭してしまう所があるんだ。 でも、あの手紙は、僕の本心を有りのままに伝えたかっただけなんだ。ただ、それが君にとって怖いものであったのなら、申し訳ないと思う。 もちろん、もう二度とあんな手紙を書くつもりはない。あの事はもう忘れてしまって欲しい。それより、こうした時間を大切にしていきたいんだ」
行雄が素直に謝ると、百合子も納得したようにそれ以上は言及してこなかった。 暫くして行雄は、話題をクラスメートのことに切り替え、百合子の仲間の話しを持ち出した。 話題が変って彼女は明るい様子になった。高校時代からの友人である渡辺悦子らの話しになると、百合子は生き生きとした表情で語り始める。
行雄はほっとして、それから共通の学友や教授らの話題で雑談を楽しんだ。 そのうちに行雄は、百合子が膝の上に小型のグラビア雑誌をのせているのを見つけた。彼女は時たまそれに目をやっていたが、行雄がのぞき込むと、表紙は「京都」という題名になっている。
「中野さんは京都が好きなの?」「ええ、わたしは元々京都にいたんです。 父の転勤の都合で、高校の時から東京に出てきたんですが、京都生まれの京都育ちです。 あそこの方が東京より雰囲気がいいし、落ち着けますね。京都なら何度でも行ってみたいと思っています」
百合子が京都に縁があることを初めて知って、行雄は、言われてみれば彼女の風貌や雰囲気は京都風かなと思う。 どことなく“おっとり”していて穏やかに見える。柄も大きいので、ゆったりとした感じを人に与える。真正面から見ると、彼女の顔立は下膨れの“おちょぼ口”で、浮世絵によく出てくる古風な美人のタイプだ。
自分もいつの日か百合子と京都へ旅行にでも行けるのかな、と行雄は思った。 それから二、三十分ほど、京都や歌舞伎のことなど他愛ないおしゃべりをする間に、行雄が何気なくテーブルの下に目をやると、百合子の組んだ両脚が見てとれた。長くてふくよかな両脚がベージュ色のスカートから伸びている。
行雄は数秒の間それに目をやっていたが、視線を上げて彼女の顔と向き合ったとたん愕然とした。百合子が艶やかな微笑を浮かべて行雄を凝視している。 彼女の細い両眼は彼の視線を絶対に逸らせまいと、食い入るように見詰めている。少し開いたおちょぼ口がなまめかしく紅を帯び、妖しげな笑みを湛えている。それは媚びの笑み以外の何ものでもなかった。
行雄は息が詰まるような感じがして、百合子の媚笑から目を逸らせようとするが、彼女の潤んだ瞳は、彼の視線を絶対に放すまいと絡み付いてくる。 呆然とした行雄の上半身はだんだん右に傾いていく。彼の困惑と動揺を読み取ったのか、百合子は勝ち誇ったように満面に嫣(えん)然とした笑みを浮かべた。
極めてわざとらしい媚笑に行雄は息も絶え絶えになり、彼女の視線から逃れるようにうつむいた。 若い女性から、こんなに艶やかな媚びを売られたのは初めてである。 彼は暫く目を伏せていた。そして、恐る恐る視線を上げると、百合子はもう何もなかったかのように、平然とした顔付きで「京都」の雑誌に目を落としている。
やがて数分が過ぎたところで、歌舞伎研究会の部員と思われる眼鏡をかけた背の高い男が、ニヤニヤと笑みを浮かべながら百合子を迎えに来た。「そろそろ会合を始めるよ」 彼は先輩らしいきびきびとした口調で、彼女に声をかける。
百合子はニコリと微笑むと「村上さん、では失礼します」と言って立ち上がった。行雄も釣られるように立ち上がり「それじゃ、僕も失礼します」とおうむ返しに答えた。 百合子はハイヒールを履いているので、彼より十センチ以上も背が高く見える。大柄で肉付きのよい百合子を目の前にすると、行雄は圧迫感を覚え自分の背の低さを恥ずかしく感じた。 彼は彼女に軽く会釈すると、逃げるように足早に面会所を去った。
行雄はそのまま自宅に帰るのも面白くないので、近くの喫茶店に立ち寄りコーヒーをゆっくりと味わった。 つい先程の百合子の媚笑が、脳裏にこびりついて離れない。彼女は、行雄が出した手紙について「怖かった」と言っていたが、今や彼の方が百合子に対し“恐怖”を感じている。
その恐怖とは、彼女の肉体に対するものだ。彼は百合子が“女王蜂”のように思え、その妖しげな魅力にのめり込んでいくような不安を感じる。 それは一方では歓喜の絶頂に至るものだが、他方では底無しの泥沼にはまり込んでいくようなものである。 行雄は百合子の肉体を想像し、それに戦慄する自分を意識していた。
(注・・・以上、2003年4月までに執筆したものです。 以下、数字の表記など文体が少し変ります。)