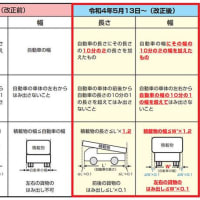順番としては2番めなんだけどね。
うちはプロパンガスの契約を切っているのだ。
風呂は灯油化したし、瞬間湯沸かし器のガスはカセットボンベで賄っていて不満は無い。
台所のガスコンロは全くの無駄になっていたのだ。
基本、料理はホエーブス625とかのガソリンのシングルバーナーストーブで賄っていたのだ。
一応、補助としてカセットコンロとIHコンロがある。
鍋ひとつ、火ひとつ、男ひとりの料理だったわけだ。
ホエーブス625
だがしかし、それで十分ではないのは明らかだった。
そこで購入、コールマンのツーバーナー!
ガソリン使用のツーバーナーコンロはほぼこれだけしか市場には無いのだ。
僕は基本、ヨーロッパ製品の方がアメリカ製品よりも好きなのだが仕方がない。
安っぽい薄い板金製ケースはマニア心を全くくすぐらない。
しかし、中古はお安い。
楽しいファミリーキャンプを夢見て買って、使いこなせなかったダディたちがたくさん居るのだ。
現代の『普通』はなんの予備知識もなく、ツマミをひねるだけで機能するものなのだ。
製品レビューなんぞを眺めると、やたら難しいだの危険だののコメントがあるが、個人的にはそれは『オレはダメだ』と言っているのと同義に思えるので恥ずかしいですわ。
例えばホエーブス625あたりではそんなことをつぶやく軟弱者は皆無に近い。
コールマンツーバーナーよりも気を使う使用法を当たり前に軽々使いこなせる猛者ばかりだからだ。
そんなわけで、軽い気分でお安いコールマンツーバーナー中古を購入。
蓋は風防になっていて、閉じるとトランク状の形になって運びやすく出来ているのだが台所での使用では邪魔なので外した。
向かって左側面にはサブバーナーのノブがあるので、コンロのスペースに収めるのは不便なので台を作った。
台は固定していないので動かせる。
例えば鍋を振って盛大に炒めものをしたいときなどは壁面からの距離が欲しいので、台ごと移動する。

火を移動する理由はもう一つ。
最大火力を使うと壁面が近すぎて危険なのだ。
そう。コイツのメインバーナーの最大火力は素晴らしく、炒めものが気持ちよく出来るのだ。
チャーハンが気持ちよく出来る。
一般家庭の低い火力でもチャーハンをパラッと仕上げる炒め方には様々なノウハウがある。
鍋を振らないとか、あらかじめご飯と卵を混ぜるとか。
プロは一般に、熱くした鍋に油を入れて溶き卵を入れてご飯を入れてほぐし混ぜるというやり方である。
火力があれば特別な工夫は要らないのだ。
写真の中華鍋は放置されてサビサビになっていたものだが、磨いて焼いてやったら実に良い具合に仕上がったのだ。
それも簡単に。
火力は鍋の仕上げにも良い効果があるのだ。
このコールマンツーバーナーの基本構造は1920年代に完成していたらしい。
しかしながらその後、予熱時間極小、火力調整可能のシングルバーナーが完成するのにはその後50年近くを要するのだ!
1950年代頃までのシングルバーナーは火力調整不能。
このツーバーナーの構造を小型化するシングルバーナーの開発は50年代から始まり、失敗作(超当たり前の失敗wwww)も出し、ようやく70年代後半あたりから製品として安定したのだ。
予熱不要とよく言われるが、少しの時間の予熱は必要だ。
ただ、着火時にガストーチを使ってジェネレーター部分を加熱してやれば予熱時間は最短で済むのだ。
そりゃあガスほど簡単ではないけれども、限りなくガスに近い使い勝手の良さがある。
コイツが来てから料理、特に炒めものが楽しくてしょうがない。
だがしかし、そんなに食事は要らないし、炒めものばかりというわけにもいかない。
ああ、火が、鍋が呼んでいる……。
炒めたい、炒めたいとオレを呼んでいる。
だがしかし、それは出来ない。
だってアタシまだダイエット中ですもの!