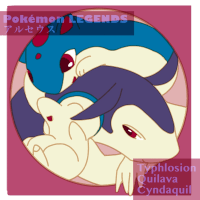今夜はレネーゼ侯爵家の庭を中心として開かれる、月見の夜会だ。
月の趣と灯りの華やかさが、絶妙の雅で催されている宴の華やかさの裏で、ジュードは、己の任務を軽く考えていた事を後悔していた。
(一体なにがどうしてこうなった?!)
侯爵家の定例夜会で、次期後継者の護衛筆頭を任されたのは初めての事ではない。
ジュード・フォルダー。
齢四十を前にして、そろそろ昇格の話も耳打ちされる中間管理職。
侯爵家の護衛任務も10年目を迎え、実績と経験も十分、人生半ばにして安泰を手に入れた上々の歩みだ。
そんな中で任される、後継者の護衛筆頭。
過去に3度、この役目を果たしてきたジュードは、残り二名を未経験の新前から選んだ。
そろそろ自分たちの下の世代にも、定例夜会ほどの規模の大きな場での要人警護を経験させておきたかったからだ。
そういう意味では、侯爵家若君の護衛が初任務として適度だと判断した。
決して若君の立場を軽んじているわけではないが、彼はまだ候主の従属の域から出てはいないし、自由意志で行動するわけでもない。
夜会では迎える側として来賓者に挨拶をするのが主だから、常に中央に構えている。護衛する側としても難易度は高くない。
「まあそう緊張するな、俺に任せてお前らは夜会の華々しさでも楽しんでおけよ」
当日までは、この大役に抜擢されて緊張している二名に、軽く笑って見せる余裕もあったのだが。
この夜会での若君は、別人のように活発だった。
若君が候主の元にいたのは、ほんの小一時間だろうか。
「皆様方にご挨拶をしてまいります」
と、その姿がその場を離れた事にジュードは残り二名に、大広間を双方で掩護できる範囲に留まるよう指示を出す。
それをあざ笑うかのように、若君の姿は広間から消え失せた。
(どういうことだ)
広間の賓客へのご機嫌伺いではないのか。
勿論、護衛筆頭を任されるこの自分が護衛対象の若君を見失うことはないが、新前の二名は予想外の事態についてこれていない。
二人を呼び、若君を追わせるだけでも一苦労だ。
自分たち護衛は華やかな席で目立つわけにはいかない。若君は自由自在に移動しても、自分たちには制限がある。
人のいない廊下を選び、立ち入れない部屋を迂回し、庭から庭へ、館から館へ、人目につかない様、宴を妨げない様行動する。
それを難なくやってのける二名を選んだとはいえ、ここまで若君に振り回されるとは思いもしなかった。
後を追う事は二名に任せ、ジュードは他の護衛との連携にも神経を向けなくてはならない。
若君の移動する先、挨拶をする相手の把握、その方々についている護衛との接触、先々でありとあらゆる連絡を取り合い、移動を明確にしておく。
これだけ派手に動かれると、その連絡網も混乱しているかもしれないな、と思ったがどうしようもない。
事前にこれを把握しておかなかった自分の手落ちだ。
そこに、別の要人警護を担当する同僚が足早に近づいてきた。
「アルセス様はもうリフォルゼ侯爵の部屋に戻られたのだったかな」
「いや、アルセス様ならついさっき、若君と池の東屋に向かわれた。至急か?」
「リフォルゼ侯爵に挨拶をしたいと公の方が来られたようだ。アルセス様もお顔を出した方がいいと思うが」
「解った、お話が済み次第、お伝えしてみよう」
上の方が一人動くだけで、数十人の人間が動く。それらすべての動機を把握し、混乱が生じない様前もって配置図も頭に入れておく。
そういう煩雑さがないのが若君の警護の良い所だと思っていたのだが、見事にその大渦に巻き込まれている。
あの二人には厳しいな、と判断し、ジュードは自分でそれを請け負った。
若君が向かったという池の東屋、そこへ続く庭へ降りる寸前、ジュードの肩を同僚が叩いてくる。
「なんだ、至急か?」
「いや、お前大変な時に筆頭を受けたな」
「何」
「若様は化けるぞ」
「はあ?」
「という見方だ。対応を間違えるなよ。ああ、アルセス様には迎えを出す」
頼んだぞ、と言って廊下の向こうへと去っていく。
化ける。うんそうだな、確かにもう化けてるな。と思いながら、ジュードも池の上に張り出した東屋へと向かった。
こんなに積極的に諸侯の方々に働きかけている若君の姿は想像だにしなかった。
華やかな場に埋没することなく注目を集め、堂々と上の方々と渡り合っている。そういう教育を受けているのだろうが、
自分ならあの歳で、ここまで臆することなく、一挙一動で周囲を圧倒することはできないだろうな、と思う。
旅から戻ってきた若君、あれは魔物か何かが化けているのかもな、などとつまらないことを考えながら、庭を回り池へ着く。
東屋から少し離れた場所で待機している二名に様子を訊ねて、機会をうかがっている間に別の護衛が到着した。
リフォルゼ侯爵家の護衛だ。
互いに確認しあい、リフォルゼ家の護衛は自身の主に用件を伝えるため東屋へ入る。
池から月を鑑賞し、対岸の園遊の様子を眺める東屋だ。四方に壁はないので会話はそれとなく聞こえてくる。
「ではなミカヅキ、次はわが夜会に招待しよう。うちの娘たちも喜ぶだろう」
「あまり姫君の期待を高めないでいてください。お会いした時に失望されるのは痛ましいので」
「何を言うか、そろそろお前も2,3の姫君を手玉に取るくらいの器量を身に付けんか」
ああ、見合いか。そうだな、そろそろ年頃でもあるし、そんな話も増えるだろうな、と考えているうちに東屋から護衛が離れた。
後に、リフォルゼ家の次期後継者であるアルセスが出てくるのに最敬礼をし、目の前を行き過ぎるのを待つ。
「少し下りになっております、お足元にご注意ください」
小径の先に控えさせていた一人が、アルセスを先導する護衛に角灯を差し出したが、この径は慣れているので、と断られている。
彼が指した先を見ればもう一人、灯りを持っているのが見えた。そこまでは大丈夫か、とジュードも二人に控えるよう合図を送る。
護衛とアルセスの無事をそれぞれに見送りながら、池の向こうへと灯りが遠くなるまで待ったが。
東屋から、自分たちの主が出てこないことに顔を見合わせた。
ここは筆頭である自分が行かねばならない。
ジュードは、先ほどの護衛がとった行動と同じに、東屋の入口まで進み、膝をつく。
「若様、どうかされましたか」
東屋にかかる四隅の灯篭の灯りでは、中で座っている人影は見えても様子までは詳細に知ることができない。
物陰から声をかけると、意外な言葉が返ってきた。
「大丈夫だ、少し寝る」
その返事には耳を疑う。
「寝る、とは」
「言葉通りだ、30…、いや20分で起こせ」
そう言われても承服できることではない。
「お体を冷やしてしまいます」
池の上に張り出した東屋だ。それにこの季節、上の方々は優雅さを競い合うので衣装も薄い。
傍まで近づいた方が良いか、迷う。自分の立場ではそう易々と声をかけていいものでもない。
一介の従者が、次期後継者ほどの方に語り掛けることはまずないので、自分の言葉遣いが正しいかどうかの不安もある。
(だが若君は、あきらかに様子がおかしい)
そう考えた時、冷やしたいんだ、という声が聞こえた。
その不穏な意味を考えようとした時、音もなく隣に寄ってきた一人が、小声で耳打ちをする。
「アルセス様の勧めで」
強いご酒を過ごされたようで、と続いた声はさらに小さく聞き取れないほどではあったが、十分に理解はできた。
ジュードにも覚えがある。年配の者が年下に強い酒を強要する事は、上流も下流も変わりはないのだな、と。
これを飲めるようになったらお前は一人前だ、などとは、もう酒宴の決まりごとのようなものだ。
だがそれで若君に何かあれば、と、二人が責を感じているのだと理解して、ジュードはその肩を叩く。
大丈夫だ。これはお前たちが口を出せる立場ではない。あとでそう言ってやらねばな、と、立ち上がる。
その気配に、かすかに吐息交じりの声。
「わかった、10分だ」
そう言われ、それ以上は譲る気はない、と言外に込められることで、自分の行為も若君を追い詰めているな、と気づいたジュードは
大人しく引き下がるしかなかった。
「かしこまりました」
彼ほどの格を持つ人間ならば、無様な姿を人前に晒すことを許されはしないのだろう。それが一介の従者なら尚更。
わずか10分で、周囲に醜態をさらす危うさを押し込め、毅然と振る舞えるように立て直せるものだろうか。
屋根の下を出て、他の仲間と共にその場で待つ。
やはり同じように若君を案じている二人に目くばせをし、それまで以上に神経が張り詰める中、10分。
10分で東屋の中に戻り、灯りを灯すかどうか迷ったが先に声をかける。
「若様」
宴の中心から離れた静かな東屋で、身じろぎする気配。それから間もなく若君が身を起こし、立ち上がる様子を見せた。
わずかながら安堵している自分がいる。
ジュードは足元の角灯に灯りを入れ、主を待つ。
ほどなくして、上着を羽織りながらミカヅキが出てきた。
「ご苦労」
その声は、何事もなかったかのように平静だった。
黙って礼を取り、後に従う。
先に行くミカヅキに外で待っていた二人が道を空ける。
「あ、若様、先導なら私が」
「いや、いい。自分で持つ」
外に控えていた一人から角灯を受け取る様子もしっかりしている。
従者にまかせず、自分の手間は自分で済ませる、いつも通りの彼に見えた。
灯りのない庭を、手元の角灯だけで行かせることに不安がなかったわけでない。これが別の人物ならあり得ないことだ。
だがこの主は身の回りのことに手を借りないでいる姿勢を貫いてきた。
それに慣れてしまっていたジュードは、当然のようにミカヅキのすぐ後ろに着いたが。
「危ない!」
闇の中、足元の地面が緩い場所があったのか、ふいにぐらつく主の体をとっさに支える。
「だ、大丈夫ですか!」
「若様!」
他の二名も慌てて駆け寄って自分を取り囲むのを見て、ミカヅキは困惑したようだった。
「過保護もすぎるぞ、お前たち」
こんなふうに、きやすくミカヅキから言葉をかけられることなど、これまでになかった事だ。
「え?過、保護…?過保護、とは…」
「言葉通りの意味だが」
今度は、ジュードたちが困惑する番だった。
「いえ、我らはそれが役目ですので…」
「ええ」
そのわずかな間。
そうか、そうだったな、と言ったミカヅキがまた先に立って歩き出す。
思わず三人で顔を見合わせたが、すぐに彼の後を追った。
なんだ、これは。どういうことだ。いったい何がどうしてこうなった。
もう今夜だけで何度胸のうちでつぶやいたか知れない言葉を、またこうして繰り返している。
今まで通りの主でありながら、今まで通りではありえない事が起こる。
(若様が旅から戻ってからだ)
そう考え、魔物が若君に化けているのではないか、などとふざけた事を考えていた自分を笑えなくなる。
(まさかな)
と思ったのは、この灯りのない道をゆらゆらと揺れる角灯だけを頼りにしているからだろう。
「若様はまだ気ままな旅の感覚が抜けておりませんか」
本来なら、護衛程度の立場で直接に話をしていい存在ではない。
だが、若様は化けるぞ、と言った同僚の、対応を間違うなという言葉が引っかかっていた。
何が正しく、何が間違いなのか、ミカヅキの反応でしか推し量れない。
無礼な、と一喝してくれるならそれで安心もできただろうから、それでも良かったのだが。
「…うん、そうだな」
と、言ったミカヅキが立ち止まり、ジュードを振り返る。
「そのせいでお前たちには余計な混乱を押し付けているよな」
そんなくだけた会話をするミカヅキは初めて見る。
このままだと、迷惑をかけてすまない、などと言い出しかねない。まだ子供だとは言え、主にそれをさせてはいけない。
「構いませんよ、たいていの事ならいい刺激になります」
わずかに灯りを持ちあげ、ことさら明るい声音になるよう、ジュードは笑って見せた。
「刺激…、か」
少し気が抜けたような反応に、ジュードは続ける。
「何事もなく、なだらかな平穏な中では多少の刺激も欲しくなる、というのが人間ですよ」
その
言葉にしばし沈黙し、そういうものか、と呟いたミカヅキに、まさか化けてませんよね、などと言えるはずもなく。
そんな心中を知るはずもない後ろの二人が、そうですよ、そんなもんですよ、と無責任に同調している。
(お前ら言葉遣いが軽いぞ)
だが彼らもまた、このあり得ない事態に、身の置き所がないのだろうなと思えば諫めることもできない。
それが功を奏したのか、自分を護衛している人間を一人ずつ確認するように見やったミカヅキが、そうか、と再びジュードを見た。
「じゃあ…、この近くに、衛兵の小屋はなかったか」
と尋ねられ。
それがどのような意味を持つのか考える間もなく、体が冷えた、と悪びれもせず言うミカヅキに思わず呆気にとられる。
まさか、だから言ったじゃないですか!と言うわけにもいかず、ええと、とジュードが口ごもれば、背後の一人が右手を示す。
「そこの脇を下ったところに、簡易の小屋がありますが」
今は誰も詰めていないかと、と言うのに、ミカヅキが、それでいい、と応じた。
「湯を沸かすくらいできるだろ」
つまり体が冷えたので衛兵小屋で温かい飲み物をご所望らしい。
もうこれだけでも十分な異常事態だが、それに続く会話も尋常じゃない。
「とんでもない!若様に白湯など出せませんよ!」
「そうですよ、私でも茶を淹れるくらいはできますので!」
と続ける二人に、ジュードは、おいおいお前ら若様を衛兵小屋に招待する気か、安い茶を出して良いと思ってんのか、と
これ以上は止めた方が良いのか、ここは敢えて見て見ぬふりをするのがいいのか、迷いに迷う。
対応を間違うなよ、という言葉の重さが、今更ながら抱えきれない荷となってきた。
それも数秒。
先に行って使えるかどうか様子を見てまいります、と一人が先に駆けだす。
「あ、おい、灯り…」
それを追って、ミカヅキが自分の角灯を手渡そうとすることに、もう主従関係の有無があいまいになっている。
「いやー平気ですよ、奴は暗闇専門なので」
同僚といるような錯覚に陥っているのか、主にそんな口をきいている部下には、さすがにジュードも声を荒げる。
「おい!」
「あっ、も、申し訳ございませんッ!!」
可哀想な事をした、と思うほど、我に返った部下は恐れおののき、その場で文字通り飛び上がり、足を踏み外して体制を崩した。
それに慌てて手を伸ばし体を支えてやったのは、ジュードとミカヅキと、同時。
その場で三人が固まり、この始末をどうしようかとそれぞれに窮地に追いやられている間に。
「そう怒るな、いい刺激なんだろ」
そう言ったミカヅキの声音が柔らかいことに救われた。暗闇では表情までは解らないが、おそらく、流してくれたのだろう。
先にミカヅキが手を離し、ジュードが強く引いて体制を立て直すのに手を貸せば、彼はミカヅキに最敬礼をとる。
「ご無礼をいたしました!」
「いや、今宵は観月。灯りの宴だ。月明かりの届かない場所での無礼を見咎めるのは無粋というもの」
と、まるで詩でも読んでいるかのような優雅な口調で空を指す。つられてそちらに目をやれば、月が雲に隠れている事に気が付いた。
だからこんなに暗い、と思っていると。
「と、いう事にしておけ」
と軽い口調で、それまでの切迫した空気を振り払ってしまった。
まだ16,7の身でも、生まれながらにして上に立つ者としての才覚は疑うべくもない。
ジュードたちの手落ちを問わないと同時に、自分の今の奔放も見逃せ、と場を和ませることも含め。
ジュードは無言で敬礼をすることで、この場を流してくれたことに謝意を表した。
「では、参りましょうか」
様子を見に行った仲間を追うように、部下をミカヅキの前に立たせ、先に進むように促す。
「ここから下りなので、ご注意を。躓くと止まれませんよ」
と、ミカヅキの後につき、ジュードが声をかければ、ミカヅキは笑ったようだった。
「躓いたら、お前にぶつかればいいんだろう?トリオス」
ああ、トリオスを先に立たせた理由をちゃんと理解している。
そのこともジュードの気を引いたが、何よりも、トリオス、と名前を読んだことに驚いた。
「どっ、どうして私の名を」
驚いたのは彼も同じ、いやそれ以上か。思わず背後を振り返り、ミカヅキとジュードを交互に見やる。
「…なぜ、そんなに驚くか」
勤めてくれている人間の名前くらい解っていて当然だ、とミカヅキは。
「先に行ったのがウォルター、お前がジュードだろう」
と何でもない事のように、背後のジュードを振り向いて言うが。
こんな末端の護衛まで見知っていてくれているのか、という思いに胸は熱くなる。
旅に出て屋敷を空けているばかりの主だが、確かに自分たちの主なのだ、という思い。
ご苦労、と言われるその言葉の意味。
飾りではなく、真に、主は自分たちをねぎらって言葉をくれているのだと信じられる。
「光栄です」
それ以上は言葉にならない。
このことがジュードたちにどれほどの衝撃を与えたのか、などと思いもよらないのだろうミカヅキが
「大袈裟だな、幾ら観月でも大手合いは控えるぞ」
と、夜会の言葉遊びを言いかけ。
いや、と、その場で硬直する。
「…今のは言ってはまずいことなのか、…ひょっとして」
護衛二人の反応が異常に熱っぽいこと、感極まっていることに、ようやく気が付いたようだった。
主がそれを口にすべきことでないのかどうかは、自分たちには解らない。ただ、このような経験は過去に一度もなかったと思う。
どう反応していいか解らず、思わず立ち止まっている護衛二人を見て、ミカヅキも動揺したようだった。
今のは聞かなかったことにしてくれ、と、つぶやくように言う。
それにもどう反応すべきか迷うジュードより早く。
「誰も聞いていませんよ、月明かりの届かない今だけの話ですからね」
と、トリオスが精いっぱい虚勢を張り、そう言ってのけた事に、救われた。内心で称賛する。今だけだ。
今だけは、きっと主と歳の近いトリオスの感覚が正しいのだろう。
先ほど自身が言った言葉で切り返されて、ミカヅキも失笑するしかない様だった。
「いや聞いてないならいいんだ」
「ええ、はい、急ぎましょう。せっかくのお茶が冷めてしまうやも」
き易く、そんな軽口を叩けるのも若気の至り様様だな、とジュードは選んだ二人の助力を痛感する。
周囲を難なく圧倒するほどの才覚を、常に維持していることは、やはりミカヅキであっても負担であるのだろう。
ここで軽口を叩ける相手がいることに、重要な意味があるのかもしれない。
「あいつは本当に茶を淹れられるのか」
「酔いを醒ますほど苦いですよ」
と、ジュードもこの戯れに乗れば、「…それは良いな」と、先を行くミカヅキが本音をこぼしたように思えた。
(ああ、そうか)
若様は化けるぞ、と言っていた同僚の言葉がようやく解った気がした。
かつて、正統後継者として屋敷中の人間に慕われている若君がいた。
まだ少年兵だったジュードも、彼が候主となる日の事を疑いもしなかった。
人柄も良く、誰からも慕われていた。諸侯らの覚えも良く、領地もこぞって彼の継承を待ち望んだほどの若君だった。
彼の人のためになら命を代えてでもお守りするのだと、人生のすべてを彼に捧げるつもりで鍛錬した。
そんな自分の若い時代を思い返し、新前たちにもミカヅキという主を唯一無二の主だと、お前たちだけの主なのだと、
命を賭して余りある方であると身をもって解らせるつもりで今夜の夜会に指名したのだ。
自分は主を喪ってしまったから。
もう二度と、あのような忠義はないのだと思っていたから。
せめて若い世代に託そうと、考えていた己の浅はかさを思う。
ミカヅキという次なる正統後継者に、全てを捧げる人員を育てることが、自分の新たな忠誠の誓いだと思っていたけれど。
ミカヅキは、化ける。
まだ少年の域も出ない主は、成長し、後継者としての階を着実に上っていく。
(我らは今、それに立ち会っている)
初めから後継者として立つ若君に頭を垂れる自分は、過去にしかいない。
完成された後継者は、過去にしかいないのだ。
(対応を間違ってはならない)
一度主を喪った自分にできることは、今ある新しい主の正しい姿を見ることだ。
そして、確実に上り詰めていく姿を見上げる事になるだろう。
地へ向けていた視線が、天を向く未来は、輝かしい。
新しい主は、それをひとつひとつ見せてくれるのだ。
観月夜会は、集う貴族たちに次期後継者という月を捧げたのではない。
自分たち従者にも、正真正銘の主を下されたのだ。
陸 ジュード 4 フォルガー
海 ウォルター 0 パゼロス
空 トリオス 2 トゥーナ