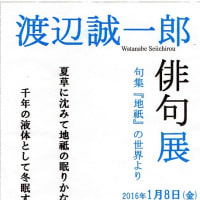今村明恒の日記を最初にご紹介いたします。ですが、「くだまき」本編はこの日記の後に語っております。
日記は、参考として頂ければよろしいかと存じます。ですが、今村のこの記録は割愛すべきではないと判断し、特に1日部分は全文掲載といたしました。
携帯での御高覧でありますれば、かなり読みにくいと存じます。
ご容赦下さいませ。
先に、申し上げました通り、この日記の後の部分でも十分に酔漢の真意は伝わることかと考えております。
「関東大震災」この災害を予測し得た一物理学者の数奇な運命とこの史実を語ります。
その日の朝、文京区本郷にある東京帝大の地震学教室に出勤していた八月下旬に私が訪問した北海道の樽前山の噴火の写真を並べて見ながら、よく撮れている、と皆で感心していた、ちょうどそのとき、正午から一分一六秒前のことだった。あの大地震が襲ってきたのだ。しかし最初は、それほど大きな地震だとは思わなかった。
いつも地震のときにはそうするように、座ったまま初期微動の継続時間を数えた。主要動が来るまで一二秒であった。
その初期微動の途中から振幅が見る見る大きくなって、いや、これはずいぶん大きな地震だぞ、とは感じた。だが、それでもまだあんな大地震とは、まだ思っていなかった。そのうちに主要動が来て、屋根の瓦が動き出し、次々に落ち始めた。しかも地震の揺れは私の予想を次々に裏切って、建物の揺れはさらに激しくなっていった。
そして初動から一五~一六秒後、つまり主要動になってから三~四秒経って地震の揺れは最大になった。揺れの方向は、北西と南東方向を往復するものであった。建物はあちこちできしみ、屋根の瓦が飛び散って、耳を聾するばかりの騒音があたりに満ちていた。
地震学教室にいた者たちのうち一人か二人は建物の外に飛び出したようだが、多くは私と同じように室内にとどまっていた。なかには、素早く、やや離れたところにある地震計室に飛んでいった者もあった。いままで東京で感じたことがある大きな地震ならば地震の揺れが急に小さくなって収まる頃をすぎても、今度の地震だけはそうではなかった。揺れが最大を記録した後も、ゆらゆらとゆっくりした揺れが一向に収まらずに、ただ揺れの周期だけが延びたような感じであった。なんだか大船に揺られているような気持ちだった。
そして、そのゆっくりした大揺れが収まらないうちに、早くも大きな余震が起きて、大きくて早い揺れが襲ってきて肝を冷やした。
やがて揺れも、ようやく次第に小さくなった。私は教室員たちに地震計の点検を命じた。私がまずやったことは、地震計が記録したばかりの記録紙を記録ドラムから取り外して持ってこさせ、その記録を読みとって解析を始めることだった。
●私はかつて、日本の「外側大地震群」中、相模湾の部分が、大地震を起こす可能性がありながら過去の歴史に大地震の記録がないので将来大地震が起きる場所として想定していた。
じつはこの想定は、私が世間に発表して以来、二〇年近くの長年にわたって、私に茨の道を歩かせたものだった。亡くなった故郷の鹿児島の父にも「ありもしない大地震の予測で世の中を騒がせた」という報道や非難ゆえに、多大の心配をかけた想定でもあった。
教室員が持ってきた地震計の記録紙を見た瞬間、これは私が想定していた場所で起きた地震だと直感した。揺れかたは東京直下型の地震でもなく東京湾に起きた地震でもない。地震の揺れはじめの方向と主要動までの到着時間差が、明瞭にそれを裏付けていた。
●大地震から三〇分ほど経っていた。早くも二〇人ほどの新聞記者たちが駆けつけて来た。うち二人は外国人記者だった。彼らは私の説明を聞きに来たのである。
私は次のように発表した。「この本郷での発震時は午前一一時五八分四四秒で、震源は東京の南方二六里、つまり伊豆大島付近の海底と推測される。ここ本郷では振幅が四寸にも達する大きな振動だったから、東京では安政地震以来の大地震になる。もし震源が海底であるという推定が間違っていなければ一時間以内に津波が襲ってくるかも知れない。その場合津波は相模湾、とくに小田原方面では大きいだろう。しかし東京湾では津波の振幅は小さくて無事だろう。今後多少の余震活動は続くだろうが、あれほどの大地震が繰り返すことはない」
そして、さらに食い下がる外国人記者の質問に対して、この地震は火山性の地震ではなく構造性の地震だということも付け加えておいた。
記者たちに、この発表をしている最中の午後〇時四〇分には、余震の中でも最大級の地震が起きた。記者の中には驚いて屋外へ駆けだした者もいた。しかし私が室内から笑って見ていたので、きまり悪そうに「もう大丈夫でしょうか」と恐る恐る聞きながら帰ってきた。
このときに感心したことは、外国人記者は私の姓名をカタカナ書きで正確に、そして姓のローマ字綴りまで聞かれたことだった。一方、日本人の新聞記者たちは私の名前さえ確かめなかった。私の名前を、そのときはオーストラリア出張で不在だった大森房吉博士と間違って報道した社も一つ二つではなかった。大森先生にもご迷惑なことであろうと苦笑せざるを得なかった。
●こうして記録紙を点検し記者発表も終えたので、はじめて教室の建物の玄関から出てみると屋根の瓦が何枚も落ちかかっていた。これら危ない瓦を突き落として玄関の出入りを安全にしておいてから、大学の内外の様子を見ようと、大学の前を通っている本郷通に向かった。
まず帝大の正門に向かうと、法文学部新館の煉瓦建築の蛇腹が崩壊しているのに驚き、さらに進むと今度は工学部の応用化学教室が燃えていたので、さらに驚いた。正門から本郷通に出ると、通りの大学側は、反対側に広がる民家から飛び出してきた人々で埋まっていた。通りの向こう側の商店の屋根瓦はほとんど形をなしていなかったり崩落したりしていたし、土壁の多くも崩れ落ちていた。それだけではない。遠く南のお茶の水方向には火の手が上がっていた。
●ここにいたって私はようやく、これは容易ならざる事態が起きたということを実感した。折悪しく風も強まってきていた。かつて私が警鐘を鳴らしていた地震後の大火災が現実にならなければいいがと心配しながら、急いで教室に戻った。教室で、机の上に拡げていた北海道の樽前火山の噴火の写真などを片づけていたところ、今度は教室から風上に当たる大学の中央図書館あたりから煙が吹き出した。医化学教室から出火した火が図書館に燃え移ろうとしているという情報が入った。私はしかし、まだ油断していた。図書館から地震学教室までの間には法文系の旧館や新館や八角の大講堂があるが、いずれも煉瓦建築で耐火性があるから類焼はせずに自然に鎮火するに違いないと楽観していたのだ。
●だが事態は刻一刻悪化して私の予想を裏切っていって火の手が教室にも迫ってきたのであった。このため教室の金工場や木工場の職工や小使いたちを私が指揮して屋根に登らせ、飛んでくる火の粉を防がせた。また中では教室員を指揮して、もっとも重要で焼けたら困る地震計の記録紙など、貴重な資料を外へ運び出させた。私も大わらわになって飛び回った。しかし図書館で煙が見えてから約一時間後には、火は早くも地震学教室の隣の数学教室にまで燃え広がってきていた。 教室も風前の灯火である。しかも大地震のために屋根瓦が落ちてしまって瓦を支える木材が露出してしまっている。もっとも延焼しやすいものが火の粉に曝されているのである。教室の屋根も三回にわたって燃え上がった。しかも水道は地震で地下の配管が壊れてしまったのか、一滴の水も出ない。しかし職工たちは勇敢だった。あっちだ、こんどはそちらだ、という下からの指示に従って屋根の上を平地の上のように飛び回って、燃え上がった火を踏みつけて消したり、箒で掃き落としたり、また、燃え上がってしまった部材は剥がして屋根から落としたりして、水のない消火に努めてくれた。こうして二〇分ほどの奮闘のあと、幸い風向きが東に変わってくれた。数学教室からの火の粉は、教室ではなくて西のほうに飛ぶようになったのである。こうして地震学教室は窮地を脱することができた。じつは教室の火消しに必死になっている間、やや離れたところにある地震計の観測室が危ないという情報も来ていた。しかし教室の火の手を防ぐだけで精一杯で、どうすることもできなかった。地震計室には地震計はあるが、過去に取った記録は教室に保管してあったからすでに運び出していた。失うとしても地震計だけである。教室の火が一段落したので、教室員に見に行かせると、幸い、化学教室の人たちが類焼を防いでくれたことが分かった。不幸中の幸いであった。だが、その後風は一層強くなった。しかし風向きが北になったので、理学部の本館も類焼の恐れがなくなった。すでに午後六時になっていた。私の自宅が気にならないわけではなかった。午後四時頃、長男が自転車を飛ばして駆けつけて来て、家族の無事を知らせてくれた。これで初めて安心したものの、家そのものはいまにも潰れそうなくらい傾いてしまったという。私が帰宅するまで、家族は家に入らず、外に居なさい、と伝えた。余震で倒壊したら命の問題だからである。
●教室はこうしてひとまずの危機は脱したので、大学のまわりはどうなっているだろう、と周囲を見渡せる新築中の工学部の屋上に行ってみた。そこからは凄惨な光景が広がっていた。東にある上野の山を越えた彼方から、南にある麹町、さらに西にある新宿方面まで、真っ赤な火の手と煙が入道雲のようにわきあがっていた。(この入道雲が、火災によって生まれた火災旋風が作った積雲であったことは、あとで寺田寅彦博士に聞いた)。 立ち上っている真っ赤な煙は、見えているだけで二〇数条にもなっていた。中には二重三重になっていて奥にあるものは見えていないものもあるだろうから、もっと多いに違いない。
●折悪しく、風も強まってきていた。ああ、これでは、かねて私が警告していた東京の大震災が現実になってしまうのではないだろうか。私の警告は「学術的な根拠のない浮説」とか「治安を妨害する憶説」とかいって非難され嘲られていたが、それが現実に起きてしまう、なんという不幸なことであろう。うなだれて教室に帰ってくると、今度は地震計の観測室がまた危ないという知らせが来た。よし来た、とばかりに、屋根の上で大活躍してくれた職工たちと、消火用の梯子を担いで駆けつけた。もし観測室が燃えてしまうと、火は隣の化学教室、さらにはその隣の大学病院にも延焼する。大火災になってしまうのである。このため、防火の応援の人手が、今度はたくさん出てくれていた。化学教室の人たちはもちろん、近藤病院長や入澤学長まで駆けつけてきていた。屋根では医科の助手が先ほどの地震学教室の職工たちの働きを圧倒するように活躍していた。また病院から出てきた二〇〇人ほどの看護婦たちも人海作戦で消火作業のなかでも、この水が効いた。午後九時には、この火も消し止められたのであった。
●こうして、ようやく一段落してみると、改めて腹が減っているのに気がついた。考えてみれば朝飯以後はなにも食べていなかったのである。友人である大谷文学士が、とりあえずの食べ物を調達してきてくれた。午後一〇時になっていた。燃えてはいけない、と教室から運び出していた地震計の記録紙や貴重品も、ふたたび教室に運び込んだ。時間も遅いので遠くに住む教室員をまず帰宅させ、家の心配がない独身教室員などで徹夜の地震観測をしてもらうことにして、私は午後一一時頃に大学の門を出た。しかし本郷南方に火の手が広がっていたから、いつもの通り道ではなくはるかに迂回せざるを得なかった。東大久保の自宅にたどり着いたのは翌日、午前一時になっていた。
家を見てみると、幸い余震で崩壊するほどの被害ではなかった。心配顔で集まってきた近所の人たちに、もはや大地震が来ることはないので安心するように、と告げ、家族にも、家の中で寝なさい、と屋内で寝かせることにした。
重ねて、今村明恒の日記。関東大震災当日のものです。
今村は、この地震を予測し、発表しております。
太字で記した部分です。(寺田寅彦の部分も同様です)
「先生(大森房吉)、やはり、どう考えても、関東で大きな地震が来ます。これは本当です。先生はどう思われるのですか」
帝大、理学部、大森研究室。
教授、大森房吉は日本地震学の祖とも言うべきその先端におります。教授です。大森の公式(震源特定の公式→地学の教科書に載っていたなぁ・・・・)立案し地震計を作った。
「何を馬鹿なことを言っているんだ。人々の動揺を君は知らんのかね!あんな発表をして、東京が嘘やうわさで大騒ぎの状況を君は知らんのかね!」
「しかし、先生!」
「今すぐ訂正文を掲載するんだ!今だ!・・・・イマスグニダ!」
「間違い・・・だとは思っていません!」
私はかつて、日本の「外側大地震群」中、相模湾の部分が、大地震を起こす可能性がありながら過去の歴史に大地震の記録がないので将来大地震が起きる場所として想定していた。じつはこの想定は、私が世間に発表して以来、二〇年近くの長年にわたって、私に茨の道を歩かせたものだった。亡くなった故郷の鹿児島の父にも「ありもしない大地震の予測で世の中を騒がせた」という報道や非難ゆえに、多大の心配をかけた想定でもあった。
「おおかみ少年」有名な童話です。
今村は、たった一回の論説発表によって「おおかみ少年」に仕立て上げられたのでした。
明治38年(1905年)雑誌「太陽9月号」に今村は論説を掲載いたします。
「市街地に於ける地震の損害を軽減する簡法」というものです。
安政大地震より50年目の年。
今村は「江戸に甚大なる被害を及ぼした『慶安二年の地震』から54年後に『元禄地震』が発生している。大地震は近未来的に発生する」と論じました。
雑誌「太陽」だけでは、それほど大騒ぎにはならなかったものの、四か月後「東京二六新聞」が「今村博士の大地震襲来説、東京市大羅災の予言」と報じます。
「年の丙午、凶か吉か、あるひは言いつたへられているやうな丙午の年には火災が多い。現に今年は新年以来各所で火災が発生、閑院邸も焼けたのを見よ。あるひは丙午の年には天災が多いとも言われる。現に新年以降二回の強震があり、大森海岸には津浪さへあつたの見よ」その記事の後半「帝大今村博士が大地震襲来を予言」とあります。
この記事が多くの大衆を扇動し、パニックを引き起こしております。
これには、数多くの問題点が潜んでいるということに気づきます。
メディアはやはりその部数を伸長させることで、その存在価値が生きてきます。
「予言めいた記事」はこれは今現在でも一面を飾ることが多い。
「東京二六新聞」もそれによった記事だったと推察いたします。
(某夕刊紙の一面「○○大発見!・・・・か」←「か」が小さくなっていたりいたします。それ適なものかと・・)
しかし、当時の大衆はこれで大騒ぎとなりました。
「本意ではない。私は震災での防災強化が必要と言っただけだ!しかも丙午とは言ってない」
今村は、そう語りますが、もうすでにそうはいかない状況です。
今村は一旦孤立しそうな状況になりますが、同年1月24日の「萬朝報」では、その今村の真意について掲載し、この騒ぎは収まりかけました。
同年、2月23日 千葉沖地震。24日 東京湾地震。これは横浜の煙突が倒壊している。
この二つの地震が再び、「首都大震災予言」を人々が思い出す結果となります。
大森は、ことの鎮静化に努めます。
「私が思うところ、東京大地震は浮説極まりない話しで、二十万人もの死者に至っては笑止と言うほかない。今村博士の話すことはありえない。今後、百年は大地震は起こらない。東京のような近代的な都市にいたっては大火災は起こらないのある」
当時大森は帝大教授。今村は助教授。この差も人々の信頼するべく材料になります。
「大森先生がああ言っているのだから」
何故か、人々は安心するのでした。
今村は自身の妻にこう漏らしております。
「友人からは大法螺吹きと呼ばれ、鹿児島の父からは勘当。挙句『私利私欲の為に嘘をついた』とまで言われている。関東大地震は必ず50年内に起きる。俺が死んだら墓前に報告してくれ」
今村の警告から十八年後。
冒頭の通り「関東大震災」が発生致します。
折悪しく、風も強まってきていた。ああ、これでは、かねて私が警告していた東京の大震災が現実になってしまうのではないだろうか。私の警告は「学術的な根拠のない浮説」とか「治安を妨害する憶説」とかいって非難され嘲られていたが、それが現実に起きてしまう、なんという不幸なことであろう。うなだれて教室に帰ってくる。
大森房吉は病を押して「汎太平洋学術会議」副団長としてオーストラリアシドニーにおります。
7月10日に日本を出発したものの船中から体調が悪く、嘔吐の連続でした。
大森の責任感だけが、彼をオーストラリアへ向かわせたのです。
9月1日正午。
彼はシドニーにあります「バビュー天文台」におります。くしくも、ドイツ製新型地震計の目の前。
揺れを感じました。
「な!なんだ!この揺れは!地震計の針が!針のぶれが通常ではない」
周りにいた、海外の学者達も驚きます。
「豪州内での地震?」
「あり得ない!震源は!・・・・どこなんだ!」
新型地震計の記録。それを頼りに大森はすぐさま震源域を計算致します。
ペンを取り、計算が終わった瞬間。大森の顔が蒼白となります。
「先生!・・・先生!しかして、震源は!震源は!どこなんです!どこなんです震源は!」
大森は嘔吐しながら小さい声で答えます。
「と・・・・とう・・・きょう・・わん・・付近」
「先生!何と!」
「東京湾としか考えられん!豪州でこの揺れ。東京は?東京はどんな状況なんだ!」
現在、同天文台には、大森の立っていた場所を記し(足跡)、その地震計の記録も額に入れ展示されております。
「日本へ!早く日本へ!今村君と連絡を取らなくては!」
大森は、6日に一行とは離れ、ハワイ経由で日本へ向かいます。
途中、病状悪化の電報が帝大へ入ります。
10月4日、横浜着。
「今村君、大森先生が横浜へ着いた。即刻横浜へ!」理学部長からの命令。
その船中で二人は再開致します。
「先生」
「今村君か・・・君には・・・この震災には責任を私は感じている・・・」
船はちょうど午後三時に到着した。すぐに上船し、先生と面会したが、ご病気はかなり重いご様子で、衰弱も甚だしかったが意識だけは明瞭であった。
私が挨拶したのに対して、すぐに、息も苦しげに「今度の震災については自分は重大な責任を感じている。譴責されても仕方がない。ただし、水道の改良について義務を尽くしたことで自分を慰めている」と言い終わるか終わらぬうちに嘔吐を始められた。興奮による発作とのことだった。(10月4日 今村日記より抜粋)
関東大震災の年。大森はその任を今村、寺田等に預けるように、11月8日に亡くなりました。
大正14年(1923年)東京帝国大学内地震研究所設立。
各メンバーと研究内容。
地震計測器の研究→石本巳四雄
地震観測の整備・地震計の改良・微傾斜観測水準変動→今村明恒
構造物耐火試験・建築物の振動→内村洋三
中央気象台に於ける研究→岡田武松
構造物試験及び模型実験→末廣恭二
地殻及地震波弾性力学的研究→妹沢克椎
地形調査→多田文雄
火山調査・岩石閲覧歴的研究→坪井誠太郎
弾性波の生成及波及実験→寺田寅彦
高圧下の岩石の性質→長岡半太郎
捩・皺・庇割の研究→藤原咲平
材料強弱研究→物部長穂
地形調査→山崎直方
現在でも通用しそうなメンバー。
否、今すぐにでも、故郷の現状をこのメンバーで調査していただきたい。
こう考えてしまう、酔漢でございました。
日記は、参考として頂ければよろしいかと存じます。ですが、今村のこの記録は割愛すべきではないと判断し、特に1日部分は全文掲載といたしました。
携帯での御高覧でありますれば、かなり読みにくいと存じます。
ご容赦下さいませ。
先に、申し上げました通り、この日記の後の部分でも十分に酔漢の真意は伝わることかと考えております。
「関東大震災」この災害を予測し得た一物理学者の数奇な運命とこの史実を語ります。
その日の朝、文京区本郷にある東京帝大の地震学教室に出勤していた八月下旬に私が訪問した北海道の樽前山の噴火の写真を並べて見ながら、よく撮れている、と皆で感心していた、ちょうどそのとき、正午から一分一六秒前のことだった。あの大地震が襲ってきたのだ。しかし最初は、それほど大きな地震だとは思わなかった。
いつも地震のときにはそうするように、座ったまま初期微動の継続時間を数えた。主要動が来るまで一二秒であった。
その初期微動の途中から振幅が見る見る大きくなって、いや、これはずいぶん大きな地震だぞ、とは感じた。だが、それでもまだあんな大地震とは、まだ思っていなかった。そのうちに主要動が来て、屋根の瓦が動き出し、次々に落ち始めた。しかも地震の揺れは私の予想を次々に裏切って、建物の揺れはさらに激しくなっていった。
そして初動から一五~一六秒後、つまり主要動になってから三~四秒経って地震の揺れは最大になった。揺れの方向は、北西と南東方向を往復するものであった。建物はあちこちできしみ、屋根の瓦が飛び散って、耳を聾するばかりの騒音があたりに満ちていた。
地震学教室にいた者たちのうち一人か二人は建物の外に飛び出したようだが、多くは私と同じように室内にとどまっていた。なかには、素早く、やや離れたところにある地震計室に飛んでいった者もあった。いままで東京で感じたことがある大きな地震ならば地震の揺れが急に小さくなって収まる頃をすぎても、今度の地震だけはそうではなかった。揺れが最大を記録した後も、ゆらゆらとゆっくりした揺れが一向に収まらずに、ただ揺れの周期だけが延びたような感じであった。なんだか大船に揺られているような気持ちだった。
そして、そのゆっくりした大揺れが収まらないうちに、早くも大きな余震が起きて、大きくて早い揺れが襲ってきて肝を冷やした。
やがて揺れも、ようやく次第に小さくなった。私は教室員たちに地震計の点検を命じた。私がまずやったことは、地震計が記録したばかりの記録紙を記録ドラムから取り外して持ってこさせ、その記録を読みとって解析を始めることだった。
●私はかつて、日本の「外側大地震群」中、相模湾の部分が、大地震を起こす可能性がありながら過去の歴史に大地震の記録がないので将来大地震が起きる場所として想定していた。
じつはこの想定は、私が世間に発表して以来、二〇年近くの長年にわたって、私に茨の道を歩かせたものだった。亡くなった故郷の鹿児島の父にも「ありもしない大地震の予測で世の中を騒がせた」という報道や非難ゆえに、多大の心配をかけた想定でもあった。
教室員が持ってきた地震計の記録紙を見た瞬間、これは私が想定していた場所で起きた地震だと直感した。揺れかたは東京直下型の地震でもなく東京湾に起きた地震でもない。地震の揺れはじめの方向と主要動までの到着時間差が、明瞭にそれを裏付けていた。
●大地震から三〇分ほど経っていた。早くも二〇人ほどの新聞記者たちが駆けつけて来た。うち二人は外国人記者だった。彼らは私の説明を聞きに来たのである。
私は次のように発表した。「この本郷での発震時は午前一一時五八分四四秒で、震源は東京の南方二六里、つまり伊豆大島付近の海底と推測される。ここ本郷では振幅が四寸にも達する大きな振動だったから、東京では安政地震以来の大地震になる。もし震源が海底であるという推定が間違っていなければ一時間以内に津波が襲ってくるかも知れない。その場合津波は相模湾、とくに小田原方面では大きいだろう。しかし東京湾では津波の振幅は小さくて無事だろう。今後多少の余震活動は続くだろうが、あれほどの大地震が繰り返すことはない」
そして、さらに食い下がる外国人記者の質問に対して、この地震は火山性の地震ではなく構造性の地震だということも付け加えておいた。
記者たちに、この発表をしている最中の午後〇時四〇分には、余震の中でも最大級の地震が起きた。記者の中には驚いて屋外へ駆けだした者もいた。しかし私が室内から笑って見ていたので、きまり悪そうに「もう大丈夫でしょうか」と恐る恐る聞きながら帰ってきた。
このときに感心したことは、外国人記者は私の姓名をカタカナ書きで正確に、そして姓のローマ字綴りまで聞かれたことだった。一方、日本人の新聞記者たちは私の名前さえ確かめなかった。私の名前を、そのときはオーストラリア出張で不在だった大森房吉博士と間違って報道した社も一つ二つではなかった。大森先生にもご迷惑なことであろうと苦笑せざるを得なかった。
●こうして記録紙を点検し記者発表も終えたので、はじめて教室の建物の玄関から出てみると屋根の瓦が何枚も落ちかかっていた。これら危ない瓦を突き落として玄関の出入りを安全にしておいてから、大学の内外の様子を見ようと、大学の前を通っている本郷通に向かった。
まず帝大の正門に向かうと、法文学部新館の煉瓦建築の蛇腹が崩壊しているのに驚き、さらに進むと今度は工学部の応用化学教室が燃えていたので、さらに驚いた。正門から本郷通に出ると、通りの大学側は、反対側に広がる民家から飛び出してきた人々で埋まっていた。通りの向こう側の商店の屋根瓦はほとんど形をなしていなかったり崩落したりしていたし、土壁の多くも崩れ落ちていた。それだけではない。遠く南のお茶の水方向には火の手が上がっていた。
●ここにいたって私はようやく、これは容易ならざる事態が起きたということを実感した。折悪しく風も強まってきていた。かつて私が警鐘を鳴らしていた地震後の大火災が現実にならなければいいがと心配しながら、急いで教室に戻った。教室で、机の上に拡げていた北海道の樽前火山の噴火の写真などを片づけていたところ、今度は教室から風上に当たる大学の中央図書館あたりから煙が吹き出した。医化学教室から出火した火が図書館に燃え移ろうとしているという情報が入った。私はしかし、まだ油断していた。図書館から地震学教室までの間には法文系の旧館や新館や八角の大講堂があるが、いずれも煉瓦建築で耐火性があるから類焼はせずに自然に鎮火するに違いないと楽観していたのだ。
●だが事態は刻一刻悪化して私の予想を裏切っていって火の手が教室にも迫ってきたのであった。このため教室の金工場や木工場の職工や小使いたちを私が指揮して屋根に登らせ、飛んでくる火の粉を防がせた。また中では教室員を指揮して、もっとも重要で焼けたら困る地震計の記録紙など、貴重な資料を外へ運び出させた。私も大わらわになって飛び回った。しかし図書館で煙が見えてから約一時間後には、火は早くも地震学教室の隣の数学教室にまで燃え広がってきていた。 教室も風前の灯火である。しかも大地震のために屋根瓦が落ちてしまって瓦を支える木材が露出してしまっている。もっとも延焼しやすいものが火の粉に曝されているのである。教室の屋根も三回にわたって燃え上がった。しかも水道は地震で地下の配管が壊れてしまったのか、一滴の水も出ない。しかし職工たちは勇敢だった。あっちだ、こんどはそちらだ、という下からの指示に従って屋根の上を平地の上のように飛び回って、燃え上がった火を踏みつけて消したり、箒で掃き落としたり、また、燃え上がってしまった部材は剥がして屋根から落としたりして、水のない消火に努めてくれた。こうして二〇分ほどの奮闘のあと、幸い風向きが東に変わってくれた。数学教室からの火の粉は、教室ではなくて西のほうに飛ぶようになったのである。こうして地震学教室は窮地を脱することができた。じつは教室の火消しに必死になっている間、やや離れたところにある地震計の観測室が危ないという情報も来ていた。しかし教室の火の手を防ぐだけで精一杯で、どうすることもできなかった。地震計室には地震計はあるが、過去に取った記録は教室に保管してあったからすでに運び出していた。失うとしても地震計だけである。教室の火が一段落したので、教室員に見に行かせると、幸い、化学教室の人たちが類焼を防いでくれたことが分かった。不幸中の幸いであった。だが、その後風は一層強くなった。しかし風向きが北になったので、理学部の本館も類焼の恐れがなくなった。すでに午後六時になっていた。私の自宅が気にならないわけではなかった。午後四時頃、長男が自転車を飛ばして駆けつけて来て、家族の無事を知らせてくれた。これで初めて安心したものの、家そのものはいまにも潰れそうなくらい傾いてしまったという。私が帰宅するまで、家族は家に入らず、外に居なさい、と伝えた。余震で倒壊したら命の問題だからである。
●教室はこうしてひとまずの危機は脱したので、大学のまわりはどうなっているだろう、と周囲を見渡せる新築中の工学部の屋上に行ってみた。そこからは凄惨な光景が広がっていた。東にある上野の山を越えた彼方から、南にある麹町、さらに西にある新宿方面まで、真っ赤な火の手と煙が入道雲のようにわきあがっていた。(この入道雲が、火災によって生まれた火災旋風が作った積雲であったことは、あとで寺田寅彦博士に聞いた)。 立ち上っている真っ赤な煙は、見えているだけで二〇数条にもなっていた。中には二重三重になっていて奥にあるものは見えていないものもあるだろうから、もっと多いに違いない。
●折悪しく、風も強まってきていた。ああ、これでは、かねて私が警告していた東京の大震災が現実になってしまうのではないだろうか。私の警告は「学術的な根拠のない浮説」とか「治安を妨害する憶説」とかいって非難され嘲られていたが、それが現実に起きてしまう、なんという不幸なことであろう。うなだれて教室に帰ってくると、今度は地震計の観測室がまた危ないという知らせが来た。よし来た、とばかりに、屋根の上で大活躍してくれた職工たちと、消火用の梯子を担いで駆けつけた。もし観測室が燃えてしまうと、火は隣の化学教室、さらにはその隣の大学病院にも延焼する。大火災になってしまうのである。このため、防火の応援の人手が、今度はたくさん出てくれていた。化学教室の人たちはもちろん、近藤病院長や入澤学長まで駆けつけてきていた。屋根では医科の助手が先ほどの地震学教室の職工たちの働きを圧倒するように活躍していた。また病院から出てきた二〇〇人ほどの看護婦たちも人海作戦で消火作業のなかでも、この水が効いた。午後九時には、この火も消し止められたのであった。
●こうして、ようやく一段落してみると、改めて腹が減っているのに気がついた。考えてみれば朝飯以後はなにも食べていなかったのである。友人である大谷文学士が、とりあえずの食べ物を調達してきてくれた。午後一〇時になっていた。燃えてはいけない、と教室から運び出していた地震計の記録紙や貴重品も、ふたたび教室に運び込んだ。時間も遅いので遠くに住む教室員をまず帰宅させ、家の心配がない独身教室員などで徹夜の地震観測をしてもらうことにして、私は午後一一時頃に大学の門を出た。しかし本郷南方に火の手が広がっていたから、いつもの通り道ではなくはるかに迂回せざるを得なかった。東大久保の自宅にたどり着いたのは翌日、午前一時になっていた。
家を見てみると、幸い余震で崩壊するほどの被害ではなかった。心配顔で集まってきた近所の人たちに、もはや大地震が来ることはないので安心するように、と告げ、家族にも、家の中で寝なさい、と屋内で寝かせることにした。
重ねて、今村明恒の日記。関東大震災当日のものです。
今村は、この地震を予測し、発表しております。
太字で記した部分です。(寺田寅彦の部分も同様です)
「先生(大森房吉)、やはり、どう考えても、関東で大きな地震が来ます。これは本当です。先生はどう思われるのですか」
帝大、理学部、大森研究室。
教授、大森房吉は日本地震学の祖とも言うべきその先端におります。教授です。大森の公式(震源特定の公式→地学の教科書に載っていたなぁ・・・・)立案し地震計を作った。
「何を馬鹿なことを言っているんだ。人々の動揺を君は知らんのかね!あんな発表をして、東京が嘘やうわさで大騒ぎの状況を君は知らんのかね!」
「しかし、先生!」
「今すぐ訂正文を掲載するんだ!今だ!・・・・イマスグニダ!」
「間違い・・・だとは思っていません!」
私はかつて、日本の「外側大地震群」中、相模湾の部分が、大地震を起こす可能性がありながら過去の歴史に大地震の記録がないので将来大地震が起きる場所として想定していた。じつはこの想定は、私が世間に発表して以来、二〇年近くの長年にわたって、私に茨の道を歩かせたものだった。亡くなった故郷の鹿児島の父にも「ありもしない大地震の予測で世の中を騒がせた」という報道や非難ゆえに、多大の心配をかけた想定でもあった。
「おおかみ少年」有名な童話です。
今村は、たった一回の論説発表によって「おおかみ少年」に仕立て上げられたのでした。
明治38年(1905年)雑誌「太陽9月号」に今村は論説を掲載いたします。
「市街地に於ける地震の損害を軽減する簡法」というものです。
安政大地震より50年目の年。
今村は「江戸に甚大なる被害を及ぼした『慶安二年の地震』から54年後に『元禄地震』が発生している。大地震は近未来的に発生する」と論じました。
雑誌「太陽」だけでは、それほど大騒ぎにはならなかったものの、四か月後「東京二六新聞」が「今村博士の大地震襲来説、東京市大羅災の予言」と報じます。
「年の丙午、凶か吉か、あるひは言いつたへられているやうな丙午の年には火災が多い。現に今年は新年以来各所で火災が発生、閑院邸も焼けたのを見よ。あるひは丙午の年には天災が多いとも言われる。現に新年以降二回の強震があり、大森海岸には津浪さへあつたの見よ」その記事の後半「帝大今村博士が大地震襲来を予言」とあります。
この記事が多くの大衆を扇動し、パニックを引き起こしております。
これには、数多くの問題点が潜んでいるということに気づきます。
メディアはやはりその部数を伸長させることで、その存在価値が生きてきます。
「予言めいた記事」はこれは今現在でも一面を飾ることが多い。
「東京二六新聞」もそれによった記事だったと推察いたします。
(某夕刊紙の一面「○○大発見!・・・・か」←「か」が小さくなっていたりいたします。それ適なものかと・・)
しかし、当時の大衆はこれで大騒ぎとなりました。
「本意ではない。私は震災での防災強化が必要と言っただけだ!しかも丙午とは言ってない」
今村は、そう語りますが、もうすでにそうはいかない状況です。
今村は一旦孤立しそうな状況になりますが、同年1月24日の「萬朝報」では、その今村の真意について掲載し、この騒ぎは収まりかけました。
同年、2月23日 千葉沖地震。24日 東京湾地震。これは横浜の煙突が倒壊している。
この二つの地震が再び、「首都大震災予言」を人々が思い出す結果となります。
大森は、ことの鎮静化に努めます。
「私が思うところ、東京大地震は浮説極まりない話しで、二十万人もの死者に至っては笑止と言うほかない。今村博士の話すことはありえない。今後、百年は大地震は起こらない。東京のような近代的な都市にいたっては大火災は起こらないのある」
当時大森は帝大教授。今村は助教授。この差も人々の信頼するべく材料になります。
「大森先生がああ言っているのだから」
何故か、人々は安心するのでした。
今村は自身の妻にこう漏らしております。
「友人からは大法螺吹きと呼ばれ、鹿児島の父からは勘当。挙句『私利私欲の為に嘘をついた』とまで言われている。関東大地震は必ず50年内に起きる。俺が死んだら墓前に報告してくれ」
今村の警告から十八年後。
冒頭の通り「関東大震災」が発生致します。
折悪しく、風も強まってきていた。ああ、これでは、かねて私が警告していた東京の大震災が現実になってしまうのではないだろうか。私の警告は「学術的な根拠のない浮説」とか「治安を妨害する憶説」とかいって非難され嘲られていたが、それが現実に起きてしまう、なんという不幸なことであろう。うなだれて教室に帰ってくる。
大森房吉は病を押して「汎太平洋学術会議」副団長としてオーストラリアシドニーにおります。
7月10日に日本を出発したものの船中から体調が悪く、嘔吐の連続でした。
大森の責任感だけが、彼をオーストラリアへ向かわせたのです。
9月1日正午。
彼はシドニーにあります「バビュー天文台」におります。くしくも、ドイツ製新型地震計の目の前。
揺れを感じました。
「な!なんだ!この揺れは!地震計の針が!針のぶれが通常ではない」
周りにいた、海外の学者達も驚きます。
「豪州内での地震?」
「あり得ない!震源は!・・・・どこなんだ!」
新型地震計の記録。それを頼りに大森はすぐさま震源域を計算致します。
ペンを取り、計算が終わった瞬間。大森の顔が蒼白となります。
「先生!・・・先生!しかして、震源は!震源は!どこなんです!どこなんです震源は!」
大森は嘔吐しながら小さい声で答えます。
「と・・・・とう・・・きょう・・わん・・付近」
「先生!何と!」
「東京湾としか考えられん!豪州でこの揺れ。東京は?東京はどんな状況なんだ!」
現在、同天文台には、大森の立っていた場所を記し(足跡)、その地震計の記録も額に入れ展示されております。
「日本へ!早く日本へ!今村君と連絡を取らなくては!」
大森は、6日に一行とは離れ、ハワイ経由で日本へ向かいます。
途中、病状悪化の電報が帝大へ入ります。
10月4日、横浜着。
「今村君、大森先生が横浜へ着いた。即刻横浜へ!」理学部長からの命令。
その船中で二人は再開致します。
「先生」
「今村君か・・・君には・・・この震災には責任を私は感じている・・・」
船はちょうど午後三時に到着した。すぐに上船し、先生と面会したが、ご病気はかなり重いご様子で、衰弱も甚だしかったが意識だけは明瞭であった。
私が挨拶したのに対して、すぐに、息も苦しげに「今度の震災については自分は重大な責任を感じている。譴責されても仕方がない。ただし、水道の改良について義務を尽くしたことで自分を慰めている」と言い終わるか終わらぬうちに嘔吐を始められた。興奮による発作とのことだった。(10月4日 今村日記より抜粋)
関東大震災の年。大森はその任を今村、寺田等に預けるように、11月8日に亡くなりました。
大正14年(1923年)東京帝国大学内地震研究所設立。
各メンバーと研究内容。
地震計測器の研究→石本巳四雄
地震観測の整備・地震計の改良・微傾斜観測水準変動→今村明恒
構造物耐火試験・建築物の振動→内村洋三
中央気象台に於ける研究→岡田武松
構造物試験及び模型実験→末廣恭二
地殻及地震波弾性力学的研究→妹沢克椎
地形調査→多田文雄
火山調査・岩石閲覧歴的研究→坪井誠太郎
弾性波の生成及波及実験→寺田寅彦
高圧下の岩石の性質→長岡半太郎
捩・皺・庇割の研究→藤原咲平
材料強弱研究→物部長穂
地形調査→山崎直方
現在でも通用しそうなメンバー。
否、今すぐにでも、故郷の現状をこのメンバーで調査していただきたい。
こう考えてしまう、酔漢でございました。