白人アルト奏者アート・ペッパーは重度の麻薬中毒のため、キャリアの多くを棒に振っています。そのため、残された録音は50年代後半と70年代後半に集中していますが、私を含めジャズファンに人気が高いのはやっぱり50年代の演奏ですよね。ジャンル分け的にはウェストコーストジャズなんですが、その天才的なアドリブは同時代のどんな黒人ハードバッパー達に劣るものではなく、モダンジャズの歴史に輝かしい足跡を残しています。特に西海岸の名門レーベルであるコンテンポラリーには多くの名作を残しており、かの有名な「ミーツ・ザ・リズム・セクション」はじめ、「プラス・イレブン」「インテンシティ」等6作品をこの時期に吹き込んでいます。本作は1956年に録音された同レーベルへの初吹き込みです。
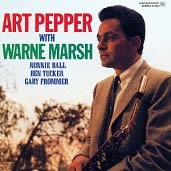
さて、アート・ペッパーのことばかり述べましたが、本作のもう一人のリーダーはウォーン・マーシュ。白人テナー奏者でリー・コニッツとのコンビでよく知られていますが、正直私の好みではあまりない。クールジャズだか何だか知りませんが、モソモソと起伏に乏しいアドリブは調子っぱずれにしか聞こえません。リズムセクションもロニー・ボール(ピアノ)、ベン・タッカー(ベース)、ゲイリー・フロマー(ドラム)とインパクトに欠ける面々ですし。ずばり本作の魅力はペッパーの輝かしいアルトに尽きるでしょう。冒頭の軽快なミディアムナンバー“I Can't Believe That You're In Love With Me”に始まり、マイナー調の“All The Things You Are”、急速調のテンポの中でペッパーのアドリブがほとばしる“Avalon”、自作のスローブルース“Warnin'”、そしてラストの幸福感に満ちあふれた“Stomping At The Savoy”。どの曲でもメロディアスなフレーズを連発するペッパーに酔いしれるべし!
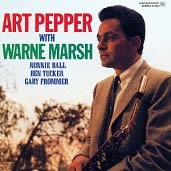
さて、アート・ペッパーのことばかり述べましたが、本作のもう一人のリーダーはウォーン・マーシュ。白人テナー奏者でリー・コニッツとのコンビでよく知られていますが、正直私の好みではあまりない。クールジャズだか何だか知りませんが、モソモソと起伏に乏しいアドリブは調子っぱずれにしか聞こえません。リズムセクションもロニー・ボール(ピアノ)、ベン・タッカー(ベース)、ゲイリー・フロマー(ドラム)とインパクトに欠ける面々ですし。ずばり本作の魅力はペッパーの輝かしいアルトに尽きるでしょう。冒頭の軽快なミディアムナンバー“I Can't Believe That You're In Love With Me”に始まり、マイナー調の“All The Things You Are”、急速調のテンポの中でペッパーのアドリブがほとばしる“Avalon”、自作のスローブルース“Warnin'”、そしてラストの幸福感に満ちあふれた“Stomping At The Savoy”。どの曲でもメロディアスなフレーズを連発するペッパーに酔いしれるべし!


















