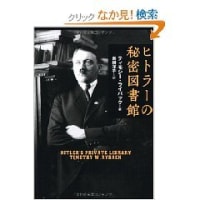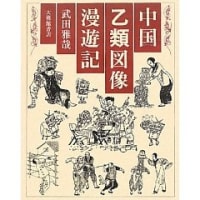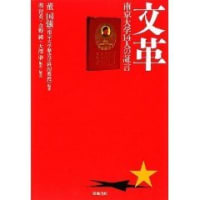マルティン・ルターが1517年10月31日にヴィッテンベルク城の教会の扉に「九十五カ条の提題」を貼りだして宗教改革が始まり、新しい宗派であるプロテスタントを生み出したと世界史で習ったが、筆者によると提題は貼られたのではなく、読んでもらうべき相手に書簡として送付されたもので、プロテスタントを生み出したと言うのも間違いで、教会の改革や刷新を願ってはいたが、新しい宗派を創設する意志はなかったということらしい。改革ではなくリフオームが適当とのこと。ルターの賛同者たち、あるいは彼を保護した政治勢力は、今日のドイツでも「プロテスタント」ではなく、「福音主義教会」と呼ばれている。プロテスタントは、ルター以後に発生した様々な教会とその信者たちを指し、プロテスタンティズムとは、ルター以後の潮流が生み出した、その後のあらゆる歴史的影響力の総称である。本書はその歴史的変遷をたどり、現状を分析する。私にとって未知の知見が随所に披歴されており、一気に読めた。
興味深かったのは第六章の「保守主義としてのプロテスタンティズム」だ。ドイツはヴァイマール期にルター派が伝統的に行なってきた王と教会との関係を軸とする政治的な体制が、王を失い共和制に移行した。これはルター派教会がその成立時から維持してきた前提が失われたということである。ルター派はヴァイマール期ドイツでは政治の舞台から追い出され、彼らと敵対関係にあったカトリック中央党と社会民主主義勢力が政治を支配するようになった。それゆえルター派は後にヒトラー率いる国家社会主義が台頭したとき、この新しい指導者を「上に立つ権威」として違和感なく受け入れたという指摘は重要だ。
王政と親和性があり、デモクラシーや資本主義に対して否定的なルター派は社会主義者、共産党、カトリック中央党に批判的なプロパガンダを繰り返すナチズムに親近感を感じ、大ドイツを再建すべく血と大地に訴える政治に取り込まれてしまった。プロテスタンティズムの負の側面である。ドイツのヴァイマール期では革新的ではなかったわけである。
第七章ではアメリカに渡ったプロテスタントについて書かれている。これを新プロテスタンティズムと言っているが、これは教会を作る自由を主張し、信じる自由を徹底しようとしたがゆえに古プロテスタンティズムから追い出され迫害された勢力である。イングランドのピューリタンたちのアメリカへの移住は、最終的には国営の教会によって独占されていた宗教市場を自由化・民営化しようとした。これをリベラリズムと定義すると、アメリカの流儀がよくわかる。アメリカの宗教市場は、この民営化の中で、伝道と呼ばれる競争を続けて民衆の取り込みに躍起となっている。メガチャーチと言われる巨大教会で牧師がカリスマのごとく分かりやすい言葉で説教する姿は、この競争の一側面を現出させたものだ。マックス・ヴェーバーによると、神が救いへと予定に定めた者は天国に行けるだけでなく、この世でも祝福に満ちた人生をを送れるという考え方を超えて、逆にこの世で成功している者こそが天国に行けるものであり、それが神が救いを予定したことの証明になっているという。だからこの世での成功がアメリカでは宗教的な救済の証明となったのだ。アメリカの拝金主義の容認はここに根拠がある。「神は俗事に関わらない」という宗教本来の趣旨が大きく変容している。この伝でいくとトランプ大統領は真っ先に天国に行けることになる。
興味深かったのは第六章の「保守主義としてのプロテスタンティズム」だ。ドイツはヴァイマール期にルター派が伝統的に行なってきた王と教会との関係を軸とする政治的な体制が、王を失い共和制に移行した。これはルター派教会がその成立時から維持してきた前提が失われたということである。ルター派はヴァイマール期ドイツでは政治の舞台から追い出され、彼らと敵対関係にあったカトリック中央党と社会民主主義勢力が政治を支配するようになった。それゆえルター派は後にヒトラー率いる国家社会主義が台頭したとき、この新しい指導者を「上に立つ権威」として違和感なく受け入れたという指摘は重要だ。
王政と親和性があり、デモクラシーや資本主義に対して否定的なルター派は社会主義者、共産党、カトリック中央党に批判的なプロパガンダを繰り返すナチズムに親近感を感じ、大ドイツを再建すべく血と大地に訴える政治に取り込まれてしまった。プロテスタンティズムの負の側面である。ドイツのヴァイマール期では革新的ではなかったわけである。
第七章ではアメリカに渡ったプロテスタントについて書かれている。これを新プロテスタンティズムと言っているが、これは教会を作る自由を主張し、信じる自由を徹底しようとしたがゆえに古プロテスタンティズムから追い出され迫害された勢力である。イングランドのピューリタンたちのアメリカへの移住は、最終的には国営の教会によって独占されていた宗教市場を自由化・民営化しようとした。これをリベラリズムと定義すると、アメリカの流儀がよくわかる。アメリカの宗教市場は、この民営化の中で、伝道と呼ばれる競争を続けて民衆の取り込みに躍起となっている。メガチャーチと言われる巨大教会で牧師がカリスマのごとく分かりやすい言葉で説教する姿は、この競争の一側面を現出させたものだ。マックス・ヴェーバーによると、神が救いへと予定に定めた者は天国に行けるだけでなく、この世でも祝福に満ちた人生をを送れるという考え方を超えて、逆にこの世で成功している者こそが天国に行けるものであり、それが神が救いを予定したことの証明になっているという。だからこの世での成功がアメリカでは宗教的な救済の証明となったのだ。アメリカの拝金主義の容認はここに根拠がある。「神は俗事に関わらない」という宗教本来の趣旨が大きく変容している。この伝でいくとトランプ大統領は真っ先に天国に行けることになる。