下根子桜時代の真実の宮澤賢治を知りたくて、賢治の周辺を彷徨う。
宮澤賢治の里より
賢治宅訪問応諾のドタキャン


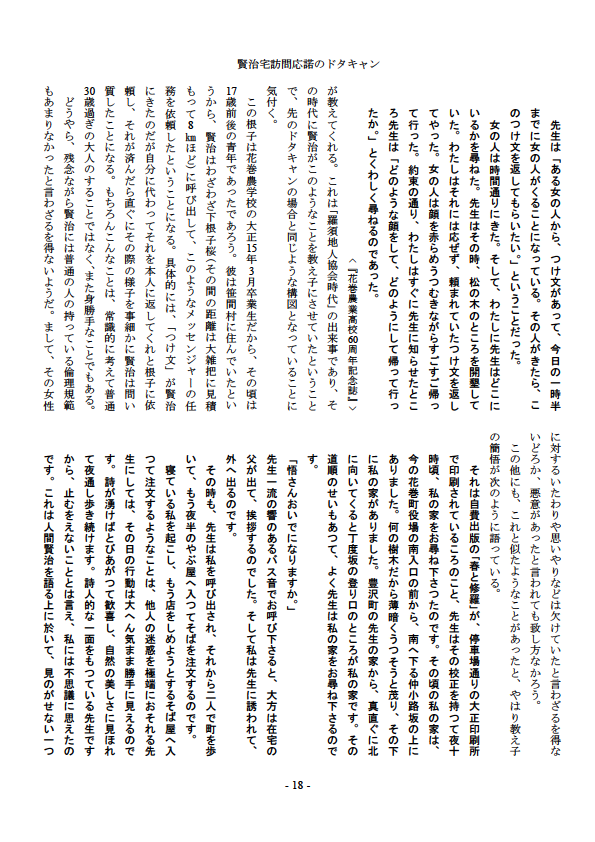

 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 ”『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ移る。
”『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ移る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。*****************************なお、以下はテキスト形式版である。****************************
賢治宅訪問応諾のドタキャン
さて、大正15年6月には五百二十円もの大金を手にした賢治だったが、その後はどんなおかしいことがあったのか。それは同年翌月、7月25日の、最初にも述べた次の出来事、
賢治も承諾の返事を出していたが、この日断わりの使いを出す。使者は下根子桜の家に寝泊りしていた千葉恭で午後六時ごろ講演会会場の仏教会館で白鳥省吾にその旨を伝える。
に関わるもう一つのことだ。だからもちろん「独居自炊」のことではなく、応諾していた白鳥省吾の賢治宅訪問のドタキャンについてである。
ところでこのドタキャンの出典は何か。それは、『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)年譜篇』(筑摩書房)(以下、『新校本年譜』と略称)によればそれは千葉恭の次の追想「宮澤先生を追つて㈢」だという。ではそこには何が書かれているかというと、
ある年の夏のことでありましたが朝起きると直ぐ
「盛岡に行つて呉れませんか」
私は突然かう言はれて何が何だか判らずにをりますと、先生は靜かに
「實は明日詩人の白鳥省吾と犬田卯の二人が訪ねて來ると云ふ手紙を貰つているのだが、私は一應承諾したのだが― 今日急に會ふのをやめることにしたから盛岡まで行つて斷はつて來て貰ひたいのです」
そこで私は午後四時の列車に乗つて盛岡に出かけることにしました。車中で出る前に聞いた先生の言葉が、何んだかはつきり分からずに考へ直してみたのでした。
「私を岩手にかくれた詩人で宮澤と云ふ者がいるさうだが、是非會つて見たいという話だが彼等は都會の詩人で職業詩人だから、我々が考へているやうな詩の詩人ではない――何かうつぼな外美のもので、それを藝術と云ふなら藝術といふものは價値がないと思ふ――私はベートーベンのあの藝術の強みを考へているのです。その場合に彼等に會ふのは私は心をにごすことになるし、また會ふたところでどうにもならないから彼等のためにも私のためにも會はぬ方が良いようだから――」と云はれたのでした。
盛岡に着いた時は午後六時でした。あまり出かけたことのない私には盛岡は物珍しく思はれました。邊りを眺めながら講演會の會場である佛教會館に行きました。聽衆は若い女性や若い男性で一杯でしたが、控室に案内されて詩人達に會はして貰ひました。そして「私は宮澤賢治にたのまれて來た者ですが、實は先日手紙でお會ひすることにしていたのださうですが、今朝になつて會ひたくない―斷つて來て下さいと云はれて來ました。」田舎ものゝ私は率直にかう申し上げましたところ白鳥さんはちよつと驚いたやうな顔をしましたが、しばらくして、
「さうですか、それは本當におしいことですが、仕方ありません―」
私が直ぐ立ち去ろうとしましたら白鳥さんは
「ちよつと待つて下さい―ゆつくりしていたらどうですか」
「實は早く歸りたいのですから」
「それでは宮澤さんの事を少し聞かして下さいませんか」
私はしかたなく待つことにしたのでした。
「濟みませんが先生が私達に會はないわけを聞かして下さい」
私はちよつと當惑しましたが、私の知つていることだけもと思ひまして
「先生は都會詩人所謂職業詩人とは私の考へと歩みは違ふし完成しないうちに會ふのは危險だから先生の今の態度は農民のために非常に苦勞しておられますから――」
私はあまり話せる方でもないのでさう云ふ質問は殊に苦手でしたし、また宿錢も持つてゐないので、歸りを忙ぐことにしたのでした。盛岡を終列車に乗つて歸り、先生にそのことを報告しました。
私は弟子ともつかず、小使ともつかず先生に接して來ましたが、詩人と云ふので思ひ出しましたが、山形の松田さんを私がとうとう知らずじまひでした。その后有名になつてから「あの時來た優しそうな靑年が松田さんであつたのかしら」と、思ひ出されるものがありました。
<『四次元7号』(昭和25年5月、宮沢賢治友の会)、16p>
という、当時賢治と一緒に下根子桜で暮らしていたあの千葉恭の追想である。
さて、この恭の追想に従えば、賢治は応諾していた訪問を前日にドタキャンしたことになる。しかもこの断りの理由はあくまでも賢治の都合だから、事前に打診して賢治から応諾を得ていた白鳥からすれば当然納得できぬことだし、その訪問前日に、『今日急に會ふのをやめることにしたから』と賢治からこともなげに告げられ、その旨を断りに行くのが賢治よりも約10歳年下の、二十歳そこそこの恭としては気が進まなかったのは当然であったであろう。そのような心理が、「弟子ともつかず、小使ともつかず先生に接して來ました」という自嘲めいた表現を恭になさしめている大きな理由に違いない。
だから逆に、もしかすると賢治はこのようなドタキャンなど案外何とも思っていなかったのかもしれない。それは、関登久也が、
もし無理に言うならば、いろんな計画を立てても、二、三日するとすつかり忘れてしまつたやうに、また別の新しい計画を立てたりするので、こちらはポカンとさせられるようなことはあつた。
<『宮澤賢治物語』(関登久也著、岩手日報社)の「前がき」>
と賢治のことを述懐しているが、このドタキャンもそのような一つの事例だったとすれば、善し悪しは別として理屈としては成り立つからだ。
どうやら、賢治は一般的な倫理規範は持ち合わせていなかったこともあったということを否定できないようだ。だから、賢治本人は何とも思っていなくとも周りから見ればこのような賢治の性向は身勝手だと見られがちだったであろう。そしてこのような場合、以前の私であれば、賢治は天才だからそのドタキャンもやむを得ないことだったのだと苦笑いして済ましていたが昨今は改めた。それでは賢治のことを客観的に評価していないし公平でもないということは、常識的に判断すれば当たり前のことだからだ。今後は、賢治といえどもおかしいところはおかしいと、悪いところは悪いと冷静に判断してゆきたいと。
ところで、この断りの使者のように、困ったことは他人を頼みにするという傾向が実は賢治には見られる。そのような事例を、教え子の根子吉盛の次のような回想、
ある日、先生から手紙を受けとった。内容はいつそれまでにきてくれというので出かけて行った。
先生は「ある女の人から、つけ文があって、今日の一時半までに女の人がくることになっている。その人がきたら、このつけ文を返してもらいたい。」ということだった。
女の人は時間通りにきた。そして、わたしに先生はどこにいるかを尋ねた。先生はその時、松の木のところを開墾していた。わたしはそれには応ぜず、頼まれていたつけ文を返してやった。女の人は顔を赤らめうつむきながらすごすご帰って行った。約束の通り、わたしはすぐに先生に知らせたところ先生は「どのような顔をして、どのようにして帰って行ったか。」とくわしく尋ねるのであった。
<『花巻農業高校60周年記念誌』>
が教えてくれる。これは「羅須地人協会時代」の出来事であり、その時代に賢治がこのようなことを教え子にさせていたということで、先のドタキャンの場合と同じような構図となっていることに気付く。
この根子は花巻農学校の大正15年3月卒業生だから、その頃は17歳前後の青年であったであろう。彼は笹間村に住んでいたというから、賢治はわざわざ下根子桜(その間の距離は大雑把に見積もって8㎞ほど)に呼び出して、このようなメッセンジャーの任務を依頼したということになる。具体的には、「つけ文」が賢治にきたのだが自分に代わってそれを本人に返してくれと根子に依頼し、それが済んだら直ぐにその際の様子を事細かに賢治は問い質したことになる。もちろんこんなことは、常識的に考えて普通30歳過ぎの大人のすることではなく、また身勝手なことでもある。
どうやら、残念ながら賢治には普通の人の持っている倫理規範もあまりなかったと言わざるを得ないようだ。まして、その女性に対するいたわりや思いやりなどは欠けていたと言わざるを得ないどろか、悪意があったと言われても致し方なかろう。
この他にも、これと似たようなことがあったと、やはり教え子の簡悟が次のように語っている。
それは自費出版の「春と修羅」が、停車場通りの大正印刷所で印刷されているころのこと、先生はその校正を持つて夜十時頃、私の家をお尋ね下さつたのです。その頃の私の家は、今の花巻町役場の南入口の前から、南へ下る仲小路坂の上にありました。何の樹木だから薄暗くうつそうと茂り、その下に私の家がありました。豊沢町の先生の家から、真直ぐに北に向いてくると丁度坂の登り口のところが私の家です。その道順のせいもあつて、よく先生は私の家をお尋ね下さるのです。
「悟さんおいでになりますか。」
先生一流の響のあるバス音でお呼び下さると、大方は在宅の父が出て、挨拶するのでした。そして私は先生に誘われて、外へ出るのです。
その時も、先生は私を呼び出され、それから二人で町を歩いて、もう夜半のやぶ屋へ入つてそばを注文するのです。
寝ている私を起こし、もう店をしめようとするそば屋へ入つて注文するようなことは、他人の迷惑を極端におそれる先生にしては、その日の行動は大へん気まま勝手に見えるのです。詩が湧けばとびあがつて歓喜し、自然の美しさに見ほれて夜通し歩き続けます。詩人的な一面をもつている先生ですから、止むをえないこととは言え、私には不思議に思えたのです。これは人間賢治を語る上に於いて、見のがせない一つのエピソードだと、私は思うのです。
<『宮澤賢治物語』(関登久也著、岩手日報社)、272p>
このエピソードのような行為、「寝ている私を起こし……注文するようなこと」もまた、普通三十も過ぎた大人はしないだろう。その点教え子の簡は、「詩人的な一面をもつている先生ですから、止むをえないこととは言え」と賢治のことを庇ってはいるが、簡がいみじくも言っているように「大へん気まま勝手」以外の何ものでもない。だからおそらく、賢治のこのよううな性向は以前からあったと言えそうだ。
どうやら、このドタキャン事件を始めとしたこれらのエピソードからは、
「羅須地人協会時代」の賢治は、端から見れば自分勝手な振る舞いが少なからずあった。そしてこのことを敷衍すれば、少なくとも同時代の賢治は人間としては聖人でもなければ君子でもなく、よくあるタイプの人間であり、逆にある意味親しみやすくて愛すべき人間であった。
ということが導かれそうだ。
そして、これは最初に述べた岩田純蔵教授の「嘆き」、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだがそのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
とも符合する。おそらく、恩師は伯父である賢治のこのような性向を間近にいてよく知っていたのであろう。
もちろん、だからといって私は賢治を全否定するつもりなどは毛頭ない。そんなことではなく、まずはあるがままの賢治を恐れずに受け容れることによってこそ、「賢治研究」の新たな地平が見えてきそうだという期待と確信が私にはどんどん膨らんできているだけだ。そして、このような賢治の「不羈奔放さ」が賢治をして沢山の素晴らしい作品を書かしめたとは言えないだろうか。
***************************** 以上 ****************************
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
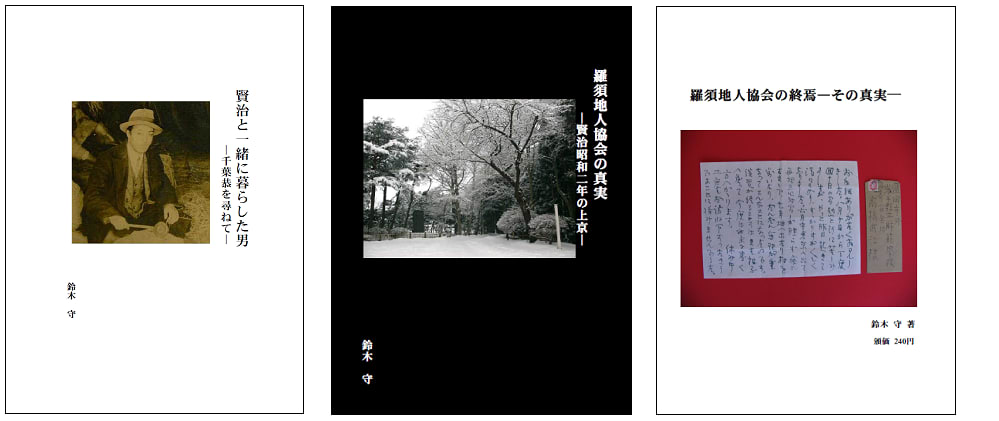
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 五百二十円も... | 賢治・家の光... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




