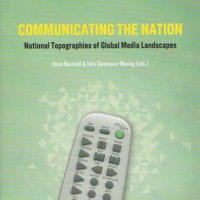1998年春、武道館での入学式。九段下の駅から、満開になった美しい桜並木の下を歩いて行く途中、私の心は悔しい気持ちで一杯だった。
受験に失敗したのである。ちくしょう、俺の人生はどうなっちまうんだ、これで良いのか、その悔しさ、さらには劣等感が、私の心の中で渦巻いていた。
--
私が通った高校は、静岡県にある大学付属のマンモス高校で、私が入ったクラスは、確か1年24組だった。高校が巨大だった為、先生も同級生もどこか他人同士、そんな感じだった。
高校時代、私は受験勉強というものが嫌で嫌でしょうがなかった。私は高校受験も失敗していたのだが、受験なんて本当にくだらないと思っていて、何故、ただ単に受験だけを目標とした、何の役にも立たない勉強をしなくてはらないのか、理解できなかった。面白い授業をしてくれる先生もいれば良かったのだが、愛と魅力に溢れた教師を、平均年齢が50歳を超えたこのマンモス高校の中の教師たちの中に見出すことは難しく、学校に対して「くだらない」と思う、どこかスレた感情を持っていた。そして私と教師とは、どこかで常に一触即発の危機になりうる、そんな冷戦状態にあった。
また私自身、高校時代には精神的に大分落ちていたと思う。未来に対する夢や希望が持てなくて、現実からもある種の逃避をしていた。ヴァーチャルな空間に逃げ込んで、インターネットチャットばかりしていた気がする。
しかし、そんな私にも、高校に入ったらやりたい事が一つあった。サッカー部に入ることである。
私は静岡県出身ということもあり、サッカー部は部活の花形で、プロを目指してサッカーをやっている友人も多く、ある種の憧れがあった。近所には、同い年の小野伸二や、高原直泰がいた。しかし、ある種の英才教育を受けた経験者が多く、その中でやっていくだけの自身が無かったので、中学時代にはサッカー部には入らなかった、いや、入れなかったのだ。しかし、高校時代には、自分の好きなサッカーを気が済むまでやりたい、そう思っていた。
私は、高校では特別進学クラスというのに入っていた。これは大学進学を目指す学生が入るクラスで、授業数も1時間多かった。もちろん、下校時間も遅かったし、部活をやっている人たちは、遅れて参加することとなっていた。
高校入学後、私はすぐにサッカー部に入る際に必要とされるトレーニングシャツとシューズを用意するやいなや、教員室に行くと、サッカー部の先生に「入れて下さい」と直訴した。しかし、答えはNoだった。特別進学クラスなんだから勉強しなさい、それと皆プロを目指している様な人たちだから、君とは合わない、そんな答えをされたと思う。
確かに、高校のサッカー部もプロ志向の人が多く、それなりに強かった。通っていた高校そのものがスポーツで有名で、一つ上には、水泳の金メダリストの岩崎恭子さんもいた。そんな中、私の意図は、たしかに「合わなかった」のかもしれない。しかし、「入りたい」と言っている学生に対して、あまりにも冷たくないか、そんな反感があった。
そんなこともあってか、だんだんと学校に興味が湧かなくなってしまった。何の為に学校に行っているのか、そして何の為に俺は生きているんだ・・・そんな疑問さえ持つ様になった。
また何よりも、田舎町の高校という閉塞感は、私にとって耐えがたいものだった。多感な青年にとって、田舎暮らしは、退屈以外の何物でもなかった。早く東京に出て、もっと文化度の高いものに常に触れていたい、そんな思いが絶えず募っていた。
さらに、まだ漠然とした感覚ではあったが、「日本」という閉鎖空間にさえ、どこかうんざりしていた。どう足掻いても、それより外には行けない、という土管の様な閉じられた空間。そこに、アメリカやらヨーロッパやらから情報だけが投げ込まれている、それに対して有無を言わずに満足しなくてはならない、そんな状況に疑問や不快感を覚えつつ、悶々としたものをため込んでいた。
学校にも興味が湧かず(今考えると、本当によく辞めなかったと思う)、世の中にもそんなに興味が湧かない、そんな時、私にとって唯一の救いとなったのが、「芸術」であった。
高校1年生くらいまでは、私はファッション大好き少年だった。ファッション雑誌を見て、流行りの服を着る、そんなことが大好きだったのだが、高校2年生くらいになると、それにも飽きてしまった。ファッションという文化がの底が見えてしまい、浅いな、これ以上追及しても意味がないな、と感じる様になったのである。それ以上に何か刺激的なものはないか、と思いながら、Studio VoiceやEsquireマガジンなどをくまなくチェックしていた。
そんな時に、偶然Esquireマガジンにて、「アンディ・ウォーホルとは、誰か?」という特集があり、夢中になって読んだ。確か椹木野衣が記事を書いていたのだが、これが実に見事な記事だった。おそらく、映画「バスキア」に合わせて特集されたものだったと思うのだが、ウォーホルの周辺人物がダイアグラムと解説と一緒に書かれていて、とても興味が湧いたのである。それからすっかりウォーホルにハマってしまい、「ウォーホル日記」を読んで、しまいには、NYのアートシーンへと思いを巡らす様になった。ニューヨーク、行ってみたいな、そんな漠然とした思いも生まれた。
学校が終わると、私は駅の近くにある立派な図書館に通うのが日課となり、そこで好きな音楽を聞いたり、写真集を見ていた。この図書館の蔵書が素晴らしく、私の興味に対して、それ以上の手ごたえで応じてくれた。特にロックミュージックのコレクションは素晴らしく、クラシックロックの定番を聞き漁った。お気に入りは、パティ・スミスと、ジャニス・ジョプリン、べルヴェッド・アンダーグラウンド、クイーン、スライ・アンド・ザ・ファミリーストーンなど。借りてきてはカセットテープに録音し、自宅で聴いていた。
音楽と並行して、今度は画集や写真集を見る様になった。私のお気に入りは、画家ではジャン・コクトー、アンリ・マティス、そしてフランチェスコ・クレメンテ、写真ではロバート・フランクと森山大道だった。アラーキーの「東京日和」も大好きだった。これらの写真集の中に、中平卓馬の名前が沢山出ていることに気づいて、図書館司書の方に「中平卓馬の写真集は無いのですか?」と聞くと、すぐに入荷してくれた。学校以上の、私だけの秘密の勉強の場所、それが図書館だった。
そして、暇があったからだろうか、映画も良く見た。映画も図書館でレンタルできたし、近所のビデオ屋さんも比較的充実していた。映像の美と世界の歴史や文学が繋がって行くのを見るのは、いろいろな発見があり、爽快だった。
黒沢映画から、ジム・ジャームッシュ、ヴィム・ ヴェンダース、エリック・ロメール、クシシュトフ・キェシロフスキ、スパイク・リー、そしてゴダールまで、幅広く見た。手に入らないものは、行きつけのレンタルビデオ屋さんで借りて、無い時にはリクエストして仕入れてもらったり、時には鈍行列車に乗って2時間半かけて東京に出て、渋谷の映画館で見てきたりした。そんなことをしているうちに、私はヨーロッパのしっとりとした映画が好きだ、ということに気がついた。
それが昂じて、地元の映画好きサークルに出入りする様になり、随分年の離れた人たちと、映画談義をする様になった。私はその方たちにも随分かわいがってもらい、映画のことなど、よく教えてもらった。
またサッカーも、結局地元のクラブチームに入ることになった。同じ高校に通う友人のKくんが誘ってくれたのだ。Kくんはサッカーがめちゃめちゃ上手くて、勧誘されたにも関わらず、高校のサッカー部に入らなかったのだ。どうして?という理由を聞いてもなかなか教えてくれなかったのだが、ある日、彼は敬虔なクリスチャンで、日曜日には教会に行かなくてはならないのでサッカーができない、ということをこっそり教えてくれた。(その後彼は高校を卒業すると、神父になる為にアメリカへと発ったのであった)
20-30代の方たちに交じって、私もサッカーの試合に出る様になった。ここでも、年長者の方々に随分と可愛がってもらい、試合後の打ち上げでは「ホッピー係」として、パーティの盛り上げ役となった。そんな中で、私は年長者との社会的な社交性を身につけていった様に思う。私の末っ子根性が生きたのかもしれない。
映画や音楽など、文化に関しては、同級生の誰よりも精通していて、上質なものを見ている、しかもちゃんと学校の外に出て自分のことをしている、私には、そんな不思議な自負だけはあった。そして、何よりも、私の魂は芸術に救われていた。私の人生における精神の危機は、芸術の魂によって救われたのである。
そんな矢先、高校でこんなイベントがあった。「読書感想文コンテスト」。大学の付属高校が一斉に行う、作文コンテストである。
私はウォーホルの流れから、60年代のアメリカ、特にビートニックに興味が湧き、アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックにぞっこんだった。特に「路上」からは強烈な影響を受け、私も路上をテーマに何かものを作ってみたい、そう空想を巡らせる様になった。そこから文学、というものにも、なんとなく興味が湧いてきた。ちょうど17歳になったその時、ランボーの詩に出会い、強烈な印象を受けていた。ゴダールの「気狂いピエロ」のラストシーンから導かれた私は、彼の代表作「永遠」を、何度も読みながら反芻していた。
見つけたぞ、 何を? 永遠を。それは太陽と繋がった海だ。
「永遠」において、太陽と繋がった海の赤と青の美しいグラデーションのイメージを、母音に色付けし、子音とのコンビネーションで絵画的に表現する、という鮮やかな発想や、ナポレオン戦争以降のフランスをテーマとした作品「酔いどれ船」などを、たった16歳の少年が作ったことに衝撃を受け、そして嫉妬した。この時は本当に、私は彼に負けたと思った(そう、私は負けず嫌いなのだ)
そこで私は一念発起し、高校時代の怠惰なエネルギーからため込んだパワーを、読書感想文「ジャック・ケルアック 地下街の人びとを読んで」としてコンテストに発表し、世に問うことにした。私が考え付くだけの、最も的確な言葉を使って、素直に、そして精一杯書いた。今読んでもきっと後悔することのない、そんな文章であったろうと思う。私のライバルは、そう、アルチュール・ランボー。
1か月ほどして、結果発表があった。受賞者のリストの中に、私の名前はどこにも無かった。どうしても納得できなかったので、国語の先生に聞いてみた。
「あのぉー、先生、読書感想文コンテストなんですけど、俺の文章、ダメでしたか?」
「ええ?君、何を書いたの?」
「ジャック・ケルアックの感想文を書いたんですけれど・・・」
「誰それ?」
「アメリカ60年代を代表する作家で、ビートジェネレーションの人です」
「聞いたことがないな。そんなのは文学でも何でもないんじゃないか。」
そこで話を切られてしまった。悔しかったので、聞いてみた。
「では先生、文学とは、たとえば誰のことを言うのでしょうか?」
「太宰だ」
私はその答えを聞いて、彼から学ぶものは何も無い、と決め込んだ。それから、私は学校での勉強というのを放棄する様になった。それは私にとって、有害だと思ったからだ。ちなみに大賞受賞作品は「火垂るの墓を読んで」であった。きっと高校生が書く文章としてふさわしい、と評価されたのだと思うが、私は学校という小さなコンテクストは一切信用せず、これからはずっとユニバーサルなものだけを追及しよう、そう心に決めた。
そんな時、私が夢中になったのが、映画「Trainspotting」だった。多感だった田舎暮らしの17歳の私の肌に、イギー・ポップやルー・リードの音楽と、強烈なイングランド的な感覚が、スっと私の中に入ってきた。こんな映画があるんだ、そしてこんな文化があるんだ、面白そうだな、見てみたいな、そんな風に思った。
私の興味は尽きず、ついに私は、父にこう頼んでみた。
「お父さん、イギリスに行かせて下さい」
-- つづく --
受験に失敗したのである。ちくしょう、俺の人生はどうなっちまうんだ、これで良いのか、その悔しさ、さらには劣等感が、私の心の中で渦巻いていた。
--
私が通った高校は、静岡県にある大学付属のマンモス高校で、私が入ったクラスは、確か1年24組だった。高校が巨大だった為、先生も同級生もどこか他人同士、そんな感じだった。
高校時代、私は受験勉強というものが嫌で嫌でしょうがなかった。私は高校受験も失敗していたのだが、受験なんて本当にくだらないと思っていて、何故、ただ単に受験だけを目標とした、何の役にも立たない勉強をしなくてはらないのか、理解できなかった。面白い授業をしてくれる先生もいれば良かったのだが、愛と魅力に溢れた教師を、平均年齢が50歳を超えたこのマンモス高校の中の教師たちの中に見出すことは難しく、学校に対して「くだらない」と思う、どこかスレた感情を持っていた。そして私と教師とは、どこかで常に一触即発の危機になりうる、そんな冷戦状態にあった。
また私自身、高校時代には精神的に大分落ちていたと思う。未来に対する夢や希望が持てなくて、現実からもある種の逃避をしていた。ヴァーチャルな空間に逃げ込んで、インターネットチャットばかりしていた気がする。
しかし、そんな私にも、高校に入ったらやりたい事が一つあった。サッカー部に入ることである。
私は静岡県出身ということもあり、サッカー部は部活の花形で、プロを目指してサッカーをやっている友人も多く、ある種の憧れがあった。近所には、同い年の小野伸二や、高原直泰がいた。しかし、ある種の英才教育を受けた経験者が多く、その中でやっていくだけの自身が無かったので、中学時代にはサッカー部には入らなかった、いや、入れなかったのだ。しかし、高校時代には、自分の好きなサッカーを気が済むまでやりたい、そう思っていた。
私は、高校では特別進学クラスというのに入っていた。これは大学進学を目指す学生が入るクラスで、授業数も1時間多かった。もちろん、下校時間も遅かったし、部活をやっている人たちは、遅れて参加することとなっていた。
高校入学後、私はすぐにサッカー部に入る際に必要とされるトレーニングシャツとシューズを用意するやいなや、教員室に行くと、サッカー部の先生に「入れて下さい」と直訴した。しかし、答えはNoだった。特別進学クラスなんだから勉強しなさい、それと皆プロを目指している様な人たちだから、君とは合わない、そんな答えをされたと思う。
確かに、高校のサッカー部もプロ志向の人が多く、それなりに強かった。通っていた高校そのものがスポーツで有名で、一つ上には、水泳の金メダリストの岩崎恭子さんもいた。そんな中、私の意図は、たしかに「合わなかった」のかもしれない。しかし、「入りたい」と言っている学生に対して、あまりにも冷たくないか、そんな反感があった。
そんなこともあってか、だんだんと学校に興味が湧かなくなってしまった。何の為に学校に行っているのか、そして何の為に俺は生きているんだ・・・そんな疑問さえ持つ様になった。
また何よりも、田舎町の高校という閉塞感は、私にとって耐えがたいものだった。多感な青年にとって、田舎暮らしは、退屈以外の何物でもなかった。早く東京に出て、もっと文化度の高いものに常に触れていたい、そんな思いが絶えず募っていた。
さらに、まだ漠然とした感覚ではあったが、「日本」という閉鎖空間にさえ、どこかうんざりしていた。どう足掻いても、それより外には行けない、という土管の様な閉じられた空間。そこに、アメリカやらヨーロッパやらから情報だけが投げ込まれている、それに対して有無を言わずに満足しなくてはならない、そんな状況に疑問や不快感を覚えつつ、悶々としたものをため込んでいた。
学校にも興味が湧かず(今考えると、本当によく辞めなかったと思う)、世の中にもそんなに興味が湧かない、そんな時、私にとって唯一の救いとなったのが、「芸術」であった。
高校1年生くらいまでは、私はファッション大好き少年だった。ファッション雑誌を見て、流行りの服を着る、そんなことが大好きだったのだが、高校2年生くらいになると、それにも飽きてしまった。ファッションという文化がの底が見えてしまい、浅いな、これ以上追及しても意味がないな、と感じる様になったのである。それ以上に何か刺激的なものはないか、と思いながら、Studio VoiceやEsquireマガジンなどをくまなくチェックしていた。
そんな時に、偶然Esquireマガジンにて、「アンディ・ウォーホルとは、誰か?」という特集があり、夢中になって読んだ。確か椹木野衣が記事を書いていたのだが、これが実に見事な記事だった。おそらく、映画「バスキア」に合わせて特集されたものだったと思うのだが、ウォーホルの周辺人物がダイアグラムと解説と一緒に書かれていて、とても興味が湧いたのである。それからすっかりウォーホルにハマってしまい、「ウォーホル日記」を読んで、しまいには、NYのアートシーンへと思いを巡らす様になった。ニューヨーク、行ってみたいな、そんな漠然とした思いも生まれた。
学校が終わると、私は駅の近くにある立派な図書館に通うのが日課となり、そこで好きな音楽を聞いたり、写真集を見ていた。この図書館の蔵書が素晴らしく、私の興味に対して、それ以上の手ごたえで応じてくれた。特にロックミュージックのコレクションは素晴らしく、クラシックロックの定番を聞き漁った。お気に入りは、パティ・スミスと、ジャニス・ジョプリン、べルヴェッド・アンダーグラウンド、クイーン、スライ・アンド・ザ・ファミリーストーンなど。借りてきてはカセットテープに録音し、自宅で聴いていた。
音楽と並行して、今度は画集や写真集を見る様になった。私のお気に入りは、画家ではジャン・コクトー、アンリ・マティス、そしてフランチェスコ・クレメンテ、写真ではロバート・フランクと森山大道だった。アラーキーの「東京日和」も大好きだった。これらの写真集の中に、中平卓馬の名前が沢山出ていることに気づいて、図書館司書の方に「中平卓馬の写真集は無いのですか?」と聞くと、すぐに入荷してくれた。学校以上の、私だけの秘密の勉強の場所、それが図書館だった。
そして、暇があったからだろうか、映画も良く見た。映画も図書館でレンタルできたし、近所のビデオ屋さんも比較的充実していた。映像の美と世界の歴史や文学が繋がって行くのを見るのは、いろいろな発見があり、爽快だった。
黒沢映画から、ジム・ジャームッシュ、ヴィム・ ヴェンダース、エリック・ロメール、クシシュトフ・キェシロフスキ、スパイク・リー、そしてゴダールまで、幅広く見た。手に入らないものは、行きつけのレンタルビデオ屋さんで借りて、無い時にはリクエストして仕入れてもらったり、時には鈍行列車に乗って2時間半かけて東京に出て、渋谷の映画館で見てきたりした。そんなことをしているうちに、私はヨーロッパのしっとりとした映画が好きだ、ということに気がついた。
それが昂じて、地元の映画好きサークルに出入りする様になり、随分年の離れた人たちと、映画談義をする様になった。私はその方たちにも随分かわいがってもらい、映画のことなど、よく教えてもらった。
またサッカーも、結局地元のクラブチームに入ることになった。同じ高校に通う友人のKくんが誘ってくれたのだ。Kくんはサッカーがめちゃめちゃ上手くて、勧誘されたにも関わらず、高校のサッカー部に入らなかったのだ。どうして?という理由を聞いてもなかなか教えてくれなかったのだが、ある日、彼は敬虔なクリスチャンで、日曜日には教会に行かなくてはならないのでサッカーができない、ということをこっそり教えてくれた。(その後彼は高校を卒業すると、神父になる為にアメリカへと発ったのであった)
20-30代の方たちに交じって、私もサッカーの試合に出る様になった。ここでも、年長者の方々に随分と可愛がってもらい、試合後の打ち上げでは「ホッピー係」として、パーティの盛り上げ役となった。そんな中で、私は年長者との社会的な社交性を身につけていった様に思う。私の末っ子根性が生きたのかもしれない。
映画や音楽など、文化に関しては、同級生の誰よりも精通していて、上質なものを見ている、しかもちゃんと学校の外に出て自分のことをしている、私には、そんな不思議な自負だけはあった。そして、何よりも、私の魂は芸術に救われていた。私の人生における精神の危機は、芸術の魂によって救われたのである。
そんな矢先、高校でこんなイベントがあった。「読書感想文コンテスト」。大学の付属高校が一斉に行う、作文コンテストである。
私はウォーホルの流れから、60年代のアメリカ、特にビートニックに興味が湧き、アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックにぞっこんだった。特に「路上」からは強烈な影響を受け、私も路上をテーマに何かものを作ってみたい、そう空想を巡らせる様になった。そこから文学、というものにも、なんとなく興味が湧いてきた。ちょうど17歳になったその時、ランボーの詩に出会い、強烈な印象を受けていた。ゴダールの「気狂いピエロ」のラストシーンから導かれた私は、彼の代表作「永遠」を、何度も読みながら反芻していた。
見つけたぞ、 何を? 永遠を。それは太陽と繋がった海だ。
「永遠」において、太陽と繋がった海の赤と青の美しいグラデーションのイメージを、母音に色付けし、子音とのコンビネーションで絵画的に表現する、という鮮やかな発想や、ナポレオン戦争以降のフランスをテーマとした作品「酔いどれ船」などを、たった16歳の少年が作ったことに衝撃を受け、そして嫉妬した。この時は本当に、私は彼に負けたと思った(そう、私は負けず嫌いなのだ)
そこで私は一念発起し、高校時代の怠惰なエネルギーからため込んだパワーを、読書感想文「ジャック・ケルアック 地下街の人びとを読んで」としてコンテストに発表し、世に問うことにした。私が考え付くだけの、最も的確な言葉を使って、素直に、そして精一杯書いた。今読んでもきっと後悔することのない、そんな文章であったろうと思う。私のライバルは、そう、アルチュール・ランボー。
1か月ほどして、結果発表があった。受賞者のリストの中に、私の名前はどこにも無かった。どうしても納得できなかったので、国語の先生に聞いてみた。
「あのぉー、先生、読書感想文コンテストなんですけど、俺の文章、ダメでしたか?」
「ええ?君、何を書いたの?」
「ジャック・ケルアックの感想文を書いたんですけれど・・・」
「誰それ?」
「アメリカ60年代を代表する作家で、ビートジェネレーションの人です」
「聞いたことがないな。そんなのは文学でも何でもないんじゃないか。」
そこで話を切られてしまった。悔しかったので、聞いてみた。
「では先生、文学とは、たとえば誰のことを言うのでしょうか?」
「太宰だ」
私はその答えを聞いて、彼から学ぶものは何も無い、と決め込んだ。それから、私は学校での勉強というのを放棄する様になった。それは私にとって、有害だと思ったからだ。ちなみに大賞受賞作品は「火垂るの墓を読んで」であった。きっと高校生が書く文章としてふさわしい、と評価されたのだと思うが、私は学校という小さなコンテクストは一切信用せず、これからはずっとユニバーサルなものだけを追及しよう、そう心に決めた。
そんな時、私が夢中になったのが、映画「Trainspotting」だった。多感だった田舎暮らしの17歳の私の肌に、イギー・ポップやルー・リードの音楽と、強烈なイングランド的な感覚が、スっと私の中に入ってきた。こんな映画があるんだ、そしてこんな文化があるんだ、面白そうだな、見てみたいな、そんな風に思った。
私の興味は尽きず、ついに私は、父にこう頼んでみた。
「お父さん、イギリスに行かせて下さい」
-- つづく --
 | 地下街の人びと (新潮文庫)ジャック ケルアック新潮社このアイテムの詳細を見る |