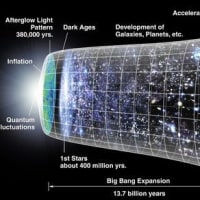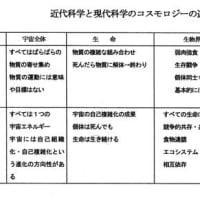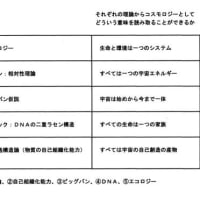「環境なくして〔人間〕社会なし、社会なくして経済なし」というのはまちがいのない論理だと思いますし、その環境が大変な危機にあることはデータと予測を見るとほぼまちがいないようなのですが、どうやら日本人はそういう論理やデータや予測では動かない国民のようです。
長年、環境問題の深刻さについて多くの人に論理で伝えてきて、なかなか理解されず、ようやく理解してもらえたかなと思っても、動かない(動いても適切とは思われないやり方で動く)、ごく少数動く人がいても、長続きがしないのはなぜか、どうしたら多くの日本人が、問題を正確に理解し、適切に行動し、解決するまであきらめないで持続するのだろう、と特に最近深く考え込んでいます。
そこで、いろいろ読んだり考えたりしていて、「なぜか」について、1つなるほどと思った解明がすでにご紹介した小室直樹氏の説でした。
それに続いて、小室氏と山本七平氏の本格的な対談『日本教の社会学』(学研)を読んで、「そうか、日本人は理論やデータによる予測・警告では動かず、空気で動くんだなあ」と理解し、さらに山本氏の『「空気」の研究』(文春文庫、原著は1977年刊)も読んで、そうとうな残念感をともなって「そうか、これはもう前からわかっている人はわかっていたんだ。これまでの私のアプローチは、まるでムダだったとまでは思いたくないが、日本人にはおよそ有効性の低いやり方だったんだなあ」と納得しました。
山本氏は、「戦艦大和の出撃などは〃空気〃決定のほんの一例にすぎず、太平洋戦争そのものが、否、その前の日華事変の発端と対処の仕方が、すべて〃空気〃決定なのである。だが公害問題への対処、日中国交回復時の現象などを見ていくと、〃空気〃決定は、これからもわれわれを拘束しつづけ、全く同じ運命にわれわれを迫い込むかもしれぬ。」(『空気の研究』p.58)と警告しています。
そして山本氏は、何とか「空気」の正体を見抜き、対処法を考え出そうと努力しておられますが、1977年初版の刊行以降30年以上たって、本はそうとう売れた(読まれた?)ようですが、それでも全体としての情況はまったく改善されていないように思えます。
つまり、環境問題に関して今日本には、「政治主導で経済・財政と福祉と環境のバランスのとれた、エコロジカルに持続可能な国家を創ろう」という「空気」はなく、それ以外のたぶん「やっぱり景気だ」とか「このままでも何とかなるんじゃないか」という「空気」があって、それは「われわれを拘束しつづけ」、どんなにちゃんとしたデータと理論で示しても、なかなか理解しない、理解しても動かない、動きはじめても持続しないという情況を生み出しているのであり、やがて「全く同じ」ような「運命」――茹で蛙――「にわれわれを追い込むかもしれぬ」ではなく、確実に追い込むとシミュレーションできます。
以下、ご存知の方はとっくにご存知のことですが、私同様、ご存知なかった方もおられると思いますので、山本氏の論旨がよくわかる部分を、長くなりますが、引用、紹介しておきたいと思います(読みやすくするために、若干改行等を加えています)。
……この「空気」という言葉……この言葉は一つの〃絶対の権威〃の如くに至る所に顔を出して、驚くべき力を振っているのに気づく。「ああいう決定になったことに非難はあるが、当時の会議の空気では……」「議場のあのときの空気からいって……「あのころの社会全般の空気も知らずに批判されても……」「その場の空気も知らずに偉そうなことを言うな」「その場の空気は私が予想したものと全く違っていた」等々々、至る所で人びとは、何かの最終的決定者は「人でなく空気」である、と言っている。
驚いたことに、「文藝春秋」昭和五十年八月号の「戦艦大和』〔吉田満監修構成)でも、「全般の空気よりして、当時も今日も〔大和の)特攻出撃は当然と思う」(軍令部次長・小沢治三郎中将)という発言がでてくる。この文章を読んでみると、大和の出撃を無謀とする人びとにはす べて、それを無謀と断ずるに至る細かいデータ、すなわち明確な根拠がある。だが一方、当然 とする方の主張はそういったデータ乃至根拠は全くなく、その正当性の根拠は専ら「空気」なのである。従ってここでも、あらゆる議論は最後には「空気」できめられる。最終的決定を下し、「そうせざるを得なくしている」力をもっているのは一に「空気」であって、それ以外にない。これは非常に興味深い事実である。
……「空気」と「論理・データ」の対決として「空気の勝ち」の過程が、非常に興味深く出ている一例に、前述の『戦艦大和』がある。これをもう少し引用させていただこう。
注意すべきことは、そこに登場するのがみな、海も船も空も知りつくした専門家だけであって素人の意見は介入していないこと。そして米軍という相手は、昭和十六年以来戦いつづけており、相手の実力も完全に知っていること。いわばベテランのエリート集団の判断であって、無知・不見識・情報不足による錯誤は考えられないことである。まずサイパン陥落時にこの案が出されるが、「軍令部は到達までの困難と、到達しても機関、水圧、電力などが無傷でなくては主砲の射撃が行ないえないこと等を理由にこれをしりぞけた」となる。従って理屈から言えば、沖縄の場合、サイパンの場合とちがって「無傷で到達できる」という判断、その判断の基礎となりうる客観情勢の変化、それを裏づけるデータがない限り、大和出撃は論理的にはありえない。だがそういう変化はあったとは思えない。もし、サイパン・沖縄の両データをコンピューターで処理してコンピューターに判断させたら、サイパン時の否は当然に沖縄時の否であったろう。従ってこれは、前に引用した「全般の空気よりして……」が示すように、サイパン時になかった「空気」が沖縄時には生じ、その「空気」が決定したと考える以外にない。
このことを明確に表わしているのが、三上参謀と伊藤長官の会話であろう。伊藤長官はその「空気」を知らないから、当然にこの作戦は納得できない。第一、説明している三上参謀自身が「いかなる状況にあろうとも、裸の艦隊を敵機動部隊が跳梁する外海に突入させるということは、作戦として形を為さない。それは明白な事実である」と思っているから、その人間の説明を、伊藤長官が納得するはずはない。ともにベテラン、論理の詐術などでごまかしうるはずはない。だが、「陸軍の総反撃に呼応し、敵上陸地点に切りこみ、ノシあげて陸兵になるところまでお考えいただきたい」といわれれば、ベテランであるだけ余計に、この一言の意味するところがわかり、それがもう議論の対象にならぬ空気の決定だとわかる。そこで彼は反論も不審の究明もやめ「それならば何をかいわんや。よく了解した」と答えた。この「了解」の意味は、もちろん、相手の説明が論理的に納得できたの意味ではない。それが不可能のことは、サイパンで論証ずみのはずである。従って彼は、「空気の決定であることを、了解した」のであり、そうならば、もう何を言っても無駄、従って「それならば何をかいわんや」とならざるを得ない。
ではこれに対する最高責任者、連合艦隊司令長官の戦後の言葉はどうか。「戦後、本作戦の無謀を難詰する世論や史家の論評に対しては、私は当時ああせざるを得なかったと答うる以上に弁疏(べんそ)しようと思わない」であって、いかなるデータに基づいてこの決断を下したかは明らかにしていない。それは当然であろう、彼が「ああせざるを得なかった」ようにしたのは「空気」であったから――。こうなると「軍には抗命罪があり、命令には抵抗できないから」という議論は少々あやしい。むしろ日本には「抗空気罪」という罪があり、これに反すると最も軽くて「村八分」刑に処せられるからであって、これは軍人・非軍人、戦前・戦後に無関係のように思われる。
「空気」とはまことに大きな絶対権をもった妖怪である。……何しろ、専門家ぞろいの海軍の首脳に、「作戦として形をなさない」ことが「明白な事実」であることを、強行させ、後になると、その最高責任者が、なぜそれを行なったかを一言も説明できないような状態に落し込んでしまうのだから……こうなると、統計も資料も分析も、またそれに類する科学的手段や論理的論証も、一切は無駄であって、そういうものをいかに精緻に組みたてておいても、いざというときは、それらが一切消しとんで、すべてが「空気」に決定されることになるかも知れぬ。とすると、われわれはまず、何よりも先に、この「空気」なるものの正体を把握しておかないと、将来なにが起るやら、皆目見当がつかないことになる。
では一体、戦後、この空気の威力は衰えたのであろうか、盛んになったのであろうか。「戦前・戦後の空気の比較」などは、もちろん不可能だから何とも言えないが、相変らず猛威を振っているように思われる。もっとも、戦後らしく「ムード」と呼ばれることもあり、昔なら「議場の空気」といったところを「当時の議場の全般のムードから言って……」などという言い方もしている。そして時にはこの「空気」が竜巻状になるのがブームであろう。いずれにせよ、それらは、戦前・戦後を通じて使われる「空気」と同系統に属する表現と思われる。そしてこの空気が、すべてを制御し統制し、強力な規範となって、各人の口を封じてしまう現象、これは昔と変りがない。
……もし目本が、再び破滅へと突入していくなら、それを突入させていくものは戦艦大和の場合の如く「空気」であり、破滅の後にもし名目的責任者がその理由を問われたら、同じように「あのときは、ああせざるを得なかった」と答えるであろうと思う。こうなるとますます、この「空気」なるものの実体を解明せざるを得なくなるのである。
(p.15-20)
……明治的啓蒙主義は、「霊の支配」(筆者注:つまり「空気の支配」)があるなどと考えることは無知蒙昧で野蛮なことだとして、それを「ないこと」にするのが現実的・科学的だと考え、そういったものは、否定し、拒否、罵倒、笑殺すれば消えてしまうと考えた。ところが、「ないこと」にしても、「ある」ものは「ある」のだから、「ないこと」にすれば逆にあらゆる歯どめがなくなり、そのため傍若無人に猛威を振い出し、「空気の支配」を決定的にして、ついに、一民族を破滅の淵まで迫いこんでしまった。戦艦大和の出撃などは〃空気〃決定のほんの一例にすぎず、太平洋戦争そのものが、否、その前の日華事変の発端と対処の仕方が、すべて〃空気〃決定なのである。だが公害問題への対処、日中国交回復時の現象などを見ていくと、〃空気〃決定は、これからもわれわれを拘束しつづけ、全く同じ運命にわれわれを迫い込むかもしれぬ。(p.58)
……われわれの世界は、一言でいえばアニミズムの世界である。この言葉は物神論(?)と訳されていると思うが、前に記したようにアニマの意味は〃空気〃に近い。従ってアニミズムとは〃空気〃主義といえる。この世界には原則的にいえば相対化はない。ただ絶対化の対象が無数にあり、従って、ある対象を臨在感的に把握しても、その対象が次から次へと変りうるから、絶対的対象が時間的経過によって相対化できる――ただし、うまくやれば――世界なのである。それが絶えず対象から対象へと目移りがして、しかも、移った一時期はこれに呪縛されたようになり、次に別の対象に移れば前の対象はケロリと忘れるという形になるから、確かにおっちょこちょいに見える。だがこの世界では、「おっちょこちょい」に見える状態でないと、大変なことになってしまうはずである。簡単にいえば、経済成長と公害問題は相対的に把握されず、ある一時期は「成長」が絶対化され、次の瞬間には「公害」が絶対化され、少したって「資源」が絶対化されるという形は、「熱しやすくさめやすい」とも「すぐ空気に支配される」とも「軽挑浮薄」ともいえるであろうが、後でふりかえってその過程を見れば、結構「相対化」したような形になりうる世界である。それは良くいえば、その場その場の〃空気〃に従っての「巧みな方向転換」ともいえ、悪くいえば「お先ぱしりのおっちょこちょい」とも言えるであろうが、見方によってはフランスの新聞が日本のオイルショックへの対処を評したように「本能的」とも見えるであろう。
……アニミズム的ジグザグ相対化に基づく自由、それによる対象からの解放という状態は、確かに、平和・平穏を保障された環境を前提とする転換期・成長期に起る諸問題の解決には、よい方法であったと思う。これが明治と戦後のあの行き方を可能にし、福沢諭吉型啓蒙主義を可能にした。
ただこの行き方は、日本軍と同じく「短期決戦連続型」となるから、「長期持久・長期的維持」はできない。さらにこの維持を前提とする超長期的計画はたてられないのである。そのため、成熟社会ではきわめて危険な様相を呈する。
では、どうすべきなのか。われわれはここでまず、決定的相対化の世界、すべてを対立概念で把握する世界の基本的行き方を調べて、〃空気支配〃から脱却すべきではないのか。ではどうすればよいか、それにはまず最初に空気を対立概念で把握する〃空気の相対化〃が要請されるはずである。
(p.69-71)
日本人は「情況を臨在感的に把握し、それによってその情況に逆に支配されることによって動き、これが起る以前にその情況の到来を論理的体系的に論証してもそれでは動かないが、瞬間的に情況に対応できる点では天才的」という意味のことを、中根千枝氏は大変に面白い言葉で要約している。「熱いものにさわって、ジュッといって反射的にとびのくまでは、それが熱いといくら説明しても受けつけない。しかし、ジュッといったときの対応は実に巧みで、大けがはしない」と。
……この傾向は確かにわれわれにあり、またあって当然と言わねばならない。われわれは情況の変化には反射的に対応はし得ても、将来の情況を言葉で構成した予測には対応し得ない。……言葉による科学的論証は、臨在感的把握の前に無力であったし、今も無力である。戦時中もそうであったが、このことは戦後も変っていない。
「大躍進」のとき桶谷繁雄氏が専門の冶金学の立場から中国の土法製鋼で鉄ができるはずがないことを論証したところ、総攻撃にあった経験を記しておられる。冶金学者の科学的技術的専門的論証はだれも信用せず、土法高炉が立ち並ぶ壮大な写真に人びとは反応するわけである。同じように洗剤騒動のとき、メーカーは少しも売りおしみをしていないし、減産をしているわけでないことをいかに論証しても無駄であったことを、ある会社の社長が、「あれにはホトホト弱り果てた」といった口調で話されたことがあった。この場合も、この社長がどのように論証したところで、洗剤が倉庫に山積みになっており、代議士などの摘発隊が、勇ましくブッている写真と記事の方に人は反応するわけである。
同じことは今もなお行なわれている。先日原子力発電の今井隆吉博士が「その人に提供し、その結果その人がもっているはずの情報量と、その人の態度変更とは関係ない」ことが、さまざまの調査の結果明らかになり非常に驚いた旨話された。簡単にいえば原子力発電について三、四時間かけて正確な情報を提供し、相手の質問にも応じ、相手は完全に納得したはずなのに、相手はそれで態度は変えない。そして、いまの説明を否定するかの如く見える一枚の写真を見せられると、その方に反応してしまうという。これも土法高炉の写真に反応するのと原則的には同じことであろう。これは桶谷氏の二十年近い昔の体験ときわめて似ている――いかに土法で鉄が出来ぬと専門家が学問的にこれを論証しても、また人びとがその論証に納得してもそれで態度を変えず、一枚の壮大な写真の方に反応してしまう。そしてこれはまさに戦争中の状態なのである。こういう事倒は挙げて行けば際限がない、というより逆の事例を探す方が困難なわけである。
(p.212-4)
以上のように、日本人は「情況の変化には反射的に対応はし得ても、将来の情況を言葉で構成した予測には対応し得ない。……言葉による科学的論証は、臨在感的把握の前に無力であったし、今も無力である。戦時中もそうであったが、このことは戦後も変っていない」のであり、「この行き方は、日本軍と同じく「短期決戦連続型」となるから、「長期持久・長期的維持」はできない。さらにこの維持を前提とする超長期的計画はたてられないのである。そのため、成熟社会ではきわめて危険な様相を呈する」といわれているとおり、日本社会は「きわめて危険な様相を呈している」と思われます。
スウェーデンの「予防志向」「バックキャスト」とまるで逆で、日本人の環境への対応は「治療志向」「フォアキャスト」である、と環境スペシャリストの小澤徳太郎氏が指摘しておられますが、それは日本人の宿瘂(しゅくあ、慢性病)ともいうべき国民性のようです。
山本氏は精神分析の岸田秀氏と『日本人と「日本病」について』(文春文庫、青土社)という対談もしておられますが、まさに「日本病」――これはもちろん集合的な内面=無意識的文化の問題です――というべきでしょう。
では、「空気」の正体は何か、どうしたらそれに対処できるか、つまり日本病の治療法はあるか、ということですが、山本氏は『「空気」の研究』で正体はかなり――完全ではないと思われますが――見破っていますが、対処法については、ともかく「自覚化・意識化」するという必要・不十分な条件しか見いだせていないように思えます。
そのあたりについては、また書きたいと思っています。
| 山本七平全対話 (4)山本 七平学研このアイテムの詳細を見る |
 | 「空気」の研究 (文春文庫 (306‐3))山本 七平文藝春秋このアイテムの詳細を見る |