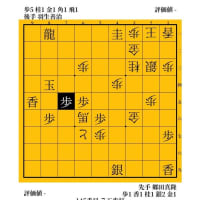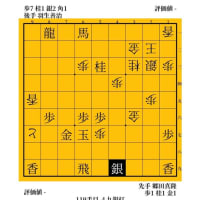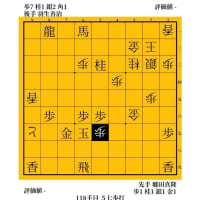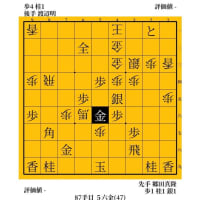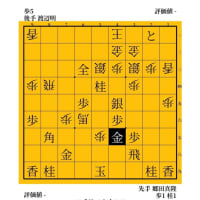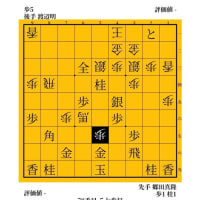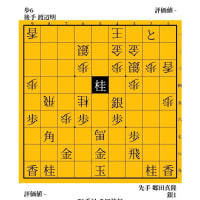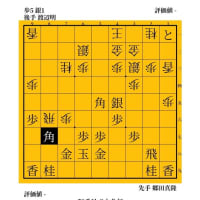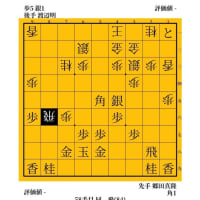前回(→こちら)に続いて、山本茂『白球オデッセイ』を読む。
戦前の日本テニス黄金期に、プレーヤーとして大きな実績を残した佐藤俵太郎の評伝だ。
この本を読むと、当時のテニス界というのが、いかに優雅な世界であったかというのがよくわかるが、俵太郎の華やかなテニス人生はコート上だけではなかった。
デ杯選手として、破格の待遇で欧州を転戦した彼は、ビル・チルデンや、イタリア貴族でテニスプレーヤーでもあるジョルジォ・デ・ステファーニらと友情をはぐくみ、ウィーンでは香水『Mitsuko』として名を残すクーデンホーフ=カレルギー伯爵夫人である青山光子にむかえられる。
国境を越えた友情、ヨーロッパの貴族、そしてウィーンの日本人伯爵夫人。まるで藤田宣永の傑作冒険小説『鋼鉄の騎士』(こっちは自動車レース)のようではないか。
プロ転向後は、「金に魂を売った」という陰口などなんのその、ビジネスチャンスを求めてアメリカ大陸を駆け回る。このアグレッシブなところが、また俵太郎の魅力だ。
中でも美しいのは、ヴェネチアにあるリド島で出会った、ユージニ・ピルツィオとのロマンスだろう。
長旅の疲れで、大会は初戦負けを喫した俵太郎だが、むしろそれが幸いした。
敗れてボールをたたきつけるなどマナーに難のあった選手がいる中、落胆を押し殺し毅然と去っていく姿に感銘した21歳のユージニと、夢のような一週間を過ごす。
そして、ついに島を去る日、別れのあいさつに来たユージニに俵太郎はキスをする。
もちろん気持ちはそれ以上と高ぶるが、転戦中エジプトのピラミッドもパリの凱旋門も見物せず、ひたすたテニスに打ちこんできた俵太郎は、道を極めるためにと、紳士的にそっと体をはなした。
もったいない。というのは、野暮というものであろう。そういう時代であったし、それにこの二人は物語のラストで、まるでドラマのように再びめぐり逢うことになるのである。
そのやりとりは、そのまま映画にできそうな、いやそうするにはあまりにも出来すぎな気もする。75歳になるユージニの、すてきな一言で本書は幕を閉じる。
かくして、日本テニス界の黄金時代は同時にスポーツ界における、テニスという競技の黄金時代であった。まだ木のラケットで、ポロシャツに長ズボンでプレーしていた。
華があり、プレーも優雅で美しかった。戦争のせいで、とかく暗く語られがちな昭和初期だが、このような世界もまた当時の日本にあったのだ。
そこがもうひとつの本書の読みどころだろう。
序章から引用しよう。
「スポーツの世界では国を越え、膚の色を越えて友情が芽生えた。異国の乙女と淡い恋もした。豪華汽船の一等船客として国々をめぐった。高級ホテルのスィートルームの客となったし、ウィーンの貴族の館にも招かれた。雅びた女性とダンスに興じた。コンチネンタル・タンゴを愛し、カンツォーネを歌った。テニスが上流階級のスポーツであり、テニスプレーヤーが最も尊敬された時代だった」。
読むと、一度木のラケットを持ってコートに立ってみたくなる。そんな一冊でした。
戦前の日本テニス黄金期に、プレーヤーとして大きな実績を残した佐藤俵太郎の評伝だ。
この本を読むと、当時のテニス界というのが、いかに優雅な世界であったかというのがよくわかるが、俵太郎の華やかなテニス人生はコート上だけではなかった。
デ杯選手として、破格の待遇で欧州を転戦した彼は、ビル・チルデンや、イタリア貴族でテニスプレーヤーでもあるジョルジォ・デ・ステファーニらと友情をはぐくみ、ウィーンでは香水『Mitsuko』として名を残すクーデンホーフ=カレルギー伯爵夫人である青山光子にむかえられる。
国境を越えた友情、ヨーロッパの貴族、そしてウィーンの日本人伯爵夫人。まるで藤田宣永の傑作冒険小説『鋼鉄の騎士』(こっちは自動車レース)のようではないか。
プロ転向後は、「金に魂を売った」という陰口などなんのその、ビジネスチャンスを求めてアメリカ大陸を駆け回る。このアグレッシブなところが、また俵太郎の魅力だ。
中でも美しいのは、ヴェネチアにあるリド島で出会った、ユージニ・ピルツィオとのロマンスだろう。
長旅の疲れで、大会は初戦負けを喫した俵太郎だが、むしろそれが幸いした。
敗れてボールをたたきつけるなどマナーに難のあった選手がいる中、落胆を押し殺し毅然と去っていく姿に感銘した21歳のユージニと、夢のような一週間を過ごす。
そして、ついに島を去る日、別れのあいさつに来たユージニに俵太郎はキスをする。
もちろん気持ちはそれ以上と高ぶるが、転戦中エジプトのピラミッドもパリの凱旋門も見物せず、ひたすたテニスに打ちこんできた俵太郎は、道を極めるためにと、紳士的にそっと体をはなした。
もったいない。というのは、野暮というものであろう。そういう時代であったし、それにこの二人は物語のラストで、まるでドラマのように再びめぐり逢うことになるのである。
そのやりとりは、そのまま映画にできそうな、いやそうするにはあまりにも出来すぎな気もする。75歳になるユージニの、すてきな一言で本書は幕を閉じる。
かくして、日本テニス界の黄金時代は同時にスポーツ界における、テニスという競技の黄金時代であった。まだ木のラケットで、ポロシャツに長ズボンでプレーしていた。
華があり、プレーも優雅で美しかった。戦争のせいで、とかく暗く語られがちな昭和初期だが、このような世界もまた当時の日本にあったのだ。
そこがもうひとつの本書の読みどころだろう。
序章から引用しよう。
「スポーツの世界では国を越え、膚の色を越えて友情が芽生えた。異国の乙女と淡い恋もした。豪華汽船の一等船客として国々をめぐった。高級ホテルのスィートルームの客となったし、ウィーンの貴族の館にも招かれた。雅びた女性とダンスに興じた。コンチネンタル・タンゴを愛し、カンツォーネを歌った。テニスが上流階級のスポーツであり、テニスプレーヤーが最も尊敬された時代だった」。
読むと、一度木のラケットを持ってコートに立ってみたくなる。そんな一冊でした。