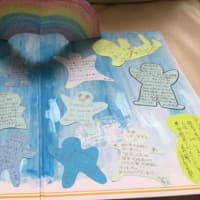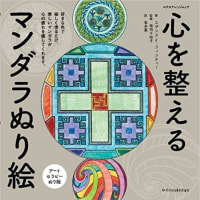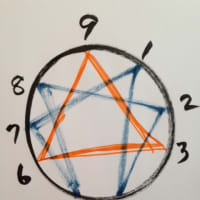マウンテンバイクの、その朝、天気予報は「十勝地方、カミナリ」と表示されていました。
雲は多いものの、雨が降るかどうかは疑わしい天気でしたが、残念ながら予報は的中でした。
途中で、雨が降り出します。
でも、これも、グロースの面白さのひとつ。
時折強く降り、風にあおられて雨が体にぶつかってきます。
子どもたちはヘルメットに、ひじあてひざあて、と厳重装備です。
そのせいもあってか、子どもたちにはこの雨が全く気にならないようでした。
もちろんボクは、路面のスリップや、事故が気になります。
今年は、無事全員が走破し終えて、承認です。
最後のチームが、到着するときには、いつも自然と拍手が起きます。
待っていた子どもたちが出迎えるシーンは、格別です。
そういえば、もう8年ほど前になりますが、途中の砂利道でギブアップ寸前になってしまった、1年生のウッチーのことを思い出します。
お菓子をリュックの中にいっぱい詰め込んで、グロースに参加して、ほとんど食事を取らずにお菓子ばかり食べていたまだ小さな少年です。
天気はまるで冬のように寒い日でした。
ラストの5キロは砂利道です。
ここで、寒さと、疲れで力つき果てたウッチーは、ミツグさん(士幌のオヤジ)の車に乗り込んで、すやすやと眠ってしまったのです。
昼ごはんを食べずに待っている子どもたちは、ウッチーを心配するやら、お腹はすくやら・・・・
約2時間後、ウッチーは走り始めました。
前にも増して、元気いっぱいに。
そしてゴールに集まった、子どもたちに盛大な拍手で迎えられたのです。
ウッチーも、自分で言ったことを見事にやり遂げました。
お弁当を食べ終わると、子どもたちは「いねむりおじさん」を始めます。
子どもたちの大のお気に入り遊びです。
これもネイチャーゲームのひとつ。
居眠りをしている宝の番人(おじさん)のもとへ、そっと近づき、その宝物を持っていく・・・というゲーム
「いねむりおじさん」は、目隠しをします。
その後ろに審判が1人立ちます。
ちょうど野球のキャッチャーと審判のようなかたち。
10メートルくらい離れたところから、その宝物を「盗み」に子どもたちが、足音を忍ばせながらやってきます。
「いねむりおじさん」は、耳をそば立て、やってくる子どもたちの足音や服のすれる音、息遣いに耳を傾けます。
聞こえた音の方向に指をさします。
審判は、その指された方向にいた子どもを、そのゲームからはずします。
歩いてくる子どもたちの顔は真剣そのもの。
見事に音の方向に指をさす「いねむりおじさん」
その攻防を、見ていると、ボクもすぐに参加したくなっていまうほど。
宝物は鈴や、鍵束などの音の出るものをおいておきます。
宝物に手が届いても、それを持ち上げるときに音が出てしまえば元もこもありません
とるのがダイスキで得意な子ども
やって来る子どもたちの音を聞きわけるのが得意な子ども
静かな公園に、更に静寂が包み込んでしまうほどに、子どもたちは息を殺して興じます。
このゲームをやるたびに、グロースの2回目か3回目の頃に参加していた、ムネ君のことを思い出します。
ムネ君は小学校2年生。3回ほど連続で参加していました。
ムネ君の夢は天文台で働くこと。
星がダイスキで、科学が好きな男の子。
時々、大人びたことを言ってはボクたちを驚かせたり、感心させられたり・・・
そんなムネ君も、いねむりおじさんがダイスキでした。
あるとき、ゲームが終わると、ムネ君は、僕の元へやってきました。
そしてボソッとつぶやきます。
あのね、しばふをふむおとと、おおばこのはをふむおとはちがうんだよ
それだけ言うと、ムネ君は行ってしまいました。
ボクは、唖然としてしまいました。
だって、目の前に広がっているのは全部「芝生」だと思っていたんですから。
でも、確かによく見ると、ところどころに「芝生」ではない、何かが生えています。
それが「オオバコ」でした。


ボクは、歩いて見ました。
しばふと、オオバコの上を。
音は、何も違わない・・・・・
もう一度、目を閉じて歩いてみました。
一生懸命、耳を傾けます。
すると、どうでしょう、違うんですよ。
しばふと、オオバコを踏む音は、たしかに違うんです。
小学校2年生のムネ君が教えてくれた、大切な自然からのメッセージです。
それ以来、いねむりおじさんをした後に、ボクの近くにいる子どもには、ムネ君に習って
あのね、しばふとおおばこは踏むと音が違うんだよ
中には「ふーん」とだけ言って、いなくなってしまう子どももいます。
でも、「どんなふうに?」と、聞いてくる子どもには、必ず
「自分で聞きわけてごらん」と、自慢げに伝えています。
ボクのひそかな楽しみの一つです。
さて、この日は、天気予報が見事に当たり、いねむりおじさんの途中から、カミナリがどんどん近づいてくるのがわかります。
雨もどんどん激しくなって、ボクたちは全員公園の真ん中にある あずまやに避難。
このままでは、士幌高校での芋ほりが出来ません。
そのうち子どもたちは、ボクにはわけの分からないゲームを始めます。
しばからはじまるリズムにあわせて トントン
 えりよん
えりよん
えりえりえりえり トントン
 みほさん
みほさん
みほみほみほ・・・・・・
これ知ってますか?
2-3人で始めたこの遊びが、あっという間にほとんど全員に広がり、40人がいっせいにこの遊びを始めます。
子どもたちは、何時でもどこでも遊びの体勢ができています。
大笑いをし、もりあがってこの遊びに夢中になっていると、雲間に太陽が見え始めます。
これで、芋ほりが出来る・・・
グロースは、守られている・・・・
士幌高校では、いつもの先生が農場で待っていてくれます。
ボクたちは、いつも裸足になって、芋ほりを実施します。
本州の子どもたちが、いろいろなところから芋ほり体験に来るそうですが、裸足になるのはグロースだけだそうです。
なんででしょう。
はだしは、とても気持ちいいのに。
どんなに泥だらけになっても、農場の隣が牧草地です。
牧草地を走り回ると、あっというまに草つゆがボクたちの足に付いた泥をキレイに洗ってくれます。
ことしは、一番「でかい芋」をほりだしたのはマリエちゃんでした。
そしておかしな形の「へんな芋大賞」は、ヨウスケ
名づけて「ムンクの叫び」
たしかに、あのムンクの絵の中の叫んでいる人間の表情にそっくり。
ヨウスケに、その顔を、やってくれーと、言うと、恥ずかしげに、なんども何度もやってくれました。
あのシャイなヨウスケが、です。
写真にも撮りましたが・・・本人がきっと嫌がりますから掲載はやめておきます。

さて、搾乳も、大きな牛の温かい乳を手絞りで体験します。
1年生のミウは、大泣きでしたが、シバシバと一緒に体験。
泣きながらでも、ちゃんと「自分でやる」と決めて、見事にやり遂げました。
士幌高校は、いつも、ボクたちを温かく迎えてくれます。
グロースは、士幌の人たちに、本当に受け入れられているのです。
士幌高校で掘ったお芋は、いよいよ今晩の、「子どもたちだけで作るカレーライス」に入ります。
本当においしいんですよ、これが。
雲は多いものの、雨が降るかどうかは疑わしい天気でしたが、残念ながら予報は的中でした。
途中で、雨が降り出します。
でも、これも、グロースの面白さのひとつ。
時折強く降り、風にあおられて雨が体にぶつかってきます。
子どもたちはヘルメットに、ひじあてひざあて、と厳重装備です。
そのせいもあってか、子どもたちにはこの雨が全く気にならないようでした。
もちろんボクは、路面のスリップや、事故が気になります。
今年は、無事全員が走破し終えて、承認です。
最後のチームが、到着するときには、いつも自然と拍手が起きます。
待っていた子どもたちが出迎えるシーンは、格別です。
そういえば、もう8年ほど前になりますが、途中の砂利道でギブアップ寸前になってしまった、1年生のウッチーのことを思い出します。
お菓子をリュックの中にいっぱい詰め込んで、グロースに参加して、ほとんど食事を取らずにお菓子ばかり食べていたまだ小さな少年です。
天気はまるで冬のように寒い日でした。
ラストの5キロは砂利道です。
ここで、寒さと、疲れで力つき果てたウッチーは、ミツグさん(士幌のオヤジ)の車に乗り込んで、すやすやと眠ってしまったのです。
昼ごはんを食べずに待っている子どもたちは、ウッチーを心配するやら、お腹はすくやら・・・・
約2時間後、ウッチーは走り始めました。
前にも増して、元気いっぱいに。
そしてゴールに集まった、子どもたちに盛大な拍手で迎えられたのです。
ウッチーも、自分で言ったことを見事にやり遂げました。
お弁当を食べ終わると、子どもたちは「いねむりおじさん」を始めます。
子どもたちの大のお気に入り遊びです。
これもネイチャーゲームのひとつ。
居眠りをしている宝の番人(おじさん)のもとへ、そっと近づき、その宝物を持っていく・・・というゲーム
「いねむりおじさん」は、目隠しをします。
その後ろに審判が1人立ちます。
ちょうど野球のキャッチャーと審判のようなかたち。
10メートルくらい離れたところから、その宝物を「盗み」に子どもたちが、足音を忍ばせながらやってきます。
「いねむりおじさん」は、耳をそば立て、やってくる子どもたちの足音や服のすれる音、息遣いに耳を傾けます。
聞こえた音の方向に指をさします。
審判は、その指された方向にいた子どもを、そのゲームからはずします。
歩いてくる子どもたちの顔は真剣そのもの。
見事に音の方向に指をさす「いねむりおじさん」
その攻防を、見ていると、ボクもすぐに参加したくなっていまうほど。
宝物は鈴や、鍵束などの音の出るものをおいておきます。
宝物に手が届いても、それを持ち上げるときに音が出てしまえば元もこもありません
とるのがダイスキで得意な子ども
やって来る子どもたちの音を聞きわけるのが得意な子ども
静かな公園に、更に静寂が包み込んでしまうほどに、子どもたちは息を殺して興じます。
このゲームをやるたびに、グロースの2回目か3回目の頃に参加していた、ムネ君のことを思い出します。
ムネ君は小学校2年生。3回ほど連続で参加していました。
ムネ君の夢は天文台で働くこと。
星がダイスキで、科学が好きな男の子。
時々、大人びたことを言ってはボクたちを驚かせたり、感心させられたり・・・
そんなムネ君も、いねむりおじさんがダイスキでした。
あるとき、ゲームが終わると、ムネ君は、僕の元へやってきました。
そしてボソッとつぶやきます。
あのね、しばふをふむおとと、おおばこのはをふむおとはちがうんだよ
それだけ言うと、ムネ君は行ってしまいました。
ボクは、唖然としてしまいました。
だって、目の前に広がっているのは全部「芝生」だと思っていたんですから。
でも、確かによく見ると、ところどころに「芝生」ではない、何かが生えています。
それが「オオバコ」でした。


ボクは、歩いて見ました。
しばふと、オオバコの上を。
音は、何も違わない・・・・・
もう一度、目を閉じて歩いてみました。
一生懸命、耳を傾けます。
すると、どうでしょう、違うんですよ。
しばふと、オオバコを踏む音は、たしかに違うんです。
小学校2年生のムネ君が教えてくれた、大切な自然からのメッセージです。
それ以来、いねむりおじさんをした後に、ボクの近くにいる子どもには、ムネ君に習って
あのね、しばふとおおばこは踏むと音が違うんだよ
中には「ふーん」とだけ言って、いなくなってしまう子どももいます。
でも、「どんなふうに?」と、聞いてくる子どもには、必ず
「自分で聞きわけてごらん」と、自慢げに伝えています。
ボクのひそかな楽しみの一つです。
さて、この日は、天気予報が見事に当たり、いねむりおじさんの途中から、カミナリがどんどん近づいてくるのがわかります。
雨もどんどん激しくなって、ボクたちは全員公園の真ん中にある あずまやに避難。
このままでは、士幌高校での芋ほりが出来ません。
そのうち子どもたちは、ボクにはわけの分からないゲームを始めます。
しばからはじまるリズムにあわせて トントン

 えりよん
えりよんえりえりえりえり トントン

 みほさん
みほさんみほみほみほ・・・・・・
これ知ってますか?
2-3人で始めたこの遊びが、あっという間にほとんど全員に広がり、40人がいっせいにこの遊びを始めます。
子どもたちは、何時でもどこでも遊びの体勢ができています。
大笑いをし、もりあがってこの遊びに夢中になっていると、雲間に太陽が見え始めます。
これで、芋ほりが出来る・・・
グロースは、守られている・・・・
士幌高校では、いつもの先生が農場で待っていてくれます。
ボクたちは、いつも裸足になって、芋ほりを実施します。
本州の子どもたちが、いろいろなところから芋ほり体験に来るそうですが、裸足になるのはグロースだけだそうです。
なんででしょう。
はだしは、とても気持ちいいのに。
どんなに泥だらけになっても、農場の隣が牧草地です。
牧草地を走り回ると、あっというまに草つゆがボクたちの足に付いた泥をキレイに洗ってくれます。
ことしは、一番「でかい芋」をほりだしたのはマリエちゃんでした。
そしておかしな形の「へんな芋大賞」は、ヨウスケ
名づけて「ムンクの叫び」
たしかに、あのムンクの絵の中の叫んでいる人間の表情にそっくり。
ヨウスケに、その顔を、やってくれーと、言うと、恥ずかしげに、なんども何度もやってくれました。
あのシャイなヨウスケが、です。
写真にも撮りましたが・・・本人がきっと嫌がりますから掲載はやめておきます。

さて、搾乳も、大きな牛の温かい乳を手絞りで体験します。
1年生のミウは、大泣きでしたが、シバシバと一緒に体験。
泣きながらでも、ちゃんと「自分でやる」と決めて、見事にやり遂げました。
士幌高校は、いつも、ボクたちを温かく迎えてくれます。
グロースは、士幌の人たちに、本当に受け入れられているのです。
士幌高校で掘ったお芋は、いよいよ今晩の、「子どもたちだけで作るカレーライス」に入ります。
本当においしいんですよ、これが。