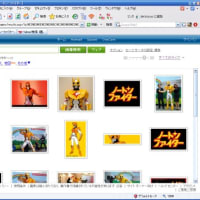SS企画「一枚絵で書いてみm@ster」参加作品
--
・後編へ続きます。
--
夢を見ていた。
いつもの夢。
私は、朽ち果てた廃墟の真ん中に、ひとり佇んでいた。
周囲には、かつては建物だったであろう白亜の石材が散乱していて、人間どころか生き物の気配すら感じない。
背後を振り返ると、すっかり枯れてしまった泉がある。もう水どころか湿り気すら感じないほど乾き切っている。それなのに、なぜ泉だったとわかるのだろう。考えてみれば不思議だけれど、夢なのだからわかって当然なのかもしれないと思い直す。
足下に視線を移せば、地面を舗装する石畳はボロボロで、既に風化が始まっていた。
そんな殺風景という言葉でも足りないような荒廃した景色の中で、私は淡いブルーのパジャマ姿で突っ立っている。場違いにも程がある、と思った。
これが現実であるわけがなかった。
私は溜息ひとつ吐いて、歩き出す。
何度も通った道だ。もう迷うこともない。
しばらく歩いていると、肌に触れる空気の質が変わるのがわかる
延々と続くかと思われた廃墟が途切れ、目の前が開ける。
湿り気を含んだ風が頬を撫でて、潮の匂いを鼻腔に残してゆく……。
海だった。
かつては港だったであろう岸壁にもたれかかるような格好で数隻の船が朽ちたまま着底し、見るも無残な姿を晒していた。
これは骸なのだ――と、もう何度目になるかわからない感慨を抱く。
大昔には、この船は外国との交易に使われていたのだろうか? と、そこまで考えてから、私は自分の浅はかさを笑った。
目の前に広がる光景は、全て私の夢の中にあるものだ。
骨組みだけになってしまった船の残骸を見て、その往事の姿を想像するなど、あまりにも馬鹿げていた。
ここには、最初から過去も未来もないのだから。
益体もない思考を振り捨てるように、私は両手を掲げて伸び上がる。その勢いのまま、体が浮き上がる。
夢だから、空を飛ぶことだってできる。
そのことに気づいたのは、いつだっただろう。
私は、私以外には誰もいない、このひっそりと静まりかえった世界で、不可視の翼を広げた。
船の墓場と化した港湾跡を眼下に見て、私は身を翻す。急角度で降下しつつ、廃墟に屹立する古びた石柱の間を縫うように飛ぶ。もし誰か見ている人がいたのなら、私はまるでピーター・パンのように見えたかもしれない。いや、パジャマ姿だから、ウェンディの方が喩えとしては適切だろうか?
そうして、ひとしきり荒っぽい空中散歩を楽しんでから、私は再び港湾跡へ舞い戻り、朽ちた船の残骸の上に降り立った。
寸断された竜骨から、まさに巨獣のあばら骨のように突き出た肋材の突端に腰を下ろして、私は歌を歌う。
この世界には、私の歌を聴いてくれる人はいない。
それでもよかった。好きな歌を歌って過ごせるのなら、そこがどこだって構わないと思った。
けれど、と私は自分に問いかける。
私は歌が好きなのだろうか?
歌を愛しているのだろうか?
そこで、いつも夢は終わる。
計ったようなタイミングで。
まるで、答えを出すことを避けるかのように。
目覚まし時計のアラームを止めて、私は身を起こす。
カーテンの隙間から漏れる光に目を細めてから、時計を覗き込んで時刻を確かめる。
いつも通りの時刻に起床したことに安堵し、私はパジャマを脱いで制服に着替え、階下へ降りた。
朝だというのに、一階のダイニングには誰もいない。
もう何年もこんな有様だから、すっかり心が慣れっこになっていて、今となっては何の感慨も湧いては来ない。
これでは、夢も現実も大して変わらない。
無人の台所に入り、買っておいた食パンをトースターに放り込みつつ、お湯を沸かす。
焼き上がったトーストにマーガリンを塗りつけ、苦いだけのインスタントコーヒーで流し込む。
そうやって朝食を済ませて、手早く身支度を調える。
早めに登校したからといって、特に何かするべきことがあるわけではない。
だけど、この家でゆっくりしていたくはなかった。
だから、まるで何かから逃げるように、私は家を出た。
本当に、逃げられたらよいのに……。
いつも通りに一日を過ごし、下校する。
部活はしていない。
一応、合唱部に籍を置いてはいる。けれど、他の部員と部活動の方針を巡って一悶着あってから顔を出していなかった。あれから一ヶ月ほど経っているけれど、もうどうでもよかった。
帰宅部の生徒たちに紛れるように校門を通り抜け、最寄り駅から自宅へ向かうのとは逆方向の電車に乗る。数ヶ月前まで縁もゆかりもなかった駅で降り、改札を抜け、商店街を歩く。
私の目的地は、その商店街の外れにあった。
どこにでもあるような雑居ビルの3階を見上げると、窓ガラスに貼り付けられたガムテープが「765」の数字を形作っているのがわかる。それが目印。看板代わりにしては、あまりにも拙く、貧乏くさいとも思ったけれど、あえて口にするほど子どもではない。
私は黙って歩を進め、芸能事務所――765プロダクションへと通じる階段を登った。
今、私が置かれている状況に全く不安を感じていないと言えば嘘になる。
もともと事務所の規模には興味がなかった。私に歌う機会を与えてくれるかどうか。それだけが関心事だった。
とは言っても、これといってやることもないまま事務所のCDライブラリを片端から聴いていくだけの日々が続くと、さすがにいろいろと考えてしまう。私がこのまま765プロに所属し続けていてよいのかどうか問い直し始めたのを察したわけではあるまいが、今から二週間ほど前に急遽デビューすることが決まり、担当プロデューサーが付くことになった。
私を担当することになった年若いプロデューサーの資質には幾許かの疑問と不安を感じないでもなかったが、今はまず無事にデビューすることが大事だ。オーディションに備えてレッスンを繰り返していれば、気持ちも紛れる。余計なことを考えなくていい。そう思うことにしていた。
階段を登り切ると、目の前に「765PRODUCTION」と小さく英字で記された扉が現れる。
扉の前に立ち、私は呼吸を整える。
控えめにノックをして、ドアノブに手を掛ける。
「おはようございます」
ようやく慣れてきた業界流の挨拶で、事務所に足を踏み入れる。
「おう、おはようさん」
私の担当プロデューサーが軽く手を上げて、挨拶を返してくれた。
まあ、悪い人ではないのだということは何となくわかってきた。だから、プロデューサーとしての手腕も優れている、とは限らないけれど。
我ながら、頑なだとは思う。
けど、仕方ないとも思う。
「今日は、ダンスレッスンだ」
その言葉に、私はきっと不機嫌な表情になっていたのだろう。
「ま、気持ちはわかるけどな」と言って、プロデューサーは私の肩をポンと軽く叩いた。
「千早の歌への思いが強いのは認めるよ。実際、誰に習ったわけでもないのに、あの歌唱力だ。大したもんだと思うさ。でもな、アイドルとしてやっていくためには、ボーカル一本槍ってわけにはいかない。ダンスやビジュアルレッスンは好きではないかもしれないが、疎かにすることはできないんだ。わかるな?」
それは正論だと思った。
だから、私は頷いた。
けれど、と私は自分に問いかける。
私は歌が好きなのだろうか?
歌を愛しているのだろうか?
「行くぞ、千早」
プロデューサーの言葉が私の思考を遮って、そこでいつも疑問は立ち消えになる。
計ったようなタイミングで。
まるで、答えと向き合うことを避けるかのように。
また、夢を見ている。
白い瓦礫が周囲に広がる、いつもの廃墟。
枯れた泉のほとりに腰掛けて、私はすっかり見慣れてしまった風景をぼんやりと眺めていた。
いくら夢とはいえ、なぜこんな寂しい世界に私はいるのだろう。
そう思わないではない。
一切の他人が登場しない世界。家族も、友人も、知人も、赤の他人もいない。私ひとりだけの世界。この上なく孤独だが、同時にあらゆる種類の人間関係に煩わされることもない世界。
それが、私の望みなのか?
そうなのかもしれない、と思う。
そうなのだろうか、とも思う。
あれから何年経っただろうか。
家が安らぎの場でなくなって、それでも生きていくためには家族を――もう私のことを見ようともしない両親を頼るしかない現状。頼れるだけマシではないかという諦め。早く自活できるようになって家を出て行くんだという焦りにも似た気持ち。それを希望と読み替えてみても、何も変わりはしなくて……。
「幾ら考えても堂々巡りだとわかっているのに、ね……」
私は独りごちつつ立ち上がり、荒れた石畳の道を海へ向かって歩き出す。
吹き寄せた風に流されるようにして空へと舞い上がり、あぁ、この世界にも風だけはちゃんと吹いているんだなぁ……なんて、妙なことに感心しながら、港に散らばる船の残骸に向かって私は飛んだ。
そして、いつもの場所に腰かけて、歌を歌う。
誰もいないこの場所で、誰に聴かせるわけでもない歌を歌う。
最初は自己満足だと思っていた。
けれど、途中で気がついた。そうではないのだと。自分を満足させるために歌っているわけではないのだと、気づいてしまった。
つまり、私は歌を聴かせたい相手を見失っているだけだったのだ。
いちばん歌を聴いて欲しい人を失くしてしまい、次に誰に向かって歌えばいいのかわからないまま、ここまで来てしまっていた。
その行き着く果てが、この廃墟なのだろうか。
そうだとは思いたくなかった。
自分の歌には価値があるのだと信じたかった。
他に取り柄がないから歌に逃げているだなんて認めたくなかった。
だけど、それも限界かもしれない。
これまでに感じたことのない倦怠にとらわれて、私は歌うことをやめて空を見上げた。
こんなふざけた世界でも、空はやっぱり青かった。
パチパチパチパチ……
突然の拍手に、私は心臓が口から飛び出るかと思うほど驚いた。
ここは夢の世界で、私以外には誰もいない廃墟だ。
そう思い込んでいたから、ほんのささやかな拍手が私をひどく狼狽させた。
内心の動揺を押し殺して、周囲に視線を走らせる。
拍手の主はすぐに見つかった。
淡い橙色のドレスを着た少女が朽ちかけた桟橋に立ち、まっすぐにこちらを見上げている。
ここは夢の世界だから、相手が見たままの存在かどうかはわからない。
けれど、目に見える姿を持っていたことは、私を多少なりとも安堵させた。
どこから来たのか。
何者なのか。
いつからいたのか。
そう自問することで、心を落ち着けることができた気になっていると、不意に少女が口を開いた。
「とても素敵な歌ですね」
そう言って、少女は花が咲くように微笑んだ。
しかし、私は返すべき言葉を知らなかった。
口を噤んだままの私に構わず、少女は言葉をつなぐ。
「私も、お姉さんみたいに上手に歌えるようになりたいです」
お姉さん、というのは私のことだろうか。
他に誰もいない。
私のことに違いなかった。
だが、少女のまっすぐで裏のない言葉が、今の私には身を切る刃のように感じられた。
彼女の眼差しから逃れるように私は俯き、そして呟いた。
「私には、他に何の取り柄もないから……」
その声が彼女の耳に届いたかどうかはわからない。
そこで、夢が終わったから。
計ったようなタイミングで。
まるで、彼女から逃げ出すかのように。
目覚まし時計のアラームを止めて、身を起こす。
静まりかえる薄暗い部屋の中で、私は膝を抱えた。
また逃げてしまったという苦い思いが、私の中でじわじわと広がってゆく。
嫌なことから目を逸らし、耳を塞いで、それで生きていけるわけがないのに。
わかっているはずなのに……。
わかっているつもりだったのに……。
「おはようございます」
正直なところ、全く気乗りはしなかったが、デビューもしていないうちからレッスンをサボるようではいけないだろうという義務感だけで事務所に顔を出す。
「おう、おはよう」
プロデューサーが返す脳天気な挨拶に、少しムッとする。
それが単なるわがままなのはわかっている。わかっていて、腹を立てる。
本当に度し難い生き物だなと思う。
「あぁ、ちょうどよかった。折角だから、紹介しておくよ。……おーい!」
しかし、私の気持ちなど知らぬ顔で、プロデューサーは誰かを呼んでいる。
私はソロでやっていくと決めたのだ。誰とも馴れ合うつもりはない。
そんな冷め切った気持ちで、私は踵を返す。プロデューサーの準備ができるまで、空いている会議室のオーディオシステムを借りて音楽でも聴いているつもりだった。
「千早!」
プロデューサーに呼ばれて、足を止める。
「紹介しておく。お前と同じアイドル候補生の高槻やよいだ。仲良くしてやってくれな」
溜息を吐いて振り返る。
次の瞬間、私は息が止まるかと思った。
夢で会った少女――にそっくりの少女が、そこにいた。
危うく声を上げそうになったが、どうにか踏みとどまる。
「はじめまして、高槻やよいです。よろしくお願いします」
「……よ、よろしく。高槻さん……」
深々とお辞儀をする少女――高槻さんに、私はたどたどしい挨拶をすることしかできなかった。
そんな私を見つめて高槻さんは小首を傾げ、そして言った。
「あの、私、如月さんにお会いしたことがあるような気がします……」
「そ、そう?」
前触れなく放たれた言葉は胸元に突き出された剣のようで、私は内心の動揺を悟られまいとするだけで精一杯だった。
確かに、私は夢の中で高槻さんによく似た――それこそ瓜二つの少女と出会った。服装は違えど、ふんわりしたボリュームのある髪を頭の後ろで二つにまとめた髪型は全く同じだったし、声もよく似ていると思う。
だが、それはあくまでも夢なのだ。
落ち着け、と自分に言い聞かせながら、乱れた呼吸を整える。
「どこで会ったのかなあ……。うーん……」
「……きっと、他人の空似ではないかしら?」
しきりに首を捻る高槻さんにそう言い捨てて、私は彼女に背を向ける。
これ以上、高槻さんと向き合い続けては、平静を保つ自信がなかった。
「そう、なのかなぁ……」
「そうよ。きっとね」
あれは、夢なのだ。
そう自分に言い聞かせる。
他人の空似だと言ったのは、他でもない私自身ではないか。
「行きましょう、プロデューサー。スタジオを使える時間は限られているのですから、有意義に使うべきだと思いますが」
「あ、あぁ……、そうだな……」
私たち二人の間に流れる微妙な空気に戸惑っていた様子のプロデューサーを促して、レッスンへ向かう。
何かに打ち込めば、忘れられると思った。
忘れたいと思った。
忘れて、どうするのかまでは、考えなかった。
--
・後編へ続きます。
--
夢を見ていた。
いつもの夢。
私は、朽ち果てた廃墟の真ん中に、ひとり佇んでいた。
周囲には、かつては建物だったであろう白亜の石材が散乱していて、人間どころか生き物の気配すら感じない。
背後を振り返ると、すっかり枯れてしまった泉がある。もう水どころか湿り気すら感じないほど乾き切っている。それなのに、なぜ泉だったとわかるのだろう。考えてみれば不思議だけれど、夢なのだからわかって当然なのかもしれないと思い直す。
足下に視線を移せば、地面を舗装する石畳はボロボロで、既に風化が始まっていた。
そんな殺風景という言葉でも足りないような荒廃した景色の中で、私は淡いブルーのパジャマ姿で突っ立っている。場違いにも程がある、と思った。
これが現実であるわけがなかった。
私は溜息ひとつ吐いて、歩き出す。
何度も通った道だ。もう迷うこともない。
しばらく歩いていると、肌に触れる空気の質が変わるのがわかる
延々と続くかと思われた廃墟が途切れ、目の前が開ける。
湿り気を含んだ風が頬を撫でて、潮の匂いを鼻腔に残してゆく……。
海だった。
かつては港だったであろう岸壁にもたれかかるような格好で数隻の船が朽ちたまま着底し、見るも無残な姿を晒していた。
これは骸なのだ――と、もう何度目になるかわからない感慨を抱く。
大昔には、この船は外国との交易に使われていたのだろうか? と、そこまで考えてから、私は自分の浅はかさを笑った。
目の前に広がる光景は、全て私の夢の中にあるものだ。
骨組みだけになってしまった船の残骸を見て、その往事の姿を想像するなど、あまりにも馬鹿げていた。
ここには、最初から過去も未来もないのだから。
益体もない思考を振り捨てるように、私は両手を掲げて伸び上がる。その勢いのまま、体が浮き上がる。
夢だから、空を飛ぶことだってできる。
そのことに気づいたのは、いつだっただろう。
私は、私以外には誰もいない、このひっそりと静まりかえった世界で、不可視の翼を広げた。
船の墓場と化した港湾跡を眼下に見て、私は身を翻す。急角度で降下しつつ、廃墟に屹立する古びた石柱の間を縫うように飛ぶ。もし誰か見ている人がいたのなら、私はまるでピーター・パンのように見えたかもしれない。いや、パジャマ姿だから、ウェンディの方が喩えとしては適切だろうか?
そうして、ひとしきり荒っぽい空中散歩を楽しんでから、私は再び港湾跡へ舞い戻り、朽ちた船の残骸の上に降り立った。
寸断された竜骨から、まさに巨獣のあばら骨のように突き出た肋材の突端に腰を下ろして、私は歌を歌う。
この世界には、私の歌を聴いてくれる人はいない。
それでもよかった。好きな歌を歌って過ごせるのなら、そこがどこだって構わないと思った。
けれど、と私は自分に問いかける。
私は歌が好きなのだろうか?
歌を愛しているのだろうか?
そこで、いつも夢は終わる。
計ったようなタイミングで。
まるで、答えを出すことを避けるかのように。
*
目覚まし時計のアラームを止めて、私は身を起こす。
カーテンの隙間から漏れる光に目を細めてから、時計を覗き込んで時刻を確かめる。
いつも通りの時刻に起床したことに安堵し、私はパジャマを脱いで制服に着替え、階下へ降りた。
朝だというのに、一階のダイニングには誰もいない。
もう何年もこんな有様だから、すっかり心が慣れっこになっていて、今となっては何の感慨も湧いては来ない。
これでは、夢も現実も大して変わらない。
無人の台所に入り、買っておいた食パンをトースターに放り込みつつ、お湯を沸かす。
焼き上がったトーストにマーガリンを塗りつけ、苦いだけのインスタントコーヒーで流し込む。
そうやって朝食を済ませて、手早く身支度を調える。
早めに登校したからといって、特に何かするべきことがあるわけではない。
だけど、この家でゆっくりしていたくはなかった。
だから、まるで何かから逃げるように、私は家を出た。
本当に、逃げられたらよいのに……。
*
いつも通りに一日を過ごし、下校する。
部活はしていない。
一応、合唱部に籍を置いてはいる。けれど、他の部員と部活動の方針を巡って一悶着あってから顔を出していなかった。あれから一ヶ月ほど経っているけれど、もうどうでもよかった。
帰宅部の生徒たちに紛れるように校門を通り抜け、最寄り駅から自宅へ向かうのとは逆方向の電車に乗る。数ヶ月前まで縁もゆかりもなかった駅で降り、改札を抜け、商店街を歩く。
私の目的地は、その商店街の外れにあった。
どこにでもあるような雑居ビルの3階を見上げると、窓ガラスに貼り付けられたガムテープが「765」の数字を形作っているのがわかる。それが目印。看板代わりにしては、あまりにも拙く、貧乏くさいとも思ったけれど、あえて口にするほど子どもではない。
私は黙って歩を進め、芸能事務所――765プロダクションへと通じる階段を登った。
今、私が置かれている状況に全く不安を感じていないと言えば嘘になる。
もともと事務所の規模には興味がなかった。私に歌う機会を与えてくれるかどうか。それだけが関心事だった。
とは言っても、これといってやることもないまま事務所のCDライブラリを片端から聴いていくだけの日々が続くと、さすがにいろいろと考えてしまう。私がこのまま765プロに所属し続けていてよいのかどうか問い直し始めたのを察したわけではあるまいが、今から二週間ほど前に急遽デビューすることが決まり、担当プロデューサーが付くことになった。
私を担当することになった年若いプロデューサーの資質には幾許かの疑問と不安を感じないでもなかったが、今はまず無事にデビューすることが大事だ。オーディションに備えてレッスンを繰り返していれば、気持ちも紛れる。余計なことを考えなくていい。そう思うことにしていた。
階段を登り切ると、目の前に「765PRODUCTION」と小さく英字で記された扉が現れる。
扉の前に立ち、私は呼吸を整える。
控えめにノックをして、ドアノブに手を掛ける。
「おはようございます」
ようやく慣れてきた業界流の挨拶で、事務所に足を踏み入れる。
「おう、おはようさん」
私の担当プロデューサーが軽く手を上げて、挨拶を返してくれた。
まあ、悪い人ではないのだということは何となくわかってきた。だから、プロデューサーとしての手腕も優れている、とは限らないけれど。
我ながら、頑なだとは思う。
けど、仕方ないとも思う。
「今日は、ダンスレッスンだ」
その言葉に、私はきっと不機嫌な表情になっていたのだろう。
「ま、気持ちはわかるけどな」と言って、プロデューサーは私の肩をポンと軽く叩いた。
「千早の歌への思いが強いのは認めるよ。実際、誰に習ったわけでもないのに、あの歌唱力だ。大したもんだと思うさ。でもな、アイドルとしてやっていくためには、ボーカル一本槍ってわけにはいかない。ダンスやビジュアルレッスンは好きではないかもしれないが、疎かにすることはできないんだ。わかるな?」
それは正論だと思った。
だから、私は頷いた。
けれど、と私は自分に問いかける。
私は歌が好きなのだろうか?
歌を愛しているのだろうか?
「行くぞ、千早」
プロデューサーの言葉が私の思考を遮って、そこでいつも疑問は立ち消えになる。
計ったようなタイミングで。
まるで、答えと向き合うことを避けるかのように。
*
また、夢を見ている。
白い瓦礫が周囲に広がる、いつもの廃墟。
枯れた泉のほとりに腰掛けて、私はすっかり見慣れてしまった風景をぼんやりと眺めていた。
いくら夢とはいえ、なぜこんな寂しい世界に私はいるのだろう。
そう思わないではない。
一切の他人が登場しない世界。家族も、友人も、知人も、赤の他人もいない。私ひとりだけの世界。この上なく孤独だが、同時にあらゆる種類の人間関係に煩わされることもない世界。
それが、私の望みなのか?
そうなのかもしれない、と思う。
そうなのだろうか、とも思う。
あれから何年経っただろうか。
家が安らぎの場でなくなって、それでも生きていくためには家族を――もう私のことを見ようともしない両親を頼るしかない現状。頼れるだけマシではないかという諦め。早く自活できるようになって家を出て行くんだという焦りにも似た気持ち。それを希望と読み替えてみても、何も変わりはしなくて……。
「幾ら考えても堂々巡りだとわかっているのに、ね……」
私は独りごちつつ立ち上がり、荒れた石畳の道を海へ向かって歩き出す。
吹き寄せた風に流されるようにして空へと舞い上がり、あぁ、この世界にも風だけはちゃんと吹いているんだなぁ……なんて、妙なことに感心しながら、港に散らばる船の残骸に向かって私は飛んだ。
そして、いつもの場所に腰かけて、歌を歌う。
誰もいないこの場所で、誰に聴かせるわけでもない歌を歌う。
最初は自己満足だと思っていた。
けれど、途中で気がついた。そうではないのだと。自分を満足させるために歌っているわけではないのだと、気づいてしまった。
つまり、私は歌を聴かせたい相手を見失っているだけだったのだ。
いちばん歌を聴いて欲しい人を失くしてしまい、次に誰に向かって歌えばいいのかわからないまま、ここまで来てしまっていた。
その行き着く果てが、この廃墟なのだろうか。
そうだとは思いたくなかった。
自分の歌には価値があるのだと信じたかった。
他に取り柄がないから歌に逃げているだなんて認めたくなかった。
だけど、それも限界かもしれない。
これまでに感じたことのない倦怠にとらわれて、私は歌うことをやめて空を見上げた。
こんなふざけた世界でも、空はやっぱり青かった。
パチパチパチパチ……
突然の拍手に、私は心臓が口から飛び出るかと思うほど驚いた。
ここは夢の世界で、私以外には誰もいない廃墟だ。
そう思い込んでいたから、ほんのささやかな拍手が私をひどく狼狽させた。
内心の動揺を押し殺して、周囲に視線を走らせる。
拍手の主はすぐに見つかった。
淡い橙色のドレスを着た少女が朽ちかけた桟橋に立ち、まっすぐにこちらを見上げている。
ここは夢の世界だから、相手が見たままの存在かどうかはわからない。
けれど、目に見える姿を持っていたことは、私を多少なりとも安堵させた。
どこから来たのか。
何者なのか。
いつからいたのか。
そう自問することで、心を落ち着けることができた気になっていると、不意に少女が口を開いた。
「とても素敵な歌ですね」
そう言って、少女は花が咲くように微笑んだ。
しかし、私は返すべき言葉を知らなかった。
口を噤んだままの私に構わず、少女は言葉をつなぐ。
「私も、お姉さんみたいに上手に歌えるようになりたいです」
お姉さん、というのは私のことだろうか。
他に誰もいない。
私のことに違いなかった。
だが、少女のまっすぐで裏のない言葉が、今の私には身を切る刃のように感じられた。
彼女の眼差しから逃れるように私は俯き、そして呟いた。
「私には、他に何の取り柄もないから……」
その声が彼女の耳に届いたかどうかはわからない。
そこで、夢が終わったから。
計ったようなタイミングで。
まるで、彼女から逃げ出すかのように。
*
目覚まし時計のアラームを止めて、身を起こす。
静まりかえる薄暗い部屋の中で、私は膝を抱えた。
また逃げてしまったという苦い思いが、私の中でじわじわと広がってゆく。
嫌なことから目を逸らし、耳を塞いで、それで生きていけるわけがないのに。
わかっているはずなのに……。
わかっているつもりだったのに……。
*
「おはようございます」
正直なところ、全く気乗りはしなかったが、デビューもしていないうちからレッスンをサボるようではいけないだろうという義務感だけで事務所に顔を出す。
「おう、おはよう」
プロデューサーが返す脳天気な挨拶に、少しムッとする。
それが単なるわがままなのはわかっている。わかっていて、腹を立てる。
本当に度し難い生き物だなと思う。
「あぁ、ちょうどよかった。折角だから、紹介しておくよ。……おーい!」
しかし、私の気持ちなど知らぬ顔で、プロデューサーは誰かを呼んでいる。
私はソロでやっていくと決めたのだ。誰とも馴れ合うつもりはない。
そんな冷め切った気持ちで、私は踵を返す。プロデューサーの準備ができるまで、空いている会議室のオーディオシステムを借りて音楽でも聴いているつもりだった。
「千早!」
プロデューサーに呼ばれて、足を止める。
「紹介しておく。お前と同じアイドル候補生の高槻やよいだ。仲良くしてやってくれな」
溜息を吐いて振り返る。
次の瞬間、私は息が止まるかと思った。
夢で会った少女――にそっくりの少女が、そこにいた。
危うく声を上げそうになったが、どうにか踏みとどまる。
「はじめまして、高槻やよいです。よろしくお願いします」
「……よ、よろしく。高槻さん……」
深々とお辞儀をする少女――高槻さんに、私はたどたどしい挨拶をすることしかできなかった。
そんな私を見つめて高槻さんは小首を傾げ、そして言った。
「あの、私、如月さんにお会いしたことがあるような気がします……」
「そ、そう?」
前触れなく放たれた言葉は胸元に突き出された剣のようで、私は内心の動揺を悟られまいとするだけで精一杯だった。
確かに、私は夢の中で高槻さんによく似た――それこそ瓜二つの少女と出会った。服装は違えど、ふんわりしたボリュームのある髪を頭の後ろで二つにまとめた髪型は全く同じだったし、声もよく似ていると思う。
だが、それはあくまでも夢なのだ。
落ち着け、と自分に言い聞かせながら、乱れた呼吸を整える。
「どこで会ったのかなあ……。うーん……」
「……きっと、他人の空似ではないかしら?」
しきりに首を捻る高槻さんにそう言い捨てて、私は彼女に背を向ける。
これ以上、高槻さんと向き合い続けては、平静を保つ自信がなかった。
「そう、なのかなぁ……」
「そうよ。きっとね」
あれは、夢なのだ。
そう自分に言い聞かせる。
他人の空似だと言ったのは、他でもない私自身ではないか。
「行きましょう、プロデューサー。スタジオを使える時間は限られているのですから、有意義に使うべきだと思いますが」
「あ、あぁ……、そうだな……」
私たち二人の間に流れる微妙な空気に戸惑っていた様子のプロデューサーを促して、レッスンへ向かう。
何かに打ち込めば、忘れられると思った。
忘れたいと思った。
忘れて、どうするのかまでは、考えなかった。
(続く)