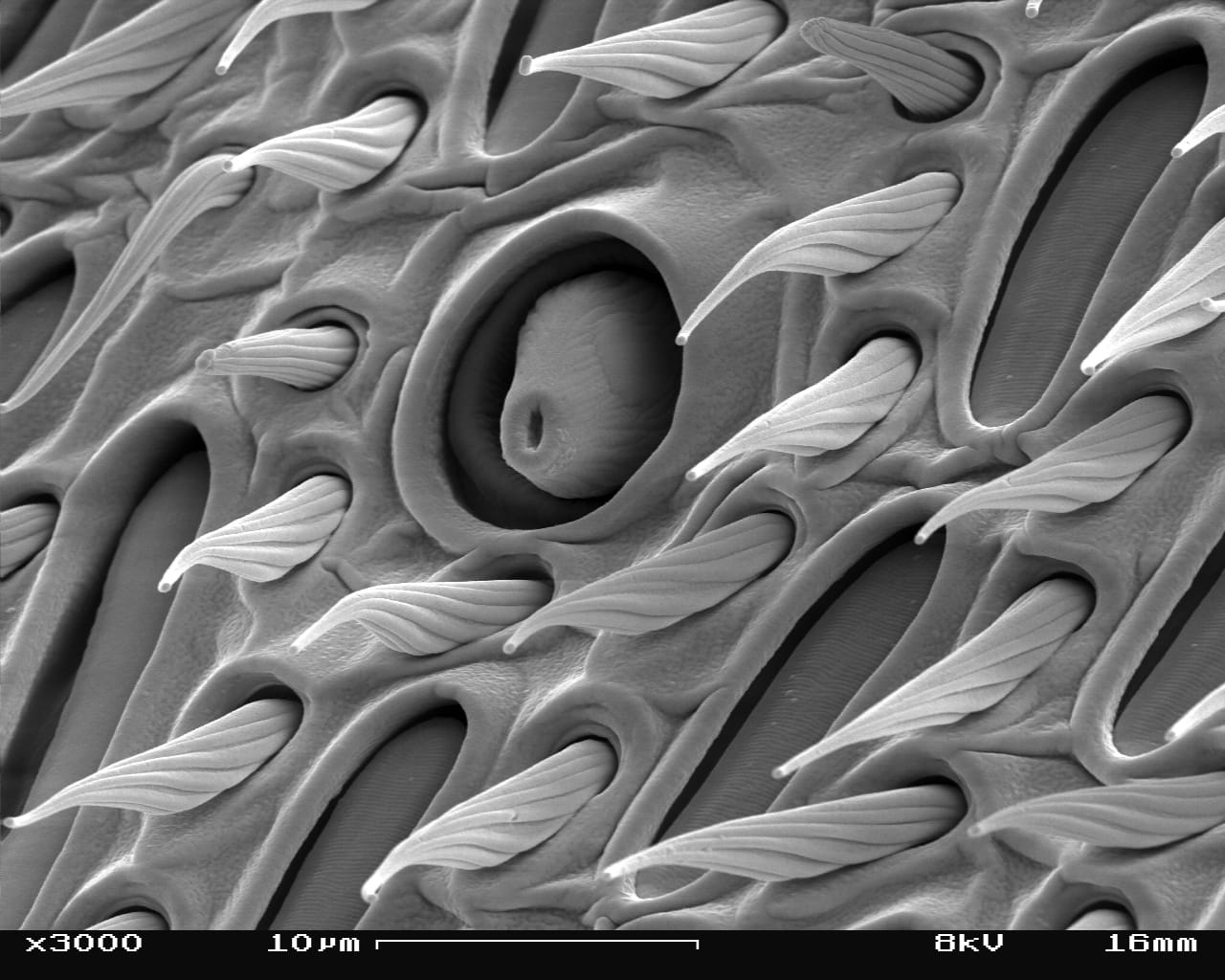会社の同僚の方のお薦めで、お借りして読んでみました。
著者の伊藤祐靖氏は元海自特殊部隊の小隊長。自らの実体験を踏まえての記述は、その主義主張の立ち位置如何に関わらずいろいろな面で興味深い内容でした。
著者が「特殊部隊」創設の必要性を痛感したのは、能登半島沖日本海において北朝鮮の工作母船に遭遇したときの経験でした。著者が乗船していたイージス艦の隊員たちが、官邸から海上警備行動の発令にもとづき工作母船船内の立入検査に向かうことになりました。当然相手は武装しています。選抜された若い立入検査隊員を前にこう思ったと著者は記しています。
(p18より引用) 彼らを、政治家なんぞの命令で行かせたくない、と思った。・・・“わたくし”を捨てきった彼らを、それとは正反対の生き方をしているように見えてしまう政治家なんぞの命令で行かせたくなかったのだ。
この能登半島沖不審船事件が契機となって海上自衛隊内に特殊部隊が作られました。まさにその事件当事者として部隊創設を訴えていた著者の理由はこうでした。
(p51より引用) あの日、我々は任務を完遂できる可能性がゼロなのを何人もの者が知っていながら、若者たちを工作母船の立入検査に投入しようとした。その当事者たる彼らは、すっきりと不思議な満足感に満ちた目で行こうとしていた。日本は、そういう目で死地に赴く若者を、二度と出してはならない。そのために特殊部隊は不可欠だった。
論理構成・因果関係による具体的結論が「特殊部隊が不可欠」というところに至る点については、私として首肯できるものではないのですが、理不尽なことを許してはならないという著者の真摯な想いについては理解はできますね。
特殊部隊創設の第一歩は「人集め」です。特殊部隊に配属された隊員は、自衛隊の中でもそれぞれの部隊で「浮いていた」人材でした。それ故、著者は人間関係においても厄介な状況になるであろうと覚悟していたのですが、隊員どおしのトラブルは皆無だったとのこと。この推定理由が面白いですね。
(p95より引用) 人間関係のトラブルというものは、意見の食い違いではなく、生きている目的の違いだったり、相手の真意を理解しようとしない態度から起きるのだろう。
特に本ケースにおいては、共有していた「生きている目的」の深さが特殊だったのだと思います。
さて本書は「特殊部隊」創設が主要テーマですが、その周辺系の記述でもとても興味を惹かれるくだりがありました。むしろそちらの方が多かったのですが、それらの中からいくつか書き留めておきます。
まずは、著者が分析する海軍(海上自衛隊)と陸軍(陸上自衛隊)との文化の違いに言及しているところ。海軍は多くの者がひとつの乗り物に乗って戦闘をします。他方、陸軍は個人が歩いて戦闘する、このスタイルの違いがスタートです。
(p112より引用) ビークルコンバットにおける指揮官の存在意義は、戦闘中にある。それは、報告させて、自分が判断して、実施させるからである。
一方、インディビジュアルコンバットにおける指揮官の存在意義は、戦闘前にある。それは、作戦の真の目的を理解させ、なぜこのような組織編制や任務分担にしたのか、なぜ、このような命令を出したのかを事前に理解させるからである。
陸上自衛隊と共同訓練をした時、私に状況を聞いてきた高級幹部は一人もいなかった・・・
「始まってしまったら、現場の指揮官に自由裁量の余地を少しでも多く与えること、現場指揮に専念できる環境を整えてやること、これが僕の仕事だからね」・・・
これが文化の違いである。
これはいろいろと考えさせられるコメントです。
次に二つ目、言い様については気分的にいいものではありませんが、突いているポイントに関しては結構納得感がありました。
(p130より引用) 日本という国は、何に関してもトップのレベルに特出したものがない。ところが、どういうわけか、ボトムのレベルが他国に比べると非常に高い。優秀な人が多いのではなく、優秀じゃない人が極端に少ないのだ。・・・
あくまで一般的傾向としてだが、軍隊には、その国の底辺に近いものが多く集まってくるものなのだ。・・・
要するに戦争とは、その国の底辺と底辺が勝負するものなのである。だから、軍隊にとってボトムのレベルの高さというのは、重要なポイントなのである。・・・
「最強の軍隊は、アメリカの将軍、ドイツの将校、日本の下士官」というジョークがあるが、なかなか頷ける話なのである。
三つ目は、フィリピンで格闘技量を磨いていたときに気付いた「相手に勝つための方法」について。自分が闘いやすい環境下で闘うことが相手に勝つ確率を高めると考えるのが常人ですが、著者の考えは違います。
(p165より引用) 自分が能力を発揮できる環境ではなく、自分も発揮しにくいが、相手がさらに発揮しにくい環境を創出すべきなのである。なぜなら、相手の方が戦闘能力が高くとも、それを発揮しづらい状況に引きずり込んでしまえれば勝てるからだ。
フィリピン時代、著者はこうした「闘いの本質」に触れるところで改めて自らの考え方の原点を再確認したようです。
(p171より引用) 我々は「できない」と簡単に口にしてしまうが、実は、できないのではなくて、できるのである。多くの場合は単に、そこまでしてやりたくないとか、そんなリスクを負うならやらないという話なのである。
逆に言うと、「リスクを負いさえすれば『何でもできる』」のであり、「自らを犠牲にすれば闘いには勝てる」ということです。それを「勝ち」というのかはともかく、「闘い」とはそういうものだというのです。
(p173より引用) 「自分が大切だと決めたもののために何かを諦める」という極めてシンプルで当たり前のことだった。
真剣に真摯に物事に取り組むとはこのことだったとの著者の言葉はとても印象的でした。
さて本書、自分からは決して手にとることはなかった本ではありますが、それ故に予想外に面白い気付きをたくさん得ることができました。
根っこの考え方の部分では、私として明確に共感しかねるところがあるのですが、それでも著者のメッセージの真剣さは十分伝わってきます。その点ではとても興味深い本でしたね。
ちなみに、1945年9月2日、アメリカ海軍の戦艦ミズーリ艦上において、対連合国降伏文書への調印がなされ太平洋戦争は終結しました。8月6日広島へ原爆が投下された日から1か月間、毎年、戦争についていろいろと考える時間です。